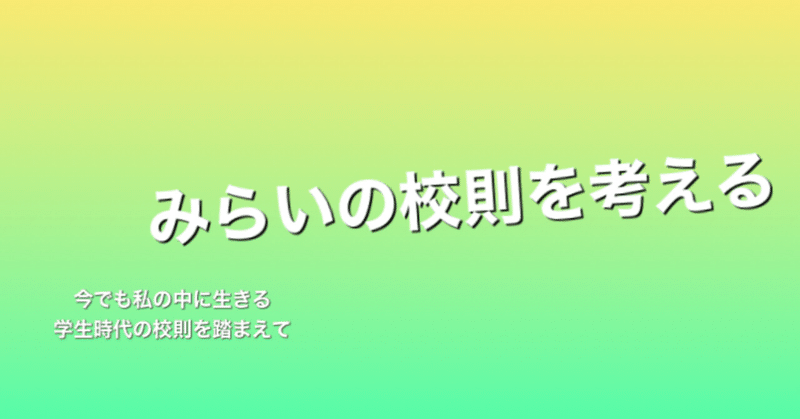
縛る校則と考えさせる校則
年末年始休暇を迎え、執筆活動を再開します。
書きたいことはたくさんありますが、どれもまとまらず急上昇タグを検索中に『#みらいの校則』を見つけました。高校を卒業したのは5年前ですが、私はその校則を覚えています。
「なぜ覚えていられるのか?」と思われる方も多いと思います。その理由はたった1つの校則、だけどしっかり考えて行動しなくてはならない難しい校則だったからです。
『校則』のイメージ
多くの人が校則というとたくさんの項目があるもので、すべては覚えていないものが当たり前だと感じているのではないでしょうか?
・学校に通学するときは決められた服装(制服)を着用しなければならない。
・静かに授業を受けなければならない。
といったあたりまえのことを記載したものが多数あると聞きます。
その一方で、「時代は令和だぞ!」と言いたくなるような校則もあります。
・下着の色は白色のみとする。
・髪型は男子短髪のみとする。(ツーブロック禁止)
校則を考えるとき、様々な論点があると思います。
1)そもそも校則が必要なのか
2)時代に合わせたアップデートは必要なのか
今回のnoteではこの点について考えてみたいと思います。
1)そもそも校則が必要なのか
『最低限の校則は必要である』
これが私の考えです。
どんな国にも憲法や法律、条令があるように一定のルールは必要ですが、0から10までを決めようとすることは不必要だと考えます。
先ほど挙げた『静かに授業を受けなければならない。』というルールですが、このルールをあえて記載する必要はどこにあるのでしょうか?
学校に行き、教室の椅子に座ると必然的に授業は始まります。そして、その授業を静かに受けることはあたりまえなのではないでしょうか?
確かに授業中に静かに受けることができない学生に対して、授業中静かにすることがルールだという明確な根拠にはなるかもしれません。ですがこのルールでは授業中に寝ることに対しては注意ができなくなります。
(※あくまでルール上はの話です)
このようにルールを細かく作成すると、その分だけルールを作らなくてはならなくなります。そして、そのルール間で矛盾が生じたり、時代に合わない(と思われる)ルールがクローズアップされ、ブラック校則と揶揄されてしまうのだと思います。
私が考える最低限の校則とは、所属する多くの学生が「校則は何か?」と問われたときほぼ完璧に校則を答えることができる程度の量で、かつ、抜け穴が少ないルールを確立するべきだとまとめることができます。
2)時代に合わせたアップデートは必要なのか
『時代に合わせたアップデートが必要である』というのが私の考えです。
私は1990年代に創立された比較的新しい公立高校の出身ですので、時代に合わない校則と揶揄される校則についてはインターネットで取り上げられているものしか知りません。
ですが、先に述べた『下着の色は白色のみとする』や『髪型は男子短髪のみとする』といった校則はいかにも時代に合っていないと一言でよいのではないでしょうか?
下着の色の指定に関して言えばだれが確認するのかという論点がありますし、男子だから髪型はこうするべきであるという価値観は今の時代には合わないと思います。
(『〇〇だからこうするべきである』は価値観の押しつけではないでしょうか)
『高校生であるのであればこのように生活するべきだ』という表現も耳にします。
ですが、その高校生らしくは誰が決めたものなのか考えなおすべきだと思います。年月が流れれば、高校生らしくは変化しているでしょう。
その変化に対して柔軟に対応していくことが子どもたちにとっては有意義なのではないかと思います。
これまでをまとめて
『社会の変化』はすさまじく、子どもたちが中心となった文化も多く形成されるようになりました。
学校は勉強をするだけの場所ではなく、総合学習に集約される『考える場所』になっているのも事実ではないでしょうか?
『みらいの校則』を考えるにあたって
新しい価値感に合わせたアップデートすることや指導することを第一とするのではなく考えさせる校則が良いのではないかと私は思います。
例えば『高校生らしく生活をしなさい』それだけでもよいのではないでしょうか?
その高校生らしくを時代の変化に合わせて学生、教職員、地域住民と共同で考えていくことが、生きる力を養い、誰かと協力しながら物事を考えられるクリエイティブな力をもった人財の育成につながると私は思います。
『社会のルールとマナー』
たった1つの校則で難しい校則の答えは今もなお変化しているのだと私は思います。そしてその校則を今でも私は頭の片隅に置きながら生活しているのです。
サポートいただけると執筆活動の励みになります! スキ・コメントもよろしくお願いします!
