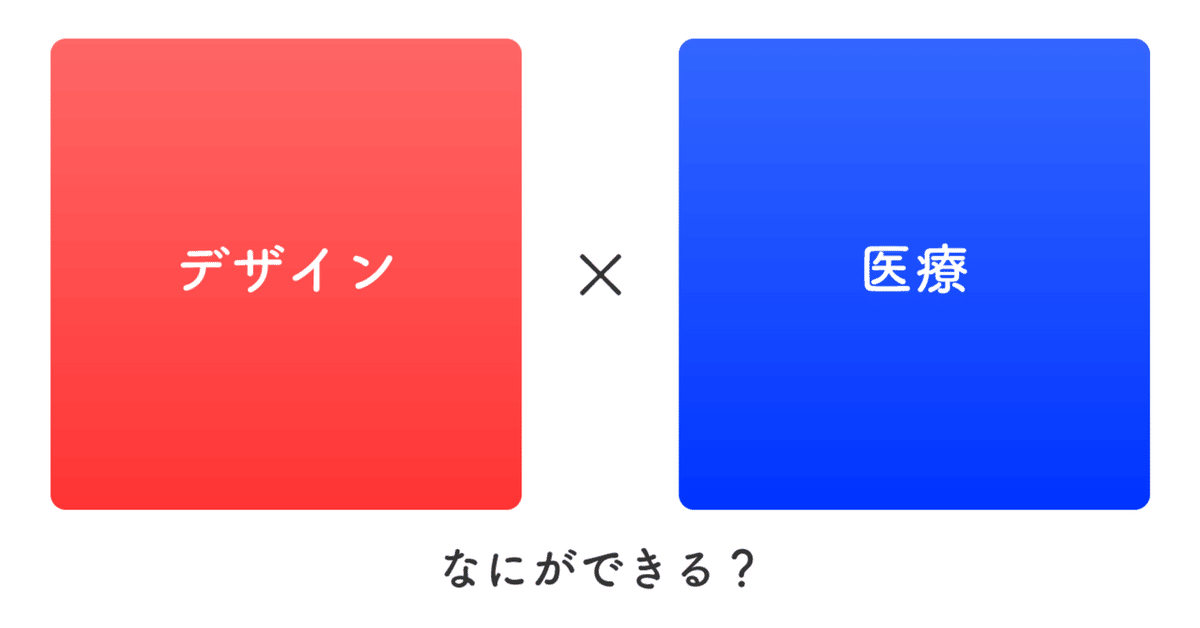
「デザイン×医療」はなぜピンとこないのか?デザインは医療になにができる?
こんにちは、株式会社CureAppデザイナーの小林です。精神科の医師ですがデザインが好きすぎてデザイナーとして働いています。
「デザイン×医療」。なんとなくこの二つを組み合わせることで立派なことができそうに思えますし、過去に多くの取り組みがなされていそうに思えます。
しかし「これこそがデザインと医療を組み合わせた成果物」というものをパッと想像できるでしょうか?意外と出てきそうで出てきません。今回はこの問題について考えてみます。
この記事でわかること
「デザイン×医療」はイメージがつかみづらい
デザインも医療も領域が広すぎる
医療自体がデザインに見えてしまう
医療の歴史と権威と規制がデザインを阻んでいる
それでもやっぱりデザインは医療に必要だ
「医療〇〇」と「〇〇デザイン」
「デザイン×医療」はなぜピンときにくいのか?まずは他の例と比較しましょう。世の中には「医療〇〇」とつくものや「〇〇デザイン」とつくものが存在します。
例えば「医療工学」。内視鏡やMRIといった検査機器、ロボット手術のような治療機器、そして医療者とエンジニアが協働するイメージを持てます。
もしくは「医療経済」。医療にまつわる経済的な介入とその成果物が思い浮かびやすいです。
一方「ファッションデザイン」はわかりやすいですし「建築デザイン」も美しく機能的な建造物が思い浮かびます。「研究デザイン」もいいでしょう。より社会的な意義の高い研究をするためのメソッドを確立し、優れた論文として成果をあげる、といった感じで理解ができる言葉です。
これらに対して「医療デザイン」。これがピンとこない。事例としてよく目にするのは小児科のMRIが怖くないように、かわいくデコレーションしてみました!など。これはこれで子どもに寄り添った良いデザインなのですが「これぞ医療のデザイン!」と言い切るのはすごく抵抗があります。なぜならいかにも表層的で素人っぽいアイデアであり、医療の本質とだいぶ離れた印象を受けるからです。

https://www.siemens-healthineers.com/
では医療の本質をとらえたデザインとはなんなのでしょう?
たとえば聴診器はすごいデザインです。これは胸の音を聞くことで多くの病気を発見することを可能にしてくれました。しかし聴診器はもはや医療そのものであり、これを今さらデザインの成果というのは何となくはばかられます。
ではCTスキャンはどうでしょう?放射線を用いることで患者の体内の情報が視覚的に得られる大発明です。これもまたデザインそのものというより工学の成果という印象になります。
このように、医療におけるデザインの貢献を考えるほど、その成果物があいまいになっていくことに気づきます。どうしてこうなってしまうのか?その理由についてさらに掘り下げましょう。
デザインも医療も領域が広すぎる

ピンとこない第一の理由。
デザインというと「見た目をよくするもの」と思われますが、これは狭い意味でのデザインと最近はとらえられています。現代のデザインが網羅する範囲はとても広く、コンセプトやユーザーの体験、エンジニアリング、ビジネスモデル、流通手段など、サービス全体の制作過程を含む概念に拡張されています。
つまり、ものを作る段階だけでなく、作る前のリサーチからユーザーに届く最終段階まで、デザインはさまざまな形で介入することができるのです。デザインの職能も多様化しており、デザインリサーチャー、UXデザイナー、UIデザイナー、グラフィックデザイナー、ビジネスデザイナー、デザインエンジニアなど、新しい肩書きが生み出されて整理がつかない状況です。
反対に現代のプロダクトは、デザイナーだけで完結することはできません。最終的な成果物がデザイナーの手柄のみで語られることは少なく、作るものが複雑になるほどデザインを含むすべての要素の重みが増していきます。
一方で「医療」も非常に多元的で複雑な概念です。臨床と基礎研究では世界が大きく異なり、内科、外科、眼科のような診療科によっても取り扱う内容はまったく変わってきます。病気の種類も星の数ほどあり、病気によって患者の抱える問題も違います。公衆衛生のようなマクロな医療もあれば、外来の待ち時間をどうするかのようなミクロな医療もあり、課題のレベルも千差万別です。
デザインは多様で複雑な概念であり、医療も多様で複雑な概念です。こうした複雑な概念どうしをぶつけると、無限の可能性をもった極度に複雑な概念が誕生します。
「デザイン×医療」には、俯瞰しきれないほどの可能性がありすぎるのです。
医療自体がデザインに見えてしまう

ピンとこない第2の理由。
デザインにおける共通の考え方として「ユーザーの視点に立って本質的な社会課題を発見し、解決するためのプロセス」を重視しています。「自分がこうしたいから」ではなく「ユーザーがこうしたいから」の発想を起点に作ることがデザインの基本です。
ここで「ユーザー」を「患者」に置きかえるとどうでしょう?「患者の視点に立って本質的な社会課題を発見し、解決するためのプロセス」は、医療そのものに見えます。
そうなると新しいワクチンの開発や、居心地のいい病院の建設、日常診療のちょっとした工夫にいたるまで、あらゆる行為がデザインに見えてきてしまいます。
「医療行為そのものが、患者というユーザーの理想を追求するデザインなのです」というとなんだかすごく立派に聞こえますが、この発想の拡大解釈は危険です。「医療におけるデザインとは何か?」の問いが極端に希釈されてしまい、一般的なデザインの考え方と医療におけるデザインの考え方に大きな隔たりが生まれてしまいます。
医療の歴史と権威と規制がデザインを阻む
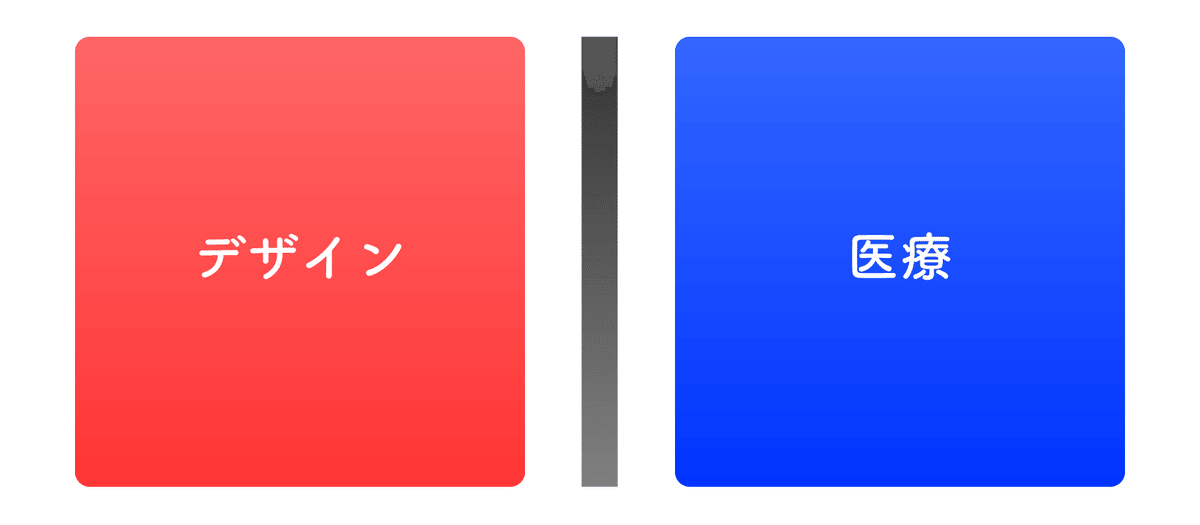
第3の理由。
医療はとても長い歴史で培われた学問であり、人の命を救う責任の重い行為でもあります。そこには膨大な量の情報と慣習、そして複雑な規制があり、外からのアイデアを容易には受け入れてくれません。たとえばデザインに優れたベンチャー企業が日本の医療に貢献したいと考えても、その中核にたどり着くまでのハードルが非常に高いことが現状です。
しかも多くの業界と同様、医療の上層部にいくほどデザインのリテラシーは浸透しなくなります。自由競争の市場が限られるため「デザインがよければ売れる」という商売の原則にも医療はあまり関心を示さず、デザインの価値啓発もなかなか届きません。
外部のデザインの専門家が入り込めないとなると、中の人間がはたらきかけることになります。たとえば私のようなデザインに関心のある医師が医療にデザインをもたらすために奮闘したとしても、しょせんは非デザイナーの考えるデザインです。
デザインは流動的で体系化が難しい概念であり、豊かな経験と業界全体への感度がものを言います。中途半端に聞きかじっただけの人間が土壌を作ってしまうことで、明らかに質の低いデザインが「日本の医療におけるデザイン」としてはびこってしまうことは懸念すべきです。
デザインの質を的確に評価し、高品質なデザインを提供しなければ社会に浸透することはありません。日本の医療はまだまだその域まで達していないと考えられます。
それでもやっぱりデザインは医療に必要だ
ここまで「デザイン×医療」がピンとこない理由について考えてきました。医療とデザインの網羅する範囲の広さ、医療自体が広義のデザインを含んでしまう、外からのデザインが医療に介入しづらい、といった理由をあげましたが、まだいくらでも理由はあるでしょう。
デザインが医療に受け入れがたいものであるなら、誰かが無理して介入させなくてもいいのかもしれません。
しかし私はそう思いません。医療の課題は常に山積みであり、デザインは社会課題を解決することを目的にしています。医療業界のデザインへの関心がまだ低いのであれば、積極的に導入することで新しい価値を生み出すポテンシャルが十分にあります。
とはいえやみくもに喧伝することが得策とは思えません。医療にデザインを浸透させるためにはどこにフォーカスするべきか。最後に考えていきます。
課題の中でデザインの役割を考える
「デザインは医療になにができるか?」と漠然と考えるのではなく「医療における課題はなにか?」から、問いをスタートさせましょう。その課題を解決する過程にデザインは必ず存在し、どのようにデザインを介入させるかで可能性は具体化されます。「プロジェクトは走り始めたけどどこがデザインの範疇かわからない」という状態であれば、できるだけ早くデザインの専門家に相談することで最終的な質を高めることができます。
デザインの「質」を考える
医療にちょっとした工夫を加えるだけでデザインと言っていいかもしれませんが「優れたデザイン」と「優れていないデザイン」は確実に存在します。デザインしていればなんでもいいわけではなく、いかに社会に適したデザインに近づけるかは重要です。
しかしデザインの質を評価することは容易ではなく、誰かの審査で決まるものでもありません。医療業界全体のデザインレベルが上がる中で自然淘汰が起こり、世のデザイン基準と食い違わないかたちで進歩できると理想的です。
デザインリテラシーを高める
デザインはデザイナーのものではなく、ユーザーのためのものです。デザイナーはデザインを熟知していますが、医療者はユーザーである患者や医療者自身について誰よりも深く知っています。ユーザーを知る医療者がデザインに対する関心を高めることができれば、デザイナーとのコミュニケーションは円滑になり、より優れたデザインを生み出すことができます。
優れたデザインを観察し、その背景にあるデザインの考え方を知ることはとてもおもしろい作業です。このおもしろさを伝えることが、私の役割なのかもしれません。
書いていくほどに医療におけるデザインはまだまだ未開拓で、多くの可能性を持っていると実感できます。いろいろな人とデザインについてディスカッションしていきたいです。
追記
2023年2月6日に「医療者のスライドデザイン プレゼンテーションを進化させるデザインの教科書」を出版しました。医療がデザインに関心を持ってもらうきっかけになるよう努めていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
