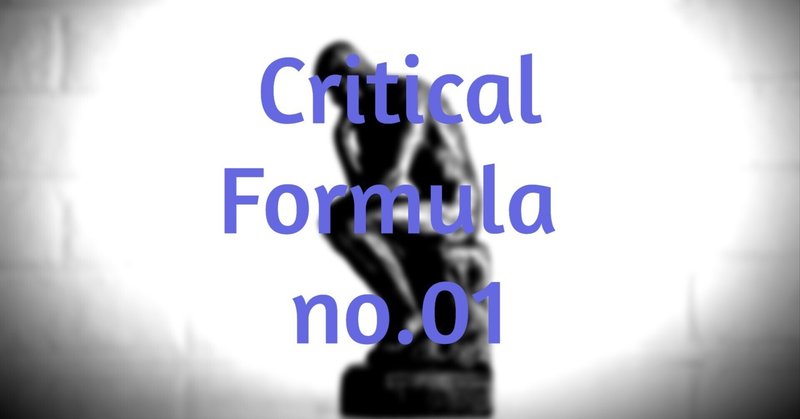
小説初挑戦:「クリティカル・フォーミュラ」第一話
こんにちは、皆さん。
私は45歳で銀行を退職し、現在はプライム市場に上場する企業の経営企画部で活動しています。
今回、初めての試みとして管理会計をテーマにした小説を書いてみました。
この小説は、実務的な知識を駆使して現実のビジネスシーンを描き、読者の皆さんに役立つ知識を提供することを目指しています。
物語は、銀行を辞めて新たな職場に転職した主人公が、管理会計の知識を駆使して部長の計算ミスを指摘するシーンから始まります。
登場人物たちのやり取りを通じて、固定費と変動費の区別や差額利益計算の重要性が自然に理解できるように構成しました。
皆さんがビジネスの現場で直面する課題を解決するヒントとなることを願いながら、物語の中で管理会計の世界を楽しんでいただければ幸いです。
それでは、物語の世界へどうぞ。
登場人物
主人公 :銀行から転職した30代女性
佐藤部長:銀行から出向してきた経営企画部長
意思決定会議

午前中の柔らかな陽光が会議室に差し込む中、私は一枚の資料を手にしていた。私が銀行を辞め、転職して以来、これが初めての意思決定会議の場だ。
「皆さん、これが今回の議題です。」経営企画部長の佐藤が話し始めた。
彼は私と同じく銀行出身である。ただ、私と違って自ら職を変えたのではなく、銀行から出向してきた男だ。ポジションも私の役職よりは、かなり上の役職で迎え入れられていた。
佐藤は銀行員時代から出世にしか興味がないと言われていたらしい。確かに彼の自信に満ちた口調は一見頼りがいがあるが、実務には疎いと囁かれていた。
おそらく、優秀な部下を従えて、口八丁で銀行では出世してきたのだろう。私は正直、佐藤のことがあまり好きではなかった。
「現在、我々の生産ラインの稼働率には余裕があります。これを活用して、X社からの新たなB製品の注文を受けるか否かを決定しなければなりません。」佐藤は室内によく響く、少し高い声質で資料の要点を説明し始めた。
佐藤が用意した資料には既存のA製品と、新たに受注を検討するB製品のコストが書いてあった
B製品の製造原価

会議室の空気が引き締まり、会議に参加している全員が真剣な表情で資料に目を通す。
私もまた、説明に耳を傾けながら、資料の数値に目を走らせた。
佐藤の資料は、伝統的な原価計算に基づいていた。
B製品の追加生産には17,600円の原価がかかるが、販売価格は17,000円のため損失が発生すると結論づけていた。
<B製品の製造原価>
材料費 :@6,000円
直接労務費:@4,000円(300万円÷3,000時間×4時間)
製造間接費:@5,600円(1,400円×4時間)
消耗品費 :@2,000円(25万円÷125個)
原価合計 :@17,600円
--------------------------
販売単価 :@17,000円(▲6,000円損失)
資料を一瞥しただけで、私はその計算が誤っていることに気づいた。
会計の素人が作成したようなミスだが、実務に疎い銀行出身の佐藤らしいとも思った。
佐藤部長への指摘

「ちょっといいですかぁ?」私はぶっきらぼうに口を開いた。
「どうぞ、何か意見がありますか?」佐藤は少し驚いたように私を見た。
「この計算、固定費が混ざってますよ。B製品の追加生産で実際にかかるのは材料費と一部の間接費だけじゃないです?」
「固定費を含めたら、そりゃ赤字になりますよ。」私は配られた会議資料を片手でヒラヒラさせながら冷たく言った。
佐藤は私の態度に一瞬戸惑った表情を見せたが、すぐに反論してきた。
「しかし固定費は無視できないのではないですか?生産全体のコストに影響するはずです。」
「それは違いますねぇ。」
私はネイルを見つめながら冷ややかに続けた。
「固定費はすでに発生しているから、B製品を新たに作っても変わりませんよ。重要なのは変動費です。もし、新たな受注の可否について考えるなら、差額利益で計算すべきですね。」
会議室が一瞬静まり返った。佐藤は再度資料を見直すフリをしたが、反論は見つからない様子だった。
最新のスマホをいじりながらも、私は容赦なく話を続けた。「具体的に言えば、B製品の直接材料費は6,000円、特殊な工具費用が250,000円、製造間接費は1,400円ではなく、時間あたり400円でしょ。」
佐藤が急いで計算する素振りを見せたので、私は話を続けることにした。私はこういう意地の悪さを持っている。
「おそらく部長は、A製品とB製品を生産する場合、直接の作業時間はA製品は1個あたり5時間で500個作るから2,500時間、B製品は1個作るのに4時間で125個作るから500時間、合計で3,000時間で計算してますよね。」私は根拠となる数値の計算式について解説した。
「そうです。AとBを製造するのにかかるのは3,000時間です。」佐藤は私を見つめながら冷静に答えた。しかし、目が泳いでいるのは分かった。
「つまり、製造間接費を計算するため3,000,000円の基本給を3,000時間で割ると1時間あたり1,000円かかるから、400円+1,000円で製造間接費は1,400円にしたんじゃないですか?」
「何か問題がありますか。」会議に参加している幹部たちは佐藤と私のやり取りが、頭に入っていない様子だったため、私はホワイトボードを使うことにした。
製造原価の説明

「部長の計算では、新たにB製品を生産する、という意思決定には関係のない費用を含んでるんですよ。」
私はホワイトボードに以下の式を書いた。
A製品のみ生産:賃金1,200円(300万円÷2,500時間)
B製品を追加 :賃金1,000円(300万円÷3,000時間)
「確かに、B製品を作るのに賃金は支払わないといけません。でも、B製品を作ろうが作るまいが、これって払わないといけないでしょ。」
「つまり基本給の300万円はB製品とは関係なく発生する賃金です。だから、今回の意思決定に含めるべきではないですね。」
私は佐藤の資料に記載された数値をホワイトボードにサラサラと転記し、不要な費用に太い横線を引いて幹部たちに示した。
<B製品の製造原価>
材料費 :@6,000円直接労務費:@4,000円(300万円÷3,000時間×4時間)製造間接費:@5,600円(1,400円×4時間)製造間接費:@1,600円(400円×4時間)
消耗品費 :@2,000円(250,000円÷125個)
原価合計 :@9,600円
--------------------------
販売単価 :@17,000円(+7,400円利益)
「製造間接費は追加の400円だけ考えないとダメですね。だからB製品の原価は9,600円です。販売価格は17,000円だから利益は7,400円になりますね。」私は冷静に言い放った。
会議の収束
佐藤は口を開きかけたが、結局何も言わずに再度資料を見つめた。部屋の空気が変わり、全員が再び資料に目を通し始めた。
私の指摘によって議論がどう展開するのか緊張が高まっている様子だった。
佐藤は自分の面目が潰れたことに気づきながらも、その表情には冷静さを保っていた。
彼は私の方を向いて微笑んだ。「君の指摘は非常に重要だ。これからも積極的に意見を出してほしい。」
「間違った意思決定で、損するとこでしたねぇ。」私は、この議論には興味がない感じで、視点を合わさずにつぶやいた。
「部下に計算させ直して、再度会議で報告いたします。」佐藤は、部下のミスであるかのように一言加え、椅子に座った。
私は佐藤のミスではないのか、と問うことも出来たが、それは止めておいた。言い訳を聞く時間ほど、勿体無いことはないからだ。
その後、会議は滞りなく進行したが、佐藤はその間、チラチラと私を見つめていた。
私は、佐藤の視線よりも、スマホに届いた ”祭りの屋台の件で相談” という友人からの通知への興味の方が大きかった。
続く
書籍紹介
この小説は以下の書籍を参考に物語を構成しています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

