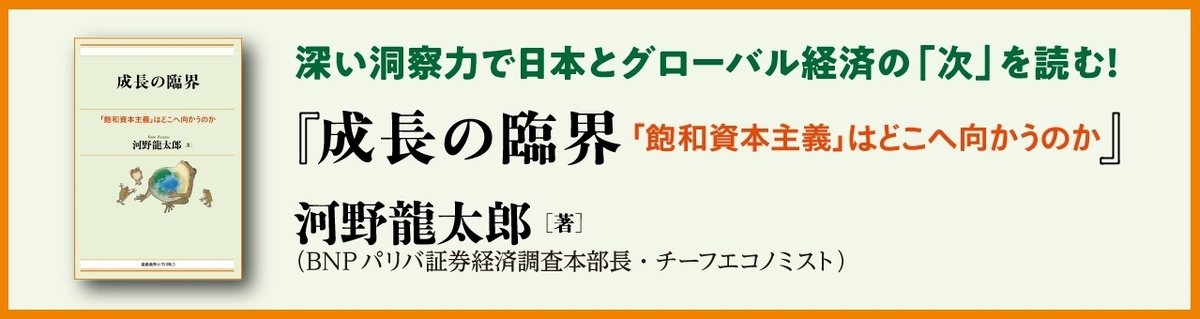【試し読み】『成長の臨界——「飽和資本主義」はどこへ向かうのか』
2022年7月上旬発売予定の『成長の臨界——「飽和資本主義」はどこへ向かうのか』は、『日経ヴェリタス』のエコノミスト人気ランキングで、これまでに9回も首位に選出(2021・2022年は連続選出)されている著名エコノミスト、河野龍太郎氏による十数年ぶりの書き下ろし作品です。
経済・金融の視点だけでなく、歴史学・心理学・政治学などの知見も交えて現況を怜悧に分析。迫り来る「次の世界」を、大胆かつ精緻に展望します。
なぜ、このタイトルなのか、なぜ、このカバーのイラストなのかや本書の魅力が分かる「はじめに」を公開します。ぜひご一読ください。
***
カエルと牛
イソップ童話の中に「カエルと牛」という話がある。
ある牧場で、子ガエルの兄弟の一匹が牛に踏みつぶされた。カエルの子はオタマジャクシだが、この際、細かな詮索は置いておこう。要は、小さなカエルということである。生まれて初めて牛を見た子ガエルたちは、母ガエルに「弟ガエルを踏みつぶしたのは、とても大きな動物だった」と報告する。母ガエルは自分のおなかをふくらませ、「こんな大きさだったかい?」と尋ねる。「いいや、もっともっと大きかった」と子ガエルが答えると、母ガエルはさらに大きくふくらませた。「これくらいかい?」「まだまだ(大きさが)足りない」。何回か繰り返したあげく、とうとう母ガエルのおなかは破裂してしまった……。
この寓話は、まさに今のわたしたちの姿を投影してはいないだろうか。日本の公的債務残高しかり。日銀のバランスシートしかり。そして、地球温暖化問題しかりである。母ガエルの破裂寸前のおなかは、せめてギリギリのところで止めておけばよかったのに、もう一息吸い込んだがために、あわれにも破裂した。
この「ギリギリの線」という状態を表すことばの一つに「臨界」がある。物理学では、物理的性質が異なる境界を指す用語として使われる。特に原子炉や核燃料などでは、核分裂反応が時間とともに増大し始める境目の状態を臨界状態と呼ぶ。別の使い方として、「限界」や「境界」を表すことばでも
成長の臨界
本書のタイトルは、この「ギリギリの線」を示す用法としての「臨界」であり、激変する地球環境の下で存亡の縁(臨界)を綱渡りする人類が、どのような経済活動を行うべきかを考察しようとするものである。現在の社会システムのまま、同じような経済活動を続けていけば、いずれ限界(=臨界)が訪れる。一方で、たとえばわたしたちが脱物質化社会に移行するのであれば、これまでとは別のかたちで、経済成長を含め、豊かさを追求できる。いずれにせよ、これまでとはまったく異なる領域に入る。それゆえ、タイトルを「成長の臨界」とした。
1972年、「ローマクラブ」が第1回目の報告書『成長の限界』を公表した。ローマクラブとは1968年に、オリベッティ社副会長だったA・ペッチェイが元国家元首や経営者、科学者、経済学者ら世界の有識者に呼びかけ、70年に発足したグローバルな民間の研究機関である。人間の際限なき欲望の妄想を脱し、「持続可能な成長」というソフトランディングの実現を考えていくという、新たな次元の発想を提唱した。本書が刊行される2022年は、ちょうどこの『成長の限界』の報告書から50周年を迎える。この年の間に、グローバル経済はどのように変貌したのだろうか。
本書の扱うテーマ
念のために言っておくと、本書は、地球環境問題だけを扱ったものではない。グローバル金融・経済の中での日本経済の過去、現在、そして未来を論じたものである。筆者としては、本書は日本経済論という位置づけであり、カーボンニュートラルにも紙幅を割いているが、それは本書のテーマである日本経済の長期停滞からの脱却との関連で論じている。
これまでも日本の長期停滞を論じた著作は多数あり、その中には優れたものも少なくない。それでも今回、本書で日本経済論を新たに展開しようと考えたのは、経済・金融からのアプローチのみならず、グローバルな視点、歴史的な視点、政治的な視点など多角的な視点から描きたかった、という理由からである。その点を、本書の内容の紹介がてら、もう少し説明しよう。
まず、グローバルな視点というのは、単にグローバル金融危機などの日本経済への波及経路を分析した、といった話ではない。日本経済の過去30年
に及ぶ停滞は、たとえば1990年代後半以降に始まった第二次グローバリゼーション時代や第二次機械時代から甚大な影響を受けている。すなわち、ITデジタル技術の発展で、サプライチェーンの細分化と生産工程の海外移転が可能になり、収益性の高い大企業・製造業の事業所が国内から消え去ったが、それを穴埋めし、高い賃金を支払う仕事が国内では生み出されなかった。
そのことは、労働市場の二極化構造をもたらし、十分なセーフティネット(安全網)を持たない非正規雇用を増大させ、日本の長期停滞をより強固にした。その過程で、2000年代には、高齢化で膨張する社会保障給付の原資を、被用者の社会保険料の引上げで賄ったため、正規雇用の人件費がさらに割高になり、企業が非正規雇用への依存を強めた。意図せざる政策効果も働いたのである。
また、日本経済は、長年、基軸通貨であるドルの変動に翻弄されてきた。少なくとも2010年代 までは、ドル安・円高を回避することが日本銀行の隠れた責務だった。多くの人は、中国人民元やユーロの擡頭で、基軸通貨としてのドルの地位が揺らいでいると考えているが、豊かになっても安全資産をいつまでも供給できない新興国のドル国債への需要は旺盛で、ドルの基軸通貨性はむしろ増している。ただ、中国との新冷戦開始やウクライナ危機に伴うロシアへの金融制裁の発動などによって、もはや中国はドルシステムに安住することはない。新たな国際金融システムと円の未来を探るために、ドル基軸通貨体制をその誕生から歴史的に掘り下げる。
このように、本書は、グローバルな視点だけでなく、歴史的な視点も重視している。そもそも「経済成長の時代」が19世紀初頭に訪れたのは、18世紀後半の第一次機械時代の開始や、続く19世紀初頭の第一次グローバリゼーション時代の開始が背景にあった。そのとき、グローバル経済の重心は、一気に中国から欧米にシフトした。1990年代後半以降に、第二次機械時代と第二次グローバリゼーションが訪れ、1980年代に製造業の黄金時代を迎えていた日本が転落すると同時に、中国の大復活劇が始まった。
加えて、2010年代後半からAIやロボティクスによって無人工場が技術的に可能となっていたところに米中新冷戦が始まり、テレワークなどリモート・インテリジェンス(遠隔知能)技術が普及し始めていたところにコロナ禍が訪れた。これらは、製造業のリショアリングを容易にするとともに、先進国のホワイトカラー業務を人件費の安い新興国のホワイトカラーで代替する第三次グローバリゼーションをもたらす可能性がある。同時に、現代は、250年前に始まった化石燃料文明社会が臨界に達し、脱物質化社会に向かう助走期でもある。
これらの問題を分析する際、本書では、政治的な視点も重視している。すでに古代ギリシャのアテ ナイの時代から、経済格差問題は、貧者の過剰債務問題を引き起こすと同時に、市民の債務奴隷転落によって民主主義の存続を危うくした。アテナイの政治改革は、経済格差対策でもあったが、それは現代の先進国だけでなく、権威主義的資本主義体制の中国でも最重要課題となりつつある。これが習近平の不動産市場や教育産業への介入の背景である。
さらに、現在のリベラル民主主義体制は、19世紀の成長の時代に整い始め、20世紀の戦間期に完成した。これまでは、成長の時代であったがゆえに、政治がその果実を再分配することで社会の安定が保たれた。低成長時代への移行は、分配する果実の縮小を意味し、費用の分担を決めなければならないため、必然的に政治体制は脆弱化する。世代を跨(またぐ)問題の解決は、経済学が最も苦手とする分野であるため、政治学や社会学、認知心理学、生物進化学などからの知見も援用しつつ、解決策を探っていく。
以上のように、第二次機械時代と第二次グローバリゼーションは、先進国では中間層の崩壊を助長し、国内政治を不安定化させたが、同時に、それは中国の躍進をもたらし、国際政治も不安定化させた。覇権国である米国への中国の挑戦が始まり、ロシアのウクライナ侵攻もあって、すでにリベラルな国際秩序は瓦解している。極東に位置するわが国にとって、米中の確執は決定的に重要な問題だが、覇権国と擡頭国の軋轢がどのような帰結をもたらすのか、歴史的観点から論じるとともに、日本への影響についても展望する。
筆者が専門とする財政政策や金融政策についても、グローバルな視点、歴史的な視点、政治的視点を交えながら分析している。そもそも中央銀行制度は成長の時代につくられたものであり、低成長の時代にはうまく機能しなくなる。達成困難な目標を掲げ超低金利政策を固定化することが、財政規律の弛緩を含め、資源配分や所得分配を歪め、実質賃金の回復を遅らせるとともに、潜在成長率を低迷させているというのが筆者の長年の仮説である。一方で、日本銀行の金融政策は、事実上、公的債務管理に組み込まれてしまった。マクロ経済と物価の安定のためにも、長期金利の安定が不可欠となっており、本書はこの厳しい制約の中での出口戦略についても論じている。
公的債務問題については、最新の経済理論をもとに、日本のデフレ均衡の崩壊の可能性や米国債の持続可能性などについても分析しているが、これらはいずれも極力数式を使わず、言葉でのわかりやすい説明に努めた。初学者も理解可能だろう。
このように、本書では筆者の主戦場である経済学だけでなく、歴史学、政治学、社会学、認知心理学、文化人類学など多岐にわたる分野からの貢献を援用している。もともと人間、そして人間の集まりである社会を研究する学問として、19世紀末までは、文化人類学、法学、歴史学、哲学、経済学、心理学、政治学、社会学は一つのまとまった学問であった。経済学者のジャン・ティロールは『良き社会のための経済学』(村井章子訳、日本経済新聞出版社、2018年)で、再びこれらの学問は一つにまとまるべきであり、多くの学問分野が他分野の知識や技術に対して開かれた姿勢で臨む必要があることを論じている。本書も幅広い視野から、グローバル経済、そして日本経済の今後を見定めていきたいと思っている。
河野 龍太郎(こうの りゅうたろう)
1964年愛媛県生まれ。87年、横浜国立大学経済学部卒業、住友銀行(現・三井住友銀行)入行。89年、大和投資顧問(現・三井住友DSアセットマネジメント)へ移籍。97年、第一生命経済研究所へ移籍、上席主任研究員。2000年、BNPパリバ証券に移籍、経済調査本部長・チーフエコノミスト。
財務省財政制度等審議会、東日本大震災復興構想会議検討部会、資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会基本問題委員会、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会、内閣府行政刷新会議ワーキンググループなど多くの審議会で委員を務める。日経ヴェリタスの「債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」エコノミスト部門で2022年までに9回、首位に選ばれる。
主著として、『円安再生』東洋経済新報社、2003年、クルーグマン『通貨政策の経済学』共訳、東洋経済新報社、1998年、ブラインダー『金融政策の理論と実践』共訳、東洋経済新報社、1999年、『金融緩和の罠』共著、集英社、2013年がある。
***
↓本書の詳細はこちらから