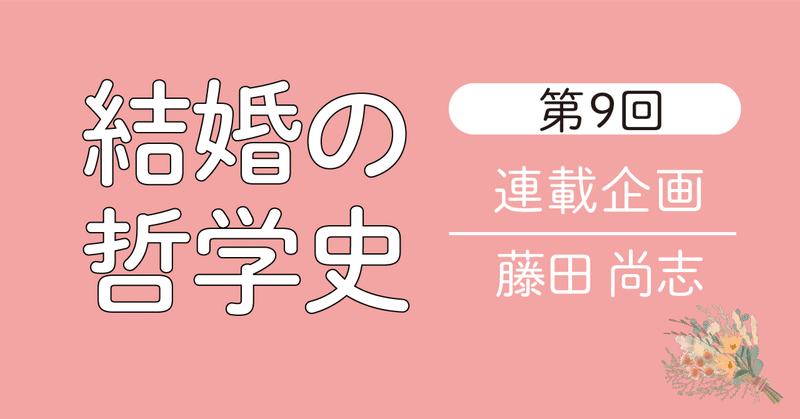
連載第9回:『結婚の哲学史』第2章フーリエ第3節 全婚と均衡遺言――『愛の新世界』を読む
結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――
九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。3回にわたって考察したフーリエも今回で最終回となります。
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
***
フーリエを笑いものにするとき、われわれが何を犠牲にしているのかを問うべきである。――福島知己
先駆的フェミニスト
Trésor de la langue françaiseやLe Robertなど定評のある辞書ですら、フーリエを「フェミニズム」という語をフランスで最初に用いた人物としているが、実際にはそうではないようである(福島 2013:717注(63))。だが、いずれにせよ『四運動の理論』で「女性の社会的地位の向上が社会発展の一般原理である」と喝破したフーリエが、フェミニスト的思考の先駆者であったという事実に変わりはない。また、ジェンダー多様性に関してもフーリエは大胆な先駆者の一人であった。彼は年老いてから自分が「サッフォー主義者」であることに気づいたと告白している。
フーリエは、彼自身が生きた当時の社会(文明世界)を、理性による抑圧によって情念が不当な仕方で歪曲された社会だと考えていた。理性によるそのような不当な抑圧から情念を解き放ち、その正確な分類に基づく「情念引力」の理解から感情の論理の全面展開を試みることこそが理想の社会(調和世界)建設の基礎となる。だとすれば、フーリエが書いたものの中に、当時の視点から見て「不道徳」と判断される記述が含まれるのは、いわば必然であろう。フーリエ主義的社会運動の実現を本気で考えた弟子たちが、当時の世論によって「猥褻」と判断される危険性のあるテクストは秘匿しようと考えたとしてもそれほど不思議ではない。なにしろボードレールとフローベール、共に1821年生まれの小説家と詩人の処女作『惡の華』と『ボヴァリー夫人』が「公衆および宗教道徳ないし良俗に対する違反」の容疑で同じように告発されたのは、フーリエの死(1837年)から20年を経た1857年のことなのである(滝澤 1983)。
『愛の新世界』は、そのように秘匿されてきた草稿群から切り出された著作である。「切り出された」という表現を選んだのは、フーリエが1817年前後に執箪したと推定される草稿群の中から、校訂者がさまざまなテクストを継ぎ接ぎし、『フーリエ全集』第7巻として1967年に初めて世に出た著作だからだ。タイトルもフーリエ自身がそれらの草稿全体に与えたものではない。だが、訳者の福島知己によれば――現在日本のフーリエ研究を牽引する存在であり、本節では彼の研究に大きく依拠することになる――、その公刊は、当時のフーリエ研究にとって一時代を画する出来事であった。これによって、「単なる経済理論家としてのフーリエではなく、人間と社会について宇宙論的視野から考察する包括的思想家としてのフーリエの存在が、一挙に明らかになった」(福島 2013:710)からである。
結婚の全面展開
福島(2013)によれば、「フーリエ研究にとって大変厄介な問題の一つ」は、フーリエの理論体系全体における「恋愛のもつ二重性」である。どういうことか。一方では、前節でも説明した通り、フーリエの情念の分類によれば、恋愛は、野心・友情・家族愛と並んで、対人関係の中で惹起される4つの感情情念の一つにすぎない。だが、他方で、とりわけ『愛の新世界』を読む限り、恋愛が他の3つの感情情念より「はるかに人々の絆をつなぐに適したもの」であり、「その至高の形態においてはほとんど「統一情念」(unitéisme)と呼ばれるすべてを統括する情念に匹敵するはたらきを持ちうる」。
もちろん私はこの問題を解決するために必要な、専門家としての十分な見識を持ち合わせないが、一つ言えるのではないかと思うのは、すべての情念がうまく制御されているなら、上記の二重性はさほど問題にならないのではないかということだ。例えば、次の一節を見てみよう。
調和世界が要求する原則とは、名誉こそがどんな情念にも優越し、恋愛でさえ名誉には一歩譲るということである。細かないちいちについては恋愛が最大の影響力を持ちうるが、全体の仕組みにおいては完璧に名誉に従属している。けれども、文明世界の恋愛では、名誉がまったく知られていない。
恋愛心は名誉心と組み合わされて、文明世界で想像される懸念とは無縁のものになっている。なぜ文明世界では、「非社交的ないし排他的な恋愛」を名誉あるものにできないのか。情念が歪曲され、「何一つとして、充分段階づけされ対照化された一連の策謀〔情事〕によって魂を高揚させるよう配置されていない」(フーリエ 2013:387)、つまりフーリエ的な弁証法がうまく作動しない状況にあるからだ。愛・性・家族に関してこのフーリエ的弁証法が十全に作動するや、結婚は全面展開されるに至る。「全婚」という様式を見てみよう。そこには両極端の二つの様式、つまり直行様式としての「無限大の恋愛の絆」と、逆行様式としての「無限小の恋愛の絆」がある。
無限大の恋愛の絆とは、入門者たちすべてを誰彼のない混乱状態にする狂宴〔乱交〕の絆である。無限小の絆とは恋愛の嗜癖による絆であり、また各々が恋愛においてもあらゆる情念においても身につけている、慣習的なまたは気まぐれにあらわれる嗜癖による絆である。調和世界はこういう気まぐれをすべて分類し、それぞれの嗜癖にふけるすべての人々をセクトに結束させるだろう。
無限大の恋愛の絆とはどこまでも関係を拡大し同一化・融合を進めていくこと、無限小とはどこまでも嗜癖を差異化し区別を増やし続けることである。このような構想は、仮にフーリエがどれほど「そこから結論を引き出し、その適用例を示す」ことをしたとしても、「きわめて滑稽に見える」であろう。また、他の三つの枢要情念(友情・家族愛・野心)については文明世界の人々は「無限大の絆」「最大の拡がりをもった絆」を望んでいるのに、「それなのになぜ彼らは、四つ目の枢要情念である恋愛についてのみ、ありうる絆のうち最小限しか認めようとしないのか。奇妙な矛盾と言うべきだろう」。彼らはどう答えるのか。
すると彼らはこう答える。「恋愛におけるそんなくだらない絆は、われわれの社会体制の基盤である排他的結婚の掟に抵触するものだ」、と。この制度のためを思って彼らは恋愛の絆の必要性を過小評価するのだが、かといって結婚の掟があらゆる意味で冒涜されているのだから、結婚のためになるものを何一つ得ているわけではないのである。
これで分かることは、フーリエの考える「愛の新世界」は決して恋愛のことだけを考えているわけではない、ということである。だからこそ、フーリエは結婚の哲学史において重要な位置を占め得るのである。
均衡遺言
フーリエの特異な結婚論の最後に、その重要な側面をもう一つ指摘しておこう。それは彼が「均衡遺言」と呼んでいるものである。福島がある論文で加えている解説に沿って(福島 2016)、フーリエが用いている架空の実例によって説明することにしよう。抽象的な定義に代えて、そのような架空の実例の提示によって説明が進んでいくのがフーリエの常套手段だからである。
全情念女アルテミスは1200万の富をもち、彼女の〔情念の〕交代についての記録によれば、しばしば8つの情念を同時にかきたてる。この結果、80歳のとき、彼女は800回の交替を経て、彼女の情念管理に服する約40の渦巻でおよそ1200人の男と600人の女を愛したことになる。(…)アルテミスは遣言でその1200万のうち300 万を、多婚愛の発現期間中に得た男女の〔彼女の〕恋人たちに遺贈する。(…)このようにして富裕なアルテミスから1800人がわずかずつ遺贈を受けるのである。今日なら6人ほどの悪辣な相続人たちが、彼女を墓へ押しやっていながら、その巨額の財産を食いものにするだろう。調和世界では恋愛なりほかの枢要情念なりのおかげで、この財産が細分化され、一群の相続人たちに遺贈されるのである。
富裕なアルテミスの遺産は、彼女の人生の中で恋愛関係にあった相手に対する感謝を形にするために配分的に遺贈される。思い出しておけば、ヘーゲルは、長子相続のような不平等な貴族的遺産相続に対して、均等相続を主張したのだった。だが、それはあくまでも個人に立脚した限定的な近代家族内の平等にすぎない。フーリエが考えているのは、宇宙的な規模と言って言い過ぎなら、近代家族の枠をはるかに超えた規模での平等である。調和世界では文明世界よりはるかに豊かな人間関係が育まれるので、必然的に感謝を捧げる相手も多くなり、その分遺贈する人数も増えるのだ。翻って文明世界の相続は、「人間を人間全体との戦争状態に置き、各々の家族を他のすべての家族のひそかな敵にする」(フーリエ 2013:333)ものだ。まさにヘーゲル的な相続の限界を示してはいないだろうか。
だが、ここで正確を期しておけば、フーリエの考える調和世界にあっても貧富の差は存在するのであり、みんながアルテミスのように富裕なわけではない。これもまたフーリエのきわめて独創的なところで、大塚(1990)によれば、彼の構想した「ファランジュ」という共同社会では、経済的不平等が不可欠とされ、その格差は大きければ大きいほど良いとされる。なぜか。それは、富裕階級が資産ないし所得の一部を貧困階級に贈与することを、フーリエはファランジュの分配の要と考えたからである。この贈与が貧困層の富裕層に対する不満を解消するばかりか、感謝に満ちた熱狂を喚起し、労働意欲すら掻き立てるというのだ(大塚 1990:108)。私たちが「そんなことはありえない」と考えるのは、情念が歪曲され、所有に対する嫉妬という形をとってしまうからである。フーリエはこんな例を挙げている。
全情念男イルスはびた一文も資産をもっていないが、80歳のとき、恋愛において多婚をいとなんでいたということのみのおかげで、すでに受けとったものとこれから受けとる予定のものあわせて1000人に及ぼうかというほどの、大勢からの遺贈を受けるだろう。前述のように、富裕のまま死んでいくすべての人々が、多婚愛発現期間中に恋人だった者たちへいくらかずつ財産を残すからである。
フーリエはこのとき形成される感謝の念を「幻想」と呼ぶが、こうして他者から到来した「幻想」を通じて人々が結びつき、「大きな家族」(フーリエ 2013:333)が生まれる。ヘーゲルの近代的な核家族が、近代以前的(貴族的)な大家族の否定として、個人間の葛藤を通じて形成されるのに対し、フーリエの超近代的(調和世界的)家族は、まさにヘーゲル的な近代的核家族の拡大・包摂として、葛藤(嫉妬)を先回りによって回避し肯定的情念(感謝という「幻想」)によって形成される。調和世界では財産の不平等を前提としつつ、「均衡遺言」によって、単なる博愛的な慈善では決して生じないような人々の熱狂的な社会的結合が生じている。
この均衡遺言に関して福島(2016)は興味深く独創的な指摘を二つしている。一つは、均衡遺言とアフリカのアンズィク族の一見残虐な食人行為(生に飽きて自死する人間が生前自分の肉を死後譲渡する相手を複数選び、遺贈された近親者・友人がそれらを食する)のあいだに、「自分の持ち物を差し出すという点で変わりはない」という共通点を見出すところである。アンズィク族の食人は自分と受贈者、そして受贈者同士の(食人という行為を介しての)共同性を現出させている。
もう一つの指摘は、男子同性愛、姦通、タヒチ人の自由恋愛というこれまた一見雑多な例の羅列に見えるものがそれぞれ、「多婚」によって開かれる世界を垣間見せており、「破廉恥極まりなく見える多婚の奨励は、数多くの元恋人たちへの遺贈を実現させ、受贈者の感謝の念を掻き立てて、同様に共同性を現出させる」というものである。多婚は、単なる乱倫ではない。なぜならそれは恋愛の暴走でもなければ、単なる性欲の解消でもないからだ。もう一度思い出そう。調和世界ではすべての情念が十全な発展を遂げるように仕向けられている。一つの関係の終わりは、愛が憎しみに取って代わられるということを意味せず、むしろより豊かな愛・性・家族の経験へと拡大・包摂されることを意味する。
結婚の創造的進化?
本章では、19世紀の異形の思想家シャルル・フーリエの『愛の新世界』という実に独創的な本に注目し、そこに見なれない家族の風景、しかし歴史上まったく存在しなかったわけではない家族の風景、つまり三人以上の結婚またはパートナーシップ、序論で紹介したエリザベス・ブレイクなら「最小結婚」に含めるかもしれないものの原型を見て取ることを試みた。簡単に要約すれば、フーリエによれば、今まで人間は理性的に文明を基盤として、情念を抑えつけて道徳的な生活を送っていこうとしてきたが、それは間違いである。情念を抑圧するのではなく、むしろ情念の本性を厳密に分析し、“情念の論理”に即した調和的な社会を作っていく方がより合理的だ、と。つまり発想を逆転させるわけだ。例えば、彼の言う12 の「根本情念」の中に「蝶々情念」がある。これは、蝶々が花から花に移っていくような「移ろいやすい」「移り気」な情念で、我慢強く一つのことに専念することが美徳とされる現在の文明社会では否定的に捉えられているわけだが、しかし考えてみれば、人間は大なり小なり蝶々情念を持って生まれてきているのだから、それを理性的に抑圧して枠にはめるのは土台無理な話で、どこかで無理がくる。だとしたら、蝶々情念を強く持っている人に関しては、別の労働形態、別の社会的結合形態を考えた方がいい。結婚は、現状の社会においては一夫一婦制だが、これが果たしてすべての人にとって適合的なのか、“情念の論理”に即した調和的なシステムを再構築する必要がある、とフーリエは言うわけだ。「〔恋愛の〕多数性は今日では互いの裏切りの結果でしかないから、文明世界は心情愛を標榜してはいるものの、率直かつあたうかぎりの友情を抱いているときにも多数性に到達できるとは、どうしても思い至らないのである」(フーリエ 2013 : 387)。
結婚を一つではなくて、複数の型で考えることができるとすれば、つまり二人でいたい人は二人でいていいし、一人でいたい人は一人でいていいし、三人以上でいたい人は三人以上で“結婚”してもいい、というような制度は可能であろうか。カウンターカルチャーが隆盛した1960年代後半から1970年代初頭にかけての性革命の時代、アメリカの社会学者オニール夫妻が『オープン・マリッジ』(1973年)――『アンチ・オイディプス』の出版は1972年である――を出版、150万部以上の大ベストセラーになった。オープンマリッジ(開放型結婚)とは、インモラルなフリーセックス主義ではなく、夫婦が互いを社会的・性的に独立した個人として認め合い、所有欲や独占欲、嫉妬心に妨げられず、合意の上で自由に愛人を作る結婚スタイルである。
また近年、このオープン・マリッジやグループ・マリッジ、トライアッドなどを包括したより広範な関係性として、ポリアモリーが注目されている(深海 2015 ; 坂爪 2015)。ラテン語のpoly(多くの)とamor(愛)の合成語で表現されるこの関係性は、浮気や二股とも不倫とも違う多様な愛の形である。その第一の特徴は、交際状況をオープンにし、複数の人を誠実に嘘偽りなく愛することである。これは、一対一の愛だけが正しいわけではなく、愛する人の人数は自分の意思で決めるべきだという考えに由来する。第二の特徴は、互いに互いを所有しないということである。パートナーになることは、相手のすべてを独占所有することではない。むしろ所有や束縛は、互いの成長を邪魔することすらある。そうではなく、感情的にも身体的にも深く持続的にかかわる関係を目指し、自然発生的で無自覚的な家族ではなく、いわば自覚的・選択的に選びとった家族(family-by-choice)を目指す。その背後には、家族は所与のものではなく意識的に築いていくものだという考えがある。メリットはこのように、①乳兄弟や血を分けた兄弟ならぬ「水兄弟・姉妹」(同じコップから水を飲む、同じ理念を共有する者同士)の存在による血縁関係を超えた協力体制が構築できること(少子化で血縁関係が細っている現状では有効な打開策である)、②モノガミー的関係以上にコミュニケーション重視、③意識的な家族づくり(後者二点は、社会的多数性・制度的安定性のうえに胡坐をかいたモノガミーでは、むしろ往々にして蔑ろにされがちである)などがある。これに対して、デメリットは、①複雑な家族関係・出産・養育、②複雑な金銭関係、③複雑な老後の生活であるが、これらはいずれも従来のモノガミー的な関係性においてもすでに問題となってきたことであり、ポリアモリーのみに発生する問題ではない。
分人主義の先駆者としてのフーリエ
私は前回こんな風に話を終えていた。《共同体「ファランジュ」において、契約・所有・個人の概念は完全に放棄されるのではなく脱構築され、結婚は大きく形を変える。すなわち結婚は、多夫多妻制である「多婚」あるいはその究極形態である「全婚」にまで拡大され、一夫一婦制はその中に吸収されていく。私たちが特に注視したいと考えているのは、そこに見られる人間観の変容である。》最後にこの点に触れてこの章を閉じることにしよう。
フーリエが見通していた社会は、ユートピア、理想郷なのか。そうではなく、むしろ冷徹に未来社会を見通していたのではないか。フーリエとドゥルーズということですぐに念頭に思い浮かべられるのは、『アンチ・オイディプス』における記述であろう。「欲望の流れの接続と切断」に強調点が置かれ、個人性・個体性が限りなく弱められた記述が特徴的だ。だが、今回強調しておきたいのは、個人性・個体性の消去でも、その代わりとなりうる非人称性や個体化プロセスの強調でもない。むしろ個人性・個体性に代わる「分人性」という概念の案出に、フーリエとドゥルーズをつなぐ連関を見たいのである(「分人」概念自体については、ドゥルーズについて論じる際に詳しく見ることにしよう)。この点に関して、ドゥルーズの「分人」概念とフーリエの「全情念者」概念を接続しつつ、現代社会における愛・性・家族に関して考察を深めようとすることは、決して無意味でも単純にユートピア的でもないのではないか。
原則とはすなわち、すでに述べたように、超越愛と排他的恋愛が代わる代わる営まれる、ということである。調和世界には、いつでも多婚的だとか、いつでも全婚的だという者がいるわけではないし、第11節で述べたような複合セラドン愛に絶えず身を捧げている者がいるわけでもない。排他的な利己主義愛を営む時期が誰にでもあるからである。それは社会的な休眠状態と見なされているのだ。だから私はファクマに、累進超越愛に身を置く以前に、テムガン・ハンとの排他的恋愛、利己主義愛を割り当てたのである。日がまた昇り同じ月がまた来るようにして新秩序の恋愛も経巡り、一致、配合ないし超越様式と不一致、利己主義、排他様式とを、定期的に行き来するのである。排他的恋愛とはある意味で、魂が大規模な行動ないし偉業を成し遂げる合間に行なわれる休憩、気分転換であり、恋愛のもつ社交的特質が睡眠をとっている状態なのである。
私たちがこのようなフーリエ的人間観に「分人性」を見て取るのは誤りなのか。この点を詳しく検討をするという作業は別の機会に委ねることにして、ここでは先の福島論文から次の一節を引いて満足することにしよう。
ところで、均衡遺言は一生の中で経験した情念の発露をもとにして、その総計で財産の総額を分割している。とすれば、分割されているのは財産だけではなく、その人の人生そのものであるとも言えないだろうか。もっと言えば、ここで行なわれているのは単なる財の贈与ではなく、自己自身を分割し、分有すべきものとして捧げているということではないだろうか。個人が情念の束として見られているというばかりか、時間の要素が加味され、一生に経験した「恋愛交替」(フーリエ 2013:335)に沿って分割されるのである。もはや個人が単位ではなくなり、その時々に発露した情念に沿って切り刻まれ、分け与えられている。しかしそれは主体に加えられた暴力ではなく、むしろその対蹠なのである。
***
後年捏造された逸話かもしれないが、晩年のフーリエは、自説の正しさをあまりにも確信していたので、面会時間として指定していた正午には毎日何があっても帰宅し、得られるはずもない財政支援の申し出をじっと待ち続けていたという(福島 2013:676)。フーリエ的な結婚の脱構築の壮大な帰結を見届けるには二百年程度ではまったく足りない。
次回:4月5日(金)更新予定
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #フーリエ #ドゥルーズ #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
