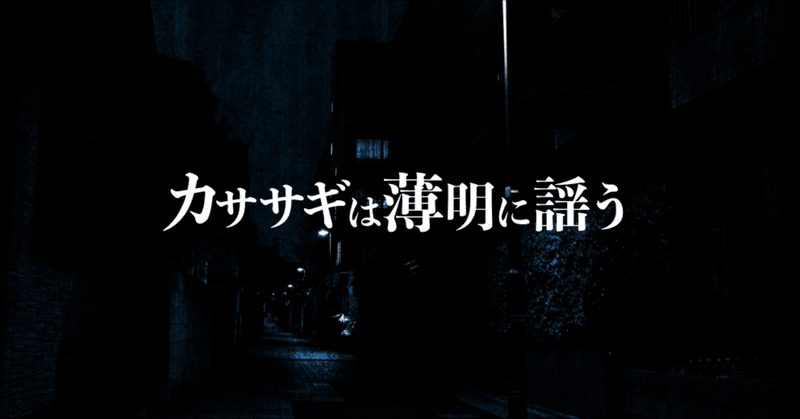
カササギは薄明に謡う 【7,8】
全21シークエンスを11日間にわけて連載します。
<2,700文字・読むのにかかる時間:6分>
【7】
未舗装の道路に入り、使われなくなったビニールハウスの脇に車を隠した。頭上まで木の葉が覆うような深い森が背後に迫っている。U字型の小さな水路が足元を流れていて、そこにコンクリートの蓋が被せてある。俺はそれを通路として使い、田畑の間を縫うようにして中心地に出た。瑠華とヒロトは車に残してある。つまり偵察だ。
巻いたノインシュヴァンツ・パイチェを右手で握り、身を低くして移動する。ヤツらとヤツら、どちらとも遭遇したくはない。
村営の給油所だったのだろうか。ブロック塀に囲まれたL字型の区画に、燃油タンクが設置してある。錆がひどく、使われていないのは一目瞭然だ。俺はそのタンクの隙間に身を潜ませて、ブロック塀から顔を出した。
そこはもう村役場跡地だ。73式トラックが二台しかない。残りは封鎖に出ているのだろう。
「予定より少し遅れたか」
聞き覚えのある声がする。
「ヘリで先着した部隊からは、検問と接触した対象者はいないとのことです」
「そうか。なら騒ぎはこれからか」
「はっ。深夜だったことが幸いしました」
あの眼鏡ヅラは名取二佐だ。相変わらずいけ好かない。上官のゴリラ群長の姿は見えないが、あっちのほうがまだ人間味がある。
「あいつらは侵入してないだろうな」
「巽一派ですか」
「一派か。まぁ、ふたりだがな。巽天外(たつみてんがい)と神流瑠華(かんなるか)」
「少なくとも先着部隊から目撃報告はありません」
名取二佐が頷くと、隊員は敬礼して去っていった。
こいつらは陸上自衛隊に所属する特殊部隊のひとつだ。大層にも特殊奇禍即応群などという名前がついている。Special Disaster Immediate Rescue teamの頭文字をとって、SDIRと自称している。特に笑えないのは、Rescueという言葉を選んでいることだ。
ヤツらは俺たちに仕事を邪魔されていると思っている。もちろん、こちらもそう思っているわけだが。要するに相性が悪いのだ。
一台の軽自動車が県道をやってきた。道幅を考えればスピードを出しすぎている。すぐさま隊員たちが停車させ、照明を浴びせる。運転手は手のひらで眩しすぎるライトを遮りながら、ドアウィンドウを開いた。
「どうされましたか?」
隊員が、拍子抜けするほどの優しい声で尋ねる。
「救急へ運ぶんです。息子の様子が……あの、おかしくて!」
日に焼けた肌の、白髪混じりのその女性は、縋りつきたいのを我慢しているという体だった。運転席の後ろになにかが見える。元は人間の手だろうか。遠目にも、すでに変わってしまったことが見てとれた。
後部座席を一瞬だけ覗き込んだ隊員は、すぐさま距離を取って同僚たちへ合図を送る。
「黒い粉末(ブラックトナー)の影響対象一体。影響可能性対象一体。計二体です」
一同はヘルメットから特殊奇禍用シールドを降ろし、20式自動小銃を構えた。
通常弾が一発。フロントガラスを貫いて、女性の眉間に着弾した。
続いて、白銀弾が十五発。後部ドアを串刺しにしつつ、中身に命中した。たちまち車内に黒い粉末が満ちる。弾痕から漏れ出るそれに触れないよう、隊員たちは距離を取った。直後に消化剤のような白い泡が撒かれ、一連の作業は終わった。
「お次は徒歩だぞ」
誰かが言う。
見れば、川沿いの県道を走ってくる人の姿がある。今にも転びそうなほど前のめりだ。その後ろから二人。さらにそれを追っているのは……。
「影響可能性対象三体接近中。その後背に影響対象一体を確認」
SDIRの隊員たちは、再びシールドを下ろし、銃を構えた。
気がつけば、東の山あいからも、西の川沿いからも、銃声が聞こえている。
【8】
災害というものは大きく二つに分けられる。空からやってくるものと、地中からやってくるものだ。俺たちが相手にしている災害は、後者に分類される。
地球の内部がどうなっているのか、俺には見当もつかないし、あまり興味もない。ただ、地表に出ているものしか、俺たちは見ることができない。地中にあるものは推測や想像することしかできないわけだ。だから俺は目の前で起きていることを信じている。
この災害は、小さくは二十年周期で起きることがわかっている。そして二百年周期で大規模なものが発生する。さらには千二百年周期で極端な活動期がやってくる。
前回の極端な活動期は、貞観だ。時代でいうなら平安時代。西暦でいうなら9世紀後半。この貞観期に地中から噴き出したものは枚挙に遑がない。まず富士山が大噴火を起こし、流れ出した溶岩が森林をことごとく焼き払ったあげく、北岸の湖をほとんど埋めてしまった。播磨国地震で近畿地方がダメージを受けた翌年、三陸沖で尋常でない規模の海溝型地震が起こり、東北の太平洋岸が津波に襲われ、壊滅的な打撃を受けている。さらに鳥海山、開聞岳の噴火が続く。京都では地中から這い出した魑魅魍魎が列をなして練り歩き、遭遇した人間を次々に喰らっていった。今昔物語集には、鬼や妖怪として記述されているが、そいつらは紫紺の繊維の塊だ。
「つまり、神社で待ち伏せしてた、あれってこと?」
「そういうことだ」
だいぶ稜線がはっきりしてきた。夜明けが近づいている。
「あれが、地中から出てきたの?」
「あのまま這い上がってくるわけじゃない。溶岩が吹き出すみたいに、黒い粉末が地中から湧いてくるんだ。そいつが手当たり次第に人間を飲み込んでしまう。そして間接的にヤツらが生み出される」
瑠華は後部座席で寝息を立てている。彼女には、いまのうちに睡眠を取っておいてもらったほうがいいのだ。
「千二百年周期の活動期……」
助手席のヒロトは指を折って数えている。
「え? ひょっとして、貞観から千二百年って……」
「そうだよ。今だ」
ヒロトの視線が俺を射抜く。この少年は頭がいい。
「君はまだ幼かったろうが、日本列島は2011年から、その極端な活動期に入った。地震に噴火。貞観の頃と同じってことは、つまりそれだけじゃない」
「地中からなにかが這い出してきている」
「そういうことだ。実を言うと頻発している。この集落で起きていることは、別の場所でもう何回も起きたし、これからはもっと増える。表向きにはなにも報道されないがね」
ヒロトは短パンから伸びる膝のあたりを、両手でさすっている。
「家。大丈夫かな」
「家族は何人だ?」
「姉ちゃんと、親父と、母さんが家にいる」
「……そうか」
俺は本当のことを言いそうになり、やめた。
「無事を確かめに行こう」
過去、この災害に見舞われた住民が無事だった試しがない。それはつまり、黒い粉末によって人の姿を失うか、SDIRに人の姿のまま射殺され、焼却されるかのどちらかだからだ。
「行けるの?」
「陽が昇れば、ヤツらは活動しない」
ちょうど、稜線から太陽が顔を出したところだった。
この作品は、第2回逆噴射小説大賞にエントリーした「夜明けにカササギが鳴いたら」を改題し、中編に仕上げたものです。
電子書籍の表紙制作費などに充てさせていただきます(・∀・)
