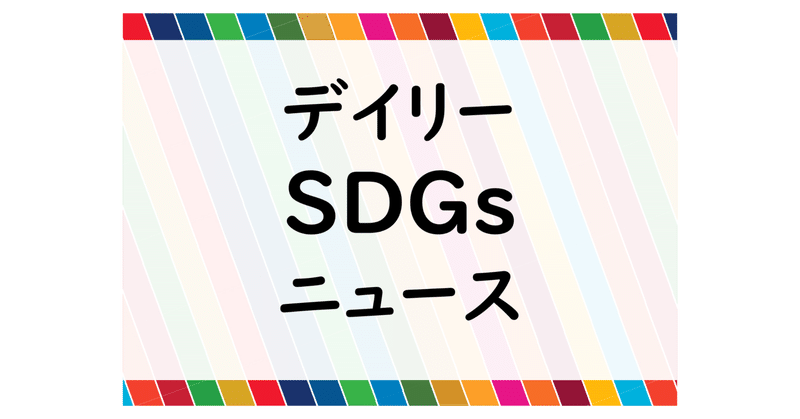
20240310SDGsニュース
「反ESG」などの動きを超えて深化するサステナブル投資、ミローバCIOに聞く世界のESG投資
米SEC、上場企業に気候リスク・排出量開示義務 経済団体反発
「作文業務」と化したコード対応の見直しへ 大転換を予想させる英国スチュワードシップ・コード改訂の問題意識
※「水は低きに流れる」となるのか、それが企業にとって本当によいことなのか、♪よ~く考えよう~。
金融庁が「インパクト投資」普及に本腰、カギは"慈善色"払拭 岸田政権の下で重要施策の1つ
※昔(半世紀以上前)、公害対策基本法の「経済調和条項」をめぐる議論がありました。生活環境の保全を目的とする法律(今の環境基本法の前身)ですが、それには当初、「経済の健全な発展との調和が図られるようにする」という条件がついていたのです。生活環境の保全はけっこうですが、経済の健全な発展を阻害しそうだったら、だめよ、ということですね。バッティングする場合、どっちが優先されるのかといえば、結局のところ経済、という考え方。1970年の公害国会で削除されたわけですが、この「経済調和」論法は、今も、脈々と深々と残っています。「SDGsはけっこうだが、それにいれあげるばかりに会社がつぶれてしまっては、元も子もないだろう」「ESGはけっこうだが、利益を犠牲にしてまでやることか」といった感じですね。「環境か経済か」「非財務か財務か」「インパクトか利益か」、要するに「あれか、これか」のトレードオフの立論自体に、構造的に、「経済調和」論法が含まれているのです。これを「OR」(か)の思想とすると、オルタナティブとなるのは、「WITH」(で)や「Through」(通じて)の思想となります。ここの切り替えができていないまま「社会課題の解決と収益性の両立」なんて言っていると、いつのまにか「と」ではなく「か」の議論になってしまうのです。
コメンテーター紹介
サステイナブル歴30年+4年目の眼
サステイナビリティ推進部に配属されたら最初に見る動画
新たに定義される中堅企業(2000人以下の上場・非上場)のサステイナビリティ推進部署の責任者や担当者に「なっちゃった」(けど、右も左もわかりませんと途方に暮れている)方向けです。辞令が出たら、配属される前に予習しておきましょう!
しばらく経つけど、実務に追われて全体像がよくわかならないんだよね、という方も、アタマの整理にちょうどよいです(ただし、詳細・専門的な知識・ノウハウではないので、ご注意)。
リリース記念で、人数・期間限定キャンペーン(50%OFF)実施中です。
SDGs/ESG/脱炭素について勉強するならこの本で
新版は、環境省認定「脱炭素アドバイザー ベーシック」対応となりました。このたび環境省の認定がおり、問題集は10月6日販売開始となります。
1回目:キーワード解説集として読む。基本的に、1キーワード3論点でまとめてあります。問題は解かずに、解説を読んで内容を理解する。それから、「どこを問題にしたのかな?」と問題文の選択肢と、解説文を見比べる。そして、不正解肢はどれで、解説文のどこをどう変えたかを確認する。
2回目:知識の定着度を確認するために、問題を解いてみる。そのときに、1回目の思考のプロセスを思い出す。
3回目~:実際に銀行業務検定試験を受ける方は、全問正解になるまで繰り返す。
