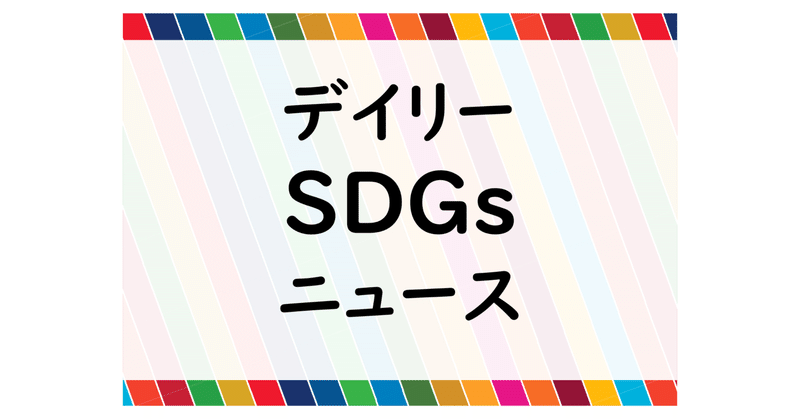
20240523SDGsニュース
再資源化促進へ新法成立 国が計画認定すれば手続き省略
※5/22までパブコメにかかっていた循環社会基本計画案を推進する目玉法案でした。再資源化施設は、基本的に廃棄物処理施設として都道府県知事・政令市長の設置許可を受けなければなりませんが、それを国が認めた計画については不要にしてしまうという荒業です。ちなみに、循環社会基本計画案をみると、2010年代、入り口側の循環利用率(投入資源に対する循環資源の割合)、出口側の循環利用率(排出量に対する循環利用の割合)が、ともに停滞していたっことがわかります。そこを打破したいわけです。しかし実は、循環「型社会」というコンセプト自体が、循環経済との矛盾をはらんでいます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273647
パリ五輪、循環型経済戦略の最初の成果を発表
※オリパラの持続可能な調達は、2012年ロンドンから始まり、2016リオ、2020東京、そして2024パリへとつながっています。「本大会では五輪史上初めて、大会で使われる全資源の総重量などを表す「マテリアルフットプリント」を計算し、必要とされた資源の詳細なマップを会場ごとに作成しています。」だそうで、これはなかなか大変な作業です。大阪万博ではやらないのかな?というか、パビリオンがどうなるかわからないから、まだ計算できないですね。リリースの原題は"circular economy strategy"なので、循環「型」経済ではなく、循環経済とすべきところ。
金融庁、主要国のサステナビリティ情報の開示・保証について報告書を発表
※すでにこの調査結果に基づいて、時価総額3兆円以上プライム企業から・早くて2027年度~の強制適用の議論が行われています。3兆円→1兆円→すべてのプライム企業に適用は、203X年とされています。0≦X≦9ですから、最遅(X=9)の場合は2039年となります、15年後!まあ、そんなことはないでしょうし、もしかしたら「3」が「2」に前倒しになるかも?という可能性もまだあるのかな、とは思います。今年度1年の議論で、明確になるでしょう。
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20240417/01.pdf
GSG国内諮問委員会「インパクト企業の資本市場における情報開示及び対話のためのガイダンス第1版」発行。関係者による建設的な対話促す
※投資家によるエンゲージメント(対話)が企業のESG促進に一定程度有効という記事は先日紹介しましたが、インパクト投資においても重要でしょう。
令和6年度SDGs債発行支援事業の開始について
※発行体ではなくて支援者(評価機関)が補助されるスキームにしたのは、なぜでしょう。直接、評価機関から報告徴収させるため?
コメンテーター紹介
サステイナブル歴30年+4年目の眼
https://note.com/keieinavi/n/n3c95efd59282
サステイナビリティ経営の「時短」学習コースを開設しました!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000087340.html
サステイナビリティ経営の全体像を一気につかむための「ファストパス」を、この分野でキャリア34年の講師がご用意しました!
①「サステイナビリティ経営の見取図2024」は、サステイナビリティ経営推進部署に新たに配属された責任者・担当者の方(上場企業・中堅企業を想定)向けの動画です。
②「サステイナビリティ経営基礎研修2024」は、サステイナビリティ経営を初歩から学びたいビジネスパーソン(上場企業・中堅企業社員を想定)向けの動画です。
リリース記念で、人数・期間限定キャンペーン実施中です。
SDGs/ESG/脱炭素について勉強するならこの本で
https://www.khk.co.jp/book/book_detail.php?pid=54236
新版は、環境省認定「脱炭素アドバイザー ベーシック」対応となりました。このたび環境省の認定がおり、問題集は10月6日販売開始となります。
1回目:キーワード解説集として読む。基本的に、1キーワード3論点でまとめてあります。問題は解かずに、解説を読んで内容を理解する。それから、「どこを問題にしたのかな?」と問題文の選択肢と、解説文を見比べる。そして、不正解肢はどれで、解説文のどこをどう変えたかを確認する。
2回目:知識の定着度を確認するために、問題を解いてみる。そのときに、1回目の思考のプロセスを思い出す。
3回目~:実際に銀行業務検定試験を受ける方は、全問正解になるまで繰り返す。
