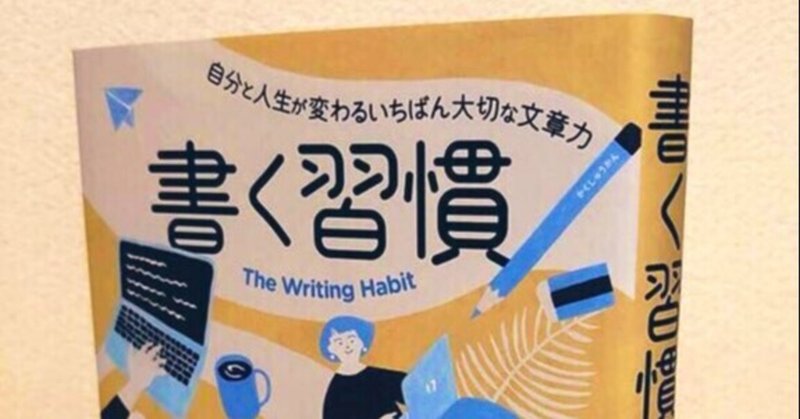
誰もが生きるために、書いていい
はじめまして。
クロスメディア・パブリッシングという出版社でビジネス書の編集をしている石井といいます。
日々、様々な原稿を拝見し、感想を述べたり、アドバイスをしたりしていますが、自分で文章を書くのは苦手です。
だから、こんなありきたりな書き出しになっていたります。
そんな私が今回、はじめてnoteを書いてみたのは、『書く習慣』という本をつくったからです。
この本は、美文や名文の書き方を教えるのではなく、「書く」こと自体の素晴らしさと、「さあ、あなたも書いてみよう」と伝える本です。
発刊以降、たくさんの方から感想をいただき、おかげさまで重版にもなりました。
それ以上に驚いたのが、実際にたくさんの方が「書く」を始めてくれたことです。
Twitterで「#書く習慣」「#1ヶ月書くチャレンジ」で検索してもらうと、
みなさんの文章がいくつも見つかります(その数は100を超えたそうです!)
でも、そんな本をつくった編集者が書いてなきゃ嘘だ。
だから今回、書きました。
ということで、この本を企画したときのことを書いてみようと思います。
企画の発端は、単純に「文章に関する本をつくりたいな」と思ったことでした。
私の前職の出版社では『文章力が身につく本』という、それはもう素晴らしい、文章術のバイブルといえるような本を出していました。
他にも、素晴らしいノウハウを教えてくれる文章術は山のようにあります。
そんな本をみて、「あれ、もうノウハウやテクニックの本て、いらないんじゃね?」と、なかば諦めみたいな気持ちになり、そこからしだいに、「いやいや、いくらテクニックを学んでも、実際に書かなきゃ身につかないでしょ」と、今度は皮肉めいたことを考えるようになりました。
でも、これが意外と真理かもという気もしてきました。
私は仕事がらたくさんの文章に触れているため、学んだ文章術はすぐに実践できます。
でも一般の方って、普段そんなに文章を書く機会ってあるのだろうか。
ないなら、まず「書く」機会をつくってもらはないといけないな。
そして書いてもらうためには、「書く」ことを好きになってもらはないとな。
そもそも、どんなにテクニックを身につけても、書くのがすきじゃなかったら、しんどいよな。
こんな形で、この本のコンセプトが決まりました。
そこで次は著者さん探しになるわけですが、「書くのを好きになる方法」なんて、いったい誰がかけるんだろう。あてもありませんでした。
そこで単純な私は、googleで「書く 好きになる 方法」みたいなことを検索しました。
すると、まさかのドンピシャな記事が見つかりました。
それが、いしかわゆきさん(ゆぴさん)の「”書く”が好きになる文章マガジン」でした。
それをきっかけにゆぴさんの文章を読んでみると、どの文章も素の言葉で綴られていて、しかも帰り道の10分程度で書いているそう。
「そうそう、書くのってこれくらいラフでいいんだよな」と思い、ゆぴさんに執筆オファーしました。
そう、この本のはじまりからして、ゆぴさんが自分のために書いた「文章」が発端になっていました。
そこから時は流れて実際に執筆に入ったあとも、
ゆぴさんの独特の軽さのある文章を良さを殺さないように編集しました。
このミネラルウォーターのように抵抗なく脳に入ってくる文章を、どう伝えるのが良いのか。
そればかり考えていたような気がします。
よくあるビジネス書って、最初に結論(主張)がきて、そのあとで説明がくる。
でもゆぴさんの文章は、あくまで読者と同じ目線で文章が流れていき、ふとした瞬間に、確信めいた言葉がポンっと現れる。
だから、立ち読みした人にもその確信めいた言葉が目に留まるように、そこだけいきなり大きくしてみました。
乾いた喉を水が流れていくようにスルスル読み進められるよう、会社に内緒で、ページをめくりやすい特別な製本にしました。
イラストについてもこだわりたいと思い、前々からいつかお願いしたいと思っていたイラストレーターの芦野公平さんに声をかけました。
芦野さんは私の「自分が書いた文章から、未来が開けていくようなイメージ」というあまりにも抽象的なオーダーを見事に表現し、素晴らしい表紙イラストを描いてくれました。
それも、著者のことを独自にリサーチしてくれて、著者にまつわるアイテムや、「17」の文字をイラスト中に散りばめてくれました。
なんて素敵な方なのだろうと、その心遣いとプロ意識に感動したのを覚えています。
ほかにも、本は読むだけじゃ意味がなくて、実践して、実際に書いてみてもらはないと、この本は完成しないよなと思い、巻末には「書きたくなるような30のテーマ」も入れてみました。
原稿に追われるなかでテーマを考えてくれたゆぴさんには感謝しかありません。
とまあ、書籍制作において感じたことや考えたことを書いたわけですが、とくにオチはありません。
構成も考えていないし、ほぼ走り書きです。
でも、それでいい。
忘れっぽい自分が、そのときに何を考えていたのか、それを忘れないために書いておく。
それくらいの気持ちでいいんだと、『書く習慣』という本は教えてくれました。
最後に余談ですが、この本を企画した当初、妻に「今度こんな本をつくろうと思うんだけど、君はとくに何も書いてないから相談してもだめかな?」と聞いてみました。
すると、なんと妻は一時期noteを書いていたと言いました。
ちらっと見せてくれると、そこには誰にも言えない日常の愚痴を書いていました。
私への不満も含めて、誰に見せるでもなく、匿名で書き留めていました。
きっと、それで自分の気持ちを落ち着けていたんだと思います。
そのとき、「書くって、別にライターさんや作家さんなどの専門家だけがやることじゃなくて、誰もが生活の一部として、生きるためにやっていいことなんだな」と感じました。
書くのって素敵なことだから、みんなにやってもらいたい。
この本が、そのための助けになれば嬉しいです。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
