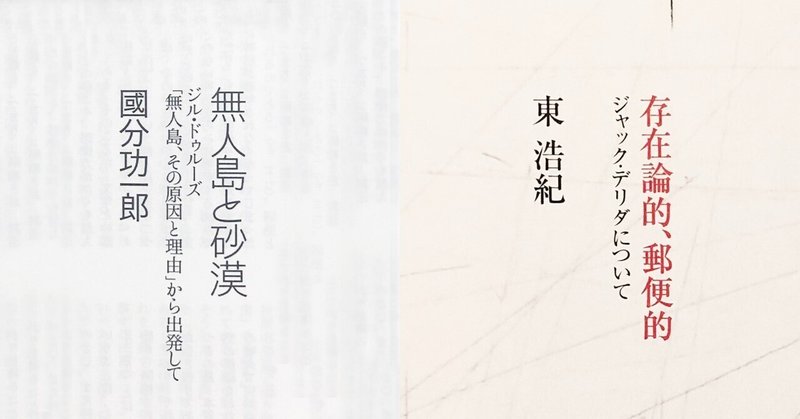
知覚のシステム図を作成してみるー『存在論的、郵便的』を下敷きに「無人島と砂漠」を読んでみた
はじめに
前回に引き続き國分功一郎「無人島と砂漠 ジル・ドゥルーズ『無人島、その原因と理由』から出発して」(『批評空間』第3期第4号 2002年、以下「無人島と砂漠」)を読みます。
私たちは巨大な謎という沼から抜け出して、明るく晴れた無人島の海辺(千葉雅也)、または砂漠(浅田彰)を目指す。その無人島の海辺と砂漠はそれぞれどんなところで、どんな違いがあるのかという謎を追いかけました。そしてこの二語(無人島の海辺と砂漠)ともドゥルーズのdésertを翻訳したものらしいということがわかりました。ではこの二語に違いはないのでしょうか。國分は「無人島」の陥穽を「砂漠」がうち砕くといいます。つまり少なくとも「無人島」と「砂漠」には違いがあることになります。今回はこの謎に迫ります。
参考書に東浩紀『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』(新潮社 1998年、以下『存在論的、郵便的』)を使います。「無人島と砂漠」『存在論的、郵便的』ともに、ポスト構造主義の哲学者が考える人間の知覚の仕様を記述しようとしている点でとても似ているので、互いが互いを理解する助けになるのではないかと考えました。
まずは「無人島と砂漠」のエッセンスを抜き出します。
陸島と洋島の二層構造
ここでいう無人島とは地理的な無人島のことではなく、想像力における無人島のことです。そして島には二種類あります。陸島と洋島です。陸島は地殻変動などによって大陸から分断されて生じた「派生的で二次的な」島、洋島は海底の地盤が変動を蒙って海上に出現して生じた「起源的で一次的な」島。そして想像力はこの二つを「往復する」といいます。
可能世界
私たちは対象全体を見ることができません。たとえば後頭部を直接見ることができません。それにも関わらず全体を想定できるのは、見えていない部分を他者が見ているはずという信仰があるからです。つまり他者とは可能世界の別名のことです。
知覚領域全体=現実世界+可能世界
となります。
そして時間について注意喚起されます。
最初に自我があり、そこに他者が現れて両者の関係という構造が出来上がり、対象の知覚が可能になったと考えてはならない。自我と他者と構造は同時に生成する。他者は可能世界、自我は過去の世界のことだといいます。自我とは再帰的にメタレベルから自分と環境を捉えることだと考えれば、確かに過去の世界と言えそうです。
他者がいないとどうなるか。そこは知覚も構造も自我もない暗い世界となり、カントのいう悟性、ラカンのいう象徴界(言語・規則の世界)、いわば人間に実装されている知覚システムがクラッシュしてしまいます。しかしおそらく現在とは異なるしかたで知覚はできます。カントの感性、ラカンの想像界(イメージ・自然の征服の世界)が機能しているからです。しかしその知覚は動物としてのヒトの知覚です。そこには人間はいません。ヒトは主語にはなり得ず、無人島そのものになるといいます。無人島の「無人」(désert)とは人間がいないことを意味しています。たとえ多くのヒトがいても「無人」(désert)なのです。
言語とイメージと時間
言語・規則の世界は差異の世界なので一気に与えられなければなりません。AはBではない、BはCではない、CはDではない、以下同様。一方イメージ・自然の征服の世界は部分から部分へ知覚されていきます。自然は少しずつ開拓されていくしかない。ここに時間のズレが生じます。このズレのある対象を人間は「何か」と呼びます。命名前の対象を感じた時にそう呼びます。(これが「浮遊するシニフィアン」と呼ばれるものです)言語・規則の世界がその対象すべてを知る日は決してこない。言語・規則は対象が知られる以前に施行されるしかないからです。
問題は言語・規則はどうやって一気に施行されるのかです。答えは既存のものを二次利用(再利用)することによってです。ドゥルーズは二次利用がなければ一次利用はないといいます。おそらく人間は再現される対象しか認識できないのではないかと思います。一次利用しただけでは認識できない。「何か」が起こったことだけ認識できる。ドゥルーズは『ロビンソン・クルーソー』を読み思索を進めますが、ロビンソンは無人島でゼロから再出発したのではなく、船から持ち出した物資を二次利用しているといいます。
島と砂漠
島と大洋はdésertと形容され、無人と砂漠という意味が重ねられています。
島が無人なのは大洋が船を遠ざけているからです。構造はそれが内包する不均衡(言語・規則の世界とイメージ・自然の征服の世界の不均衡)からだけでなく、構造を取り囲んでいる開放空間(大洋)の条件から描き出せます。この条件によって構造の瓦解を構造内の不均衡だけで説明する必要がなくなります。人間は島を産出する二つの運動を反復しています。島が閉域なのは大洋がそれを許しているからです。大洋の事情は島の事情に先行します。その大洋が砂漠に準えられています。私たちは無人島から始める思考と砂漠から始める思考を区別できる、無人島の陥穽を打ち砕くのは砂漠であると國分は言います。
「無人島と砂漠」とりあえずのまとめ
「無人島と砂漠」をまとめます。私は「無人島」の陥穽を「砂漠」がうち砕くという文章が何を意味するのかという問いを立てました。無人島とは人間以前の動物的ヒトのこと。その世界はイメージのみの世界で自我、意識、言語、規則は生じていません。時間はイメージの時間なので部分を一つずつ征服していく時間が流れていると思われます。(ただし自我がない状態なので、時間をどのように感じているのかわかりません)そこにある日、偶然、他者が海(または砂漠)からやってくる。ここでズレが生じる。他者によってイメージとは異なる世界と出会う。異なる世界に出会い続けることによって他者のイメージの世界、つまり可能世界を想定できるようになる。この時、知覚全体の世界つまり自我、意識、構造が生成する。構造が生じるということは規則が一気に施行されます。そのために規則が二次利用されます。規則は他者から持ち込まれます。
そうして社会ができあがります。
それでは『存在論的、郵便的』ではどのように説明されているかを見てみます。たいへん身近な例を使ってわかりやすく説明されています。
『存在論的、郵便的』の二層構造
二層構造の説明についてソシュール研究者、丸山圭三郎を召喚します。
記号体系は無数の風船=記号が押し込められた箱としてイメージされます。ある記号の意味=風船の形と大きさは、隣接する諸風船が加える圧力によってのみ決定されます。つまり特定の風船は、その形と大きさを制限する圧力の集合=意味の束だと見なされます。風船自体に実態はありません。もしその中の風船を一つ外に出すと、パンクして存在しなくなってしまう。また、残した穴は、緊張関係に置かれてひしめきあっていた他の風船が全部膨れ上がって空隙を埋めてしまいます。しかし風船の場所=記号の名前は同じ場所に残り続けます。つまり「無人島と砂漠」がいうところの、前者が言語・規則の世界、後者がイメージ・自然の征服の世界のことです。後者は文字を絵のようにイメージで認識します。
『存在論的、郵便的』の可能世界
可能世界の説明については哲学者 柄谷行人を召喚します。
名「アリストテレス」を私たちはプラトンの弟子であり、アレクサンダー大王を教えた人物を名指す記号として用います。しかし私たちは「アリストテレスはアレクサンダー大王を教えなかったかもしれない」と矛盾なく語ることができます。「アリストテレス」=アレクサンダー大王を教えた人物
だとするなら「アレクサンダー大王を教えた人物はアレクサンダー大王を教えなかったかもしれない」のように変換できますが、これでは矛盾した文章になってしまいます。つまり「アリストテレスはアレクサンダー大王を教えなかったかもしれない」と矛盾なく語ることができるということは、現実世界を可能世界から考えているということになります。現実世界にははじめから可能世界が含まれている。これは「無人島と砂漠」のいう知覚領域全体=現実世界+可能世界と同じことを指しています。
『存在論的、郵便的』のイメージと時間
イメージと時間についてはフロイトを召喚します。
フロイトは友人について考えていたちょうどそのとき、その本人から声をかけられるという体験をしました。これは以下のように分析されます。まず友人が遠く離れている時点で、彼の目はすでに友人の姿を認めていた。しかしその友人が不愉快な友人だったために抑圧され、意識にのぼりませんでした。その抑圧の他方で同じ情報を受け取った無意識は独自に連想の糸をたぐり、友人のことを心にのぼらせます。つまりひとつの情報が分割され、別々の回路で処理されます。その間フロイトと友人の距離が近づき、結果として、彼は意識的には、ちょうど友人について考えていたとき、その当人から声をかけられることになります。「無人島と砂漠」とは別の時間が説明されます。イメージ・自然の征服の世界の中だけでも二つの時間があります。意識的時間と無意識的時間です。
「無人島と砂漠」の知覚システム、『存在論的、郵便的』の知覚システム
『存在論的、郵便的』の説明によって「無人島と砂漠」の理解がしやすくなったのではないかと思います。さらにわかりやすくすることを目指して、『存在論的、郵便的』のシステム図を参考に「無人島と砂漠」のシステム図を作成したいと思います。
まずは『存在論的、郵便的』のシステム図を示します。説明をわかりやすくするため変形しています。それから手書きですみません。

この図は既に人間の知覚システムができあがっている状態です。
物自体あるいは他者が「今、ここ」で人間に接触します。文字+意味を認識するレイヤー(カントのいう悟性、ラカンのいう象徴界)と文字だけを認識するレイヤー(カントのいう感性、ラカンのいう想像界)それぞれで同時に処理されます。その時処理できなかったイメージは無意識の回路を流れます。無意識の回路の速度は流れる対象によってバラバラです。数時間で自我に回帰するイメージもあれば生きているうちには回帰しない行方不明になるイメージもあります。また、「今、ここ」で処理された情報はあるリズムで初期化されます。次の物自体または他者を処理できるようにするためです。「今、ここ」を初期化して断続的に処理することによって時間が生じます。もしも連続的に処理していると人間は時間を想定できないのではないかと思います。また、「今、ここ」で処理できなかったイメージが無意識回路を通って自我に回帰する時、「今、ここ」で処理したイメージと異なることがあります。というか異ならなければ、回帰に気づけないと思います。この異なるイメージの回帰(「誤配」と呼ばれます)によって自我が生じます。同時に可能世界も生じます。後で修正できる言語システムにしておかないとこの回帰に対応できないからです。「誤配」による認識の差異に気づくことができなければ、おそらく自我を想定できないのではないかと思います。つまり自我が生成しない。
以上が『存在論的、郵便的』による知覚システムの説明です。
このシステム図を下敷きにして、「無人島と砂漠」のシステム図を作成してみます。

この図も既に人間の知覚システムができあがっている状態です。
物自体あるいは他者が「今、ここ」で人間に接触します。一次的接触は既に済ませ記憶されていることが前提条件です。二次的接触の時に一次的接触の記憶が呼び出され、この一次と二次の接触を反復することによって両者の差異と同一性を知覚します。もし差異がなければ対象を認識できないのではないかと思います。差異があるから同一性も認識できる。また過去の認識と「今ここ」の認識の違いによって、自我が生成すると同時に時間が生成することになると思います。一気に浸透させなければならない規則については他者が既存の規則(資材)を持ち込みます。
「無人島と砂漠」も『存在論的、郵便的』も他者との接触が複数のレイヤーで行われること、断続的に行われることによって自我と時間が生成することを説明しています。ただ「無人島と砂漠」では『存在論的、郵便的』の無意識回路による複数の時間の処理が考慮されていません。
『存在論的、郵便的』は1998年リリース、「無人島と砂漠」が参照しているのがドゥルーズの「無人島の原因と理由」で1950年頃のリリース、しかも『存在論的、郵便的』ではドゥルーズも参照されていることを考えると、精度に違いが出るのは当然かもしれません。
「無人島」の陥穽を「砂漠」がうち砕く
ここでようやくこの記事の目的に戻ります。國分は「無人島」の陥穽を「砂漠」がうち砕くと言いますが、これが何を意味しているのかその謎にせまるというのが目的でした。「砂漠」から「他者」がやってくることによって、「無人島」ではなくなるという文字通りの解釈は可能です。しかしその場合「砂漠」ではなくて「他者」がうち砕くと表現する方が妥当ではないでしょうか。「他者」ではなく「砂漠」がうち砕くという表現になっているのはなぜか。そこでは「他者」よりも「回路」の方を強調したかったのではないかと考えてはどうでしょうか。
私は「無人島」の陥穽を「砂漠」がうち砕くとは、『存在論的、郵便的』で示された無意識(砂漠)回路からの回帰によって「無人島」ではなくなることを強調したかったのではないかと考えています。「他者」との二次的接触に加えて、その時取りこぼしたものが、無意識(砂漠)から突然回帰することがある。この場合「無人島」をうち砕くのは「他者」より「砂漠」の方が妥当ではないかと思います。「他者」とは既に二次的接触で出会っているので。しかし残念ながら國分やドゥルーズがどのように考えたのか証拠を見つけることができませんでした。
今後も検討を続けて謎が解けたら改めて記事を書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
