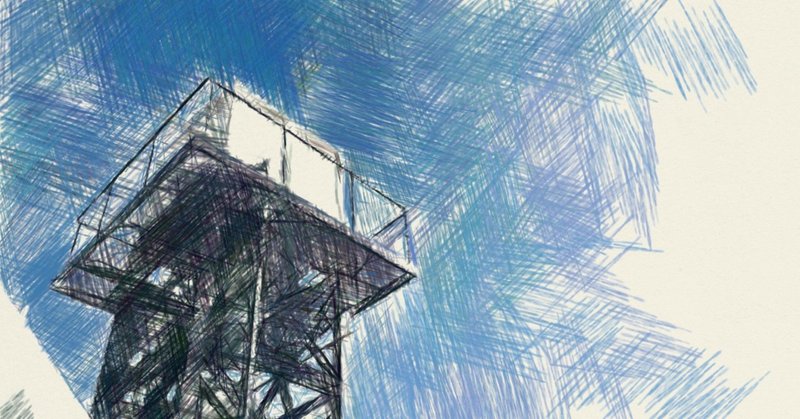
"分からないこと"の武器は、強さと経験
もっと勉強したかった。
こんなことを言うと、賢くて勉強好きな人のようだが、全くもってそんなことはない。
たしかに、小学生の頃は勉強を嫌いだと思ったことはないけど、中学の時の成績は国語・数学(図形と証明のみ)・美術以外は全て放棄していたに等しく、成績もそれに比例しているようだった。
高校はスポーツ推薦の特待生として進学したのだが、自分の成績より数段も下のランクだったため、普通にしていてもクラスの上位は入れるし、少し頑張れば学年一桁にも入れるので、「勉強しなきゃ」という意識もほとんどなかった。
振り返ると、義務教育という制度の意義みたいなのが見えてくる。きっと、小中学生で自分の勉強できるスペックのようなものが出来上がるんだと、身をもって感じている。
そして…
もっと詰め込んで欲しかったなと思う。
勉強をさせられたかった。
あの頃、嫌と言っても遊びたがっても、多少無理やりにでも勉強させられていたら、もう少し世界は広がっていたのかな、と。
・・・
詰め込み教育のゆとり教育の議論は、今でも続いている問題である。
私は詰め込みでもゆとりでもない世代なので、どちらも体験していない身としては、何も言うことはできない。
ただ、社会人1年目から教育現場に携わり、現在12年目の私としては、やはり子どもたちに詰め込み教育を行うのは躊躇われる。
できれば伸び伸び育って欲しいし、必要最低限の勉強をしつつ、体験から学べることも吸収してほしいと思ってしまう。
一方で、やっぱり勉強していたほうがいい。やらされていても詰め込まれてでも、学ぶ意味というのがある。
いざ勉強したいと思った時にこそキャパシティーがなければ、どんなに勉強しても身につかないからだ。
興味があることは誰だって楽しく学べる。
肝心なことは、興味がないことも学べるようになる少しの我慢だ。
・・・
塾講師をしていた時に、つくづく思ったのだが、小中学生の頃の勉強は覚えておく必要はない。
よく友人に「よく塾講師できるね。私もう覚えてないから教えられないわ」と言われる。
もちろん私だって忘れていることばかりだった。でも、大体のことはテキストを見ればわかりやすく書いてあるし、曖昧な場合でも答えと解説を見れば十分に理解ができるので、子どもたちに教えることもできる。
つまり、忘れてしまっても一度理解できたことは、記憶を取り出すこと、あるいはもう一度理解することができる。
そして、あの頃理解できなかったことは、大人になった今でもよく分からないままなのである。
私は中学時代、理科だけはどうしても理解できないことだらけだった。覚えるのも苦痛だし、実験も嫌いだったから同じ班の友人たちにお任せし、レポートは書くから写させてあげるということをよくしていた。
天文学を学んでプラネタリウムで働きたいと考えていた時期もあったが、天気・天体と生物の単元だけは成績が良く、学んでいても楽しかったが、その他の理科らしい理科はからっきし頭に入ってこなかったので、その夢は潔く諦めた。
元素記号や電気・電圧、光と音の速さの計算とか、空気中の酸素が何%だとかは全く理解ができなかった。
そして、大人になり塾講師という立場になっても、それは変わらなかった。テキストを読んでも答えを見ても解説を読んでも、どうしても分からなかったので、理科は担当から外してもらっていた。
そしてテスト前に自習している子たちに、天気・天体のことだけは教えてあげられた。
・・・
もっと勉強がしたい。
だから、もっと勉強したかった。
大学を卒業してから専門学校へも行って、おまけに大学院も修了しておいて、まだ勉強するのかと思われそうだけど、別に学校へ行くことだけが勉強じゃない。
最近は、独学で苦手な分野を学ぶ力が欲しい。
得意なことを独学で学べるのは当たり前だ。
だって得意なんだもん。
少々の難しいことにも立ち向かうだけどエネルギーが、「好き」や「得意」なことにはあるものだ。
しかし、正面きって「苦手」「不得意」と言えるようなことを、独学で学ぶのは大変難儀なことである。
ただ、最近は苦手で不得意分野を学ぶと、好きで得意な分野の理解も深まるのではないかと思っている。
つまり、伸ばしたい力がある時、理解を深めたい事柄がある時、それだけに集中するのではなくその周辺に混在するよく分からないことを分かっていることが武器になるんだろうと思う。
ただ、立ち向かう強さがない。
そして、その経験もない。
強さと経験が欲しかった。
だから、私はもっと詰め込んで欲しかったと、今は思っているのです。
今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。
