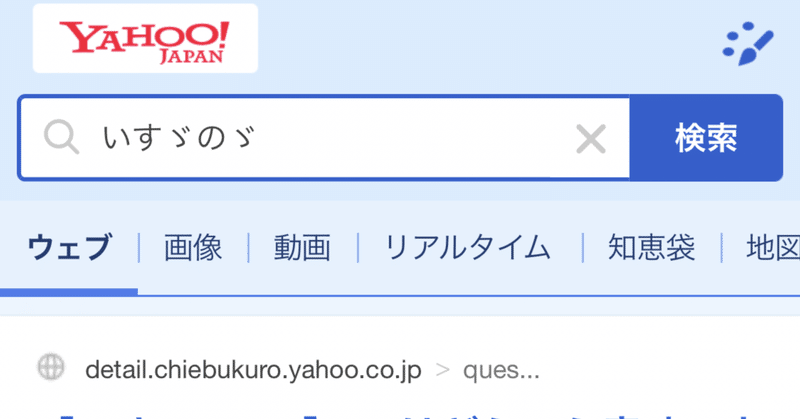
「カンペノスヽメ」
トップ画像
トップ画像はタイトルの、
「カンペノスヽメ」
の「ヽ」の入力方法が分からず、検索したワードです。
ええ、「学問ノスヽメ」をもじった訳ですから、
検索ワードを、「学問のすすめ」にした方が良かったですよね。ええ。
"ggrks"(ググレカス)
懐かしいですね。
一昔前流行ったネットスラングです。
なんでもかんでも、少し調べたらすぐ分かるようなことさえ聞こうとする者に対して、
「その程度の簡単なことは、Googleでしらべろ、ザコ。」
と、バカにするニュアンスで、某ネット掲示板で使われていたのが発端のようです。
ところが、ご経験のある方も多いでしょうが、
「ググる」ためには、その分野についてある一定以上の背景知識や暗黙知の有無で、答えにたどり着けるスピードが全然変わってきます。
知っているだけで、検索ワードを絞れるからです。
また検索ワードを選択するベースとなる経験則やセンスの有無もあります。
ggrksと言われた人たちは、そのワードさえ、思いつかない場合も多いのではないかと思うわけです。
僕が絞り出した「いすゞのゞ」も、とりあえず答えには辿り着けましたが、
センスのある人は「学問のすすめ」と、検索するはずです。
カンニングペーパー歓迎
さて枕はこれくらいにしてそろそろ、本題に。
こんなtogetterまとめがタイムラインに流れてきました。
つい最近、Facebookのとある方のコメント欄に僕が書き込んだエピソードと類似していて、このnoteに思うところツラツラ書いてる次第です。
"とある科目"
僕は大学の学部に都合9年間在籍しました。
その"都合"に関しては別の機会に譲るとして、
9年間も在籍していると、色々な科目、試験を受けました。
それでも9年かけて取れた単位は卒業ギリギリでした。
その中で、"とある科目"について、このtogetterまとめ、と類似した経験をしました。
さすがに名刺1枚ではなかったのですが、シラバス(授業予定表みたいなもの)に、
試験はA4 2枚までカンニングペーパーを試験持ち込み可
の"とある科目"に、飛びついて履修登録しました。
大学の講義の多くは数百ページの専門書を、
90分×十数回、つまり20時間前後をかけて(たった20時間で駆け抜けるスピードで)扱います。
試験前、カンニングペーパー持ち込み可、と、たかを括っていた、"とある科目”。
手元には、ノートと、専門書、大学教員というその分野の専門家が厳選したレジュメ、A3用紙に裏表数十枚。
これだけの内容を、名刺1枚ではないにせよ、A4 2枚のカンニングペーパーにするためには、なかなかの労力を使います。
ええ、もちろんレジュメを縮小コピーしてみるところからやってみるのですが、そんなもの大量の10円玉を大学生協のコピー機に寄贈するだけに終わります。
大量の10円玉と引き換えに得た、何の意味もなさない縮小コピーを眺めながら、
ここではじめて、「A4 2枚」の重さに気付きます。
当然です。質量保存の法則から言っても、
その科目の講義内容をA4 2枚に押し込めれば、かなり密度の高い物質になります。
おっと、質量保存の法則は、例えです。ええ。
Long Way To カンペ
あきらめて、オリジナルカンペ作成に取り掛かります。長い道のりです。
まず、各単元、授業、レジュメの中から、自分がカンペがなくても理解できるものと、どうしても理解できないものにまず振り分け、要点を絞るために厳選に厳選を重ねるのですが、
この過程で、その"とある科目"の教科書、授業ノート、レジュメを嫌というほど、読み"解き"、どこが重要かを見つけ出すだけの理解が必要になるわけです。
例えば何かの数式や公式にしても、紙面の節約のために、基本となる公式だけ書いておいて、他はヒントだけ残して自分で導出するできるようにしたり。
(先ほどの大量の10円玉と引き換えに得た中途半端なコピー用紙の裏面が、公式導出の練習に役立ちました。世の中無駄なものはない。)
出来上がったカンペは、当然、作った本人にしか意味のわからないものになります。もはや暗号書です。字も小さいし。
なので、誰かが作ったカンペをコピーしても意味がない。
もうそれが出来上がった段階で、他のどの科目よりも、
カンペ持ち込みOKの"とある科目"が一番深く理解してました。
ええ、まんまと、担当教員の術中にハマった訳です。はい。
そしてそれこそが、詰め込みや丸暗記ではない、「学び」であったような気がします。
”とある科目”とは。
ただ、ココまで書いて、無責任なのですが、
今となってはその"とある科目"が、何の科目だったのか、さえ思い出せないんですけどね。
おそらく今も認識していないだけで、
僕の脳の中で、血となりブドウ糖となり、使われていることでしょう。
知らんけど。
本当に身についたものは、いつどうやって身につけたかさえ、思い返すことすらできないのでしょう。
知らんけど。
"ggrks試験"
僕が学部生だった頃より、webの情報を簡単に収集できるようになりました。
簡単に収集できるような気がすることが増えてきた、と言う方が正確かもしれません。
テキストや画像はもちろん、映像コンテンツも莫大に膨れ上がっているし、調べたいことはすぐに調べられるような気になってしまいます。
実生活や実社会でも、それらを利用して成り立っています。
ですが、上述の通り、実際はそう簡単に、検索して自分が欲しかった答えにたどり着けるわけではありません。
Yahoo知恵袋を見ていると、「ああ。」と思わさられる質問はゴマンとあります。
それっぽいホームページや動画をみつけても、どこが自分の求めているないように近いのかどうか、の判断をAIにさせるには、もう少し時間がかかるでしょう。
なので早いところ、入試にせよなんにせよ、「持ち込めるものは何でも持ち込み可」「但し生き物を除く」程度にして良いんじゃないかと思います。
いや、コネクションか金銭的な余裕さえあれば、その分野の専門家を持ち込んでもいいかもしれません。
「以下の問いについて答えよ。ただし、解答に至る手段は合法的であればよい。」
って。
それらを限られた試験時間内で駆使して、正解を出せたならそれでいいわけですし、
試験時間だって90分にこだわらず、5時間くらいとっておいて、1時間早く終わるごとに5点加点、とかもアリかもしれません。
下手に考えて時間をロスするよりも、諦めて誰か聞ける人を探す方が早い場合も実社会なら当然ありますから。
そっちの方が、問題を出す側としても、より本質を突いた問題を出せるでしょう。
問題を出す側が、本質を突くことができれば、の、話ですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
