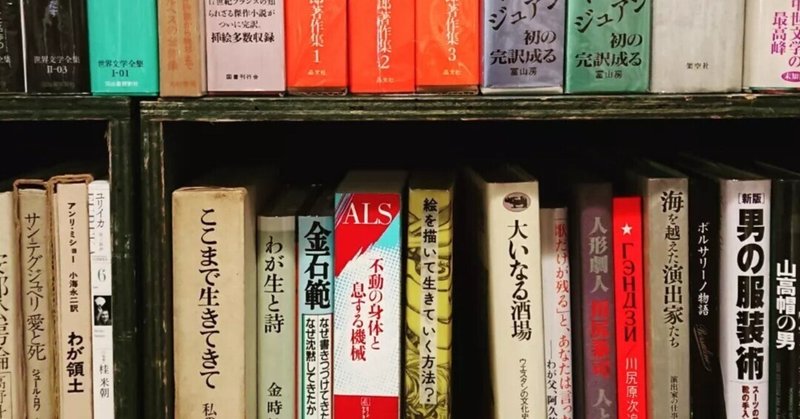
乱読のススメ
川口市出身の自称読書家 川口竜也です!
最近、近現代文学にハマってしまい、どうも完読まで時間がかかってしまう次第。私は本は一度に4,5冊ぐらい同時読みをするタイプですが、どの本も現状中間地点で、完読後の読書記録が書けない状況です。
よくそれだけ一緒に読むと、内容がこんがらがらないかとよく言われますが、慣れるとそうは思いません。
私の場合は、そもそも内容や文体が似たような本は選ばないようにしています。現在、夏目漱石の「吾輩は猫である」をメインに読んでいるのですが、他には柚木麻子さんや奥田英朗さんの短編集、時折、幸田露伴先生の「努力論」を読み進めたり、新刊のビジネス書に目を通している感じです。
本は同時に10冊読めと言ったのは、「2040年」を書いた成毛眞さんだったか。10冊は厳しいながらも、何だかんだで5冊を同時読みしています。
そもそも、私は非常に飽き性です。余程夜を忘れるほど没入感がない限り、大体30分または50ページで小休止します(これが非常に正確で、そろそろ休憩しようかと思うと、ちょうど50ページなので気味が悪いです)。そのため、同じような本を併読というよりは、今まで使っていた頭を休める意味で、乱読をしております。
また、全く別のジャンルを読んでいているにも関わらず、共通点や原則のようなものを見つけると、非常に面白いということはございます。夏目小説の作品の中に、ビジネス書に通じるものがあると考えると、やはり人間の根本は変わらないのだなと思ったりします。森見登美彦さんの「夜は短し歩けよ乙女」の如く、本は全て繋がっているのです。
ただ、急に乱読を始めるのはハードルが高いです。確かに慣れるまでは、何冊も同時に読んでしまうと、ここまで読み進めてきた内容はそもそもどんなものだったのかわからなくなることがございます。しかし、なんとこれには対処法がございます。
ひとつが、キリの良いところまで読まないこと。ドイツかどこかの研究だったか、『ツァイガルニク効果』と呼ばれるものがあります。本はキリよく読み終えるよりも、途中で中断した方が内容をよく覚えているそうです。ドラマとかでも、この続きが気になるなぁという状態で終わった方が、また観たいと思うのと一緒です。
そのため、1章読み切るまで、何ページまで読むぞ、と言うよりは、30分で読めるところまで、電車が駅のホームに着くまでなど、時間で強制的に区切るのも良いです(時折、続きが気になりすぎて、駅のホームでずっと読んでしまうこともありますが)。
もう一つは、状況や環境によって読む本を変えること。これも何かの研究であったはずですが、人間は無意識のうちに、場所と行動を関連付けしているそうです。例えば、寝るときは寝室で寝ると決めている人は、寝室に入ることから睡眠導入に繋がっていると脳は無意識のうちに認識しているそうです(寝室に仕事の道具を持ち込まないのもそれが理由だそうです)。
ならばそれを逆手に取り、読む場所を決めてしまうのも手です。私の場合、どこでも読むための本が夏目漱石ならば、お風呂に入っているときは短編集、幸田露伴やビジネス書を真面目に読みたいときはカフェに行くなど、この状況下ではこの本を読もうと先に決めてしまうことです。すると自然と、本を読む時間を作ろうと考えるようになり、一石二鳥です。
このような事は、"本の読み方"に関する本を読むと沢山出てきます。まずはそのような本を併読して、できることから初めてみてはいかがでしょうか。それではまた次回!
今日もお読みいただきありがとうございました。いただいたサポートは、東京読書倶楽部の運営費に使わせていただきます。
