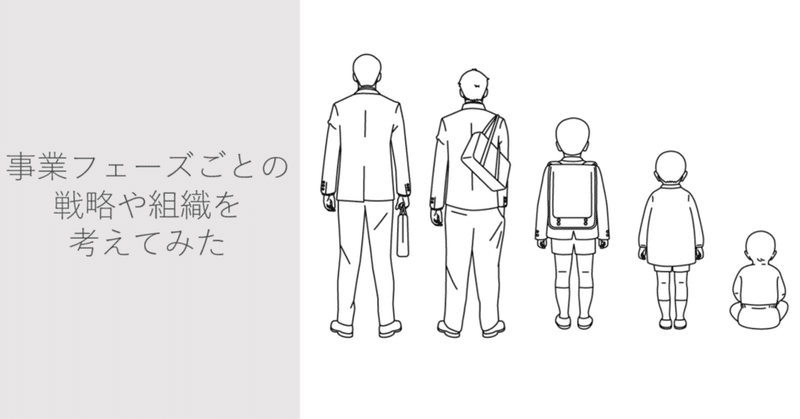
事業フェーズごとの戦略や組織を考えてみた〜壁と乗り越え方の振り返りと考察〜
この記事はなに?
これまでnoteにて自身のキャリアなど個人観点での記事が多かったのですが、組織や事業の階層における考察についても、
自分の頭の整理として書いてみよう思いたち、筆を取ってます。
私個人の当時の状況・環境から振り返って感じたことです。
他事例にそのまま当てはまるわけではありませんし、何かを規定するものでもなく私見そのものであります。
ふ~ん、くらいの軽さで目を通してもらえたら幸いです。
経験した事業について
私が経験したのはBtoC向けの動画を主軸としたサブスク事業で、社内新規事業です。
※スタートアップのような外部の資金調達を必要とする立ち上げとは若干異なる可能性があります
入社時点で1くらいの状況で
(全く初期の0→1立ち上げではありません)
1~100くらいのところを経験しました。
新規事業といっても、中長期では一定以上の規模が見込める領域でないとGOが出ません。
創業タイミングでは足元の1顧客の課題のリアリティに向き合ったサービス設計と市場シェアを取りに行く規模の両面を紡ぐ成長ストーリーが大切だと感じます。
とはいえ新規事業の見立ては、当たりませんし、試行錯誤の中で新たな兆しと解像度を手に入れながら組織能力を伸長させていったのだと思っております。
事業フェーズをまとめてみた

かなり小さくなってしまいました、、、。
事業には、戦略に沿って実行するための組織の役割があり、組織が担当する業務があります。
フェーズによって、戦略のテーマが変わっていくので、当然組織役割や業務も変わっていきます。そのため、その業務を担う人材要件も変わっていくことになるのです。
創業期
創業期のテーマはPMFなのかなと思ってます。
サブスク事業はリーズナブルな金額でサービスを利用頂き、利用期間を伸ばすことで回収する先行投資型のモデルとなります。
そのため、LTVとCPAのバランスが見合う効率と規模になりうるところまでサービスを磨き込んでいく必要があります。
成長期
成長期は、世に出したサービスを市場に浸透させていくフェーズになります。
私は成長期の中で、前期・後期を分けてみました。
・前期は、1サービスを拡大させていくステップ
→サービス認知に対して大きく投資を行い、
認知→利用意向→利活用、とったファネルを定点観測しながら、歩留まりを改善するPDCAを同時に回してします。
組織は、個々がモチベーションと行動力を発揮し相互に助け合う状況から規模拡大に有機的に対応するための機能分化(役割分担)が行われていきます。
ここで勝ちパターンとなるマーケティングの訴求軸やチャネル開発ができると一気にシェアを高めることもできるでしょう。
・後期は、その成功パターンを周辺領域に拡大再生産していくステップ
→創業時にはターゲットセグメントを絞り込んでサービス開発をしていたと思いますが、既存市場の深耕とともに周辺領域に進出し、市場を広げていきます。
こうなると、組織規模は大きくなる一方で、いかに再現(仕組み化)を高められるかの組織能力が成否を分けるのではないかと思います。
仕組み化には業務プロセスを可視化し、業務設計を行い、分業化し、有機的につなげていく必要があります。
成熟期
成熟期は、市場が成熟し、競争環境が固定化しつつ状態になります。
仕組みを磨き、効率・標準化を進めていくことはもちろんですが
大きな技術革新などのトレンドでゲームのルールや異業種参入を注視する必要があります。
市場が伸びにくい中では、オペレーションを標準化しつつ、一方で新たな商品・サービス開発のための新結合生んでいくための組織能力も必要になるのではないかと考えています。
そのため、異能を受け入れる多様性と、心理的安全性を発揮できる組閣・風土が大切ではないかと思います。
衰退期の経験がないので、そちらは割愛しています。
フェーズ移行の壁を超えていくために

フェーズ移行のタイミングでは、戦略テーマが変わり、その変化に適合した組織能力を発揮していかなければなりません。
移行とはどういうものか、どう超えていくべきなのでしょうか?
私が体験した2つの壁について簡単にまとめていきます。
創業→成長期に差し掛かる「勝ちパターン発見」の壁
PMFに到達後、いよいよ本格的に拡大するための大規模な投資を行うタイミングです。
これまで体験したことない規模の投資が行われ、ユーザー規模が増えるチャンスでもありますが、新たな施策へのチャンレンジ
(私の場合はTVCM・OOH・大型販促イベントなど)
の成功確度(勝ちパターン発見)を高めるため即戦力が求められます。
これまでは立ち上げフェーズを走る中で以心伝心だった初期メンバーだけではリソース・ノウハウが追いつかなくなるので中途採用などで補うことになると思いますが、スキル高い人材にも同じ熱量で同じ方向に動いてもらうための強烈なビジョンが必要でもあります。
立ち上げメンバーのモチベーションで担保している業務を役割ごとに分け、即戦力採用した方々の知見を活かしつつ結束を高めた事業運営が出来るか、が肝になるでしょう。
スキルがあるからといってそれだけで採用すると、スタンス面でのアンマッチを起こしパフォーマンス発揮できないまま早期退職になってしまうことを何度か目にしました。
成長前期→後期に差し掛かる「再現性と仕組み化」の壁
1つのサービスが大きく伸長してくると、更なる成長を求め
1)既存サービスの提供価値深化
2)周辺領域への進出 を行います。
サービスの深化とは、ターゲットに対し包括的に提供価値を増やしていくことになります。
具体的には顧客と向き合い、機能付加、商品付加、既存の運用改善を重ね粘着性を高めたり、口コミにおける流入にさらなるシェアアップを目指す等を指します。
周辺領域への進出は、例えば幼児向け→小学生向け→中学生向け・・・といった形で市場を広げるなどがわかりやすいのではないでしょうか。
1)と2)は運用の肥大化と、業務量の増加を意味し、
短期は一人ひとりが兼務で複数役割をこなしつつ、
中長期的には組織を分割(プロセス単位での分化)を行って分業体制でカバーしていくことになります。
ポジションは増えますが役割・管掌範囲は分割されていきますので
既存メンバーからすると裁量低下やスピード感の遅れによる停滞感で一定の離職が発生し、新規入社組は分化した役割の中で専門性を高めていくので、
全体観の喪失と個別最適化が一気にやってきてしまいます。
ここで大切なのは、そうなることを予測して
中間レイヤーの視座とマネジメント力を先に高めておくことです。
また、業務設計とOpsの人格を分け、
日常のOpsと並行し
業務プロセスの可視化、ナレッジ整備、業務スキルを棚卸し等を
整理して仕組みの再現性に目を向けるなどもポイントかと思います。
まとめ
事業フェーズが変わると、戦略・組織能力の変更が発生します。
そして適応には短期では解決できない事象もあります。
大切なのは、
・次のフェーズを先読みし、認識的に現状を認識すること
・1つ1つの施策の効果(プラス面)だけでなく逆効果(マイナス面)も認識したうえで能動的に選択している自覚を持つこと
なのかなーと思い至りました。
自分自身、↑を書き起こししながら、
整理が追いつかない大雑把な部分があることを認識しながら書いてます。
後日これらの詳細化もできたらと思っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
