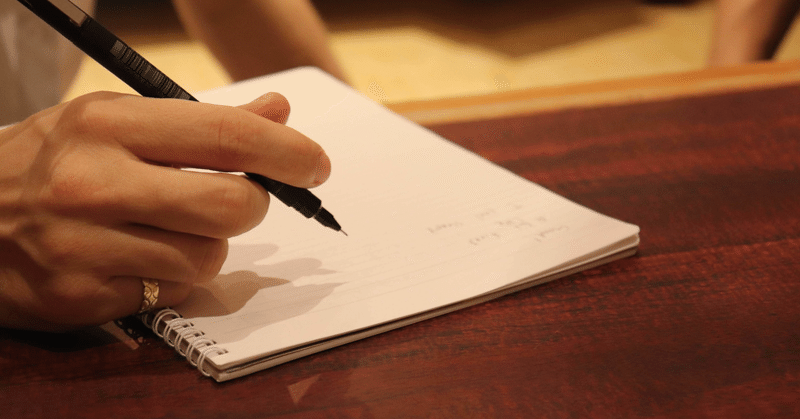
「模倣と創造」で新たなチャレンジへ(読書まとめ+ご挨拶)
今回から「企業内診断士の輪を広げる『楽しい』ブログ」に参加させて頂きます、勝田です。令和3年度試験で合格し、今年登録したばかりの新米診断士です。
受験生時代から読んで励みにしていたブログのメンバーに参加できて嬉しい一方で、より一層ちゃんとしたことを書かなければと身が引き締まっています。
というわけで、これを機に初めて私の記事をお読み頂く方もいるかもしれませんので、もしお時間があれば過去に書いた記事も読んで頂けると幸いです。(早速宣伝)
それはさておき、今回は先日の企業内チームの定例会でご紹介した「模倣と創造」から、経営、コンサルティング、診断士活動に活かせそうだなと感じた内容を共有します。
ざっくり内容紹介
デザインファームBIOTOPEのCEOであるデザイナー佐宗邦威さんによる著書で、一言でいえば”「創造」はセンスが必要な行為ではなくプロセスを踏んで訓練すれば身につけられるスキルだから、みんな「創造」しよう”、というメッセージの本です。
「はじめに」において、
創造の本質
①模倣:違いを観察し、感性のセンサーを働かせて真似をする
②想像:自分だったらどうするかを考え、世の中にあるものを変化させる
③創造:自分なりのテーマを具体化するために制作物に落とし込む
と書かれており、この3ステップについて、それぞれどのようなアクションをとるかがか具体的に書かれています。いわゆる「守破離」に近いイメージですね。
また、
創造性研究の分野では、創造性を2つのタイプに分けている。①Big-C:社会に大きな影響を与え、社会的評価も十分にされる創造性
②Mini-c:誰もが持っている創意工夫
現代は多くの人がMini-cを発揮できる、創造力が民主化された時代になっている
と書かれており、まさにこの記事もMini-cの賜物というわけです。
というわけで、それぞれの段階から特に学びと気づきがあった点を紹介します。
模倣:観察と体験、そしてアマチュアリズム
創造の第一歩として、「まねる」ことが重要であると述べられています。そしてまねるときに大事な事は、
「まねる」ときに大切なのは、小さな違いまで観察すること、それが自分の感性のセンサーを働かせることになります。
とあり、第一歩目として「観察」が重要です。
私たちは思った以上に目の前の物事を正しく認知できていないことが、じっくり観察することで見えてきます。
以前診断士の勉強会でも「観察」の重要性について話があり、その時にデッサンをやってみることを勧められ、2か月ほど続けてみました。(最近できていないので反省)
そうすると、絵の上手・下手はともかく(私はとても下手です)、じっくりと観察することで毎日見ているものも今まで見えていなかった特徴など気づきがありました。
少し飛躍させると、診断士の要素の一つである「診る」にも通じる所があります。
診断先の経営者の方や会社の状況、マーケット環境など、紙やwebの情報だけでなく、対話をしながらしっかりと観察することで、企業や経営者の抱える課題の真因を見つけ、その課題に対する改善の方向性を「創造」することにつながるのかなと考えました。
また、創造にはセンスが必要、というイメージもありましたが、まずそのセンスというのは
センスは、(中略)感じるということです。これはつまり、僕らが自分の好きを感じる「感性のセンサー」が働いていないと、自分のセンスは発動しないということです。
ということで、また、センスを磨くためには
自分のセンスを磨くために、ここぞという場合には多少お金をかけてでも、いいものを体験することに投資することが大切です。
と語られています。診断士資格を取得後、ありがたいことに企業内チームを含め勉強会やセミナーに参加させて頂く機会が増えました。
また、好きで聞いているvoicyやPodcastなどの音声コンテンツ、そして本書のような書籍からも日々学びを得ています。
自分の興味のあること、ないことを問わず、アンテナを高くして、いいものを体験する機会を増やしていくことがいいのかなと思います。
そして、創造を始めるきっかけとして、まずは何かの真似からでも続けてみる、「習慣」にすることを勧めています。
そしてその中で、
大事なのは、アマチュアリズムというキーワードです。(中略)とりあえず、何かを表現してみる。そして、それが面白そうだと思ったら、どうやったらよく出来るかを勉強する、調べる。
とあります。私も今年に入りnoteをマイペースに続けています。
いつも拙い文章で、うまい表現もできず嫌になる時もありますが、所詮アマチュア、と開き直って(もちろん有益な情報を発信する想いは持ち続けますが)続けることを意識しています。
想像:自分との対話+ビジョンパートナー探し
次の章では、模倣で研ぎ澄ませた「感性のセンサー」で感じた思いを、自分なりのエッセンスを入れて独自性を出していく、その時に行う「想像」のプロセスについて説明されています。
この中で、まず最初に
独自性を生むために必要な考え方、それが「主人公」です。言い換ええうろ、自分を主語にできているかどうかです。(中略)
自分を主語にするには次の三つの段階が必要です。
自分が感じている感情と対話する。
自分の好きな世界に浸る。
そして、自分の作りたい世界を想像する。
自分を主語に置くことができて初めて、世の中に対して新しい独自の表現が生まれてきます。
とあり、この部分は正直全然できていないなあと感じています。
いろいろな出来事や感情が動いたときに、ついついTwitterとかYahooニュースのコメントとかを見て他人がどう考えているかを知りたくなりがちだったりするので、まずは自分と対話し、自分がどう考えているかをしっかり見つめることをやっていきたいと思います。
その後も想像力を鍛えるトレーニング方法など勉強になりましたが、特に実践していきたいと考えたのは、「ビジョンパートナー」についてです。
世の中のほとんどのことは、新しく始めるより、続けることが難しいものです。(中略)
そんなときにおすすめなのが、フィードバックをもらうだけではなく、お互いのやりたいことを一緒に企むビジョンパートナーを見つけることです。(中略)
一人で頑張り続けることはとても難しいけれど、同じ境遇で仲間として一緒に頑張っている人がいれば、続けることがそれほど苦ではなくなります。
これは、私自身が診断士2次試験の勉強会をやっていても感じたことに近く、続けるためには同じ志を持った人と語り合うことがとても有効だと思います。
「楽しいブログ」についても、皆さんが続けられるモチベーションの源泉にはこの考え方があるのかもと想像します。
創造:自分に合ったやり方で「やりたいこと」を叶える
そして最後の章では、「創造」をしていくにあたって必ず経験する山・谷(自分のムードの上下)を乗り越えるために何をすべきかが書かれています。
その中で特に学びになったのは、アウトプットの「形式」についてです。
一人一人に必ず、自分に一番合った表現のフォーマットがあります。ただ、そのフォーマットと出会うのは簡単ではありませんし、自分のインプット-アウトプットの得意なフォーマットと、実際に日常考えたりアウトプットしているフォーマットにずれがあると、その人の魅力は十分に活かせないという印象を持つことが多いのです。
私自身、振り返ってみると自分に合ったアウトプットのフォーマットを見つけるために色々試してきています。
実は中学生~高校生の頃には趣味のHPを作っていたりもしましたし、診断士の勉強を始めてからはTwitter、note、音声コンテンツなどやってきました。その中では今のところnoteが一番しっくり来ているかなという実感です。今後も続けながら、他の方法にもトライしていければと思います。
また、表現へのこだわりについても響くものがありました。
創造には意味の苦しみがつきもので、迷うこともありますが、
迷子になってしまったら、改めて、自分がなぜこの作品を作りたかったのか?という原点に立ち戻ることも大切です。
と書かれており、この記事も含めてnoteで発信を続ける理由(診断士として中小企業経営者と同世代で仕事に悩む人にヒントとなる発信をして助けになりたい)は常に立ち戻って考えようと再認識しました。
また、長寿社会となる中でキャリアの考え方も変わってきており、長寿社会となる中で、いくつもの「やりたいこと」が叶えられると考えると夢がある、キャリアを積み重ねる中で自分のテーマに出会うと自ら問いを作り、世の中に問いを立て、社会における自分の存在を許容できるようになる、ということが語られています。
ここは、まさに私が診断士を目指した理由であったり、ここまでの歩みに合致していると深くうなずきました。スティーブ・ジョブズ氏の「connecting dots」のように、これまでの人生・キャリアを現在から振り返ってみたときに、中小事業者との協業経験があったり、父が中小事業者であったことなどが積み重なって中小企業診断士という目指す姿が浮かび上がってきたなと再認識しました。このありたい姿に向けて手探りながらMini-cの創造を続けていければと思っています。
「楽しいブログ」という新たなチャレンジ
というわけで、最初から長編(自己相対的に)になってしまいましたが、書かせて頂いたこと以外にもたくさん学びのある本でしたので、ぜひ一読をお勧めします。
今後「楽しいブログ」のメンバーとしてどんなテーマで書こうか考え中ですが、自分なりのMini-cを発信させて頂き、何か読んで頂いた方の気づきになれればと思います。新たなチャレンジですが楽しみたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
勝田慶
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
