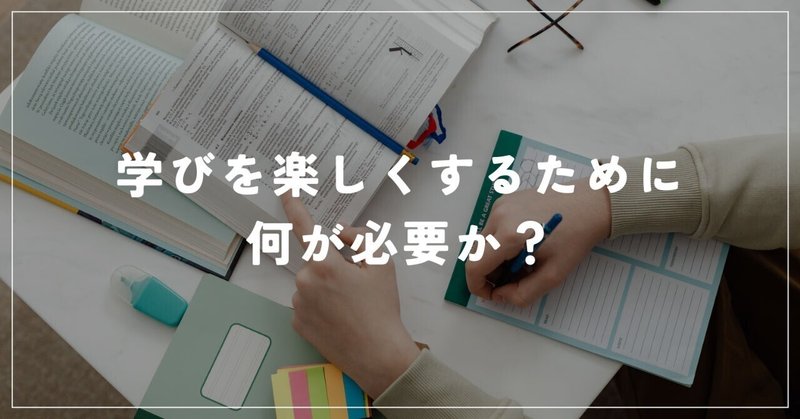
学びを楽しくするために何が必要か?(3)- 子どもの効力感を育む。というよりも、奪わない(その1)
学びを楽しくするために必要なものの2つめ。それは子どもがもつ効力感です。
効力感がある状態とは、「自分が行動すれば、自分のおかれた環境をもっと良い環境にすることができる」と信じることができる状態です。
例えば、テスト前の状況で、「テスト範囲を復習するという行動を自分がすれば、復習するという行動をしない場合に自分に訪れる環境よりも、もっと良い環境にすることができる。」と信じることができれば、復習をするでしょうし、「復習するという行動をしてもしなくても、自分に訪れる環境は変わらない」と考えてしまう場合には復習をしないでしょう。
「学びを楽しくする」という文脈で効力感がある状態を捉えなおすと、「今、これを学んでいることによって、自分のおかれた環境をもっと楽しいものにできる。」と信じることができるという状態です。
例えば、ある子どもが、友達に、深海魚の一見気持ち悪い写真(例えば、ミツクリザメの捕食シーン 等)を見せて、「この気持ち悪い姿にもこういう進化上の意味があり、環境適応の結果だ」と力説したところ、友達が驚き、感動してもっと話を聞きたいと言ってきた。その経験がその子どもにとってとても楽しかった。とします。おそらく、その子どもは深海魚について学ぶ際に、効力感がある状態で学ぶ可能性は高いでしょう。「このさらなる深海魚についての学びによって、あの友達と経験した楽しい状況をまた生み出すことができるだろう。」というふうに。
さらに、こういった効力感は、「楽しさ」の視野を広げる効果もあることがわかっています。「逆境」とは、一般的に楽しくない状況です。でも、効力感があれば、子どもは「逆境」にも突撃し、それを克服していきます。なぜか。それは、その先により大きな「楽しさ」を期待することができるからです。つまり、「楽しさ」について、時間軸を味方につける(今楽しくなくても良い)ことができるという意味で「楽しさ」の視野が広がっているのです。
先ほどの例をまた取り上げると、その子どもが深海魚についての知識を得ていくうちに、子ども向けの図鑑や書籍では満足できず、大人向けのやや専門性の高い文献に辿りついたとします。おそらく、その子どもはその文献を読もうとするでしょう。難しい言葉もたくさん使われていて、一時的にはそれは「楽しくない」経験になると思います。しかし、その先にある「友達と語る」という楽しい状況を描きながら、その「楽しくない」経験を乗り越えていけるのです。
このように、学びを楽しくするには、子どもの学びに先立って、この「効力感」をいかにして育んでおくかは非常に重要になると思います。
次回は、この「効力感」は育むことができるのか。できるとすれば、どのような方法があるのか?について考えてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
