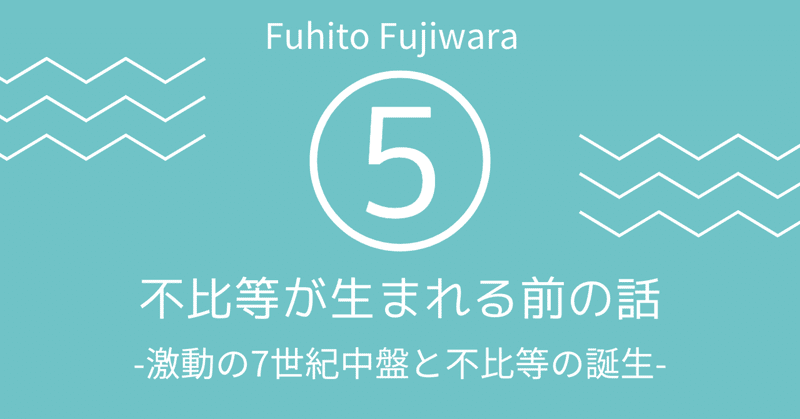
不比等が生まれる前の話⑤ -激動の7世紀中盤と不比等の誕生-
蘇我氏を中心とした中央集権国家への改革は、乙巳の変・大化の改新を経て大王家・藤原家へと受け継がれていきます。
対外戦略の違いが乙巳の変に?
というわけで645年、蘇我蝦夷・入鹿親子が殺されます。中心人物は知っての通り中大兄皇子と中臣鎌足。中臣氏は姓でいうと「連」になり、祭祀を司っていたようです。
乙巳の変に連なるエピソードは、歴史研究的にも『日本書紀』の記載のよる部分が多く、中大兄皇子と中臣鎌足のエモい話があったりとか、蘇我氏が異常なまでに悪者扱いされていたりとか、まあそんな感じです。この頃は文字通りの蘇我王朝だったという説もあり、だとするとこの政変は中大兄皇子一派によるクーデターになります。
ではなぜこの事件が起こったのかというと、そこは複合的な理由があったと考えられます。少なくともこの事変が独裁者・蘇我氏を成敗する勧善懲悪だの、中大兄皇子と中臣鎌足の権力欲だの、そんな小さい話で片づけられないことは確かで、例えばその理由の一つは外交戦略の違いが考えられます。
618年に隋を滅ぼして建国された唐は、628年ごろには国内を統一させ、徐々に対外強行路線を展開していきます。630年には朝鮮に近い東突厥を屈服させ、西部の国々も次々と属国化し、高句麗にも圧力をかけます。その結果、強い危機感を持った対唐強硬派が高句麗国内でクーデターを起こしますが、まさにこれを口実に唐が高句麗遠征を行います。一方、百済でも独裁的な政権が誕生し、高句麗と手を結びつつ、新羅との戦いが激化します。高句麗と百済の圧力を受けて、新羅でも改革が行われます。
蘇我氏の対外戦略は融和的です。元々は百済との関係が強かった蘇我氏ですが、新羅への侵攻を考えていた崇峻天皇を抑え、隋・唐との交流を始め、その後は高句麗や新羅とも交流を行います。こうして優れた外交力を発揮していたものの、唐vs高句麗、新羅vs百済と中国・朝鮮の対立が深刻化すると、各国から味方になるよう要請する使者が到来。皮肉なことに身動きが取りにくい状況に追い込まれます。
一方で中大兄皇子は、明確に百済に肩入れし、後には滅亡した百済を復興させるために朝鮮に大軍を派遣します。ちょうど、隋が生まれた頃の蘇我馬子と崇峻天皇との対立に構図が似ていますが、今回は積極的に介入することを志す中大兄皇子一派が政権を奪取しました。
中大兄皇子の権力掌握と不比等の誕生
乙巳の変で蘇我氏本家が滅び、ヤマト朝廷は大化の改新とよばれる制度改革を始めます。有力な豪族を次々と退け権力が集中していた蘇我氏本家。その蘇我氏本家を退けたことで、有力なライバルが消えたため、天皇家は自らを中心とした中央集権型の制度である律令制を推進することができるようになります。
男女の法で人民を定義し、仏教(当時は仏法)の興隆、組織体制の見直し、蘇我氏の基盤である飛鳥から難波への都の変更などがまず行われ、翌年改新の詔が発せられます。これまで各地域の豪族が有していた土地や人をすべて天皇家のものとし、天皇家の名の下に貸し与える「公地公民制」に移行します。この大化の改新の制度設計に深く関わったとされているのが、小野妹子と隋に行った僧旻と高向玄理です。彼らは共に国博士という役職に就き、日本式の律令制を設計していくことになります。同じく隋で学んだ南淵請安はこのとき既に死亡していますが、この律令制自体、彼の思想が強く影響したものとされています。
しかし、乙巳の変の立役者である中大兄皇子と、この変により即位した孝徳天皇とは、次第に関係が悪化。この対立は結局、孝徳天皇が崩御する654年まで続きます。655年、中大兄皇子の母である皇極天皇が再び斉明天皇として即位。658年には孝徳天皇の息子である有馬皇子を処刑し、ようやく中大兄皇子は朝廷での権力を確固たるものにします。
そしてこの翌年、中大兄皇子の盟友・中臣鎌足に次男が誕生します。鎌足には大化の改新以前に生まれた長男・定恵がいましたが、この時にはすでに出家し、遣唐使として唐に渡っています。そのため、この次男が事実上の鎌足の後継者となっていきます。
もちろん、この次男こそが藤原不比等です。
そして白村江の戦いへ
660年、中国・朝鮮情勢に大きな転機が訪れます。唐による百済の滅亡です。唐のライバルは高句麗ですが、高句麗は前王朝の隋のころから歴代の君主が何度も攻略に失敗している難敵です。そこで、まずは同盟国の百済を消すことで高句麗を孤立させ、新羅と共同して征服する意図があったとされています。
しかし、唐の主力が高句麗に向かうため旧百済領から離れると、各地で百済の遺臣が反乱を起こします。そこでヤマト政権は、以前から日本に滞在していた百済王の弟・豊璋を立て、当時蝦夷の征討などで成果を上げていた阿倍比羅夫などの軍勢を派遣。百済復興を目論みます。
当然、唐と新羅は百済に復興させないよう軍を派遣します。両者は白村江で戦い、結果はヤマト政権・百済連合軍の大敗。百済の滅亡は確定し、ヤマト政権は、これまで長く築いてきた朝鮮における権益や関係性を失います。朝鮮情勢への積極介入を試みた中大兄皇子の政策は、結果的に大失敗となります。
意外と勝機はあったかもしれない?
白村江の戦いは、後世の私たちから見ると、どう考えても無謀な戦いに見えます。唐との国力差は歴然ですし、百済を復興させたところでその後どうするんだという問題もあります。その悲壮感の中にはきっと、特に近代以降、日本が圧倒的に国力の差がある国に挑まざるを得なかった“歴史の記憶”による体験バイアスも含まれているかもしれません。
ただ、この戦いが本当に絶対に勝てるわけない戦だったのかと言うと、実はそうとも言い切れない微妙な背景があったりもします。
まず、当時のヤマト政権というか日本人というか、あるいは倭人というか、まあとにかくそこらへんの人は、単純に結構強かったみたいです。例えば当時東日本でヤマト政権の支配下に収まっていた人々は、ヤマト政権から中国・朝鮮の最新文化をもらう代わりに軍事力で貢献していたと言われていて、これがかなり強かったとも言われています。唐自体、官僚制度に基づく文化的な国家でいわゆる“文人”が政権の中枢を占める国。単純な軍事力の差は、国力の差ほどは無かった可能性が考えられます。
また、当時の唐は国内情勢も安泰ではありませんでした。649年に3代皇帝として即位した高宗は、当初は父である2代皇帝・太宗の側近を中心に政治を行っていましたが、655年に寵愛していた武照を皇后にし、後に則天武后と呼ばれる彼女とともに政治を行います。というより、病気がちな高宗に代わり事実上武照が政治を執り行い、最終的には高宗も彼女の言いなりになります。しかし当時の中国は、そもそも女性の権力者を認めていません。また武照自身の出自の身分も低く、皇后になること自体を側近から反対されていた経緯もあり、有力貴族との確執を抱えながらの政治となっています。
こうした微妙な国内情勢の中で、高宗・武照はこれまで歴代の君主が何度も失敗している高句麗の征討を行っています。そのため、もし局地的にでも敗戦や劣勢があれば、反対派に口実を与えかねない状況にありました。そうなると朝鮮どころではありません。案外、白村江に勝利すれば、本当に百済が復活する可能性も十分に考えられたように思います。
しかし、実際は唐・新羅が大勝して終わります。それにもいくつかの理由があるようで…。
結局、戦い以前の問題だった?
唐側の状況
上述したようないびつな権力機構ではあったものの、その権力を有している武照は、シンプルに政治家として優秀でした。有力貴族に好かれていないことで、彼女は非貴族層から優秀な人物を積極的に登用します。これにより、政権を支える人材は実力主義の様相を呈していきます。
ヤマト政権
百済復興に積極的で、自ら九州にまで赴いて陣頭指揮をする決意を示した斉明天皇が開戦前に崩御。中大兄皇子は皇太子のまま称制を開始します。
百済復興勢力
肝心の元百済勢力内では、白村江の戦い前に内輪揉めが起こります。ヤマト政権が立てた豊璋は少なくとも650年にはヤマト政権内にいたようで、旧百済領で反乱をしている武将たちの忠誠度はあまり高くありません。結局豊璋と武将たちは対立し、豊璋は有力武将の一人でいとこの鬼室福信を開戦2か月前に殺害してしまいます。
これはヤマト政権にとってもかなりの誤算だったようです。このときヤマト政権は先遣隊を派遣しており、彼らは百済軍と連携して旧百済南部の新羅兵を蹴散らすなど、戦局を優位に進めていました。しかし、この豊璋と鬼室福信の対立によって、白村江への到着が10日間遅れます。その結果、万全の態勢を取る唐・新羅連合軍を相手に正面から挑まなくてはならない状況に追い込まれました。
つまり、やりようによっては唐側にも付け入る隙はあったかもしれないが、それ以上にヤマト・百済側がゴタゴタしていて隙をつくなんて状態ですらなく、最も不利な状況で戦わざるをえなくなってしまった結果のようです。
なお、この戦いによって百済を完全に滅亡させた唐は、いよいよ孤立した高句麗を攻め立て、668年に滅亡させます。これまで、270年ぶりに中国を統一した隋の初代皇帝・文帝も、それを引き継ぎさらに拡大させた二代皇帝・煬帝も、その煬帝を倒した唐を引き継ぎ、「貞観の治」と呼ばれる治世を行った太宗もなしえなかった高句麗討伐を、武照が実現させたことで、彼女の権力は増大。後に、彼女は周という国を開き、長い中国史における唯一の女帝・武則天となります。
次回
時代は中大兄皇子から天武天皇へ。
そして、不比等の不遇の時代?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
