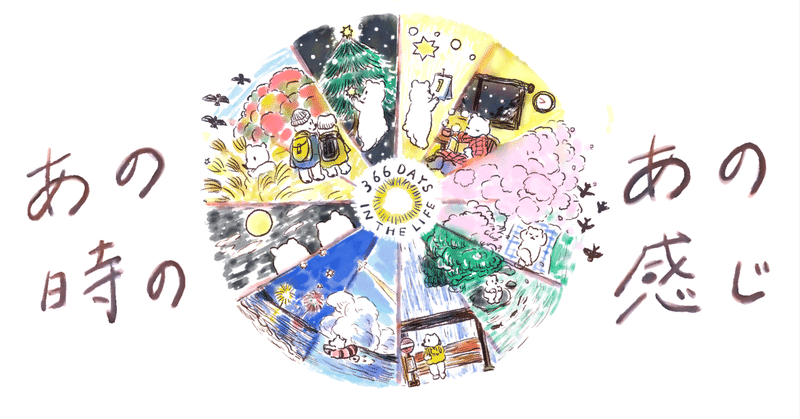
湖のそばで何もしないときのあの感じ|安達茉莉子
短い旅が好きだ。長旅じゃなくていい。数日間でいい。どんなに短くてもいいから、普段の生活の外にある場所に旅がしたい。お気に入りのストールと、両手が空く軽いバッグ、どこまでも歩けるような靴で自然の中を歩きたい。その土地の宿に泊まって、夜の気配を感じたい。朝の散歩をしたい。普段住んでいるところより寒かったり暖かかったりする気温の違いを感じたい。とにかくどこか遠くへ。
このひと月はそんな小さな旅ばかりしていた。旅行バッグから取り出した洗濯物が乾く暇もないくらいに。長野県の穂高の森、大阪の旧造船所にある北加賀屋でのブックイベント参加、韓国のソウル。ソウルから帰って数日後、群馬県は榛名湖のほとりにある榛名湖アーティスト・レジデンスに向かった。友人の現代アーティストがここで長期の滞在制作をしていて、彼女の話を聞くうちに、水辺での滞在生活に惹かれるようになった。水が満ちる田んぼに囲まれ、渓流のそばで育ったせいだろうか。昔から水辺が好きで、川や海、湖、池、何かしらの水辺がない場所では、私の何かが乾いてしまう。
JR高崎駅から路線バスで約1時間半。高度を上げてぐんぐんと山道をのぼるバス。一番後ろの席に座って窓の外を見ていたら、樹々の間に輝く榛名湖が見えた。標高1,100メートル。こんな山の上に、こんなに大きな水を湛えた湖があるとは。ここから川が下界に向かって流れ出していく。
バスを降りると空気は冷たく、澄んでいる。いっぱいに吸い込んで吐き出し、ぐるりと見渡すと、四方を山に囲まれた底がすべて湖になっていて、そのほとりに立っているようだった。秋特有の青い空、黄色、赤、緑、山全体がしっかりと色づいている。紅葉真っ盛り。綺麗な台形の「榛名富士」が湖の対岸に鎮座し、この風景の要のようになっていた。初めて訪れた榛名湖畔は、ここだけ外の世界から隔絶された舞台のような不思議な場所に思えた。
バス停から歩いてすぐのところにある、元々は旅館だった建物を改装したレジデンス。個室の部屋の窓からは湖が見えた。湖に接するように建てられていて、窓の下はすぐ湖面になっている。
畳に寝っ転がって、そのまま湖を見ていた。湖に来ようと思ったのは正解だった。湖のそばにある感覚は、海とはまた違う。海では、潮風に吹かれ、押し寄せる波の流れの音を感じているうちに、自分の中に滞っていたものが解放されていくような気がする。湖は真水で、風がなければ波も立たない。簡単に波が立つ一方で、すぐに湖面が静かに穏やかにもなる。それを見ていると、自分の内側にある湖もまた、本来静かなものだったと思い出すことができるような気がする。
畳の上で横たわっていると、背中から、いらないものがざらざらと砂になって落ちていくような感覚があった。その感覚は新幹線が走り出した時から始まっていた。走る速さで、後ろに流れていき、どんどん軽くなっていく。一日、汗と埃まみれになって作業した後に、ああ早くお風呂に入りたいと思うように、旅は私を丸ごと洗ってくれる。洗車機から出たときのように、家を出る前とでは全然違って感じる。その変化はきっと傍目にはわからない。他人から見たところで絶対わからないようなことが、大事だ。私にとって。
終わっていない原稿を持ちこんでいたので、そのあとは部屋に戻ってひたすら湖を見ながら文章を書いた。書くというより、書けなくて何度も消しては水を飲んだり窓を開けたりまた寝転がったりした。結局、書き終わったのは深夜になってしまった。カラカラと窓を開けて、部屋の電気も消して真っ暗にして、夜の榛名湖を見る。氷点下まで下がった空気に吹かれ、一瞬で体温が逃げていく。寒い。でも気持ちいい。体の中までこの冷たい空気を導入して、真夜中の湖の上で呼吸をしている。窓にもたれて外を見ていると、不思議な感じがした。音がないのだ。車の音だけではない。冬だからだ、と気づいた。
昔、兵庫県丹波篠山市の限界集落にある古民家で暮らしていたとき、季節を分けるものは温度ではなく音だった。夏の間はうるさいくらいに虫の音で賑やかで、秋になるとしみじみとするようなコオロギや名前もわからない虫が鳴いたりする。その音が一切消えたとき、冬がくる。あのときの音だ、と感じた。ここは湖のほとりだから、もう少し波の音がするかと思ったが一切しない。風のない静かな夜、無音の世界。車通りもほとんどない。見たことのない星座を描く星空と、黒々とした山々の重厚な存在感。音がないからこそかえって山の存在を感じるような、濃密な気配は昼間観光客に見せていたのんびりとした姿とはまったく違うものだった。
流石に冷えてきて窓を閉めて布団に戻ると、溶けるようにそのまま眠ってしまっていたようだった。目が覚めると既に明るくなっていた。慌てて窓辺に駆け寄る。夜明けの瞬間は見逃してしまったが、結露で濡れた窓を開けて身を乗り出すと、湖の上には遠くに靄がかかっていた。山々は朝日に照らされ、白い靄が水面を静かに移動する。
ここに泊まらなければ見られなかった景色だった。深夜も、早朝も、日帰りの旅では絶対に見られない。旅は一泊以上に限る。その土地の夜とその土地の朝を一度でも見ないと、なんだか滞在した気がしない。
朝の空気を吸いに外にでる。お腹もすいていた。昨夜の夜にテイクアウトしたポークカツカレーが美味しく、お店の雰囲気も素敵だった「カフェテラス・エヴァ」に向かった。レジデンスに宿泊していると言ったら喜んでくれて、明日は何時から空いているか聞いたら、朝7時頃からやってますよと言っていた。それも何だかかっこよかったのだ。モーニングらしいメニューはなかったので、一番軽そうな「はるなコケッコーサンド」にした。勇ましい名前でちょっと気恥ずかしい気持ちがしたが「はるなコケッコーサンドください」と正式名称で注文したら、店員さんがキッチンに「チキンカツサンドひとつ」と伝えるのが聞こえてきた。人生あるあるだ。
喫茶店の古いソファに座ると、大きな窓から湖がよく見えた。朝の日差し、大きな石油ストーブの暖かさ。朝8時の喫茶店には私の他にも何人か客がいた。バイクできた二人連れが「前もこの席だったね」と話していた。一眼レフであちこち撮っている若い女性。光の加減について「もっとこうしたい」「これよく撮れたね」と同行者と夢中になって話し合っていた。この瞬間、ここにいる人たちは、好きでここにいる。ふとそんな気がした。こんな朝っぱらから、好きなもののために、好きな景色を味わうために、ここにきている。本人たちは意識していないかもしれないが、とても得難く幸福な瞬間に立ち会っているような気持ちになった。天気もいい。まだ朝の8時。自由で、フリーだ。私たちはここからどこにだっていける。
はるなコケッコーサンドを平らげ、コーヒーもついでに頼んでぼうっと湖を眺めていると、店内のBGMに耳がとまった。ピアノでディズニーの曲をカバーした曲。美しいメロディだけれどなんの映画だったっけ……とアプリで調べると、映画『塔の上のラプンツェル』の劇中歌「I see the light(邦題:輝く未来)」だった。
好きな映画だったが、こんなタイトルの曲だったとは。I see the light——私は光を目にした。外の世界にずっと焦がれながら、長い間囚われていた塔を出た、主人公の曲。
そんな瞬間は誰にでも訪れる。ずっと暗闇の中を歩いていて、あるとき光が差し込む瞬間。ずっと囚われていたものからついに外に出た瞬間。世界は一瞬で変わり、何もかも信じられないくらい新しいものになる。そういえばあの映画にも、美しい湖のシーンがあった。
帰り道、その曲を聴きながら、湘南新宿ラインのグリーン車、2階の席に座った。半分眠りながら窓の外を見ていると、榛名湖の写真を送った友達からメッセージが入った。
「楽しいときが土日しかなくて、あとはそのためにひたすら働いているなんて、そんなの嘘だね」というようなことが書いてあった。
旅をしている間は思い出す。今この楽しくてどこまでもいけそうな感じが、本当だと。だけど、帰りどきもちゃんとわかっている。切なくて、だけど甘い。毎日が小さな旅のようになればいい。家についた後も、「この感じ」を、忘れなくていい。
結局、榛名湖では何もしていないのに遊び疲れていた。「何もしない」を本気でやるのは、実はとてもいそがしい。早く家のベッドに身を沈めたい。旅と日常、その狭間にある帰り道の列車の中でぼんやりと過ごす時間も、また良いものなのだった。

連載『あの時のあの感じ』について
今、私たちは、生きています。けれど、今を生きている私たちには、自由な「時間」が十分になかったり、過ぎていく時間の中にある大切な「一瞬」を感じる余裕がなかったりすることがあります。生きているのに生きた心地がしない——。どうしたら私たちは、「生きている感じ」を取り戻せるのでしょうか。本連載ではこの問いに対し、あまりにもささやかなで、くだらないとさえ思えるかもしれない、けれども「生きている感じ」を確かに得られた瞬間をただ積み重ねることを通じて、迫っていきたいと思います。#thefeelingwhen #TFW
著者:安達茉莉子(あだち・まりこ)
作家、文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆を行う。著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(twililight)ほか。
