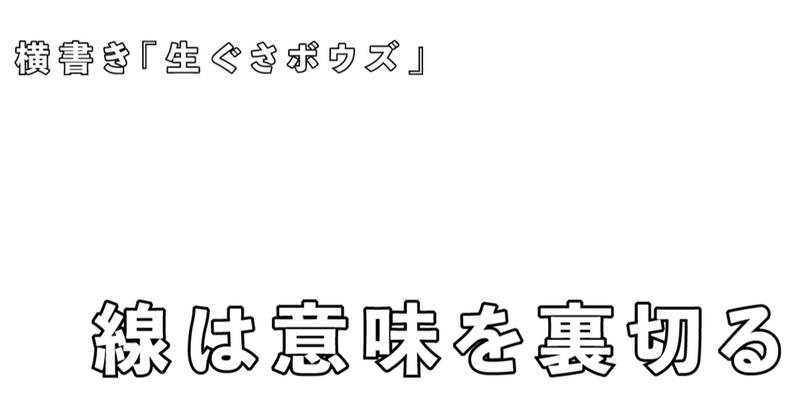
線は意味を裏切る
20211108
書をはじめて約2年になる。
前職をやめて個人で動きだすとおなじくらいにふと、やろと思ってはじめた。
筆をもち、身体を動かす。
たったそれだけのことのおもしろさに憑かれ、誰得なままにつづけている。
書って分野、取り組んでいる身ながら、しみじみと誰得な分野だと思う。
パソコンやインターネット、デジタルな世界で言葉が溢れかえってる中で、わざわざ筆で言葉を書く。
筆で一文字書く間に、タイピングであれば何字うてるか。遅い。極めて遅い。
それに情報伝達における正確性にも欠ける。
あとついでに言えば濡れる。水分を使うことと効率性の相性の悪さ。
昔のことはいざ知らず、現代で考えれば、書なんてものは不合理極まりない。いくらでもダメなところが挙げ連ねられる。
にもかかわらず、タイピングしたりこうしてフリック入力して言葉を記すのとは違った魅力がある。歴然とある。
その魅力ってやつは何だろうかと探ってみるに、文字を使う共同体が積み重ねてきた意味と、身体がもらたす線なり点なりの質感とが、せめぎあっていることなんじゃないかと、自分にとっての結論に至る。
たとえば「書」って字を書くとき、そこに書かれるべきコンテンツは10画の、線の連なりとしてある。「書」という字として共有される形をもって、「書」という意味が想起される。
ここまでは、なんてことなく、タイピングの「書」でも変わらない。
書における「書」は、意味の想起とともに、線や点の質感も一緒になってやってくる。かすれや揺れ、滲み。
その質感によって、確固たる伝達としての意味がゆらぐ。グラグラする。意味よりも、筆と紙との摩擦に焦点があう。とおもえば、文字を読み意味に帰る。
その往還にこそ、書のおもしろさがある気がしてならない。
現代の言葉(=意味)に溢れた社会にちょっと待ったをかけるスタンスで言い換えるなら、「線は意味を裏切る」。
正しくは、「線(を書いた身体)は、(正解として存在する)意味を裏切(ってゆさぶ)る」。
自分の取り組みが、自分が今記したことに見合っているとは到底思えないが、そんなことを目指せる可能性があることにワクワクする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
