
【中国の思想と文化】魏晋の「痴人」群像~『世説新語』に見る「痴」の諸相
はじめに
魏晋は、中国の精神文化史において、極めて特異な時代である。南朝宋・劉義慶の『世説新語』は、この時代の文化現象をパッチワークの如き逸話の寄せ集めによって、頗るランダムでありながらも、生き生きと鮮やかに再現している。
本稿は、「魏晋の「狂人」群像」(投稿済)と姉妹編である。
今回は、『世説新語』を中心として、『晋書』などの史書から資料を補いつつ、「痴」という概念に焦点を当てながら、魏晋の貴族サロンに集った名士たちの文人精神について考察を試みるものである。
「狂」と「痴」は、いずれも、元来はマイナスの字義を持ちながら、思想や文学の領域においては、必ずしも否定的に解釈される概念ではなく、むしろ、故意に正道から逸脱したり、世俗から離反したりしようとする文人精神が寄託されたプラスの概念として現れることが少なくない。
こうした思想性を伴った肯定的な用いられ方は、時代的には「痴」の方が「狂」に比べて大分後れる。
「狂」は、春秋時代、すでに孔子によって「進取の気」として肯定的に取り上げられている。これに対して、「痴」は、古くは専ら原義、すなわち病理的に異常であったり、知能的に劣っていたりする意味でのみ用いられており、魏晋に至って、はじめて特殊な文化的含意を以て語られるようになる。
そして、『世説新語』において端的に見られるように、「痴」は「狂」と並んで、この時代の典型的な人物評の一つを形成するようになるのである。
「狂」が動的で外向きであるのに対して、「痴」は静的で内向きであるというように、両者は、顕著な対照的性格を持ちながらも、文人精神を担う概念として通底する部分を共有している。
魏晋以後、明清に至るまで、「狂」と「痴」は、時には対峙的に、時には補完的に呈示されながら、反俗的・超俗的な文人たちが、思想的主張や文学的創作を行う際に好んで言及する概念として、中国の精神文化史にその系譜を保ち続けているのである。
一 「痴」の字義
(一)不慧
「痴」は、原義は、「慧(さと)くない、賢くない」という意味で、精神(心の働き)が足りないこと、あるいは鈍いことをいう。「痴愚」「痴鈍」「痴騃」などという場合がそうである。
清・段玉裁『説文解字注』には、
痴者は遅鈍の意、故に慧と正に相反す。此れ疾病に非ざるも、而して亦疾病の類なり。
とある。「慧」が心の動きが敏捷・活発であるのに対して、「痴」は「遅鈍」であることをいう。ゆえに、疾病とは言わずとも、それに類するものであるとしている。
「痴」の旧字(本字)は「癡」に作る。「疑」は、止まって進まないこと、迷い惑うことをいう。それが「疒」に示されるように一種の病態と見なされている状態を表す。つまり、事理に迷い、思考が停滞する心の状態を表す文字である。
(二)耽溺
「痴」には、派生義として、何か一つのことに心を奪われ、それにのめりこみ、耽溺するという意味がある。
「花痴」「書痴」などのように、一つの物や事に耽溺するものは「癖」というに等しく、また情愛に耽溺するものは「情痴」と呼ばれる。特定のことに極端な執着を示し、周囲の目には、愚かに映ることを指す。
(三)煩悩
「痴」はまた、仏教における三毒「貪・顚・痴」の一つとされる。『大蔵法数』十一に、
迷惑の心、之を名づけて痴と為す。若(も)し一切の事理の法に於いて、明了する所無く、顛倒妄取すれば、諸邪行起こる。是(これ)を痴毒と名づく。
とある。悟りを妨げる「迷惑」(煩悩)の一種である。
笑話の類で、愚行を犯す和尚をしばしば「痴」と称するのは、この文字が仏教用語として用いられることと関わりがある。
二 魏晋以前の「痴」の用例
魏晋以前の「痴」の用例は、基本的に、原義の「不慧」の意味で用いられている。
『春秋左氏伝』成公十八年に、
周子(しゅうし)に兄有れども慧無く、菽麦(しゅくばく)を弁ずること能わず、故に立つべからず。
とある。孫周の兄は、愚かで豆と麦を見分けることすらできなかったので、君主に立てることができなかったという。晋・杜預の注に、
不慧は、蓋(けだ)し世の所謂白痴なり。
とある。ここの「痴」は、低能、智恵遅れの意であり、知的能力が劣ることをいう。
また、『文子』「守法」に、
臣に任(まか)すは危亡の道なり。賢を尚(たっと)ぶは痴惑の原(もと)なり。天に法(のっと)るは天地を治むるの道なり。
とある。「痴惑」は、事に当たって分別を欠くことをいう。
以上の「痴」字は、いずれも愚昧・愚劣の意で用いている。
一方、『淮南子』「俶真訓」に、
夫(そ)れ人の天より受くる所の者は、耳目の声色に於けるや、口鼻の芳臭に於けるや、肌膚の寒燠(かんいく)に於けるや、其の情は一(いつ)なり。或いは神明に通じ、或いは痴狂を免れざるは、何ぞや。其の制を為す所の者異なればなり。
とあり、『論衡』「率性」に、
痴狂の疾(しつ)有るは、路に歌啼(かてい)し、東西を暁(さと)らず、燥湿(そうしつ)を睹(み)ず、疾病を覚(さと)らず、飢飽(きほう)を知らず、性已に毀傷(きしょう)すれば、如何(いかん)ともすべからず。
とある。「痴狂」は、癲狂病の類を指し、精神的に異常をきたして、気がふれたさまをいう。
このように、「痴」の文字は、能力的に劣ることをいう場合と、病理的に異常があることをいう場合とに大きく用例が分かれる。
さて、ここで特に注意を要するのは、「痴」字の使用頻度の推移についてである。
類義語である「愚」や「狂」の文字が、古くからごく一般的に用いられる常用字であるのに対して、「痴」は、その使用頻度が遥かに少なく、用いられる状況も限られている。
先秦の主要な文献中に、ほとんど用例が見られない。『論語』『孟子』『老子』『荘子』『詩経』『楚辞』など、先秦の思想・文学を代表する書物の中には、「痴」字の用例が一つもない。
史書においても、『史記』にはやはり皆無であり、『漢書』に1例、『後漢書』に2例、『三国志』では「魏志」に2例あり、「呉志」「蜀志」にはまったくない。
ところが、『晋書』に至ると、25個の用例があり、『世説新語』においても、計14箇所に用例を見ることができる。
この数字の推移は看過できない事実であり、「痴」字によって表される概念が、魏晋の時代に至って俄に注目されるようになったことの証左となる。
そしてこの時代、「痴」字は、単に数字上の量的な変化のみならず、生理的概念から文化的概念へと質的な転化を遂げるのである。
三 『世説新語』の「痴人」群像
『世説新語』には、多くの「痴」字の用例を見ることができる。
「痴」は、当時の貴族社会における人物評語として、しばしば用いられた言葉の一つであったが、この字に込められた含意は一様ではない。
以下、「痴」と称された人々をタイプ別に分けて、各々の典型的な例を挙げながら、その精神文化的背景を考察してみたい。

(一)愚昧の「痴」
「規箴」篇に、東方朔の機智を示す次のような話がある。
漢の武帝の乳母嘗(かつ)て外に於いて事を犯す。帝憲(けん)を申(の)べんと欲し、乳母救いを東方(とうぼう)朔(さく)に求む。
乳母既に至り、朔も亦側(かたわら)に侍し、因りて謂いて曰く、「汝は痴なるのみ。帝豈(あ)に復た汝が乳哺の時の恩を憶わんや」と。
帝は才雄にして心忍(にん)なりと雖も、亦深く情恋有り、乃ち悽然として之を愍(あわれ)み、即ち敕して罪を免ず。
「たわけ者!陛下のようなお方が、お前が乳を差し上げた時の恩など覚えておられようか」――東方朔が、武帝の乳母を罪から救おうとして演じたセリフである。武帝の同情を誘うため、わざと乳母を痴れ者呼ばわりしたのである。

ここでは、「痴」字は、原義そのもので用いられている。愚昧・愚劣の意であり、それ以上のものはない。
魏晋の時代に「痴」が特殊な精神文化的含意を以て用いられるのは、知識階級の男性に対して使われる場合のみであり、庶民階級の者や婦女に対する場合には、そのような含意はない。
また、「紕漏」篇に、息子が父親の愚行を人に言いふらしてしまう話が見える。
謝(しゃ)虎子(こし)嘗て屋に上りて鼠を熏(くん)ず。胡児(こじ)既に父の此の事を為すを知るに由無く、人の「痴人の此を作(な)す者有り」と道(い)うを聞き、之を戯笑す。時に此を道うこと復た一過に非ず。
謝虎子(謝拠)が屋根に上って鼠を燻そうとした。「馬鹿な奴が間抜けな真似をした」と人が言うのを聞いて、息子の胡児(謝朗)は、それが自分の父のこととは知らずに、周囲の者に吹聴してしまった、という話である。
ここでの「痴」も、ほとんど原義のままである。謝拠の行為には、愚昧な行いということ以上に、特に含むものはない。
(二)未熟の「痴」
「方正」篇に、名門貴族の王述が、息子の王坦之に持ちかけられた軍人の一族との縁談に激怒する話がある。
王文度(ぶんど)桓公(かんこう)の長史(ちょうし)為りし時、桓児の為に王の女(むすめ)を求め、王(おう)藍田(らんでん)に咨(はか)らんことを許す。
既に還るに、藍田、文度を愛念し、長大なりと雖も猶お膝上に抱著(ほうちゃく)す。文度因りて言う、「桓己が女の婚を求む」と。
藍田大いに怒り、文度を排して膝より下して曰く、「悪(いず)くんぞ見ん文度の已に復た痴にして、桓温の面(つら)を畏るるを。兵なり、那(なん)ぞ女を嫁して之に与うべけんや」と。
桓公(桓温)が、息子の嫁に、王文度(王坦之)の娘を望んだ。文度が、父の王藍田(王述)に相談すると、「馬鹿言うな、軍人などに嫁にやれるか!」と一蹴されたという話である。
ここでの「痴」は、分別のない愚か者という意味で原義に近いが、知的能力に劣る愚昧の意ではなく、世間知らずで、物の道理をわきまえない、という未熟の意を表す。
(三)奇態の「痴」
東晋の画家、顧愷之は、その卓越した画才・文才に加えて、数々の愚行・奇行で知られる。
「文学」篇に見える逸話に付した劉孝標注は、『中興書』を引いて、
愷之(がいし)は博学にして才気有るも、人と為りは遅鈍にして自ら矜尚(きんしょう)し、時の笑う所と為る。
とあり、「遅鈍」な上に驕り高ぶったさまが、人々の失笑を買っていたことを伝える。
さらに劉注は、宋の明帝の『文章志』を引いて、
桓温云う、「顧長康(ちょうこう)の体中、痴と黠(かつ)と各々半ばす。合して之を論ずれば、正に平平(へいへい)たるのみ」と。世に云う、三絶有り、画絶(がぜつ)・文絶(ぶんぜつ)・痴絶(ちぜつ)、と。
とある。この一節が、広く世間に語り継がれ、後世、顧愷之には「痴」というイメージが定着するようになる。

顧愷之の愚行・奇行は、例えば『晋書』の伝に、次のような逸話がある。
桓玄(かんげん)嘗て一柳葉を以て之を紿(あざむ)きて曰く、「此れ蝉の翳(かく)るる所の葉なり、取りて以て自ら蔽(おお)えば、人己を見ず」と。
愷之喜び、葉を引きて自ら蔽うに、玄就きて焉(これ)に溺(ゆばり)す。愷之其の己を見ざるを信じ、甚だ以て之を珍しとす。
身を隠す魔法の柳葉のことを信じ込んで、桓玄に小便をかけられてしまうという滑稽談である。このように、顧愷之の逸話は、人に騙されたり、コケにされたりという類の話ばかりである。
いずれも、世故に疎い間の抜けた芸術家の姿を彷彿とさせるものであり、阮籍や劉伶のような反抗的で奔放不羈な狂態とは質を異にする。
(四)有情の「痴」
「紕漏」篇には、幼少の頃は聡明を称えられていた任瞻が、江南に渡ってから様子がおかしくなった、という逸話がある。
童少の時、神明愛すべく、時人育長(いくちょう)は影も亦好しと謂う。江を過(よぎ)りし自(よ)り、便ち志を失う。王丞相先に度(わた)りし時賢を請(しょう)じ共に石頭(せきとう)に至りて之を迎え、猶お疇日(ちゅうじつ)のごとく相待するを作(な)せしに、一見して便ち異有るを覚ゆ。
席に坐し竟(おわ)り、飲を下せば、便ち人に問いて云う、「此れ茶為るか、茗(めい)為るか」と。異色有るを覚え、乃ち自ら申明して云う、「向(さき)に飲の熱為るか、冷為るかを問いしのみ」と。
嘗て行きて棺邸の下従(よ)り度り、流涕悲哀す。王丞相之を聞きて曰く、「此れは是れ有情の痴なり」と。
「志を失う」とは、精神や知能に異常をきたして、頭がぼんやりとしたさまをいう。王丞相(王導)らに出迎えられた際、お茶でもてなされた任育長(任瞻)は、茶と茗が同じものを指すことを知らずに、「これは、茶か茗か」と質問をしてしまう。
それをごまかそうとして、「熱いのか冷たいのかを聞いただけだ」と言い、茶にも酒と同様に熱いのと冷たいのとがあると思い込んでいることを露呈してしまう、という二重の失態を伝える話である。
このあとに、棺桶屋の前を通りかかって涙を流して悲しんだ任瞻のことを王導が「有情の痴」(情にもろい痴れ者)と呼んだ、というごく短い別の逸話が付け加えられている。
この一節は、「痴」と「情」とが結びついて現れる最も古い文献として、『牡丹亭還魂記』や『紅楼夢』など、後世の「情」を主題とした戯曲・小説を論じる際に、しばしば言及されている。
(五)隠徳の「痴」
「賞誉」篇には、王済が、痴れ者呼ばわりされている叔父、王湛の隠れた才能を武帝(司馬炎)に推奨する、という故事がある。
武帝、済を見る毎に、輒(すなわ)ち湛(たん)を以て之を調して曰く、「卿が家の痴叔死するや未だしや」と。済常に以て答うる無し。既にして叔を得、後に武帝又問うこと前の如し。済曰く、「臣が叔は痴ならず」と。其の実の美なるを称す。
王済は、叔父の王湛が学問にも技芸にも卓越した人物であることを知る。常々武帝(司馬炎)に「阿呆の叔父は、まだ生きているかね」と問われて、返答に窮していた。叔父の真価を知った後、また問われると、「わが叔父上は、阿呆ではございませぬ」と答え、王湛が頗る立派な人物であると褒め称えたという話である。
劉注が引く鄧粲『晋紀』に、
隠徳あるも、人の之を知る莫(な)し。兄弟宗族と雖も亦以て痴と為し、唯だ父昶(ちょう)のみ焉(これ)を異とす。
とあるように、一族の者みなが王湛の「隠徳」(隠れた人徳)に気づかず、彼を痴れ者扱いしていた。
「痴」と呼ばれる人間の多くは、実際には、決して「痴」ではなく、周囲の者がその才能や人徳に気づかないでいるだけなのである。

(六)大韻の「痴」
大人物の素質のある人間は、しばしば、痴れ者として世間の人々の目に映る。「任誕」篇に登場する羅友もそうした人間の一人である。
襄陽(じょうよう)の羅友(らゆう)大韻(だいいん)有り、少き時多く之を痴なりと謂う。
嘗て人の祠(ほこら)を伺いて、食を乞わんと欲するに、往くこと太(はなは)だ蚤(はや)く、門未だ開かず。主人神を迎え出でて見、問うに時に非ずして、何ぞ此に在るを得たるを以てす。答えて曰く、「卿の祠(まつ)るを聞き、一頓の食を乞わんと欲するのみ」と。
遂に門の側に隠れて、暁に至り、食を得て便ち退き、了(つい)に怍(は)ずる容(かたち)無し。
羅友には「大韻」(大人物の風格)があったが、若い頃は「痴」と呼ばれていた。
羅友は、物事に対して拘りが無い。祭祀の供え物をもらい受けるという乞食のような真似をしても、まったく恥じる様子がない。そうした行為を恥とする認識がもとより欠如しているのである。
同じ条の下文に、羅友の人となりを表すもう一つの逸話がある。
後に広州刺史と為り、鎮に之(ゆ)くに当たり、刺史桓豁(かんかつ)語(つ)げて莫(くれ)に来宿せしめんとす。答えて曰く、「民已に前期有り。主人貧しく、或いは酒饌の費え有らん。見(げん)に与(とも)に甚だ旧有り。請う別日に命を奉ぜん」と。
征西(せいせい)密かに人を遣わし之を察せしむ。日に至り、乃ち荊州(けいしゅう)門下書佐(しょさ)の家に往き、之に処りて怡然(いぜん)たること、勝達(しょうたつ)に異ならず。
羅友は、人と交わる際に、分け隔てをしない。地方長官から接待の誘いを受けたが、下級官吏の旧友との先約があったために辞退した。
相手の地位や身分によって自分の意向や節操を曲げたりすることがない。と言うよりも、もとより地位や身分というものが、まったく眼中にない。
「大韻」の痴れ者は、価値観が根本的に俗人と異なり、世俗的な物差しで世の中を見ることがない。それゆえ、しばしば世間体に無頓着であったり、社会常識を逸脱したりするために、人々から痴れ者扱いされるのである。
四 魏晋の時代思潮と「痴」
『世説新語』などからの用例によって明らかなように、古くは病理的な意味でのみ用いられていた「痴」字が、魏晋に至って、さまざまな文化的含意を以て当時の名士たちの人となりや振る舞いを語る言葉となったのである。
『世説新語』に登場する「痴者」の多くは、たとえうわべは愚かに見えたり、人々から痴れ者と呼ばれたりしていても、実のところは、決して愚昧・愚劣ではなく、むしろ頭脳明晰、博覧強記であったり、人徳的に優れていたりする。
彼らは、世俗と対峙した位置、あるいは世間から遠ざかった位置にいる。社会の常識やしきたりに拘ることがない、あるいは、そうした世俗的なものが、そもそも初めから念頭にない。
「痴」は、諸々の世俗的価値との対立を象徴的に示す一種の典型的人間像であり、礼教的な規範よりも人間的な逸趣を重んじる当時の思潮を反映する概念であった。
清談や人物評が盛行していた時代に在って、貴族社会のサロンでは機転の利いた談論やウィットに富んだ言辞が尊ばれた。颯爽として弁舌に巧みであってこそ、周囲の高官や文人たちに注目され、名士として認められた。
そして、サロンである以上は、そこに集うインテリたちと交際することが求められた。どれだけ学問に優れていても、周囲の人々との交際を絶って、独り書物の世界に没入しているような者は、「痴れ者」のレッテルを貼られ、疎外されたり、嘲笑の的となったりしたのである。『世説新語』の中で、寡黙・訥弁で非社交的な人間が「痴」と呼ばれているのは、そのためである。
魏晋を代表する「狂」の人、阮籍は、同時に「痴」の人でもあった。
『晋書』「阮籍伝」に、
或いは戸を閉じて書を視、月を累ねて出でず。或いは山水に登臨し、日を経て帰るを忘る。群籍を博覧し、尤(もっと)も荘老を好む。酒を嗜(たしな)み能く嘯(しょう)し、善く琴を弾ず。其の意を得るに当たりては、忽(こつ)として形骸を忘る。時人多く之を痴と謂う。
とある。何ヵ月も門を閉ざして読書に耽ったり、山水を遊覧して何日も帰らなかったりというように、世俗との没交渉が「痴」と呼ばれる一因となっている。
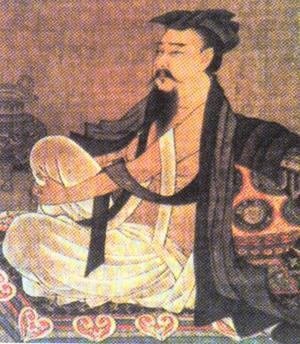
「痴」の字面は、甚だ醜悪なものであるが、この時代において、「痴」と呼ばれることは、不名誉なことではなかった。
しばしば「人は之を痴と謂う」という類のフレーズが用いられるが、ここでいう「人」とは、俗人である。俗人から誹謗中傷されることは、反俗的な文人にとっては、むしろ望むところであった。
総じて、「痴」は「俗」と対峙する概念として、当時の文人たちが好んで用いた言葉である。
「痴」は、俗気のない一種の「雅」の表現であり、また「雅」にありがちなペダンチックな気取りや臭みなどを抜き去った素朴で無垢な「雅」の心態を表すものであった。
それゆえ、「痴」に対しては、その否定的な字面にもかかわらず、肯定的な含意が賦与され、時には、文人の本来あるべき理想像として、畏敬や羨望を以て語られたのである。
魏晋は、既成の価値観に対して懐疑の目が向けられた時代であった。
伝統的に良いとされてきたものが否定され、逆に、そうでないものが肯定されるという価値観の顛倒が起きやすい風潮にあった。
「痴」が肯定的な含意を以て用いられるようになった背景には、「痴」の反義語である「慧」の字が、基本的には肯定的な意味を表すものでありながら、時として、否定的含意を以て用いられたことが、その要因の一つとしてある。
「慧」は、聡明・利発の意であるが、「黠」(悪賢い)に似た、マイナスの語気を伴うことも多い。「痴」は、まさに、そうした小賢しさや小利口さのない心態をいうものである。遅鈍であることは、小賢しい利発さが無い分だけ、むしろ純真で篤実な心態として、プラスに解釈されたのである。
おわりに
「痴」は、しばしば「狂」と併せて論じられる。「狂」が、動的で外向きの発散性を示すのに対して、「痴」は、静的で内向きの凝固性を示すというように、両者は、運動性・方向性において、顕著な対照的性格を持つ。
「狂者」が、世俗に対して反抗的で、激しい姿勢をとるのに比べて、「痴者」は、世俗に対して無関心・無頓着で、栄達や功名など、世俗的価値に対する反応が鈍い、あるいはまったく興味を示さない。
「狂」は、春秋時代、孔子が「進取の気」として、「狂狷」に対して積極的な価値を認め、また古代人の伝統的処世術として、「佯狂」が明哲保身の強い生き方として是認されてきた。
一方、「痴」は、久しく原義のまま、知性的に劣っていたり、病理的に障害があったりする意に用いられ、魏晋の時代になって、初めて精神文化的範疇の含意を備えるようになった。
なお、「痴」は、後世、とりわけ宋詞や明清の戯曲・小説において、派生義である「耽溺」の意が「情」と結びついて、専ら男女の間の凝り固まった情愛を表す「情痴」がクローズアップされるようになる。
「痴」は、通俗文学のテーマとして、重要な位置を占めるようになる。
清の『聊斎志異』や『紅楼夢』などでは、「痴人」は、愚かしいほど純真で偽りのない人間像として、文学における新しい人物形象の一典型となるのである。

関連記事:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
