
小説『エミリーキャット』第25章・マジョリティワールドで見る夢は…
美大教授の鷹柳から電話があったのはその日の午後だった。
盗まれたロートレックが無事返ってきたという。
なので保険のことはもう気にしなくていい、奔走してくれて本当に有り難う、済まなかったね、との電話に彩は胸を撫で下ろすと同時に涙が浮かぶのを禁じ得なかった。
窃盗犯はグループで、絵や彫刻ばかりを盗むので有名な窃盗犯一味であったらしく美大教授で美術品や骨董品を収集している鷹柳教授のことを噂に聴き、氏の留守を狙って鷹柳宅に入ったという。
その後別宅の弁護士宅へ盗みに入った時、家中に張り巡らされた盗難防止対策の赤外線探知機に引っ掛かり猛烈な音量のベルが執拗に鳴る中、窃盗犯達は屋外へ逃げ去りはしたものの、一味のうちの一人が広い家の中逃げ惑ううち迷子になり、鍵を壊して侵入した台所のお勝手の場所が彼だけが解らなくなってしまったというのだ。
窓も部屋々のドアというドアも、
ありとあらゆる逃げ場は悉(ことごと)く自動の施錠が卸され、窓硝子は二重硝子である上に硝子そのものが割れにくい加工硝子であったために美術盗人はその場で釘付けとなり、やがて来た警官隊にお縄になったという。
他の仲間はその‘’迷子になった”一人を除いて勝手口から全員逃げおおせたのの、その迷子になった一人からの聴かれるままに答える、まるで小学生のように素直な陳述から、仲間はその日のうちに全員逮捕された。
彩は迷子になったという犯人を莫迦にして高らかに嗤いながら
『でもそこまでの警備を室内に網羅するくらいなら、最初から侵入出来ないようにすればいいのに、そのお宅もちょっぴり片手落ちですね』
と言った。
『確かに家の主(あるじ)は留守だったが家政婦さんはちゃんと居たんだ、
居て庭の掃除をしていた。
その為、お勝手のドアだけは普通の鍵しか閉まっておらず、いつも通りになっていたんだね』
彩は口に出しては言わなかったが、心中『自分達で計画的に入っておいて迷子になったことといい、何もかもが笑える話でしかない』
と思った。
鷹柳は『まぁ然しその迷子になった彼は目の超えたある意味、ディレッタントだったわけだね、
とはいえ彼自身がそれらの作品を蒐(あつ)めていた訳でもなんでも無かったのだが…。
訊けばまだ若い四十にも満たない男らしいからどうか穏便に、と警察にも頼んでいたとこなんだよ、
これを機に足を洗って立ち直って欲しいと願ったりもしてね…』
とまるで自分の家に泥棒が入ったというのに鷹柳氏はひとごとのようにどこか和やかであった。

『何しろ彼も気の毒なとこがあってね、自閉症らしいんだが…そのせいで今までいろんな職を転々としてきたらしいんだ、
だけど彼自身は真面目に努めてる積もりでも計算が不得手だったり、
あれが出来ない、これが出来ない、おまけに相手の目を見て話さない、時々空気を読まない妙な発言がある、で、気味が悪いなどと言われてクビになる、
そんなことばかりが立て続けにあって彼も自暴自棄になっていた時期があったそうだ…
そんな時だ、クビになったもとの職場の先輩達から泥棒の一味にならんかね?
とかなんとか誘われたらしい…。
その先輩達というのは平素はコンビニの店長やその店員達で…特に美術に関心があるわけでもなんでもないが、マニアに高く売る外国のルートを知っていた為にそんなことをするようになったらしい、

偶然なんだがその自閉症の彼は絵描き志望者でね、
彼がアートオタクなのを偶々(たまたま)知っていた店長が目利きの彼を見張り番兼美術品の見識役として使えると思ったらしい、
つまり…自分の障害の為になかなか思うように普通に働くことも出来ない彼を、彼の先輩の健常者達はまんまと利用したんだよ、
コンビニエンス・ストア関連なだけにその彼を、それこそ簡便に使えるとでも思ったんだろうね、
もっと云えば‘’莫迦と鋏は使いよう”なんて思われでもしたのかもしれない、
無論、彼は単なる莫迦でも鋏でも無いのだが…彼の才智を発揮出来る場所など普通の世の中でなかなか無かっただろうし莫迦にされてばかりの人生を送ってきたのかもしれないね、
それに比べたら先輩達のほうは、
窃盗なんかしなくったって、ちゃんと仕事があるわけだし、そりゃあ素晴らしく稼ぎがいいってわけじゃなかったかもしれないが自閉症の彼と違って彼らはどうとでも出来たはずだ、
少なくとも健康で、職にあぶれてもいないし借金があったわけでもない、
泥棒家業を兼業する必要なんか全く無かったはずだからね、
彼らはもっともっと潤沢な金が欲しかったしそれだけでなくスリリングな思いもしてみたかっただけだ。
何をやってもうまくゆかず悩んでいた彼はその悩みに巧く便乗され、
おまけに利用された、
お陰で今や前科までついてしまった、
…随分な話じゃないか』

『……』
『彼の描いた絵というのを実は僕は後から知ったんだが…数点過去5年程前に観たことがあるんだ、
彼の苗字がかなり変わった苗字で無かったら、僕も気がつかなかったかもしれないがね、当時、私が審査員の一人を務めていた新人賞のコンテストで彼の絵を私は推薦したのだが…残念ながら他の審査員達全てがこれは佳くないと苦(にが)い顔をしてね、
当然ながら結果は落選だった…。
だが私の記憶を辿る限り、彼の作品はかなり激しく風変わりで粗削りではあるが素晴らしかったよ
確かにアカデミックなところは少ないが…このまま埋もれ木にしてしまうのはあまりに惜しいと思えるものだった…。
あの時、彼に声を掛けていれば少しは違っていたかもしれないなんて…今頃ふと後悔してしまったりもするんだよ、
だから私は彼が将来、刑務を終えて出所してきたら、私は秘書なんか雇わない主義だったが、私の家で秘書として雇おうかと実は思っていてね、
秘書が難しかったとしたら、家事を手伝ってもらうだけでもいい、
庭師を雇うのもお金が馬鹿にならないから彼にやってもらったら素人だし、まぁ不細工な庭木や庭にはなるかもしれないがそれはそれでキュービズムか野獣派風の庭だとでも思えば案外、楽しめるんじゃないかと思うよ、
特別行儀のいい庭じゃなくても構わないと私は思っているほうだから、』
彩は驚いて鷹柳の気は確かか?
というようにやや声が昂(たか)ぶった。
『そんなことまで先生がなさらなくても、
その人は先生の家に入った泥棒なんですよ?』
『あぁそうだよ、可笑しいかね?
だから私はみんなから鷹柳はキチガイだなんて言われるんだ』
『でも…』
『彼が今、刑務所に入っているのはなんだか私にも責任があるような気がしてね…
おまけに彼は才能がある、
どうにかしてやりたいと思うのは自然の理(ことわり)だと思わんかね?吉田くん』
『…そこまで先生が責任を感じる必要なんてあるんでしょうか?
確かに障害のある方を泥棒に誘った人達は狡猾で悪質だとは思いますが…その彼だって誘われても断ることが出来たはずですわ、
その悪い誘いに乗ったことは、彼の弱さだったと思いますし…
いくら自閉症と言ったって、本気になってちゃんと探せば他に仕事だってあったはずです。彼も自閉症といえ、もうとうに大人なんですもの、
彼自身の詰めが甘かったんだと私は思いますわ』

『詰めが甘い、か…』
鷹柳は苦笑した。
だが好ましい彩相手に議論を交わせることが初老のこの孤独なインテリ紳士を心慰めるのかもしれない。
その苦笑もどこか愉しげだった。『お陰で‘’子供の詰め手”というリチャード・ダッドの絵を思い出したよ、
あのチェスをする子供の絵は本当に子供なのだろうか…?
大人が傍で寝ている間にこっそりと駒を動かすことを楽しんでいるかのようにも見えるが、それはいかにも、な感じが私にはしてね、
私にはあの子供の快楽にひきつれたような顔に、自分の奥深くに睡る将来目覚めるであろうデーモンを感じた孤独な男の茫然とした顔を見る思いがするよ、
これは穿(うが)った私だけの見方にしか過ぎないが、あの子供は将来人々を堂々と恐喝し、ひれ伏す者にだけ施すこともある支配者としての自分の行く末を予見し、慄然(りつぜん)としているのではないだろうかとね、
と同時に駒を操れる立場に君臨する自分の未来像に心酔し、愉悦すら噛み締めてもいる、
もしかしたらこれは『子供の詰め手』と銘打ちながら、子供より悪質でたちの悪い大人を描いているのかもしれないとね、
しかもこの大人はなまじ権力と、
それを意のままに行使することの出来る特別な立場を持っているから、よりたちが悪い、
リチャード・ダッドは夢幻の世界を多く描き続けたが、象徴的で生々しく同時に鎮かな世界観の絵も少なからずある、彼は狂気に埋没する前は物静かな人柄であったともいうが、…絵描きだからね、
元来、酷く観察眼の鋭い男だったことは間違いがない。
私はダッドを知るにつれ思うんだ。
彼はパトロンに求められるがままに連作を極める為、過酷で多忙な異国での旅先で日射病に遇い…
それが病いの発端になったとは言われているが、果たしてどうなんだろう?あくまで引き金にしか過ぎないだろうね、何故ならばダッドは家系的にも精神病の人があまりにも多い、
結局段々に壊れていって…
最終的には彼に別宅をあてがって療養させていた息子思いであると同時に、現実逃避の父親を殺めるまでの狂人となってしまった…。
だが、彼の作品の中にもその病んだ芽は確かに垣間見えながらも一生を通じて決して消えることの無かったもう一つの確かな‘’夢”は、現実に豊かな実を結んだんだ。
病みながらも彼の描くファンタジーは単にファンタジーとは呼べないリアルなビジョンがある、
狂気に純然と埋もれたかのような彼の行住坐臥に置いて時折、音の無い遠雷のように遠く閃く光のような…それは絶対に狂気ではない生者が放つ光だったと思う。
その光こそが彼のビジョンだ。
眠っているような霞が掛かった世界で、彼は無自覚に生きる光を半分、麻痺して見える薄い膜の向こう側から描いていた…
残念なのはそのビジョンは彼亡き遥か後年、認められるに至るわけだが…ゴッホとて似た部分はあるよね…。
だがダッドは命のある限り、与えられた時間の限りを尽くしてそのファンタジーに命を与えるべく全てを収斂した。
描くことだけに、夢にリアルなビジョンを与える為だけに、恐らく飲食など二の次だったんじゃないだろうか?彼は持てる力の全てをカンヴァスに収斂し、注ぎ尽くした…。
彼はそうやって半生を精神病棟の中で絵を描いて過ごしたもののそのことに気がついた人は少なかったかもしれない、
当時もし、私も彼の周囲に生きていたならやはり当時の彼の周りの人々と同じように彼を恐ろしい狂人としか見ることは出来なかっただろうと思う。
それは無理もない、誰だって自分や自分の生活や自分の家族の平和を守りたい、


だが残念なのは、苦しんでいる人を社会的にあまりにも長く放置したり、無関心と同時に敢えて孤立化をさせてしまうような社会性が日本はむしろ常識的ですらあるような国だ、
でも誰もこのまま眠ったような状態でいいと思ってるんだろうか?
無関心やあるいは無関心ではないが、放置はしょうがないとする心理状態は、私は眠ってしまっているのと同じだと思う、
単なる眠りではなくて悪質な惰眠だよ、
もしかしたら明日は我が身とは思わないのかね、
楔(くさび)を打たれなくては誰も目覚めないのだろうか、
自分と自分の家族さえよければ正直あとは野となっても山となっても、まぁ気の毒だけどしょうがないって国民全体を覆う気質には、私は善良なる『眠り病』って名前をつけたいくらいだよ、

『あの人は病んでいる』とかよく言うだろう?
自分はそうでないといった無自覚の前提に基づいてそう言うんだろうが、病んだ人々のSOSを聴かなかったふりをして、見ざる聴かざるのほうはしっかり行っておきながら、言わざるのほうだけ自由自在だなんて…
狡(ずる)いじゃないか、
『穢(きたな)くて狡い』なんてそれだって物凄く病んでると私は思うがね、
同じ病んではいても社会的に巧く適応出来ているか居ないかの違いで、他者を堂々と見下ろせるだなんて、なんて厚かましい話なんだ、
たとえダッドのように息子を愛する家族が居たとしてもだ。
その家族が居ながらにして、我が子の病いを認めたくないあまりに半ばやはり放置に近い不適切な状態になってしまうことにより心優しく本来は穏やかだったダッドの気質さえも病いに犯され変わっていってしまったという…
今も昔も変わらないこの現実だ…。
…助けを必要としているのは何も子供ばかりじゃないのだがね…』
『ダッドは私も好きな画家の一人ではありますけど…
彼は確か…本当は統合失調症だったのではないか?と言われていますわね、
当時の時代背景を思えば今の時代、障害のある方達にとっても随分と受け皿の多い”選べる時代‘’というか、むしろ恵まれていると思うんですが…。
彼は泥棒なんかしなくてもそういったところへいくらでも相談出来た筈です。』
鷹柳は急に毅然としてこう言った。『それは吉田くん、
君がそれだけなんでも出来る人だからこそ言える言葉で、その言葉が大多数の人達やこの世界のほとんどの場面できっと圧倒的な黄金比となって彼のような生きづらさに喘いでいる人間をますます何も言えなくしてしまい、更に隅に追いやって
揚げ句、潰してしまい兼ねない考えでもあり風潮でもあると私は感じてしまっているのだが…どうかな?』
『……』
『吉田くん、君は優秀で聡明な女性だ、
でも優秀で聡明な君の常識が他の誰かにも当てはまる訳じゃない、
変な言葉に聴こえるかもしれないが、正論ばかりがいかにもまるで警官のように幅を利かせるこの世の中だ、
正論がいつも正しいとは限らないよ、
多分警官もだと私は思うがね、
その正論が暴力となることはかなりの比率で多いことでもあるからね、
健常者と呼ばれる我々には合う身の丈のものが合わない人間もいれば、この世の中のサイズ感があらゆるところで違うと感じていて、その為にゼェゼェヒリヒリと朝目覚めて夜、眠りにつくまで毎日を苦しみ、息切れする思いでそれでも努め、それを隠して生きているマイノリティの人達は我々や我々の為にしか作られていないこの今の世界を、一体どう思っているんだろう?
そして我々はそれについて少しでも何か違和感を感じたり真剣に想いを馳せたことはあっただろうか?
』
『…私達の為にしか作られていない世界?』

『たとえば…これは障害ではないが左利きの人には恐らくあらゆるところで暮らしにくい造りに世の中出来ていると思う、
左利きの人はある程度昔からのことだから、その多少の不自由感に慣れながら生活してゆくことに適応してゆくのだと思うが中にはどうしても適応出来ないサイズ感の違いにとても苦しむ障害者の人達だって居る、
では彼らは一体どうすればいいのか?
答えはこうだ、
どうにもならない、
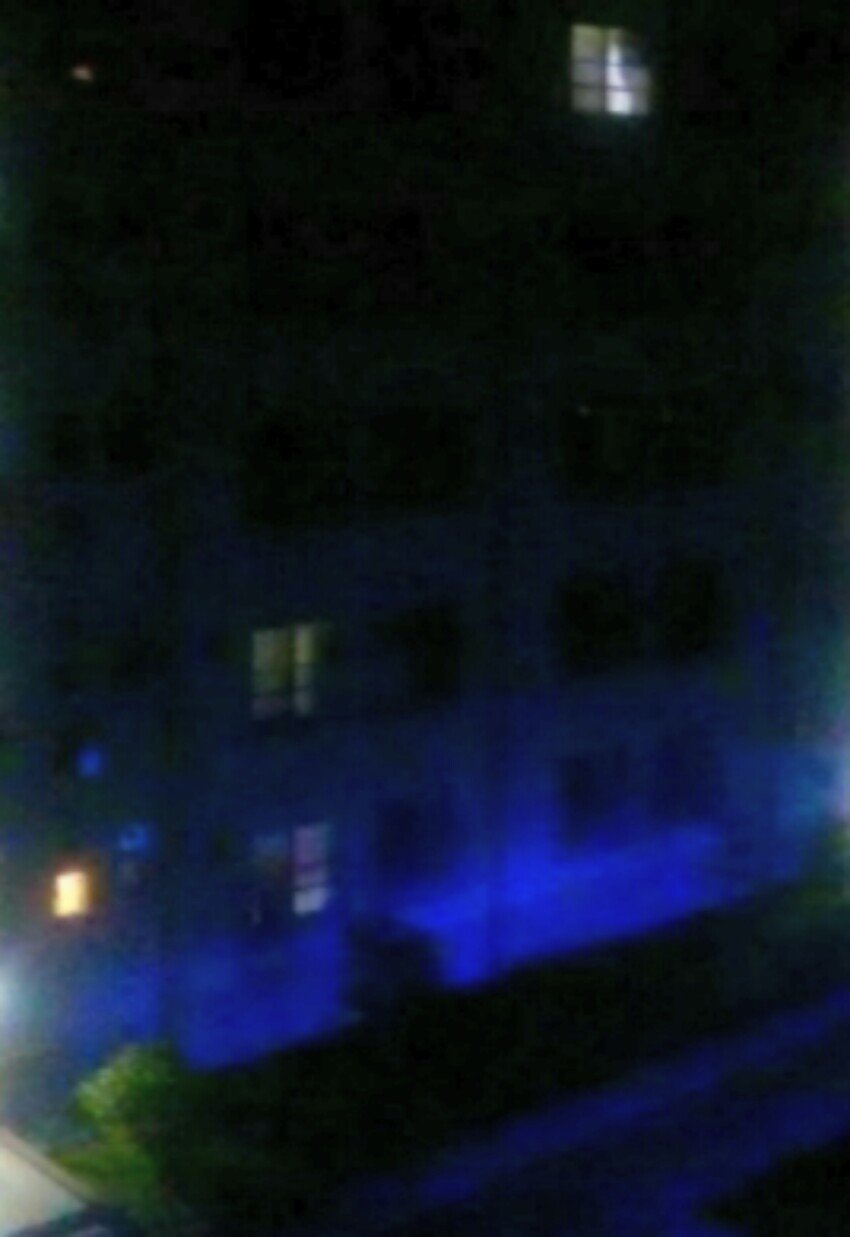
彼らのほうでこの健常者と呼ばれる私達多数派の人間達の為にしか肉体的にも精神的にも構築されていない世界は、彼らにとってはその為にとても生きづらい世の中だ、
しかしながらそれに無理矢理、慣れてもらうか、どうしても慣れることが出来ない場合は社会からあぶれてもらうか?
あぶれた場合病院か刑務所かどこかへ閉じ込めておくか?
たとえ家に居ても理解なんて微塵も無い詳しい事情すら知らない近所の者達や、あるいは無理解な家族や親族からのむしろ積極的といっていい白い目を向けられるのを一生耐えてもらうか?
マジョリティワールドはマイノリティの人達にとっては外国人がまるきりの異文化の中で生きるかのようにもう存在しているだけでも必死なんだよ、そこへ我々の文化の物差しを当てたり、測ったりしたところでなんの意味も持たないんだ、

何故ならばその物差しもこのマジョリティワールドも彼らのことは一切考えずに造られたものでしかない、マイノリティの人々にとっては常日頃から支配か、さもなくば懲罰か、その二者択一ばかりを迫られる。
辞めて余所へ行くような選択肢は、彼らにはほとんど零(ゼロ)に近いというのにだ。
尊重や思いやりすら時には生存することそのものまでもが引換券のようになって相殺されてしまうといった事態さえ無自覚と言い切ってしまうとしたならば、私達普通の人間達とは一体なんと嗜虐的な生き物なのだろう、
彼らを孤立化させてしまい兼ねないこの我々の為の世界地図は、むしろマイノリティの人達を排除して造られたものでしかないからなんだ。
だから彼らにしてみればその地図を基にあらゆるところへ行ったって、どこも皆、違う文化圏ばかりで彼らは自分達が同じ言語をしゃべる異邦人でしかないのだとついには諦めてしまう、
それは行政であり福祉であり時には医療もそうだろうね、
諦めてしまいながらも生きていて、恐らくこんな無念は無いと思うがね』

『…マイノリティの人達を排除して…創られた世界…?』
彩の遠い記憶から痛みを伴いながら赫い女の指先が風に舞う花びらのようにひらひらと甦った。
『無論、この世界の住人が創るわけだからよりよい世界、より生きやすく住みやすくと思って厚意的に構築されたものには違いない、
けど構築する際に自分達とは同じように生きるのが難しい人達のことを話し合いのテーブルの座に果たして着かせたことが一度でもあっただろうか?
テーブルに着かせるまでしなかったとしても、声くらい聴いてみたことがあったのだろうか?
そのほとんどに置いて否だと私は思う』
『…正直よく…解らないんですけど…でも先生の正義感は理解したいと思います』
『正義感なんかじゃないさ、
とんでもない、私は正論をふりかざす人間は姑息で嫌いだ』
鷹柳は笑った。
彩の前だけで見せるそれは散々傷ついて生きてきた人間が心を許した証しを見せる笑いだった。
『ただ解りやすい例を挙げれば、
私の数少ない友人がポリオでね、
車椅子に乗って生活しているんだが、彼の夢はなんだと思う?』
『…夢…さぁ…車椅子のまま奥様と一緒に、世界一周旅行へでも行くことでしょうか?』
『うんそれも素晴らしい、
だがね、70歳になる彼の夢は、近所のマクドナルドの二階に上がってあの窓辺のスツールに見知らぬ若者達と並んで座り、好きな音楽をイヤホンで聴きながら、駅から流れるように走る電車やプラットホームを行き来する人々を見て、フレンチフライとビッグマックを食べ、
コーラを飲むことなんだ』
『……マクドナルドが…夢…』

『マクドナルドは大抵が二階へは階段だ、マクドナルドに限らないがね…素敵な店や入ってみたい場所は大抵、彼らには上階へ行くことは不可能な造りにどこもかしこもまるで当たり前のように出来ている、
彼らは仕方無く諦観して暮らしてはいるものの、本当はみんなと同じようにそんな場所へも行ってみたい、と思っているんだよ、
同じ人間なんだから当たり前だよね、
それと同時に目には見えない外側から解りにくい障害を持つ人々は、
ではどうなんだろう?彼らの感じるサイズ感の違い、生きにくさは恐らく…もっと我々の世界では目には見えないだけに無視されて当然のようになってしまってはいないかな?
世の中は我々のような内にも外にも取り立てて障害や病いのない人間が暮らしやすいよう、生きやすいよう、肉体的だけでなく心理的にも構築されてはいるが、それはマイノリティの人々にあくまでもとても我慢してもらっている世界でしかないんだよ。』

電話を切った後で彩は来月オープン予定のヨーロッパからの作品郡の写真のコピーとその作品名とにファイルを繰りながら目を通した。
通しながら頭の中にそれらが
まるで入ってこなかった。
彼女はぼんやりと目の前のデスクの上に自分で淹れて置いた珈琲を見つめた。
珈琲の表面の白っぽい半透明の渦(うず)は、狭霧のように煙りながら左にゆっくりと回っていた。
自分が右利きだからそうなるのか?と思い、彩は左手でもう一度珈琲を掻き混ぜようとして気がついた。
自分はいつもブラックなので一度も珈琲を混ぜてはいないはずだと。
彼女は試しに左手で珈琲を掻き混ぜてみたが、やはり珈琲は左側に回り、どうやらそれは室内の空調の流れで無理矢理そうなるのだと解った。
湯気が立ちのぼり、その湯気で作られた一番底の渦がカップの中で二層となった霧のような湯気に吹き寄せられ、渦の回転に変化が一瞬生じた。
珈琲の表面に液状の紙撚り(こより)を寄せたような微細な捻(ねじ)れが表れるのだ。
それは程無く空調により否応無く強制的に元に戻ってしまうのだが…。
彩は胃を労りたくてその日はミルクを入れたが、ミルクを入れて2、3秒置き、底に一度落ちたミルクが表面へ浮き上がってくる様を彩はまるで生まれて初めて見るかのように驚いて瞠目した。
その様子はまるでちょっとした万華鏡のようで、
こればかりは空調に左右はされないようだった。
彩は何故だかそれを嬉々として見守った。

一度底へ沈殿したミルクが底から湧き上がり、表面に達して次々とさながら新体操の手具のリボンのように、カップの底から螺旋状にシュルシュルと揺らめきながら立ち登ってくると同時に、ミルクのリボンは珈琲の湖面でたちまち歪(いびつ)な水玉となり、無数の蕩(とろ)けた小花となって不器用に花開く。
その時さながら珈琲の表面では飽和状態のプリズムのようだ。
あらゆるものの姿を一瞬借りては消え失せ、借りては消え失せ、やがて小さなマーブル模様となったかと思えば模様は珈琲の地色にすぐに溶解し、それはフラットなライトブラウン一色と化した。
室(へや)の照明だけが映り小さく揺らいでいるのを、彩はどうしてこんなに失望して見ているのか自分が解らなくなった。
彼女は思った。
かつて自分がまだ、うら若い頃これと似た気持ちに支配されたことがあったと…。
何故あんな風に、まるで自分が異(ちが)う人間のように振る舞い、
それを止めることがどうしても出来なかったのだろう?
まるでもう一人の彩を彩自身がただ傍観することしか出来なかったかのように、あの無気力と恐怖感は何ものにも喩(たと)えようが無い。
追い詰められた人間は『異う人』
になることもあるのだと彩はあの時知った。

私は私を産んだ 母を知らない、
母の顔も知らないし当然、顔写真一枚見たことすらない、戒名を書いた黄ばんだ半紙と母子手帳だけが私の知ってる母親の形見の全てだ。
父親はもっと解らない、
知っているのはバラバラになったジグソーパズルの欠片(かけら)のような耳を塞ぎたくなるような悪い噂ばかり、
しかもその噂は現実へと地続きに繋がっている…と彩は思った。

母親はうら若くして家出、売春、窃盗で捕まり、刑務所内に併設された病院で彩を産んだ。
その時に狭骨盤による難産の為、出血が止まらず夭折していた。
別の噂では狭骨盤というより医療ミスで出血が止まらなくなり意識が戻らず亡くなったのだという説もあった。が、今となってはもうどちらが真実なのかは解らない、
母が居た最期の地である刑務所は既に遠方へと新しく移設され、
かつての土地はラブホテルが蝟集する一角となっていた。
彩は20代の時に法テラスの無料弁護士を通じて母親の実家を突き止め訪れてみたものの、
母親の両親は祖母は病没、祖父はアルツハイマーとなり施設に住んでいて逢うことは祖父母方の親戚縁者から逢うことを許されなかった。
『貴女が今更、孫だと言って現れてもなんの得にもなりませんよ、
叔父は私達で施設に入れてみんなで代わる代わる世話しているんですからね、貴女のお母さんが叔父の娘であっても貴女の父親は一体誰なのか皆目、解らないじゃないの、
恥ずかしいことね、お母様、まぁ現代的に云うならば援助交際のようなことをやっていらっしゃったのでしょう?だから娘の父親が誰なのかすら解らない、
おまけに女性の刑務所で貴女をお産みになられたとか…?』
『母は私を堕ろすことも出来た筈なのにそうしなかったんです。
受刑者の身で家族の理解も温もりも無く、独りで出産に臨んだだなんてとても愛情深い勇敢な女性だったと私は思います。』
『でもたとえそうだとしても、貴女が叔父の孫だと本当に証明出来るのかしら?叔父の遺産目当てとしかわたくし達には今更こんな風に現れても…とても思えないんだけど?』
彩は震える唇を思わず噛んでうつむくと、バッグからいつも持ち歩いていた為に印刷の色柄までもが擦り切れたようになった表紙の母子手帳を慌ただしく取り出した。
そして目上の従姉妹の菜の花色のセーターに包まれた、驚くほど豊満に堆(うずたか)く競り出した乳首のちょうど先端に向かって鋭く、まるで刃物を突き立てるような勢いで彩はそれを突き出した。
従姉妹はそれを手のひらでやんわりと押し返すと優雅な花冷えのような声で優しくこう言った。
『そんなもの…巧みな偽造品じゃないとは言いきれないでしょう?
仮にもし貴女が本当に叔父様の孫だとしても…
血は争えないって本当なのかしら?
貴女もお母様と同じなの?
つまり……ご自分を売るお仕事とかなさっていらっしゃるのかしら?
貴女のお母様もそうでいらっしゃったんですものね?』

次の瞬間、彩は小首を傾げる従姉妹の頬を張り倒していた。従姉妹の周囲には長老じみた親戚縁者が4名ほど彩を穴の空くほど、ためつすがめつ眺めていたが時折口元に手を寄せ、互いに彩を凝視しながらひそひそと話し合っていたが、彼らはまるで故意に従姉妹に挑発させているかのようにすら彩は感じたがそう感じたのはもっと冷静になったずっと後のことだった。
彼女は気がつくと従姉妹の躰の上に馬乗りになって何度もその両頬をカスタネットのように激しく打ち鳴らしていた。
不穏な空気を感じたのか、先んじて110番をされていたらしくパトカーが三分と経たずして到着した。
駆け付けた警官達に取り押さえられた彩は羽交い締めにされ、苛烈なまでに抗ったからではあったが、髪の毛を鷲掴みにして引っ張られながらパトカーへと引きずられ、まるで牝虎が咆哮を上げるかのように叫んでいた。
彩自身、自分から自分が離れてゆくのを感じ、まるでいつもとは異う自分が自分を操っているようで、それを止めることがどうにも出来なかった。
『今度逢ったらぶっ殺してやる!
母親をあんな風に言ったこと思い知らせてやる!』
『うるさい!黙れ!』警官に一喝された彩は走り出したパトカーの中から事情聴取を優雅な立ち姿で警官達から受ける従姉妹に悔し泪で滲む眼を放った。
従姉妹は頬に手を当てがい、美しく巻いた栗色の髪の乱れを次いで気にする様子を見せながらも、警官に向かって実に辛そうに何度も頷(うなず)いていた。
そしてチラとパトカーの中の彩へと一瞥を呉れたが、彼女はむしろ勝ち誇ったように血の滲んだ薄い唇の端を薬指でなぞると、その血のついた指の腹を彩に向かってまるで低い位置から優美に手を振るようにして見せた。
その赫い指先は、まるで花びらのようにひらひらと舞い、酷くねっとりと濡れて扇情的にさえ見えた。
パトカーのサイレンの音が鳴り響く中、走り出した車の中でこの『今』から逃げ出したくて、でも逃げられなくて、目を強く強く閉じた彩の瞼の裏に、その『赫』はいついつまでもしがみつくように堅牢に執拗に、残り続けた。
そしてそれは今も消えることは無い。
彩はデスク上のスマートフォンを見て鷹柳の言葉を思い出した。
『マイノリティの人々にとっては支配か懲罰か、常日頃からその二者択一ばかりを迫られる。尊重や思いやりすら時には生存することそのものまでもが引換券のように扱われ相殺されてしまうとしたならば、私達‘’普通の人間達”とは一体なんと嗜虐的な生き物なのだろう』
彩は思わず‘’あの時”のように強く瞳を閉じてこう思った。
『私は普段、泥棒をした人を、深くその背景を知ることなくいとも簡単に嘲笑ったり切り棄てたりするマジョリティの側の人間だ、
でも先生、私もまたもしかしたらあの日、あの時、マイノリティの側に立っていたのかもしれません』と…。



(To be continued…)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
