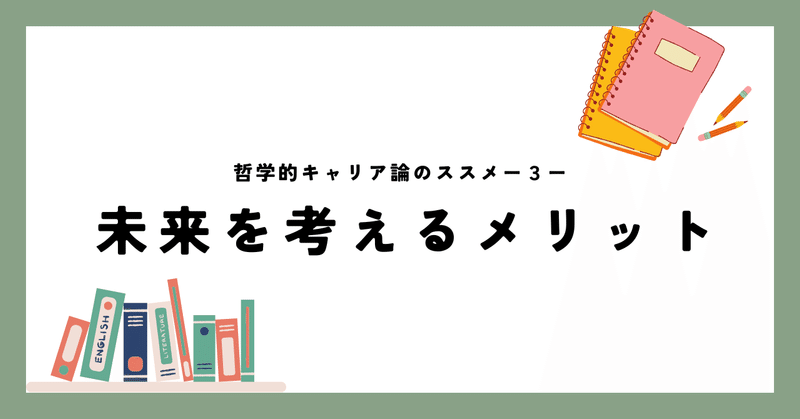
哲学的キャリア論のススメ3~未来を考えるメリット~
「働く、生きるを、HAPPYに」をビジョンに掲げる株式会社ミライフで、キャリアデザイナー兼事業企画として働いている菅野(かんの)による「哲学的キャリア論」第3回です。
「辞めたくなる三要素」を掘り下げた第2回はこちらをご覧ください!
※内容はどこから読んでも大丈夫ですのでご安心ください。
なお、このnoteでは「哲学的」という言葉をとても広い意味で使っています。
もう少しちゃんとした哲学の話が知りたいよ!という方は、Voicyで配信しているこちらの番組をお聞きいただけると嬉しいです。
それでは、さっそく始めていきましょう!
転職について考え始めるタイミングとは?
多くの人が、転職について考え始めるのはいつだと思いますか?
菅野調べですが、実はミライフを通じて転職活動をされた方のうち、7割近くが「明確な不満が生じたとき」でした。
前回の記事でも書きましたが、キャリアの不満は大きく以下の3つに区別できます。
①評価・報酬
②業務・仕事内容
③人・カルチャー
これを具体的なシーンにあてはめてみると、
・評価タイミングを迎えてみたら、思ったより全然給与が上がらなかった
・異動してみたら、まったく興味の湧かない仕事だった
・上長とウマが合わず仕事に行くのがしんどい
といった状況に陥ると、転職について考え始めやすくなる、ということです。
一方で、このような「明確な不満をきっかけに転職を考える」という場合、どうしても「現状否定」になりがちなため、なかなか「望むキャリアを実現する」というスタンスになりにくいことも事実です。
(加えて、「面接の際の転職理由を何と言ってよいか悩む」ということも起こりがちです。この辺りも「面接対策」について触れる際に、お伝えしていきたいなと思っています。)
とはいえ、そもそも転職は「理想の未来を実現する」ために行うものなのでしょうか?
というか、「理想の未来」っていったい何なのでしょうか?
その辺りを少しだけ掘り下げてみよう!というのが、今回のテーマです。
大事なのは「〇〇未来を考える」こと
キャリアを「現状否定」に留めず、未来について考えてみよう、というのは、よくあるキャリアのアドバイスかと思います。
しかし、誰もが未来に明確な希望を持っているわけではないですし、そもそも「今のつらさ」を何とかすることの方が重要です。
そこで、未来についても「3つのタイプで考えてみよう!」というのが、面談でときどきお伝えしていることです。
その3タイプがこちら。
①想定未来
②理想未来
③最悪未来
それぞれを簡単に説明してみます。
【①想定未来】
現在から予測される、自然な流れに沿った未来です。
この未来は「もし今の状況が変わらなければこうなるだろう」というもので、ここまで書いてきた「現状否定」というのは、実は「想定未来を回避したい」という想いが根底にあります。
【②理想未来】
よくある「あなたの理想は?」というやつです。
この未来を描くことで目標を明確にし、そこに向かう道筋が明らかになると、前向きにキャリアの道を進んでいくことができます。
難しいのは、必ずしも理想未来を誰もが描けるわけではないし、それが常にベストな選択肢というわけでもない、ということです。
【③最悪未来】
理想未来が浮かばない場合、代わりに考えるのがこの未来です。
「最悪」というぐらいなので、極端に言えば「会社が倒産する」とか「体調を崩して入院する」とかそういう話になりますが、一言でいうと「こんな風には絶対になりたくない」という未来です。
「理想未来」が描けずとも、この「最悪未来」を描くことで「そうならないための選択肢」を考えることができるようになります。
このように、3つの未来を意識することで、「明確な不満をきっかけに転職を考える」場合でも、実際にどのような選択肢が考えられ、どんな風に選ぶべきか?という発想の幅を広げることができます。
一方で、こうした選択肢を考えない場合に起きてしまう不幸な出来事として「今の不満は改善したが、別の不満が出てしまった」ということがあります。
例えば
・評価や給与は上がったが、その分業務量が増えてストレスフルになってしまった
・仕事は興味深いが、成果がついてこずやりがいが得られにくい
・上司との関係性はよいが、仕事がつまらない
といったように、あちら立てればこちらが立たずで、不満が明確だからこそ、それにとらわれすぎると適切でない選択をしてしまうということが、往々にしてあるのです。
もちろん、すべてが100点満点の環境はなく、あるとしても努力をして「環境を作っていく」という意識が重要ですが、それにしても環境を変えてから「こんなはずじゃなかった」と思うことは、出来るだけ避けたいものです。
3タイプのうち「いまの自分はどの未来の解像度を高めていくべきか?」という問いに向き合ってみるだけでも、より納得感の高い選択肢が見えてくるかもしれません。
転職だけに留まらない「未来を考えるメリット」
ここまでは「転職」を対象に「未来を考えるメリット」についてお伝えしてきました。
考えてみれば当たり前の話で、何かを選択するにはチャンスとリスクが両方ありますし、未来を明確に想定することで今とのギャップを明らかにするというのは、みなさんも日々行っていることかと思います。
大事なのは、自分がどのような状況にあっても、冷静に未来を見つめること、と言えるでしょう。
なぜなら、冒頭にお伝えした通り、転職を考える方の多くは「現在に対して明確な不満」があります。
この場合、どうしても冷静に未来を見つめることができず、「この不満が解消されるならどこでもいい」と考えてしまいがちです。
一方で、「現在が明確に幸福」という場合も、同様に未来に対する冷静さを失っている可能性があります。
その場合は想定未来に何の不満もないので「このまま行けば理想未来に至れるし、最悪未来が来ることなんてありえない」となってしまう、というか、そもそも未来について考える、という行動自体が起きないでしょう。
だからこそ、現在の状況によらず、定期的に「未来について考える」こと自体に、大きなメリットがあると言えるのです。
例えばミライフでは、定期的に未来について考える時間が、これでもかというぐらいあります。
・月1回の未来MTG(個々人の振り返りMTG)
・3か月に1回の「超ハピ会」(マネージャーMTG)
・半年に1回の「道ロックフェス」(全社合宿)
・その他、チームごとの振り返り会や目標設定会など
いま改めて並べてみて「多すぎない?」と思いましたが、ミライフは「未来+if(もしも未来が〇〇だったら)」の会社なので、このぐらい意図的に「未来について考える」し、「そのメリットを実感している」というのもあると思います。
実際、ちょうど4/19に「超ハピ会」というマネージャーで「2030年の未来について考える」というMTGを行ったのですが、こんな風に付箋がバンバン貼られまして、それぞれが考える「2030年」が可視化されていきました。

決してバラ色の未来だけではなく
「AIの発展によって人材エージェントは淘汰されるんじゃないか」
「労働の人口の減少からロボット派遣事業が盛り上がっているんじゃないか」
など、今の私たちの事業からすると、破壊的な影響を及ぼす付箋も沢山貼られていました。
ですが、こんな風に未来に目を向けるからこそ、見えてくる現在がある。
現在の状況を未来から捉えなおしたときに初めて、見えてくる道がある。
そんな風に考えると、あえて現在から距離を取って、冷静に「未来を考える」メリットも、感じていただきやすいのではないでしょうか。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は「未来を考えるメリット」について、転職に限らず「現在にとらわれすぎずに考えること」の重要性をお伝えしてみました。
「客観的な視点から自分の想定未来・理想未来・最悪未来の解像度を高めてみたい」という方がいましたら、ぜひ気軽にこちらのフォームからご連絡いただけたら嬉しいです。
それでは次回も、どうぞよろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
