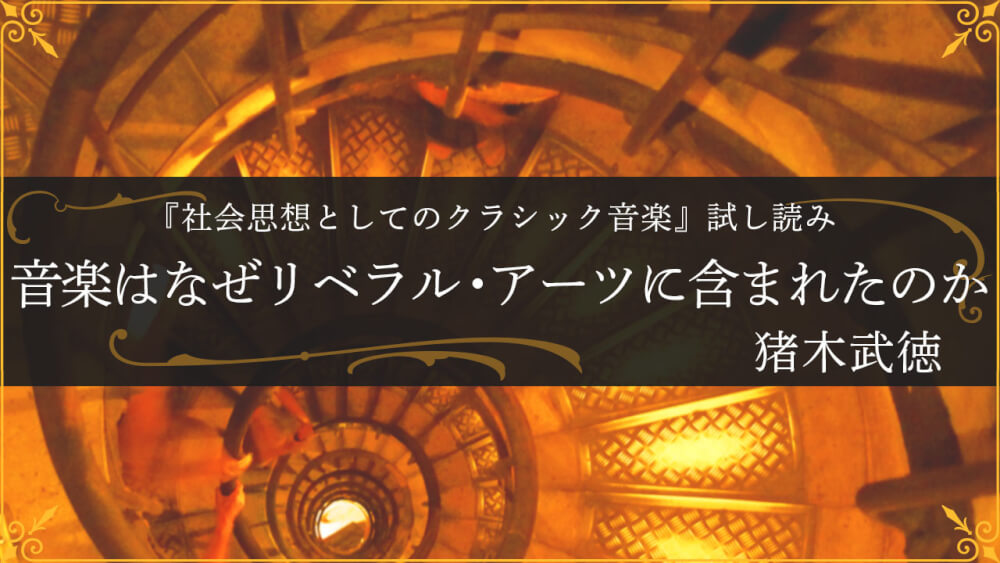村井理子さんの義両親ワクチン接種体験記が話題!(No. 916)
考える人 メールマガジン
2021年6月3日号(No. 916)
猪木武徳さん『社会思想としてのクラシック音楽』発売!
先日終了した経済学者・猪木武徳さんの連載「デモクラシーと芸術」が、『社会思想としてのクラシック音楽』と改題し、大幅な加筆修正のうえ、新潮選書から発売されました。
(本書概要)
近代の歩みは音楽が雄弁に語っている。バッハは誰に向けて曲を書き、どうやって収入を得たのか。ハイドンの曲が徐々にオペラ化し、モーツァルトがパトロンを失ってから傑作を連発したのはなぜか。ショスタコーヴィチは独裁体制下でいかにして名曲を生み出したのか。音楽と政治経済の深い結びつきを、社会科学の視点で描く。
猪木さんが新たに書き下ろした「まえがき」をこちらから試し読みできます。
アクセスランキング
■第1位 村井理子「村井さんちの生活」
遊びじゃねえんだよ~認知症の義母、ワクチンを接種する
『全員悪人』で話題になっている認知症の義理のお母さまのお話ということで、一晩で注目が一気に集まりました。
■第2位 村井理子「村井さんちの生活」
義父、ワクチンを接種する
タイムリーな話題もあいまって先週に続いてランクイン。予約を取るのも大変、付き添うのも一苦労……。
■第3位 飯間浩明「分け入っても分け入っても日本語」
赤い糸
テレビ番組で「赤い糸」の由来が取り上げられたのを機に急浮上。「赤い糸」伝説はそもそもどこから来たのでしょうか?
最新記事一覧
■大高郁子「考える猫のその日暮らし」(5/24)
それが猫
今回で100回目! そして最終回です(涙)。人見知りで隅っこが好きな子猫だったスミチ、こんなに大きくなって……最終回でもやっぱりスミチはスミチでした。
■小谷みどり「没イチ、カンボジアでパン屋はじめます!」(5/28)
18. さらば、バンデス(2)――良くも悪くも大変勉強になりました
頼りにしていた元国会議員のバンデスと袂を分かち、再起を決めた小谷さん。コロナ禍でのカンボジアの様子も。
■ジェーン・スー「マイ・フェア・ダディ! 介護未満の父に娘ができること」(6/1)
8.あきらめるところ、あきらめないところ。
少しずつ自炊能力も上がってきたお父さん。順調だと思っていた矢先、ヘルパーさんが辞めることに。原因はお父さんの「軽口」のようです。
■早花まこ「私、元タカラジェンヌです。」(6/1、6/2)
第3回 香綾しずる
「私、宝塚やめたらスパイダーマンになりたい」
宝塚時代、自分にしかできない役を追究した香綾しずるさん。退団後は、男役だった自分を誰も知らないベトナムに飛び込み、現地での日本語教師を経て、技能実習生を支えています。〈まだまだ視野を広げたい。生きるって、楽しいですよ〉。
前篇 海外で働きたい――ベトナムの日本語学校で叶えた、長年の夢。
「考える人」と私(16) 金寿煥
何回かにわたって、インタビュー記事の「文体」、とりわけ「問わず語り方式」について考察してきました。そろそろ「本題」に戻らなければと思いつつ、もう少し続けることにします。
季刊誌「考える人」の特徴のひとつとして、このインタビュー記事における「問わず語り方式」があるのではないかと前回述べましたが、これを主導したのは創刊編集長である松家仁之さんでしょう(直接確かめたわけではありませんが)。実際に、かなりの数のインタビュー記事を担当(取材・執筆)していて、前回引用した記事のほとんどが松家さんの手によるものです。
その松家さんは2010年6月に新潮社を退社し、現在は作家として活躍されています。「考える人」編集長として最後の仕事となったのが、退社直後に発売された2010年夏号の特集「村上春樹ロングインタビュー」。2009~2010年に刊行された村上さんの『1Q84 BOOK1~3』の話から始まるインタビューは、2010年5月11日の火曜日から13日の木曜日にかけて、改修前の箱根富士屋ホテルで行われました。実に90ページに及ぶ、長い、長いインタビューです。
このインタビュー記事では、「一問一答方式」が採用されています。このコラムでさんざん触れてきたように、「考える人」のロングインタビューと言えば「問わず語り方式」。そう印象づけてきた張本人が、「最後のインタビュー」で選んだのは、「問わず語り方式」ではなく「一問一答方式」だったのです。
なぜ松家さんは、村上春樹さんのロングインタビューに「問わず語り方式」ではなく、「一問一答方式」を採用したのか――。
それについて当時直接訪ねたわけではありませんし、今その真意を尋ねるつもりもありません。ただ、前々回で私は「一問一答方式」について以下のように述べました。
<聞き手の存在を際立たせたい場合は、「一問一答方式」を採用するべきでしょう。あるいは、現場での「やりとり」をそのまま届けたい場合は、「一問一答方式」でなければなりません。“独白”のように見える「問わず語り方式」では、「やりとり」それ自体を見せることは不可能です。>(「考える人 メールマガジン」2021年5月20日号(No. 914))
インタビュー記事で「問わず語り方式」を採用するということは、インタビュアーの存在を消すことだとも書きました。いわば”黒子”に徹するということです。
それまで”黒子”として「問わず語り方式」を採用し続けてきた松家さんが、新潮社最後のインタビュー仕事で「一問一答方式」を選んだ。その意味を考えてしまいます。
特集の冒頭には、「松家仁之(本誌)・聞き手」とクレジットされています。私は、このおそらく最初で最後となる「クレジット」に、松家さんの「最後の仕事」に懸ける思いを強く感じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■note
https://note.com/kangaerus
■Twitter
https://twitter.com/KangaeruS
■Facebook
https://www.facebook.com/Kangaeruhito/
Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.
発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71
新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/
メールマガジンの登録・退会
https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もしサポートしてくださったら、編集部のおやつ代として大切に使わせていただきます!