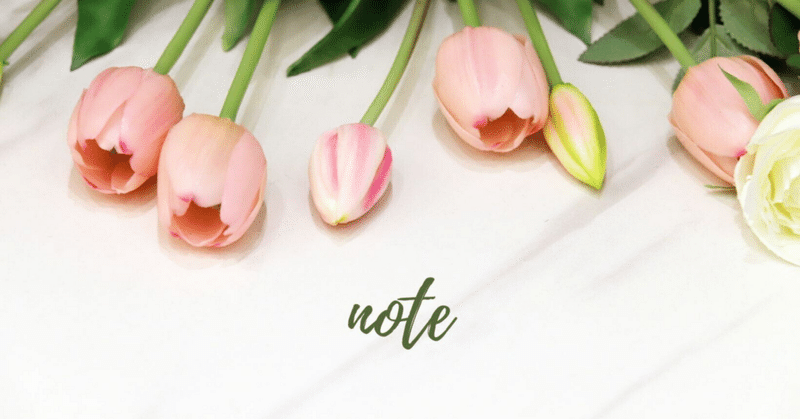
男の責任を問わない社会に異議を『射精責任』感想
大学生のときに中絶についての授業があって、「プロチョイス」「プロライフ」という言葉を学んだ。
プロチョイスは、女性の自己決定権を尊重する考え。
プロライフは、胎児の生命を尊重する考え。
女性の自己決定権と、胎児の生命。
あれ?男性の責任はどこに……?
という疑問を抱いた方にぴったりなのが本書、『射精責任』。すごい名前だね〜。
ちなみに自分はばりばりのプロチョイス派です。
本の内容
中絶の権利を保障するロー対ウェイド判決が覆され、中絶に対する政治的主張が激化するアメリカ。
「女性の自己決定権」と「胎児の生命」が天秤にかけられ議論が巻き起こる中、ひとりの女性が、「そもそも、女性が望まない妊娠をするのは、男性が無責任な射精をするからだ」と主張する。
女の名はガブリエル・ブレア。
中絶の議論において透明化されてきた、男性の「射精責任」を問う、28の提言。
「射精責任」っていい言葉!
最初、「射精責任」って聞いてすごい言葉だなと思った。いや、言いたいことはなんとなくわかるけど。
本書を読み終わった後は、「射精責任」という言葉がすごくしっくりきた。たしかに、男性には「射精責任」がある。
人々が「中絶」を考えるにあたり、男性の存在は透明化されている。
生殖は男女2人で行うものなのに、いつも「女性と胎児の権利」にされてしまって、中絶を語るテーブルに男性の存在が出てこない。
いやいや!男性に責任があるよね?だって射精したでしょ?
女性が「中絶が必要な状況」に陥るのは、必ず「男性が無責任な射精をした」はずだから。
この考えって、女性たちの頭の中にはうっすらあったと思うけど、たぶん男性の頭の中には全くない。
それを明文化したのが本書。
とにかく説得力が段違い。
この本は、高名な学者様とか、セレブなお金もちとか、そういう特殊な状況にある人が書いた本じゃない。
しばしばそういう人の描く「ジェンダー論」って、「机上の空論言ってんじゃねえよ!!!理想論ばっか語るんじゃねえよ!!!」って内容ばっかなんだけど、著者はブログで有名になっただけの一般人だからね。
とても現実的で、地に足がついている感じがした。生物学的で、事実に即している。
著者が提する28の提言は、どれもシンプルで、根拠があって、胸にストレートに響いた。
女性の無責任さをどう考える?
いかに無責任な男性が多いかは、本書で語り尽くされているし、女性の皆さんも体感でわかってるだろうから、いったん置くことにする。
私はこの本を読んでいる途中、「著者は無責任な女性についてはどう考えているんだ?」ということが気になった。
自分の周りの人に話を聞くと、避妊をせずに性行為をしたことのある人が結構いる。
その中にはもちろん「無責任な男性」もたくさんいたけども、「無責任な女性」も、決して少なくないことが気になった。
つまり、男性が「無責任な射精」を行うことを、推奨したり同意したりする女性がいるんだよね。
私からすると、そのような振る舞いをする女性にも、望まない妊娠に至る責任があり、著者が言うように「望まない妊娠は、すべて男性の責任」と言い切ってしまうのは違うのではないか?と思ったのだ。
それに対して著者は、「男性に責任ある行動を求めることは、女性が責任をとらないことを許すのと同じ意味ではありません」と主張する。
男性は現在、無責任な射精の責任をとっていない。女性を妊娠させても逃げ放題だ。
しかし、女性は自らの無責任さに対して、「望まない妊娠」という責任をとらされている。妊娠したら、産むにしろ中絶するにしろ、その責任を必ず自らの身体で負うことになる。
つまり現状、男性だけが「望まない妊娠」の責任をとっていないのだ。著者は、その不均衡さにフォーカスを当てているという話で、別に女性の無責任について許しているわけではない。
あと、「すべて男の責任」と言い切っている部分には、意思決定プロセスの影響があるとする。
同意の上で性行為をする際、男女の同意形成には2つのステップがある。
ステップ1 女性がセックスに同意する。
ステップ2 男性が責任ある射精をするかどうかを決定する。
この2つのステップが存在する。
ステップ1で女性が誘ってきたとしても、ステップ2の時点で男性は女性の誘いを断ることができる。そこに強制は存在しない。自由意志で、男性が女性の膣内に射精するか否かを決めることができる。
つまり、「無責任な射精」の最終決定権は、すべて男性にある。
ちなみに、ステップ1・2を男女逆にした場合、同じ理論にはならない。
なぜなら、男女間には腕力差があるからだ。また、避妊をしないことを断ると、露骨に不機嫌になったり攻撃的になる男性が非常に多いため、女性が男性の誘いを断るのは、男性が女性の誘いを断ることよりはるかに難しい。
単純に男女逆にして同じ結論に至るのは短絡的だ。
このような主張を読んで、私としてはかなり納得した。
私はもともと、女性から誘った場合は、責任が半々になると考えていたが、自らの無責任さの結果を女性が負っていること、最終決定権は誰にあるのか確認することで、「すべて男性の責任」と言い切る著者の主張が理解できた。
しかしやはり、「コンドームをつけないように、女性から誘った場合」においては、女性にも責任があると思う。ただし、男女で9:1くらいの割合で、男性に責任があると思うけど。
女性の責任が0%だと言えない事案もあるのではないかという部分は気になった。
残念だった点
この本すごいな!!最高だ!!と思いつつ読んだ『射精責任』であったが、ひとつ残念な点があった。
それは、巻末の解説者が男性のジェンダー学者だったということだ。
この本は女性なら当たり前に経験として知っていることを、明文化し論理的に説明したものだ。
だからそこに「男性の言い分」が入ると、正直「あーやっぱり男はわかってないな」と思う。
まず、男性はこの本を読んで責められているように感じる人が多いと思う。解説者も、「居心地の悪さ」を感じたようだ。
だから、何かを言いたくなる。本人としては「冷静な視点を投げかける自分」という認識だろうが、女性視点だと「射精責任を負いたくないがために、理屈をこねくりまわす男性」というふうに映る。
「論理的な第三者目線でいるつもりみたいだけど、お前も当事者なんだけど?(しかも責任を負わないといけない側)」みたいな気持ちになる。
端的にいうと、「お前が言うな」である。
冷静な指摘をするにしても、「男性」は本書では「責任逃れをしている」立場となるので、指摘とかは女性自身がしたほうがいい。
なので、「男性」が解説をするのは不適切だと思う。
また、日本の「ジェンダー学者」なるものは、とにかく地に足がついてない。
弱い市民の立場では考えられず、なんでも性善説で考え、科学や統計、事実などを無視して、机上の空論や理想論ばかり語っている。
現実に即して語られた本書とは、対象的な存在だ。その点からしても不適切だ。
解説者は、日本では「すでに中絶のアクセスが女性に広く開かれている」と述べているが、そんなことないと思う。
法律上必要ないにもかかわらず、未婚者が、中絶同意書にパートナーの署名を求められるケースがたくさんある。
パートナーと連絡が取れず、中絶することができなかったり、苦し紛れに友人に代筆を頼んだりするケースが多い。
また、中絶する際に産婦人科医に責められたり、的外れな説教をされて中絶ができなかった話なども聞く。そういう現状を鑑みると、いくら法律の「経済的理由」が拡大解釈されているとはいえ、解説者の言うような「すでに中絶のアクセスが女性に広く開かれている」とはいえないだろう。まさに男性の目線だ。
あと、解説者は、「無責任な射精」の定義が曖昧であるという指摘をしている。
解説者が指摘するような、「射精時点で同意があったのに、後から同意を覆した場合」が「無責任な射精」に当たらないというのは明白であるように思うのだが。
著者は無責任な射精を、「すべての望まない妊娠を生じさせるもの」と定義しているが、それは「女性の判断がすべてだ」とかそういうことではなくて、「女性が妊娠で負うダメージを考慮せず、自らの快楽を優先する射精」という意味であることは、本書を読めば明白だと思うが。どこが「マジックワード」と化しているのだろうか?
また、「男性への啓発か、女性の自衛かどちらを優先するか」とか言い出したのはかなりびっくりした。どっちかを優先するとかじゃなくて、もう女性はすでに自衛している。
男性への啓発を頑張ってください。ジェンダー学者なんでしょ?
男性のジェンダー学者って、女にご高説垂れるためにいるんじゃなくて、男性に啓発するためにいるんじゃないのか?
なのにみんな前者ばっかするよなあ……男の方を向いて話してくれ。
などと思ってしまい、素晴らしい本だったのに読後感がもやもやした。
本書は「女性が感覚的に知っていること」を明文化しているものなので、その「感覚」を知らない男性が本書に疑問を呈してくると、なんで女性ばかりが「男性にわかりやすく説明」してあげないといけないのか?という気持ちになる。
女性が感覚や体感で知っていることを、男性がわかろうとする努力はしないのか?
男性が解説をするのなら、「射精責任」を男性が受け入れるにはどうするべきかとか、どうして居心地の悪さを感じるのか、その心理を掘り下げるとか、そういう「男性に向けた話」をしたほうがいいと思うな。
いつも女性の方ばっか向いて話すなよな。
おわり
かなり興味深い本だった。以前手に取ったフェミニズム本『美とミソジニー』がかなり読みづらく、フェミニズム的な本は敬遠していたけど、簡潔で読みやすくてよかった。
ここからは完全に余談。
著者は、女性が主となる避妊にかかる費用をパートナーにも半分負担させている女性を見たことがない(女性が全部負担している)と言っていた。
私は夫に払ってもらっている。避妊のためではないがピルを飲んでいて、夫が送迎するし、夫が代金を全て負担している。
精管結紮術についても、夫が自主的に提案してきた(保留中)。
こういう男をちゃんと選んだので、世の中の女性もパートナーをちゃんと選んだほうがいいと思うし、相手が豹変したら捨てるべきだ。
自分を大切に生きよう。
ここまで読んでくれてありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
