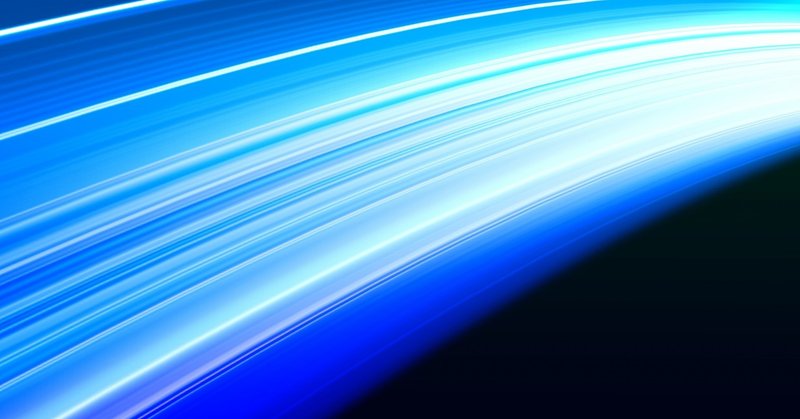
chapter4-6: 最強 VS 最速(第4章ラスト)
――冷静に考えて凄い状況だ。
グラウンドに展開されたフィールドを挟んで、向こう側には現女王チームがいる。しかもライダーは控えではなくレギュラー2名。担当技術も正規のメインオペレーター。練習試合でこんなメンツと対峙する機会なんて、他のほとんどのチームにはないだろう。正直こういう風な形で、乙羽に頼りたくない気持ちもどこかにはあった。だけどそれ以上に、今回は絵美里を泣かせた生徒会が許せなかった。現況の生徒会の面々はこちらのオペレーターサイドの近くで唖然とした表情でこのマッチングを見ていた。子本がどうしていいのかわからず、会長の顔色を伺いながらあたふたしている姿はとても滑稽だったりもする。
グラウンドを覆う生徒たちの熱気が先ほどまでとは明らかに違う。いつの間にか校舎中の窓から生徒たちがグラウンドをのぞき込んでいた。地上もグラウンド脇の安全エリアの向こうには多くの生徒の姿が見てとれる。そしてその人数はどんどん増えていっていた。現女王がグラウンドにいるという現実味のない情報が、しかしSNSを通じて桜山学園の生徒たちに徐々に拡大していってるらしかった。
そんな熱視線を一心に浴びている乙羽――クリムゾンエッジはスタンバイが完了しているらしい。地面から4・5メートルあたりで軽く腕の可動域の確認をしながら、試合の開始を待っている。その近くで、先ほどまでは制服だったDGTの部長・高宮先輩もエアロフレームへと換装を終えていた。そのフレームは以前見た時とやや外観がマイナーチェンジしていたが、ゴールドと赤という派手な装飾は変わっていない。大きな特徴的武器こそないが、様々な基本武器を詰め込んでいる高宮先輩のフレーム・デュランダルが準備を終えた。ある程度どんなレンジでも展開させられる、対応力の高い高宮先輩用にカスタムされた中長距離のオールラウンダー型エアロフレームは、まぁどちらかといえば射撃性能が高いフレームになっているはずだ。外観をあえてギラギラの派手めなデザインにしているのは、その存在で周囲を鼓舞しつつ先陣をきって敵陣内で暴れまわる【旗】としての役割があるからだ。クリムゾンエッジほど何かに特化した特徴ある機体ではないが、だからこそ敵としてみた時に対策が難しい面もある。どんな場面でも起用に対応できてしまう自在性こそがデュランダルの特徴ともいえる。
あれを姫野先輩と真心のどちらに対応してもらうのがベストか、なかなか難しいところだが……
――どちらにしてもこのマッチング、勝ち目はない。
真心は確かに素人とは思えない強さだけど、エアリアルソニックの経験値がまだ足りない。いきなり乙羽や高宮先輩を相手に勝てるなんてそんなはずはなかった。姫野先輩に関してはその才能は別格で、もしかするとDGTのレギュラー2人の実力に届く可能性はあるけれど、そうなってくると今度はフレームの差とオペレーターの差が顕著に表れてくる。相手は最高の才能と称される大丸空耶だ。そう簡単にこちらが付け入る隙を与えてはくれないだろう。であれば、どんな風に戦えばいい?
「――神谷野君、聞こえる?」
考え事をしていた頭にインカムからの姫野先輩の声が響く。
「はい、大丈夫です」
と、答えるとオレは目の前の真新しい外観のフレームの背面を見る。白く輝くボディに青いラインが外観的特徴となっている姫野先輩のホーリーナイト。声の主はそこにいた。
「……いやー、緊張するね」
そんな姫野先輩の声が聞こえてきて少し驚いた。
「先輩でも緊張するんですか?」
「そりゃそうだよ。女王だよ、ヴィーナスエース。私の目標が目の前にいて、緊張しないわけがないじゃん?」
言われてみれば、そうだな。姫野先輩が目指してきたゴールが不意に目の前に現れたんだから、そりゃ普段と同じ状況ではいられないだろう。
「神谷野君は? 好きな人と前の仲間との対戦だけど、緊張したりしないの?」
「緊張、とは違うかもしれないけど、不安はあるよ。乙羽の実力は誰よりも知ってるし、大丸の凄さも知ってる」
「私じゃ勝てないって、思ってる?」
「先輩のスピードは凄いと思ってます。だけど、相手の実力はそれより上だと思う。それに……」
「それに?」
「もしライダーの実力が拮抗したとしても、そこにフレームの差が出てくる。つまりメカニックの差というか……大丸の技術力は桁違いだから……」
そういうと、姫野先輩はふふっと笑った。
「ねぇねぇ神谷野君。私さっきね、大丸に聞いたの。日向さんに告白したのって」
「え……ん……はぁ!?」
真面目なトーンで話をしていたので、先輩の急な方向転換に頭が付いていけない。突拍子もない話に言葉を見つけられないでいた。
「そしたらね、そこまで冷静だったのに慌てふためいた感じで、凄い変な顔してた。笑っちゃった」
「なんでそんな事……」
「神谷野君、気になってたでしょ? ふふっ、まぁ私も神谷野君の話を聞いて気になってたし」
そういうと、ヘッドパーツを脱ぐことはないまま、こちらの方へと向き直る。
「できなかったんだって、告白」
「……えっ?」
「彼もさ、単純にフラれるのが怖いんだよきっと。アイツもそういう普通の人って事!」
彼女が何を言いたいのか、なんとなくわかった気がした。ふっと肩の辺りの力が抜けていく感覚がある。
「――先輩、勝ちにいきましょう」
「もちろん!」
通話回線をグループに変更し、ひとりで動きを確認していた真心とも会話ができるように変更した。
「OK真心、準備はいい?」
こちらから問いかけると、長刀を構えて型をとっていた新規フレーム・コジローの動きが止まる。
「おう。準備バッチリやで」
「ホントに? 緊張してるんじゃない?」
「いやいや、そういう感じはないんよ。先輩やお前みたいに相手の事よく知らんからかもしれんけど、全国トップってんがどんな強いヤツなんかそれに興味があってな」
とても前向きな回答がそこにあった。《知らない》は強い。知っているから知識から勝手に結果を予測してしまう事はよくある。真心の知らない強さを今回は大いにアテにしよう。
「1つ作戦を伝えるけど、準備はいい?」
オレがそう問いかけると、2人は同時に「OK」と答えた。
* * * *
初夏の暑さというだけではない、周囲をぐるりと囲む聴衆の熱気が桜山のグラウンド上の気温をジリジリと上げていく。そんな感覚だった。双方準備は完了、反重力フィールドを挟んで対角線上にオペレーション用の陣をとる。といっても長テーブルと椅子を並べただけのシンプルなものだが。テーブル上にはフレームのパラメータ確認用のモニター2枚に各種計器類を並べてある。向こうも大体同じような感じだろう。今回は裏方は1人ではあるけれど、勉強になると思うので、五十鈴にはこちらのテーブルの後ろで観戦してもらうことにしていたのだが、現在オレの背後には数名の視線があった。五十鈴以外に、何故か近くで試合が見たいと言ってきた五十鈴の友人でもあるシルヴィと、そして生徒会長だ。断っても良かったけど、別にいてもらったところで困るわけでもないし、理由はよくわからないが好きにしてもらうことにした。ちらりと後ろを確認すると、五十鈴もシルヴィも真剣な表情でグラウンドの中央の方を見つめている。そんな2人に対して生徒会長はどこか憮然とした表情で、ホーリーナイト・姫野先輩をジッと見つめているようだった。
ザザッというノイズが入り、大丸の声がイヤホンに響く。
「じゃあそろそろ始めるけど、そっちはいいかい?」
「あぁ、大丈夫」
「適度に加減はするけど、それでも破損などさせてしまったらその時は許してくれよ」
少し鼻で笑うように、そんな事を言う大丸にイラっとしたが、だが冷静に、息を1つ吸って答える。
「こっちは胸を借りるつもりで、全力でいくよう支持してあるので、そっちの機体に何かあったら悪い」
「はぁ? 日向の防御力を神谷野も知ってるだろ? 日向に万が一にも攻撃が当たるなんて、それ本気で言ってるのかい?」
震える心をギュッと押さえ込んで答えた。
「見てればわかるさ」
開始のブザーがなり始める。観衆のざわめきが一層大きくなった。
……P……P……P……
「行け!」
スタジアムかと勘違いするかのような、わーっという歓声がグラウンドを包み込む。その声に負けない温度感で開始のブザー音と同時にオレは叫んだ。呼応するように真新しい2つのフレームはまっすぐ敵フレームに向けて翔け上がっていく。デュランダルとクリムゾンエッジの2体は10メートルほどの感覚をとりつつ地上から5m程度のところで待機、試合開始位置からほとんど動いていない。積極的に動くのではなく、こちらを迎え撃つ体制のようだった。向こうが王者、こちらが挑戦者。動かないのであれば、先手をできる限り利用して、事前に立てた作戦を実行するまでだ。オレはエアロフレームとの共有マップへ座標を打ち込む。
「真心、画面に表示したポイントの位置で方向転換して急上昇、上空からクリムゾンエッジを急襲! 先輩はまっすぐデュランダルへ!」
了解という声よりも先に、こちらが支持したポイントへたどり着いた両者は、指定した通りの行動を取る事で答えてくれる。真心のコジローは背面のブースターを蒸して一気に上空へと跳ね上がる。目で追うようにクリムゾンエッジと、そしてデュランダルもそちらへ照準を合わせようとする。そこへ猛スピードで白い機体が突っ込んでいく。
オレンジ色の火花が散り、遅れてガンッという衝撃音が響く。ファーストアタックは姫野先輩のホーリーナイトによる近接攻撃だった。デュランダルは辛うじてそれを受け流すようにガードしていた。だが一撃で終わるはずがない。直線に突っ込んで行ったところから急停止、物理法則を無視したかのような挙動で来た道を戻り再びデュランダルへアタックを仕掛ける。100から0、そしていきなり100へ。こんな動きをするライダーは全国でも見たことない。これは間違いなくトップクラスのライダースキルだ。いきなりの強襲におそらく面食らっているはず。相手が姫野先輩の実力を理解していないうちに、せめてクリーンヒットが一撃でも出れば。そんな願いを込めながら、疾風怒濤の乱撃を見つめる。それと同タイミングで、20メートルあたりまで上昇していた真心が重力に任せるように一瞬運動量がゼロになったかと思うと長刀を構え、そこから一気に下降した。それを見上げるクリムゾンエッジも、背中に構えていた自身に匹敵するかの大剣を正面に構える。動かない、落ちてくる真心のコジローを待っている。これが彼女のスタイルだ。最強の盾(イージス)とも呼ばれる全ての攻撃を受けきるガード力に特化した戦闘スタイル。
「真心! とにかく無理はするな、カウンターが来る!」
オレはインカムで叫ぶ。リーチはコジローの長刀の方がある。その剣先だけが届く距離で、クリムゾンエッジを威嚇する。倒すことが目的じゃない、そういう一撃だ。
耳に劈く甲高い衝撃音、コジローの長刀の横なぎの一撃を、クリムゾンエッジは手にしていたバスターソードでいなすようにして受ける。その斬撃は勢いはそのままに、ベクトルをずらされて、地面の方へと誘導される。ガグンとコジローの姿勢が崩れ、しかし勢いのまま地面へと堕ちていく。
「……っ! 真心、そのまま加速しろ!」
声と同時、真心の超反応で地面へと一段ギアをあげる。その背面を刈り取るように巨大な影がブォンという鈍い音と共に通り過ぎた。クリムゾンエッジのカウンター、こういう隙を乙羽は逃さず捉えにくる。その事を知っていたからこその咄嗟の指示だった。紙一重で背中スレスレの空を斬った一撃、コジローは地面に背を向けて減速しつつ、両肩・ショルダー部に取り付けてある実弾であるバルカンを放つ。
――バババッ! という撃鉄音が響くも、クリムゾンエッジは自身の姿をバスターソードの刀身に隠してすべてを防いだ。ジャブ程度の価値もない。コジローはすぐに体制を立て直すと再び高度を上げていく。そうして、敵対するそれと同じ高度まで上がってくると、クリムゾンエッジへの次の一手を探るように両手で刀を構えた。その姿を見て、クリムゾンエッジも再び巨大な剣をぐっと持ち上げるようにして構える。
――そこで、動きが止まった。
静かに、だがヒリヒリとするような緊張感を湛えて。コジローとクリムゾンエッジのせめぎあいがそこにあった。
それとは対照的に、激しい乱打戦の様相を見せていたのは姫野先輩のホーリーナイトだ。先行の利で序撃こそデュランダルを押し込んだが、相手は仮にも全国女王チームの部長だ。すぐに立て直すとデュランダルは片手にハンドガン・片手に標準的なソード武器を構える。近くではソードによる攻撃を行いつつ、もう一方の銃で牽制的な射撃で押し込まれていたところからミドルレンジへと戻していく。ホーリーナイトは圧倒的なスピードでそれを回避し続けるが、攻撃手段は近距離で思いっきり殴る以外に持ち合わせていない。それでも弾丸を紙一重でかわしながら懐へと潜り込むと、右へ左へ一撃を入れようと腕を伸ばしていく。だがそれらはことごとくソードに止められる。手数こそ多くとても派手な展開だが、近接攻撃もミドルレンジも両方とも難なくこなすデュランダルに、ホーリーナイトは攻め手を失っているような様相だった。
一方は静、一方は動。とても対照的なソロバトルが2つ存在する、そんなタッグマッチとなっていた。
* * * *
――コジローの中、真心は溢れる笑みを抑え込めなかった。
これまでの練習で、うちはコジローをイメージに近い形で動かせるようにはなっとる。けど思い通りに動かせるだけで、思い描くように戦えるわけやない。練習試合で姫野先輩とやってても、まだまだどう戦ったらええのかわからん時も多い。
だけど、楽しいな。やっぱり試合はおもろい。このヒリヒリするような感覚は、どんなスポーツでも変われへんのやなって。ましてや目の前にいるのが、この世界のチャンピョンなんて……エアリアルソニックに飛び込んで早々、ウチはなんてついてんのやろって思う。
――ウチの目標までの距離、アンタで計らせてもらうで!
相手が待ちの姿勢で動かないなら、こっちから行くしかない。
右、と見せかけての左からの袈裟斬り!
剣先を揺らし、三度のフェイントをいれる。
――刹那、右足で天を全力で蹴り出して、コジローは瞬時に間合いを詰めると、リーチ差を活かしたままその刀を振り降ろす。その動作よりも数センチ早く、クリムゾンエッジが視界から消えた。目の前から一瞬で消える、脳がその認識に追いつけていない。その一瞬でクリムゾンエッジは右足付近を軸にしてくるりと反転してみせていた。消えた影跡に斬りかかった一撃は当然空を斬る。――刹那、クリムゾンエッジは回避反転をしたその勢いのまま、そこの空気を根こそぎ薙ぎ払うような大剣の回転斬を放つ。巨大すぎる剣戟が眼前に向かって飛び込んでくる。バックステップ、いや回避できない、上下移動も無理。
そう判断したのは強烈な衝撃と共に頭が揺れた後だった。鈍い音と共に、その体ごと外側へと吹き飛ばされた。意識を刈り取りに来た強烈なカウンター、だが幸いにも一瞬だけ記憶がないが、意識はまだ切れていない。すぐに宙返りをするようにして体制を立て直す。吹き飛ばされた分、クリムゾンエッジとの距離が開いていいた。残り体力ゲージをみる。今の攻撃が直撃していたらその時点でゲームオーバーだろう。そういう一撃だったが、多少のダメージはあるものの大きく問題がある状態にはなっていない。意識がハッキリしてくるにしたがって、遅れて右上腕三頭筋がビリビリとしびれるような感覚があった。そうして自分の体制を確認すると、長刀を右側面に構えて斬撃の直撃を防いでいた。それは考えてどうにかした行為ではなく反射だった。
――苦手なんよな、こういうタイプ。
一旦攻撃を受けてからのカウンタータイプ……しかもこいつの場合それは回避行動からのカウンター、返し胴というよりは抜き胴って感じやな。右手のしびれはもうとれてきている。再度刀を構える、さぁどうする。相手はこちらを試すようにあまり動かない。剣士タイプらしく飛び道具も使ってこない。不思議な感じだ、もっと猛烈なタイプの人を最強というんやと思ってた。これが現ヴィーナスエース。姫野先輩の目標で、ウチらの目標か。
――まぁあれこれ考えてもしゃーない、こっちは素人なんやからトライ&エラーで!
再び女王の懐へ踏み込んでいく、紙一重のリーチを利用してギリギリの距離でのせめぎあい。このプレッシャーを楽しみながら、だがゲームオーバーだけは避けないといけない。神谷野が考えた作戦が実行可能な瞬間までは何が何でも粘り切らんと……!
* * * *
思った以上に彼女たちは善戦していた。姫野先輩のスピードはもちろん通用すると信じていたけれど、真心もクリムゾンエッジ相手に相当善戦していた。
まぁ、それは乙羽自体が剣士VS剣士の戦いを楽しんでくれているからかもしれないが。乙羽も飛び道具などを基本使わない近接のタンクタイプであることで、真心の剣道部としての経験値が想定以上に活かされているという状態だろう。とはいえ、徐々にHPは削られてきているし、その残りを一瞬で持っていけるだけの破壊力を持っているわけで一瞬たりとも油断はできない。
姫野先輩はスピードスターらしさを存分に発揮してくれている。デュランダルの方も、近接・射撃を繰り返していて、見てみてとても派手な戦いだ。観客の多くはあちら側の戦いを見ているんだろう。
――だけど現時点で決め手はない。
一撃でも全力の拳を入れる事が出来れば勝利も可能だろうが、そういった隙をデュランダルは与えてくれない。両手には銃と剣、レンジも自在で攻守のバランスのいい、優等生タイプだ。何でもできるがゆえに器用貧乏というライダーももちろん多くいるが、器用な上に勝負を決めるだけの的確さ・力もあるのが高宮先輩――デュランダルだ。あれだけの手数をホーリーナイトがひらりとかわして見せているので何でもないように見えるが、その一撃一撃の正確性、また誘導してからの斬撃などどれもが勝負を決めるための布石になっている。その包囲網を超速度で無理やりこじ開けながら殴りかかっていっているのが現状だ。
――勝てるわけがない。
生徒会につぶされたのであろう練習試合を成立させる事が目的で、まさか乙羽や大丸、高宮先輩に勝とうなんて考えていたわけじゃない。だが、現実に試合が始まってしまえば、勝てなくてもいいなんてそんな想いは消滅する。真心の粘り、姫野先輩の実力を見ていながら、負けていいなんて間違っても思えない。
――勝ちたい。
相手が乙羽でも、相手が大丸であっても。
どれだけ才能に差があっても、全力でぶつかって勝利したい。当たり前だ、そうじゃなければ青春をかけて戦う意味がない。オレはファイに指示を出す。
「タイミングはファイにまかせる。《その瞬間》が来たら、2人に同時にスイッチの指示を」
「了解シマシタ」
音声回答と共に、ファイは局面の解析を続ける。これは激しくぶつかり合う2つの試合、ではない。
――これはタッグマッチだ。
「!! アト4秒後二交錯ノ可能性アリ」
ファイの声がオレと2人も聞こえる回線に響く。
「……真心! スイッチ!!」
「っし、了解や!」
回答と同時に、クリムゾンエッジとの距離を瞬時のバックステップで稼ぐと、コジローは鞘のない左の腰にまるで納刀するかのようにその長刀をいったん納めるように構えて――直後、一気に横なぎに振るう。さながら抜刀術ともいうべき斬撃、これまでとリズムの違う攻撃に、一瞬受け方を迷ったらしい深紅の機体はそれを受け止めるのではなく、バックステップで後ろへと下がる事で回避しようとした。
――予想通り!
グンッ! と、コジローの剣先が伸びた。いや、伸びたと錯覚した。バックステップで回避したはずの剣先がクリムゾンエッジの眼前にある。コジローが手にしていたはずの剣はその手を離れて、頭部めがけて一直線に投げ込まれていたのだ。深紅の機体が膝からガクンと崩れる。そのまま背面から倒れこむようにしてあえて地面の方へと落ちた。鼻先をかすめるようにして、クリムゾンエッジよりも長いその刀は後方へと飛び去っていく。
「――っ!」
クリムゾンエッジがその刀の行き先に気が付いたときには、すでに剣先はデュランダルの背面に届いていた。デュランダルはワンテンポ遅れて振り返りながら、その剣先をガードしようとするも、ギャンという炸裂音と共に左脇腹付近をかすめていく。その一瞬、意識が刀に向いた一瞬を、姫野先輩は絶対に見逃さない。ホーリーナイトはその異能ともいえるスピードでデュランダルの懐に踏み込むと、左手で渾身の一撃を腹部へ叩き込む。閃光があり、続いて炸裂音。気が付いたときには後方へと吹き飛んでいく機体。フィールドを歓声と悲鳴が包み込む中、それは糸が切れた人形のように力なく崩れ落ちていく。モニター上の表示はロスト、デュランダルを排除する事に成功した。
コジローの元に投げつけたはずの長刀がまるで時間を巻き戻しているかのような軌道、来た道を帰る様に戻ってくる。遠目に見ている人には魔法に見えたかもしれないそれは、単純に長刀に取り付けていたワイヤーケーブルを巻き取っているだけという実にシンプルな仕掛け。コジローの手元に再び長刀が戻った。
――状況は2VS1。これで局面は圧倒的に有利になった。
ソロバトル以外は連携がすべてだ。どうやって数的有利を作るか、作らせないか。タッグであれば基本的には1VS1か常に2VS2の状況にすることが求められる。その中で一瞬でもいいから2人が同時に1人を攻撃する瞬間を作る。これが定石、それはおそらく大丸サイドも分かっていて、だからこそ実力差がある事を鑑みて1VS1の状況を維持して戦う選択をしたのだと思う。加えて、こちらの機体がどちらも近距離タイプであった事から引き離してしまえば、遠距離からの支援攻撃はありえないはずだと。そう考えていたに違いなかった。これは一回限りの博打、外してしまえば武器をなくしたコジローがその一瞬で撃墜されていただろう。相手の虚を突いた作戦が、見事に刺さった。フィールドを囲む学生たちの歓声・空気が明らかに変わる。後ろで見ていた五十鈴とシルヴィからも「凄い」という感嘆の声が漏れていた。
残るはクリムゾンエッジ、それを前後からコジローとホーリーナイトが挟みこむ。押し込んでいく展開に、校舎から見ていた聴衆が作る声の波も一層大きくなる。
――だが、妙な感覚だ。
圧倒的に有利なのはこちら側、にもかかわらず、余裕なんて微塵も感じられない。クリムゾンエッジの背面からこぼれる排残光が輝度を増す。それと同時にどこか先ほどまでとは纏う空気が別物に変わっている。気圧されている、気圧される。だが、だからといってこちらが引く理由は現状何もない。「行け!」というオレの声を合図に、両サイドから同時にコジローとホーリーナイトが攻撃を仕掛ける。そうしてその刃が届かんとした刹那、深紅の機体が手にしていた大剣が半分に割れた。
――ガンッ!
深紅のボディを輝かせながら、クリムゾンエッジは自身に迫りくる2つの攻撃を両方の手に持つ2本の剣で同時に受け止めた。半身となった2対の剣、それは彼女の持つもう1つの顔だ。ガードからのカウンターに徹していた大剣状態の時と違い、双剣ではまるで違う動き――超攻撃的な体制に変化する。
――すぐに嵐となった。
縦横無尽にホーリーナイトとコジローが繰り出す近接打撃を、クリムゾンエッジはその見事な剣捌きですべてはじき返していく。
弾く弾く弾く、弾く。
時代劇の殺陣のように最初からそういう風に型が決まっていたかのような鮮やかな打撃戦。弾く、遅れて炸裂音。真心のコジローは正面から、ホーリーナイトは位置を変えながら打撃を入れていくにも関わらず、どの一撃も相手の意識を刈り取る全力の一撃にも関わらず。あるいは軽くいなされ、あるいは鉄壁のごとく弾かれる。
焦り、焦る、その隙を女王が赦すはずがない。
「……っ! ダメだ、踏み込み過ぎだっ!」
オレの声は真心に届かなかった。気が付いたときには、コジローの手から長刀が零れ落ちていく。
「真心!!」
手首を狙われた――武器を落としたフレームに、続けざま瞬きの間に片手で4撃。フレームの危機を告げるブザーがオペレーション側で確認できた時には、すでにコジローのHPはゼロを示していた。同時に、撃破を防ごうとして無理に前に出たホーリーナイトの腹部付近を蹴り飛ばしてフィールドギリギリのところまで突き放していた。
「真心、大丈夫か!?」
「あいたたた……大丈夫やで。すまん、しくじってもうた……」
コジローを沈めたクリムゾンエッジは照準をホーリーナイトへと向ける。これで1VS1のイーブン。いや、実力実績を考えれば圧倒的に不利な状況に逆戻りしてしまった。落胆の声はフィールドを囲む学生の空気からもわかる。
「――ねぇ、神谷野君!」
姫野先輩の声がする。
「私、全力でぶつかってもいい?」
「え?」
「そりゃ、いままでも全力だったけど、全力の全力の全力。知りたいんだ、私の目標までの距離を!」
フフッという笑みが混じった声が聞こえてきた。
「で、作ってもらってばかりで悪いけどさ。そしたらこのフレーム、壊しちゃうかも」
「まぁ……その時はまた、全力でバイトしてください」
「はーい」
「大丈夫。オレも五十鈴も、全力で戦って、全力で直します。だから、好きにしてください」
ありがとう、という言葉の代わりに、蒼の線を空に描きながらホーリーナイトは前に出た。その動きに呼応するように、クリムゾンエッジも紅の線を描きながら真っすぐそれにぶつかっていく。双剣と拳、攻撃は最大の防御といわんばかり、両者ともに絶え間なく攻撃を繰り出していく。攻撃を攻撃で受け止める、あるいは上手く体をひねりながら紙一重の回避を繰り返していく。
前へ前へ、反撃を厭わず前へ。
瞬きを許さない刹那の攻防、乱打のすべてが決定的な一撃、度重なる炸裂音が光に遅れて聞こえてくる。
明らかにギアが数段上がっていた。先ほどまでとはスピード感がまるで違う。上手さはクリムゾンエッジの方が一枚上手だ。フェイントを入れながらの斬撃に、攻撃に合わせたカウンター、すべてがホーリーナイトの急所を捉えている。それを紙一重の所で回避しながら、しかし先制を譲らないホーリーナイトのスピードは明らかにクリムゾンエッジに通用していた。足りないスキルのすべてを速さで塗りつぶしていく。
ビーっという警告音がオペレートモニターに響く。ドライブに負荷が大きくかかっていた。出力の通常での設定値を大きく上回っての飛行、それは巻き散らされている蒼の排残光の量・輝度からも明らかだった。同時に、クリムゾンエッジの排残光も明らかにその輝きを増している。日中にもかかわらず、赤と青がまじりあって眩しく光っている。
その攻撃の手をとめることなく、オープン回線で乙羽が声をかけた。
「……あなた、名前はなんだっけ?」
それはホーリーナイトに向けられた声だった。
「姫野。姫野輝夜、三年よ」
ドンッ、っと下から突き上げるように振り上げた拳を、双剣を掴む柄付近で受け止めての鍔迫り合い。
「そっか、先輩だったんだ」
「別に敬語とかどうでもいいよ」
「――速いのね。翼が、エースに帰ってきた理由がなんか分かった気がするよ」
「それはどうも《ヴィーナス》。でもまだあなたに一撃も入れてない」
「アハハッ、そう簡単に……攻撃を受けるわけないでしょう。私、これでも女王なの!」
それまでの剣戟から、不意に右足のケリを飛ばしてくる。虚を突かれたホーリーナイトはギリギリのところで腕を体の間に挟み込むも、勢いのまま吹き飛ばされる。フィールド端へと流れていく白の機体を同じ勢いでクリムゾンエッジが急襲する。上空から覆いかぶさってきた剣戟をホーリーナイトはさらに地面の方へと一段沈み込むことで回避、体をひねりながら方向転換し、今度は上空へと一気に飛び上がった。ストップ&ゴー、最大速度というよりはゼロから最高速までの圧倒的な加速こそがホーリーナイトの、姫野先輩の特徴ともいえる。
その姿を見上げるようにしながら、クリムゾンエッジが体制を整える
「大丸君!」
オープン回線のまま、乙羽はオペレートデスクの大丸に話しかける。
「機体、壊しても大丈夫? 修理間に合う?」
大丸回線をオフにしないまま、1つため息を交えながら答えた。
「全国大会前のこんな時期に……って、そんな事言っても、キミは言い出したら聞かないから」
「……ごめん」
「いいさ、そのために僕らがいるんだ。好きにしていいよ」
「……うん! ありがとう!」
返事の直後、クリムゾンエッジを中心に地面から砂塵が円形に舞い上がった。上空にいたホーリーナイトにその刃が届く位置まで一瞬で飛び上がる。半歩遅れてバックステップを踏んだホーリーナイトの胸部パーツに鋭く横一文字の傷が入る。
ビーっという警告音。装甲の上、ダメージ量は軽微、だが確実にそれらは蓄積されている。
「ファイ、ブーストレベル再調整、ドライブ出力の警告設定をすべて解除!」
「了解」
GPドライブが壊れないように設定していたリミッターを解除する。
「先輩!」
オレの声と同時、ホーリーナイトの両手が輝きを増す。
――これは練習試合。無理をしてフレームを壊してしまったら、予算もない中どうやって冬の大会を目指したらいいのか、考えるだけでも眩暈がしそうだ。だが、そうだったとして、じゃあ今、オレや先輩は目の前の戦いを諦められるのか?
先輩の動きから伝わってくる。3年間ずっと本気だった、ひとりで本気で頂点を目指してきた人が、そのゴールを目の前にして「次」なんてものを考えられるのか。
――否、そんな事できるはずがない。練習試合だからだとか、そんな事はまるで関係ない。今は、今を全力で戦いたいに決まってる!
「いけぇ! 先輩!」
最大出力でのホーリーナイトの0から100へのギアチェンジ。残像だけを残して視界からフレームの姿が消えるその超加速は、もはや人に追える動きではなくなってきていた。その影を捉えようと、クリムゾンエッジはショルダー部の実弾を繰り出して周囲へとばらまく。撃墜というよりは行動を制限するための布石。ここまで近接のみで戦っていたクリムゾンエッジが、明らかに勝ちに来ている。そりゃそうだ、乙羽はおとなしく見えて、根っからの負けず嫌い。だからこそヴィーナスなのだ。
乱撃の中で両フレームが度重なる攻防の中、徐々に、だが確実に砕け始める。両者ともに装甲下のスーツが露出している箇所が散見される。そこに直撃すれば一撃で試合終了になるだろう、パラメータ的には実弾の直撃が多いホーリーナイトの方がダメージは大きく、明らかに差をつけられている。それはシンプルに実力差といえるだろう。だがクリムゾンエッジの装甲にも大きく傷がついたこの期に及んでは、ここまでのパラメータがどうだとか、そんな話ではない。もはや確定的な一撃で流れ・勝負が決まる、そんな状況だった。
――チャンスはある。
オレにできる事はひたすらに今できる最大の状態にパラメータを調整し続ける事だ。壊れた個所の出力をバイパスして、補助出力に。それでもだめなら、OSごと書き換えてしまったっていい。今できる最高の環境を彼女のために。
――そして、一度は裏切った乙羽に今の自分を示すために。
「らあああああああああああああああああああ!」
姫野先輩が雄たけびを上げる。渾身の右ストレートは、ぐっと右へ体をずらした深紅の機体の左頬あたりをかすめた。頭部パーツに亀裂が入る。
「っあああああああああ!」
クリムゾンエッジが回避した反動を利用して右下から切り上げてくる。それを右足で蹴り飛ばす。接触面の装甲が煙を上げて吹き飛ぶ。そこから横回転、ホーリーナイトの右回転のフックも、クリムゾンエッジの左手に止められた。
息が上がる、チャンスはもう何度もない。動的エネルギーの限界が迫っていることはオレも先輩も分かっていた。
ホーリーナイトはバラまかれる実弾を旋回しながら回避しつつ、ほんの小さな可能性が少しでも上がる瞬間をひたすらに探っていた。
正面からの攻撃は、すべてあの双剣の剣戟に阻まれる。かといって、1VS1で背面をとるなんて、そんな事、並大抵の動きでは作り出せない。
――そう、並大抵の動きでは。
「先輩、正面から行きましょう」
「えっ?」
「……マップに軌道計算を」
オレはデータを共有マップへと転送する。それは、ただ正面から突っ込んでいくという作戦とは呼べないようなものだった。
「真正面から突っ込んで、攻撃をすべて回避して懐へって、こんなの作戦じゃなくない?」
当然、先輩にもツッコまれた。
「……先輩ならできるって信じてるんで」
「プッ……アハハハハハッ! ……わかった、やってみる!」
そこまで旋回を続けていたホーリーナイトは一旦高度を上げていく。そうして一瞬だけ挙動を停止すると、空を蹴りだすようにして一気に下へと加速した。上から下へ、重力エネルギーを加算しての最大加速。真正面から突っ込んでくるそれにクリムゾンエッジはできる限りのミサイルをぶっ放す。超速度の中でそれらに反応、絶妙な体バランスでそれらを受け流していくも、一部は回避しきれず腕や足に被弾する。煙が上がる中、だが決定的なダメージのないまま、両手の拳が一層強く輝き始めた。ミドルレンジでの攻撃にシフトしていたクリムゾンエッジも両手の剣をクロスさせて構える。リーチは剣に歩がある、ただ真っすぐ突っ込んでくるそれの軌道に合わせるように、左手の剣を突き出した――その刹那、体のひねりを利用して軸を一段ずらす。突き出した剣の下へと白銀の機体が潜り込む。だが、それも読まれている。クリムゾンエッジの超反応、右手の剣がそれを捉えようと動いた。
――ガンッ!
白銀の左手の拳がその斬撃を捉えた。攻撃を攻撃で弾き飛ばす、斬りかかった剣はわずかに軌道を変えた。その隙間に滑り込む。ホーリーナイトがクリムゾンエッジの胸元に滑り込んだ。だが瞬時に逆手に持ち替えた左手の剣がそこへ振り下ろされる。何段もの攻撃オプションを間髪入れずに重ねてくるその判断力の上をいかなければ、彼女には届かない。
――ホーリーナイトは今日最大の輝きを見せる。
振り下ろされた剣の軌道上に白銀の姿はもうなかった。最後のエネルギーを使ってのベリーロール、急加速で背面へとドリフトするように回り込んだ。その回転の勢いを乗せた渾身のフックがクリムゾンエッジの背面に届くか否か……その刹那、爆発が2度あった。
煙を上げて、ホーリーナイトが崩れ落ちる。オペレートモニターには赤字のアラートと、続行不能を告げる警告文が出ている。攻撃を受けたわけじゃない。だが腕と足の関節部に亀裂、自身の動きに耐え切れずに内部の履帯が自壊してしまっていた。
ブーっという大きな音が流れ、フィールド中に試合終了を告げる。地面に崩れ落ちた3機、空には深紅の機体が1機。
ブザーに遅れて、パラパラと聞こえ始めた拍手が徐々に大きな歓声と共に彼女たちを包み込んでいく。集中していて気が付かなかったが、グラウンドを囲む生徒の数は試合開始以降も増え続け、まるで全校生徒がそこにいたのではないかというくらいのものへと膨れ上がっていた。大きな歓声は途切れることなく学園を包み込んでいた。
* * * *
DGTの全ての機材を積み込んだエアロバスが出発の準備を進める。高宮先輩がこちらへと寄ってきて、すっと手を出してきた。
「今日はありがとう、勉強になったわ」
「いやこちらこそ……」
オレはその手をとり握手する。
「まさか刀を投げつけてくるとはね、相変わらず変わった事考えるのね。一杯食わされたわ」
ちょっとだけ掴んでいた手を強く握り返された。
「あはは、そうでもしないと高宮先輩の隙はつけないかなって」
「そうね……本気で勝つつもりでやってくれてたのがわかって嬉しかったし、なによりあの姫野って人と対戦出来てよかった。まさかあれほどとはね……いいデータを貰ったわ」
そういうと握手していた手を離す。
「全国、目指すの?」
「……はい。まだ人数は、こんなですけど」
そう答えると、高宮先輩は優しく微笑んだ。
「……ううん。次の、冬の予選にキミたちの名前が出てくるのを楽しみにしてる」
「はい。高宮先輩、どうもありがとうございました」
オレが頭を下げると高宮先輩は小さく手を振ってエアロバスの方へと歩いて行った。その様子を見ていた大丸はこちらを睨みつけるようにして、だが何も言わずにエアロバスへと戻っていく。そんな中、乙羽は姫野先輩と何やら楽しそうに話をしていた。だが戻る時間になったのか、大丸と高宮先輩に促されるようにして乙羽は姫野先輩との話を切り上げると、こちらに走ってくる。
「翼、今日はありがとう。楽しかったよ!」
「急に無理を言ってごめんな」
「ううん、大丈夫。私が戦いたかったの、今の翼と、それから……翼を連れ戻した人と」
そういうと彼女はチラッと姫野先輩の方を見る。
「……でも私、待ってるから」
「えっ?」
「もう一度翼と、一緒に戦えるのをさ」
「それは……どういう……」
「……じゃあまた連絡するね! バイバイ!」
オレの言葉を遮るようにして、乙羽はそう言うとオレの肩を軽くポンと叩いた。エアロバスに向かう道中、学園中から飛び交う歓声に笑顔で答えながら、彼女たちを乗せたエアロバスはふわりと空へ舞い上がった。
それを見つめながら、姫野先輩が足を引きずるようにしてゆっくりと歩み寄ってくる。
「……強かったね」
「そうですね」
先輩は大きく息を吸う。少しだけ間をおいて、言葉を綴る。
「……あー、もう! 勝ちたかったね」
「――はい。先輩の動きに耐えられるようなエアロフレーム、絶対に作るんで。だから、次は勝ちましょう」
「……!! うん!」
姫野先輩はいつものようにその白い歯を見せながら、大きく笑った。
青空の向こうにDGTのエアロバスが消えても、しばらくの間グラウンドを覆うざわめきは消えることはなかった。
「あ、そうだ! 神谷野君!」
不意に何かを思い出したかのように、先輩はオレに声をかける。
「どうしたんですか?」
「キミの事、翼って呼んでいい?」
姫野先輩は少し上目遣いに、そんな事を聞く。
「いや……それは別にいいですけど、急にどうしたんですか?」
「だってあの子、キミの事を翼って呼んでたでしょ?」
「そりゃ、幼馴染ですし」
「勝つには、まずはそこからかなって思って」
「は???そこ?」
「もっとちゃんと仲間になりたい、って思ったの。私も彼女に負けないくらい、チームになるために!」
「あ、まぁそういう事なら……」
気持ちの問題、な気もするけど、まぁ先輩の心持は分からなくもない。
「じゃあ先輩、代わりっていうとなんですが」
「ん?」
「オレも先輩の事、姫野先輩じゃなくて輝夜先輩って呼んでもいいですか?」
そういうと、先輩は一瞬きょとんと目を丸めたが、すぐに満面の笑みで
「もちろん! よろしくね、翼!」
そう応えるとギュッと手を繋ぐ。そのまま上下に大きく振りまわした。
「痛い痛い!!痛いです、姫野先輩」
「違う、輝夜にするんでしょ!」
「あーごめんなさい!!痛いです、輝夜先輩!!」
オレ達は勝てなかった。だけど、勝てないとは思わなかった。
それだけで十分、このチームはこの先を戦える、そう思った。
chapter4-6 (終)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
