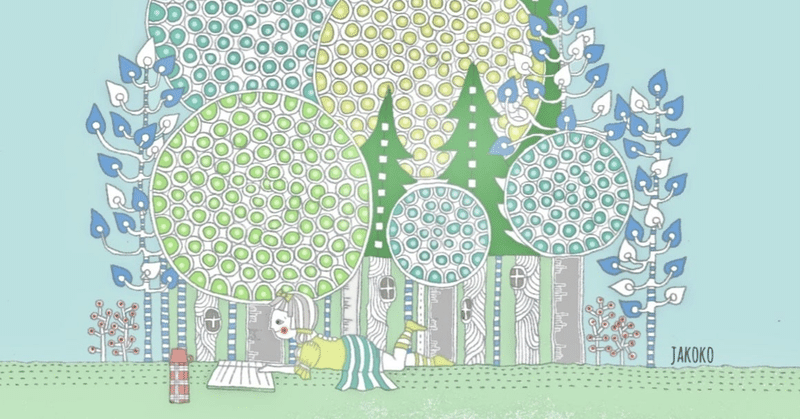
やりたいことは変わらない
この度、読書会開催に至った経緯を綴ろうと思います。
読書会についてのご案内はこちら。
私は元小学校教員として、基本的には全ての教科の授業をしていましたが、
専門は国語でした。大学では、国語教育専攻。
結果的に小学校を選びましたが、中学校で国語の授業をしてみたかった、という思いもあります。(実習はぼろぼろだったけど🤣)
就職後も、教材研究会に参加して、小〜中の教科書教材を読んではあーだ、こーだ話し合うのがとにかく好きな時間でした。どう授業するか、ではなく教材として、読み物としてどうか、を話し合う点が私にとっては貴重な勉強会でした。
でも実際に授業をしていて、一番苦手なのも国語でした。
一番あれこれ試行錯誤したと思うけれど、なかなかうまくいかないし、子どもたちもあまり楽しくないのではないか…といつも内心不安でした。
その原因は、ひとえに私の勉強不足、技術不足なのですが…
熱い思いがあるからこそ、空回りしまくりだった教員時代から、密かにずっとやりたいと思って温めていて、でもできなかった授業があります。
それは「おおきな木」の訳の比較読み。
「おおきな木」を教材に授業がしたい
原典は“THE GIVING TREE” Shel Silverstein (1964) HarperCollinsPublishers
有名な絵本なのでご存知の方も多いはず。
この訳が2010年に本田錦一郎さんから、村上春樹さんに変わったのはご存知でしょうか?
この「おおきな木」はこれまで篠崎書林から本田錦一郎さんの訳で出版されていましたが、翻訳者が物故され、出版社が継続して出版を続けることができなくなったという事情もあり、今回訳を改めることになりました。長く読み続けられた本なので、混乱を避けるために「おおきな木」という元の題はそのまま使わせていただきました。 村上春樹 2010年5月
「おおきな木」(2010)あすなろ書房
訳者あとがきより
おそらく、絵本という側面を重視した本田錦一郎さんの訳に対して、原典に忠実なのが村上春樹さんの訳なのだと思います。
訳者あとがきで村上春樹さんも、ほんのり触れていらっしゃるし。
もちろん、どちらが良いとか、優れているとか、そういうことは一切なく。
私個人は、本田錦一郎さんの訳に長年親しんできて愛着がある上で、村上春樹さんの訳に、ううむ…!と唸りました。
今でも片方の本を読むと、もう片方も読みたくなって…とついつい「おおきな木」の世界に浸っています。
同じ本を、こんな風に二度楽しめるのは、(原典も含めれば3度!)なんと贅沢なことでしょう。
教員2年目?の頃に、村上春樹さんの訳を初めて読んだ私は、いつかこれを教材にして授業したい!と野望をもったのでした。
訳の比較読み、というのは別に私のアイディアではなく、大学の授業でやったことでした。
確か魯迅の「故郷」(中学校の教科書教材ですね。)の訳の比較をしたのが楽しくて、訳者によってこんなにも解釈が変わるのか!と大変興味をもちました。
そして、この「おおきな木」は、小学校で和訳の比較をするのにもってこいの教材に思えました。
同じ原典を読んでも、訳はこんなにも違う。
もちろん内容は同じなのですが、どんな言葉を選ぶか、ということにその人が現れる。そんな言葉の面白さを授業で扱いたい!
それ以前に、子どもたちはどっちの訳が好きなんだろう。
そんな単純な興味というか、好奇心です。
きっとどちらの訳に先に触れるか、によっても印象は大きく違うでしょう。
この本を読んだことある人も、初めての人も、輪になってそれぞれの良さを語り合いたい!
何年生だったら指導要領にマッチするかな、どんな風に授業をしようか…と暇ができたらあれこれ妄想していました。
これは、単純に私のしたいこと、です。
だからこそ、本当に教材に耐えうるのか、子どもたちの力になるのか…あれこれ考えるうちに時間は過ぎて、
結局何一つ形にできないまま、私は教員を退職してしまいました。
本を味わうということ
これは尊敬する恩師が大学の講義で話していたことなのですが、
読書には「心で味わう」という側面と、「頭で理解し解釈する」という側面があります。
もちろん、これは切り離せるものではなく、内容理解ができているからこそ、おもしろさがあり、感動があるのです。
ただ、学校の授業では、この味わう…という部分を扱うのが意外と難しい。
それは個々の生活経験と結びついた読者の個人的な体験だから。
そもそも内容理解で引っかかると感動云々以前の問題なので、そこに重点が置かれるのもわかります。また、最終的にテストという存在がある以上、ただ味わっておしまい!素敵なお話だったね、で終わらないのもある意味仕方がない。
けれど、読書(ここでは特に文学作品)の楽しさって、要は芸術体験なのです。
絵を見て心震えるように、歌に感動するように、ダンスを見て胸が熱くなるように、言葉で紡がれたその世界を味わうことに意味があるように思うのです。
その感動を個人の読書体験に留まらせず、みんなで共有してみたい、そんな風に思いながらも、私は、そこまでできなかったなぁーと思うのです。
みんなで同じ本を読んで、シェアすることで、自分と他者の読みの相違に気づいたり、読みが自然と深まっていく…そんな授業がしたい、そもそもこれが私が教員になった理由の大きな一つであるように思います。
ずっとそういう授業に憧れていた、けどできなかった。
読書会で昇華させる
教員退職から約1年。
私が教員としてできなかったことは、読書会という形で昇華できないだろうか、と今考えています。
これは単純に私のしたいこと、なので学校という場を離れるからこそ、自由に好きなようにできるのかな、と思いはじめています。
教員だからできる、から、教員じゃないからできるへ。
行かねばならない学校ではなく、参加したい人だけが集う場所で、
大人とか子どもとか関係なく、教える、教わるという構造を排して、みんながフラットに思いを述べられるような。
そんな場をこれから作っていきたい、という願いをもって。
まずはオンラインで読書会を始めてみようと思います。
つまり、これは私のリベンジ戦。
教員という肩書きを脱いだことで、やっと楽しく自分らしく、やりたかったことができたらいいなぁと思っています。
と、同時に怖さもあります。
やりたいとできるは違うから。
そもそも、一人ではできないことなので、誰もこんなことに興味なかったら、成立しないのです。
どうか一人よがりではなく、誰かと本を通じた対話の時間がもてますように…と願いを込めて。
さらに、もし興味をもってくださった方がいたとして、私にそんな有意義な時間、場をつくれるのか。その不安も大きいです。
失敗したら…やってみてつまらなかったら…なんて思うけど、動かないことには始まらない!
面白くなかったら、また面白くなるように変えていけばいい。
そんな気持ちで読書会を開催します。
あれこれくどくど書きましたが、
要は同じ本を片手に、集まって話がしたい!それだけなのです。
ぜひとも、お気軽にご参加いただけると嬉しいです。
第1回読書会
テーマ:「おおきな木」訳の比較を通して、感じたことを語り合う会
3月13日(月)13:00〜1時間程度
別日程で夜or土日開催検討中です。
人数:2〜5人
参加資格等はありません。どなたでもお気軽に☺︎
申し込みはTwitter dmか、このnoteのコメント欄にお願いいたします。
ご参加お待ちしております☺︎
ありがとうございます♡ pucchen-houseの運営資金として大切に使わせていただきます。 ぜひ、応援お願いいたします🙏
