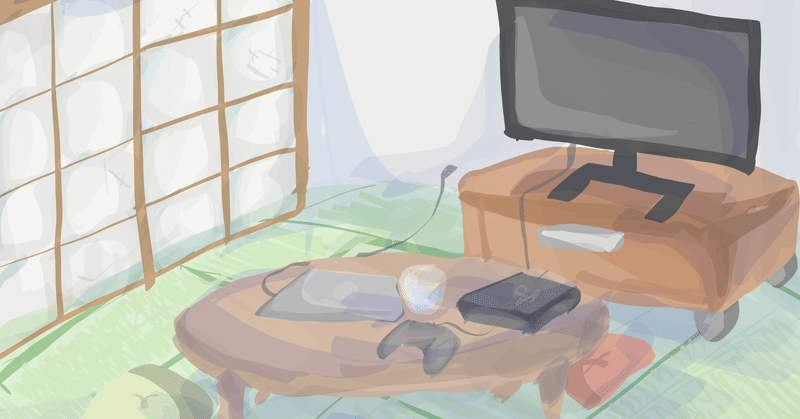
信田さよ子『家族のゆくえは金しだい』春秋社
note初めての投稿です。緊張しています(笑)試行錯誤しながらスタイルに慣れていきたいなと思います。
この本は 生き方の本、女性に関する本、家族・人間関係の本 です。
私は2018年後半に、著者が代表を務める原宿カウンセリングセンターで(著者ではない方の)カウンセリングを利用し、著者の講座を受けました。講座では学ぶことが多く、この方の本を紹介することにしました。
【著者紹介】
この本は、長年「家族問題を扱うカウンセラー」として現場に立ち、日本の家族問題を心理学的な側面から牽引してきた著者によるものです。「AC アダルトチルドレン」や「共依存」「母娘関係の難しさ」について世間にその概念を広めた人でもあります。
[信田さよ子]1946年岐阜県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部哲学科卒業、同大学院修士課程家政学研究科児童学専攻修了。駒木野病院勤務、CIAP原宿相談室勤務を経て1995年原宿カウンセリングセンター設立、現在に至る。
【内容まとめ】
長年タブー視されていた、「家族とお金」の問題に切り込み、
「お金は家族関係に潜む力関係や支配といった権力の構図を明るみにする」ことについて様々な事例を紹介しています。
また、子どもによるお金の要求は愛情要求の歪んだ形であることも多く、執拗な要求に「親が逃げる」ということは長く選択肢として許されてこなかったが、距離を置くというのはとても大切であることを伝えています。
そして、近年親を超える経済力を子どもが得られることは難しく、「持てる親と持たざる子」の関係性において、問題行動を断ち切るために「いかにお金を出さないか」ということが重要であると筆者は訴えます。
依存傾向にある子どもにお金を与えることは問題行動を支援する「イネーブラーenabler」になることであり、お金をいかに出さないかということが大事であるそうです。そして、問題を抱える子どもに対する、お金を与え方や金額の多寡は相談者のその後の方向性を左右するポイントであると臨床の経験から筆者は読者に伝えています。
本書をひもとく
【Ⅰ 家族の肖像】
〜衝撃的な家族とお金の事例〜
前項にも書きましたが「家族とお金」の様々な事例が載っており、これが実に衝撃的です。
・結婚して独立しても娘を支配しようと、小荷物にお札を忍ばせる毒母
・過食を繰り返し自分の躓きは親の責任だと責め、お金を引き出し続ける娘
・ひきこもりで母のパート代を頼りに生き、母親を何時間も説教してコントロールしようとする40代の息子
・なんのためにお金を使うのかという理由を常に親から求められていたため、お金についての罪悪感を持ち続けている娘
・母の思い通りに育ってきて結婚後も支配を受け続ける息子
・放蕩息子にお金を出し続ける父親
・見知らぬ他人に脅されているのにお金を出し続ける公務員
・夫からクレジットカードしか使わせてもらえないという経済的DVを受ける妻・・・
こうした事例が本全体の半分近く続いています。
どの事例も読んでこちらの息がつまるような苦しさがあり、読んでいて辛くなります。特に前半の事例は、子どもの問題行動から夫が目を背け、一心に問題を背負い込む母の姿が描かれており、その負担はいかばかりかと計り知れません。
【Ⅱ 時代の鏡としての家族】
戦後70年、家族問題とお金の問題はどう扱われてきたかということについて、本章ではさまざまに述べられています。
家族問題については、子どもにどんなにひどいことをされても親は受け止めなくてはならないという風潮があり、それで親が潰れてしまうケースが多くあることが書かれています。昨年も農水事務次官による子殺しの事件があり、まだまだ根強く残っている考え方でとても危険なものだと私自身思っています。
お金については、社会の変化によって価値観そのものが変化してあり、ずっと変わらないと信じられている価値観もたかだか明治以降の考え方であり、今も変わり続けていることを筆者は指摘します。そして昨今日本経済が鈍化し、親の世代を子どもが超えることは難しく、親への経済的な依存が家族関係に影響を及ぼしているということは、私を含めた親世代が子どもの成長を見守る際に持っていたい視点です。
【Ⅲ 家族をとらえなおす】
高齢化、少子化が家族関係に与える影響の他、後半は筆者による「いくつかの提言」が掲載されています。
この章は実際に子どもの問題行動に対応している親にとって、たくさんの示唆があります。どの家庭も大抵は母親が一人で子どもの問題に対応し、大抵の父親は無関心を決め込むか、子どもの問題母親のせいであると責任転嫁するという記述には胸が痛みます。
・子どもは親に謝罪を求め、最終的にはお金を求める傾向にあること
・その経済要求は親の懐事情を実に見抜いている現実的な金額であること(「春闘の労使交渉が交渉可能な絶妙な金額であるのと同じ」という例がなかなか秀逸です)
・子どもに暴力を振るわれ無理な要求を受け続けているうちに、親が反省するとその証拠として子どもはお金を要求する。子どもにとってお金と愛情は同義である
・子どもは自分に関する訴えよりも、親の育児に対する不全感や罪悪感を責めることのほうが母親を追い詰めることを知っており、いわば「質の高い親」ほど「責め甲斐のある親」であるといえる
各ポイントはどれも衝撃的ですが、説得力がありました。
【編集の視点から】
Ⅱ・Ⅲ章ともに臨床現場のこと、社会背景、筆者の考えとが行ったり来たりしてやや散漫な印象がありますが、内容が衝撃的で一気に読みすすめることができます。最初にたくさん登場する事例はそれぞれAC、各種アディクション、母娘関係と種類が異なるので、それぞれを深く知るには著者の他の本などをあたるのをおすすめします。
最後までお読み下さりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
