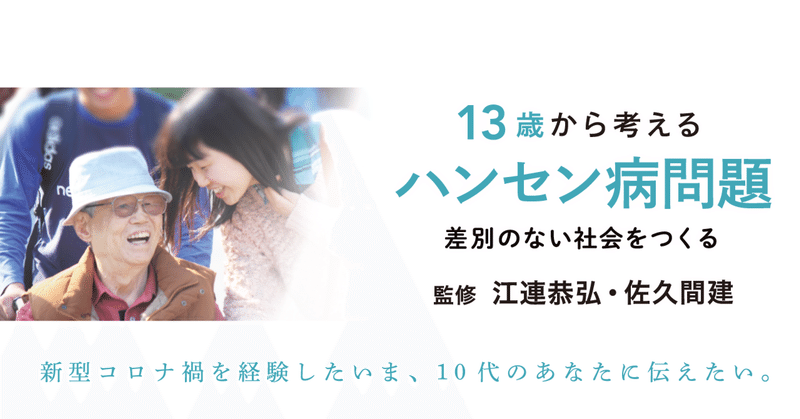
連載⑨ ハンセン病療養所の今とこれから(1)
今年5月、江連 恭弘・佐久間 建/監修『13歳から考えるハンセン病問題 ―― 差別のない社会をつくる』を刊行しました。(以下の本文では『13歳…』と略します。)
編集を担当した八木 絹(フリー編集者、戸倉書院代表)さんに、本に寄せる思いを書いていただきました。不定期で連載します。

14のハンセン病療養所で812人が生活
ハンセン病の回復者には、大別して、ハンセン病療養所で生活している方と、退所して一般社会で暮らしている方がいます。社会復帰した後で病気が悪くなって再入所した方もいます。
現在、国立ハンセン病療養所は13園、私立は1園あります。1950年代のピーク時には全国で約1万2000人の入所者がいましたが、今年の5月1日現在で812人(私立1園を含む)。昨年が929人でしたから、この1年で117人減少しました。国立の療養所入所者の平均年齢は87・9歳(厚労省医療経営支援課)と、高齢化が進んでいます。
日本では、1907年の癩(らい)予防ニ関スル件、31年の癩予防法、53年のらい予防法を法的根拠とする絶対隔離政策が長期にわたってとられたため、法が廃止された96年には、社会復帰するには高齢になっていたという方が多いのです。
『13歳…』では療養所での生活を「第3章 ハンセン病療養所はどんな場所か」で、歴史を中心に詳しく伝えました。本連載では、療養所の今と今後について、考えてみたいと思います。
多磨全生園を初めて訪れた日―― 強烈な印象を受けた風景
東京・多摩地方の東村山市に国立ハンセン病療養所多磨全生園(たまぜんしょうえん)があります。私がここを初めて訪れたのは2018年でした。ハンセン病回復者が偏見差別に苦しんできた人生を語る「語り部の会」を続けることが、高齢化のため難しくなっていると知り、参加してみたのです。

ハンセン病患者の母子遍路像が迎えてくれる(2023年、筆者撮影)
会場の国立ハンセン病資料館は、同園の敷地の隣にあります。まず私は園内をぐるっと回ってみました(現在はコロナ感染対策のため、園内の散策は一部に制限されています)。
目に入ったのは、入所者の居住棟(写真)です。国の隔離政策からくる差別を受けてきた、体の不自由な高齢者が暮らすには、不十分なものに見えました。その建物が広い敷地にズラッと並んでいる様子に、私は、かつて訪れたポーランドのアウシュビッツ絶滅収容所のビルケナウ・サイトに一部残るユダヤ人居住棟を思い出してしまったのです。入所者が待遇改善を求めてこの言葉を使うならまだしも、現在もそこに住み、終(つい)の住処(すみか)にするしかない方々がおられるのに、外から来てそのように見るのは不見識なのですが、この時の私の正直な印象です。

そのことを最近、『13歳…』の監修者である佐久間建先生に話したところ、次のような話をしてくださいました。
「今のような個別住宅の居住棟は、1950年代の療養所入所者にとっては夢であり、切実な要求であり、運動の成果によって獲得できた住環境です。それ以前は雑居部屋で共同生活を強いられ、新婚夫婦でさえも二人きりでは暮らせませんでした。個別住宅に暮らすことができるようになって、ようやく人間らしい住環境で暮らせることに安堵し、幸せを感じたという声を聞きます。私は1990年代から全生園の入所者の皆さんと交流してきましたが、皆さん楽しく明るく暮らしていて、私がクラスの子どもたちを連れて療養所内を歩いていると、子どもたちが自分たちの住まいの近くに来てくれたことを喜んで、声をかけてくださり、子どもたちにジュースを出してくれたこともありました」
今は入所者の平均年齢は90歳に近づき、居住棟から「センター」と呼ばれる医療施設に移る方が増えました。もとの居住棟での暮らしを望んでいる方も多いそうです。
初めて全生園を訪れて以降、私は国立ハンセン病資料館での映画会や企画展示、人権セミナーなどに参加するようになりました。徳田靖之著『感染症と差別』(2022年、かもがわ出版)の編集作業や『13歳…』の執筆作業で、同館の図書室で調べ物をするために、訪れた回数は50回を超えました。そこで暮らす方々の話を聞き、ハンセン病問題の歴史から学ぶ中で、最初の印象は変わり、生身の人間が暮らす生活空間として目に映るようになりました。園内の食堂「なごみ」の店主・藤崎美智子さん(全生園の明日をともに考える会代表)の優しい笑顔、そこで食べた焼き魚定食の美味しさも手伝って。

緑の森をつくり歴史を未来に残す―― 人権の森構想
ハンセン病文学の傑作「いのちの初夜」(北條民雄、1936年)は、主人公の尾田が全生(ぜんせい)病院(現在の多磨全生園)に入院する日、絶望から自死するための木を探して、周辺を歩き回る場面で始まります。私はここに行くたびに、尾田が歩き回る光景を想像するのです。
多磨全生園は東京にありながら、全国の療養所の中で最も緑が豊かだといわれています。雑木林の残る武蔵野の地域でも際立つ、260種類、3万本の樹木を誇ります。しかし、こうなるには長い歴史がありました。
本連載第3回「戦争と絶対隔離政策」でも、戦争中の療養所は空襲の危険もあり、食料や燃料、医薬品が不足し、大変な状況だったことを書きました。園内の木々は伐採され、燃料にされたり、防空壕、柩(ひつぎ)の材料としても使われました。林は食料確保のための畑に変えられたのです。一方で、重症者の付き添いをしていた軽症患者が、燃料不足で病人にお茶を飲ませることができず、路傍のプラタナスの木を切って燃料にしたところ、国の財産である木を無断で切ったという理由で、園長に監房に入れられたという事件もありました(松本信『生まれたのは何のために』教文館、1993年)。

納骨堂も患者作業で建設された(2023年、筆者撮影)
死後も故郷に帰ることができない入所者にとっては、懐かしい故郷の木を療養所に植え、故郷を感じたいというのは、切なる願いでした。そうしたことから、戦後、入所者自治会を中心に、緑化運動が取り組まれてきました。「ふるさとの森づくり」運動や、一人一木運動(*)です。
*この項は主に柴田隆行『多磨全生園・〈ふるさと〉の森』(社会評論社、2008年)を参照。
療養所では文学活動が盛んです。「桜よ」という詩からは、入所者にとって樹木がいかに大切な存在かがよく分かります。
桜よ 飯川春乃
〔…〕
広い病院の北の外れの
春浅い畑の端に
一本の幼い桜の木があった
知り合いもいない
十七歳の私の胸に
小さな桜の木が宿った
〔…〕
大きくなった桜の木は
並木に移され
他の桜の木とともに
ますます大きくなっていった
あの頃も
桜の花が咲くのを楽しみに待った
〔…〕
だが
私は盲いとなり
桜の花もその色も
目底に淡く残るだけとなった
あの幼かった桜の木
その美しさは広く知られるようになり
多くの人等が集う名所となった
また花咲く季節がめぐってくる
私は白杖をついて並木道を歩こう
桜よ
私とともにここで生きた桜よ
たくさんの人の目を楽しませておくれ
そして
全生園と私たちを語り継いでおくれ
(『多磨』多磨全生園入所者自治会、2003年9月号)
現在、多磨全生園では東村山市と協力して「人権の森構想」が進んでいます。「将来、自分たちがいなくなった時も、この緑の地を市民に残そう」というものです。同園では、今は使われなくなった歴史的建造物の取り壊しが進み、空き地が目立ってきました。これらは、ハンセン病差別の「負の歴史」を伝える証人であり、きちんと保存してほしいと望む入所者や市民の声が高まっています。私も、多摩地域の住民として、多磨全生園の将来に関心をもち続けようと思います。
同園内にある国立ハンセン病資料館は、素晴らしい学びの場です。常設展の歴史・生活展示、人間回復を求めた患者(入所者)運動の紹介など、とても勉強になります。現在、その患者(入所者)運動についての企画展示が行われています。ぜひ足を運んでみてください。
◇企画展「『らい予防法闘争』七〇年 ―― 強制隔離を選択した国と社会」
◇と き 2023年8月13日〜12月10日
◇ところ 国立ハンセン病資料館(多磨全生園内、東村山市青葉町4-1-13)
◇入場無料 月曜休館
*本稿は、多摩住民自治研究所『緑の風』2023年12月号(vol.281)にも掲載されます。

◉『13歳から考えるハンセン病問題―差別のない社会をつくる』目次から
第1章 なぜハンセン病差別の歴史から学ぶのか
ハンセン病患者・家族が受けた激しい差別/ハンセン病とはどんな病気?/新型コロナ差別にハンセン病回復者からの懸念/過去に学び、今に生かす
第2章 ハンセン病の歴史と日本の隔離政策
日本史の中のハンセン病/世界史の中のハンセン病/日本のハンセン病政策/日本国憲法ができた後も
第3章 ハンセン病療養所はどんな場所か
ハンセン病療養所とは?/療養所内での生活/生きるよろこびを求めて/社会復帰と再入所
第4章 子どもたちとハンセン病
患者としての子どもたち/家族が療養所に入り、差別された子どもたち/生まれてくることができなかった子どもたち
第5章 2つの裁判と国の約束
あまりに遅かったらい予防法の廃止/人間回復を求める裁判/家族の被害を問う裁判
第6章 差別をなくすために何ができるか
裁判の後にも残る差別/菊池事件 裁判のやり直しを求めて/これからの療養所/ともに生きる主体者として学ぶ
#ハンセン病 #ハンセン病問題 #13歳シリーズ #差別 #人権 #ハンセン病資料館
