
【洋画】グッド・シリアルキラー – 第あらすじ - ノベライズ
「善を行い、罪を犯さぬ人はこの世にいない」
伝道の書7章20節
22,000字ほど。
【感情のトリガー↓】
第一章:【驚】
第二章:【興】
第三章:【怒・驚】
第四章:【緊】
最終章:【驚・悦】
第一章:双乳の行水
《——ガチャン——》観音開きタイプのドアがひらかれる。照明度のうすぐらい病棟内の廊下をスタスタ…と、疲れきったようすで歩いていく若そうな女性看護師は、ようやっと、めんどくさい患者たちから解放され、夜勤づかれのカラダをシャワー室で洗いながそうとしていた。ボールペンをうしろで簪のように差した——首から聴診器をぶら下げながら——二十代後半くらいにみえるブロンドのわりと美しい女性は、首を左右にコキッ…コキッ…とかたむけた。ほんのすこし、血流が回復したところで、夜の不気味な妖気がただよう静かな廊下をまだ歩いている。すると、T 字のつきあたりを左にまがった。そこから一〇メートルほど歩いたところで、ようやくシャワー室にたどりつく。

彼女は左側についているドアを開けようとした——と、そのとき! なにか、ちいさな物音が遠くから聞こえたではないか。看護師はいったん立ちどまり、じぶんが歩いてきたほうをみやりだす。いちおう、その逆方向もたしかめる。……が、あたりはシーン——としており、さっき聞こえた物音はいっさいしなかった。まるで、“ヘレナ・ボナム”を若くしような看護師は、一抹の不安をのこしながらも、とりあえず、シャワー室に入っていく。すると、ほかの従業員もつかう共用の更衣室が目のまえにあり、その無愛想なツラをくずさない看護師は、じぶんのロッカーを開けて、ユニフォームを脱ぎだした。リアルで生々しい女性の着替えというのは、なんとも華がないというか……そこに色気など微塵もありはしない。とくに、一人のときは……。もうすこし、ゆっくりと……もったいぶるように脱ぐなんてことは決してしないのだ。それに、下着も地味で、しわしわよれよれで……。
身にまとっていたものをすべて脱ぎおえた看護師は、いよいよ行水にとりかかる。奥にあるシャワー室に入っていくと、共用でつかえるシャワーが横並びされている。彼女はその真んなかを使うみたいだ。おそらく、あと数名ほどくらい利用できるのではなかろうか。というのも、今、素っ裸でシャワーを浴びている女性のところしか、ダウンライトが点いていないため、両サイドが暗くてよく見えないのだ。いちおう、個人個人に手すりのしつらえられた壁で仕切られてはいるようだが、その高さは女性の腰にもとどいてはいない。となりに利用者がいれば、ふつうに丸見えじょうたいである。それでも、彼れらは気にしないのだろうか?
じぶんよりも高い位置に固定されているシャワーの水圧を受けながら、看護師はじぶんの手をスポンジがわりに洗っていく。双乳もていねいにまさぐりながら、ほんのすこし、先がとがっていた。……なぜ、わかるのかって? 背中をながすために、プリプリのお尻りをみせていた彼女が、向きを逆に変えたからである。その体型はいたって健康。やせすぎもせず、ふとりすぎもせず。そして、まだ二十代でもある。すると、また物音が鳴りだした。それも、うしろから……たしかに大きな音で……。看護師はすぐに気配をかんじて、うしろをたしかめた! シャキ——ンッと閃き、その尖った鋼が彼女の首に突き刺さる!
「……はっ!」グサッ——!!
さらにそこから、黒い手袋をはめた人物はノドにむかって、いっきに水平内転をくりだしたっ! グチャッ……と、ナイフが走るえぐい音をたてたあと、裂けたノドからはチョコレート・ファウンテンのごとく、どす黒い血がながれおちていく。声をだせなくなってしまった女性は、じぶんのノドを押さえながら後ずさり、やがて、くずれ落ちていったのだった。
ビニールにつつまれた遺体を、掘った穴に埋めていく。郊外にある開拓地で夜もおそいため、人目を気にせずに作業ができるのだ。掘った地面をきれいに平たく埋めおえると、その人物は車ではしり去った。
むかったさきは……家。なぜかカギが開いていたため、その人物はしずかに入っていく……。足音をたてずに、暖色のペンダント・ライトが点いているリビングを通っていくと、奥にある寝室へと足をはこんでいく……。おや……!? ベッドには若そう女性が眠っているではないか。二十代後半くらいにみえる移民ふうの優美な女性が。それも、月明かりが差してくる窓のほうを向きながら、スヤスヤと……。よく見ると、その女性の左手には結婚指輪がはめられている。どうやら、既婚者のようだ。彼女を起こさないように上着を脱いだあと、その人物は女性のとなりに…………
すると、目を覚ました女性が振りかえるっ!
『えんぎゃぁ……えぇぇん……』
「キミは寝ててくれ、ボクが行くから」女性のとなりで横になっていた夫のエヴァン(三十代)が言った。
「まかせて大丈夫?」目を覚ました妻のローレン(二十代)。浅黒い肌に、妖艶な瞳をした——端正なおももちである彼女の手に持っているのは、じぶんの赤ちゃんが映っているベビー・モニターである。赤ちゃんの泣き声もひろってくれる、とても便利なアイテムだ。
ドラマ『リーサル・ウェポン』にも出ていた “ショーン・ウィリアム” =夫のエヴァンは、ニコッと妻にほほえむと、じぶんの赤ちゃんをあやしに向かい、子どもをベビー・ベッドから抱きかかえた。「だいじょうぶ。パパがついているからな。す べ て う ま く い く」その腕はとても温かく、その目は慈愛に満ちていた——。
第二章:義憤の暴挙
「ぶっ殺してやる——!」荒々しい男が今にも殴りかかろうとしている。その固めた右こぶしは おさない少年の顔面に直撃した。顔がゆがむほどの強烈な拳をもらった少年は、せまくてボロい家の床にたおれこむ。すると——
「離れて!」なぐりかかった男に包丁を向けた赤毛の女性が言った。「エヴァン、部屋に行ってなさい!」包丁の先を、男のノドに突きつけた。近くにいる幼いエヴァンは、泣きながら二人の様子をうかがっている。
「……悪かったよ、マリー……」と、後退りしながら血相を変えたエヴァンの父親。
「出てって。すぐ出ていかないなら殺すわよ!」するどい眼光で射すくめているマリー。決して、はったりではない。
妻の形相におののいたエヴァンの父親は、すなおに家を出ていくのであった。
「もう大丈夫よ」マリーは泣いている息子のエヴァンを抱きしめた。「ママがついてるわ。シ〜〜」エヴァンの背中を優しくさすってあげていた——
(「心配はいらない。す べ て う ま く い く か ら……」)
「……っ!?」夢から目を覚ましたエヴァンは、子ども部屋にいるマリーを確認する。
赤ちゃんを抱きながら、ロッキング・チェアをユラユラと揺らしていたマリーは、エヴァンを見上げて言った。「勝手に入らせてもらったわ」
これは、まさに救いの神であった。はじめは、“子どもの世話を手伝うわよ” というマリーの提案を、よけい気を揉むことになるし安らげないと思った妻のローレンは “じぶんたちで育てたい” と断っていたのだが、いよいよ、そうとも言ってられない状態にまで追いやられていたのである。生まれたばかりのアンドリュー(男の子)は、なかなかローレンのおっぱいを飲まないせいで体重がぜんぜん増えず、そのせいで、担当の女性看護師から厳しく——まるで、“あなたはダメな母親ね” と言われているみたいに——怒られるもんだから、責苦の限界にまで達したローレンの精神状態はかなりヤバく、泣いてない日なんか無いくらい毎日ふさぎこんでいたのだ。エヴァンも、そんな妻の心情を汲みとり、仕事から帰宅するとアンドリューの世話をするのは彼れなのだ。オムツを替えたり、夜泣きを落ちつかせたり、ローレンの不安からくる命令にちかい頼みごとにも、いやな顔をせずに聞かなければならない……。それもこれも、じぶんが目指している理想の父親、理想の家族を築きたいがための代償なんだと……思っていたのだが……、ふと、取りだした包丁の腹に映りこむローレンの姿をみると、一瞬、おぞましいことを考えてしまったのだった。
そんなときに、アンドリューの祖母——マリーの登場である。なかなか泣き止まないアンドリューを、いとも簡単にあやしつけ、もののみごとに眠らせてみせたのだ。
「寒ければ言って」客間の寝室にあんないしたエヴァンは、マリーも一緒に住ませることにした——。
《——コンコンコン!——》
自室でミニディスクに録音された——加害者の罪の告白を聞いていたエヴァンは、少しビクッとした。が、そんな慌てるこもなく、沈着なおももちでプレーヤーをデスクの抽斗にしまったあと、部屋のドアをガチャッと開けた。入ってきたのはティーンエイジャーの男子生徒。彼れはエヴァンのカウンセリングを受けにやってきたのだ。
「……オレは長男だから……やられても耐えられる——」ゆるめのバギー・パンツに Tシャツを身にまとい、キャップのツバをうしろにかぶっているティーンエイジャーのレイが言った。「——でも、今度は弟がやられていて……止めに入ったんだ……」その声は、やんちゃそうな見ためとは想像もつかないほど、弱よわしく、意気消沈としていた。彼れの左目はひどく腫れあがっており、痛々しいほどの青痣がついていたのだ。
それぞれシングル・ソファにもたれて向かい合っているエヴァンと生徒のレイ。ふたりの近くにあるロー・テーブルの上には、会話を記録するボイス・レコーダーが置かれていた。
「ボクには通報する義務がある」湧きあがってくる憤怒をうまくおさえながら、冷静に言ったエヴァン。「仮釈放違反なら、また逆もどりだ。キミはそれでも納得できるかい?」
鼻をすすると、レイは言った。「……そうなって当然だろ?」
「レイ」前のめりになったエヴァン。「す べ て う ま く い く か ら」と、意味深長に。
その後、エヴァンはレイの父親の逮捕記録を——学校のなかに設けられている学生相談室から——しらべあげると、父親の行動パターンを分析したのだった——。
赤いバラのネオン・サインが特徴の〈カサブランカ BAR〉という質素なお店から、粗暴なふるまいでマナーの悪そうな——大柄な男がスタッフに追いだされて罵りだす。
「くたばれ! くそやろ——!」ジーンズに革ジャンを着た大柄な男は、すでに酩酊じょうたいである。おぼつかない足取りで屋外を歩きながら、内ポケットからタバコを取りだした——が、中身は空だった。『プリズン・ブレイク』の “ジョン・アブルッチ” みたいな風体をした男は、外に落ちていた——まだ、中途はんぱに残っている——タバコを拾いあげると、それを口にくわえ、持っていたマッチで火をつける——が、なかなか火がつかない。なんど擦ってもダメだった。と、そこに——
「あのー、火を貸してあげるよ」と言って、男が近づいてきたではないか。持っていたライターの火をつけると、荒っぽそうな男のタバコに火をつけてあげたのだ——あのエヴァンが。
はじめは警戒されていたエヴァンであったが、じぶんはタクシー業もやっていて、たまに誰れかを無料で乗せるんだよ、という言葉を大柄な男は信じたようだ。“家まで送ってあげるよ” という、危険じみた甘い誘惑に乗ってしまったのだから。
荒っぽそうな男にしても、じぶんに下手なマネをすれば、この小柄な男をいつでもやっつけれると高を括っていたのであろう。だから、無上な今のじょうきょうに身をまかせてエヴァンの車にのりこんだのだ……。
この社会にたいする不平不満をさんざん聞かせられたあげく、ようやく辿りついた大柄な男の家——というか、空き家になっている瀟洒なテラス・ハウスを、かってに許可もなくつかっているだけなのだが……。
大柄な男は、エヴァンをじぶんの隠れ家にあんないし、二メートルちかくあるスタンド・ライトの照明をつけだした。すると、六畳にも満たないせまい部屋——まるで、ドール・ハウスのように露出している空間で、大柄な男はさらに酒瓶をラッパ飲みしだした。目のまえのエヴァンが、なぜ革手袋を履いたままでいるのか、今、床に置いたそのボストン・バッグの中には何がはいっているのか、そして、晴天だったこの日に、なぜ、レイン・ジャケットを着ているのか——そんなことを、脳裡にも巡らずに……。
「オマエも楽にしろよ」どこかで拾ってきたかのような小汚いフロア・ベッドに腰掛けながら、大柄の男が言った。
と、そのときだったっ——!
《——ゴンッ!!——》
またたく間に、大柄な男は気を失った。エヴァンの袖から現れた鈍器によって、力づよく、振りおろされてしまったのだ。頭頂部にいっぱつ……。
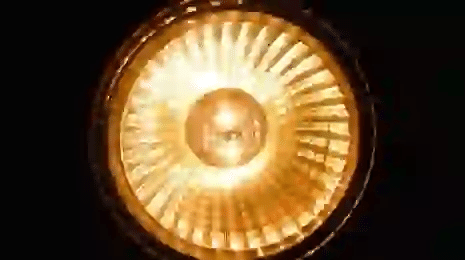
大柄の男が目を覚ます。「……!? なんだ、これは?」
彼れは、用意されたシートの上で、アーム・チェアに拘束されている。さきほどのスタンド照明を当てられながら。
「おい、これを外せよ」しかし、一メートルまえにいるエヴァンは無言のままだった。「ふざけんなよ! このサイコ野郎——!」すると、エヴァンの右拳をお腹にもらう。「ヴオッ……!」
黒のレイン・コートに着替えていたエヴァンは、バッグからボイス・レコーダーをとりだすと、録音をし始めた。それを近くの台座に置くと、ある写真を “人ちがいだ” と宣っている男のまえに見せつけた。それは今朝、学校で相談を受けていた生徒のレイの写真である。
「じゃあ、これは?」冷酷なおももちでエヴァンが言った。
「……このカマ野郎が……」また、エヴァンに殴られる。「……ヴハッ!……」
エヴァンはバッグからナイフをとりだした。「オマエが息子たちにやってることじゃないか? 手も出せない相手に殴りつける」
「オマエに関係ねぇだろ——! この変態野郎ぉぉッ!」猛然と罵声を浴びせた大柄の男は、打ってかわって態度を変えだす。「おぅッ! ……はぁはぁ……すまない、悪かった……」彼れの着ているグレーのタンクトップが、赤く滲みだしている。ちょうど、おヘソのあたりでインク漏れを起こしているかのように……。エヴァンにひと突きやられていたのだ。
「ルイス、聞かせてくれ」無表情のエヴァンが静かに言った。「息子をなぐっている時、どんな気持ちなんだ?」
「……」おずおずとしながら、ルイスがこたえた。「息子たちを傷つける気はなかった……イライラをつい、ぶつけちまっただけだ……オレも追いつめられてたんだ……だから……手を……」
エヴァンは縮み上がっているルイスの肩に手をやると、もういっぽうの手で、グサッと、さらに深く突き刺した。勢いよく抜かれたナイフによって、ルイスはまもなく絶命する。が、そのまえにエヴァンは言った。「よく話してくれた」今度はルイスの首からノドにかけて、すばやく水平内転をくりだした! ペチャっと、黒い血のしぶきを顔に受けながら、エヴァンの心は晴れだした。
それから、ルイスの抜け殻をビニールで覆いつくすと、人目のつかない開拓地にまで車を走らせ、エヴァンは遺体を埋めたのだった。もちろん、そのとき身につけていたもの——たがいのDNAが残るもの——はすべて、火消し壺のなかで燃やされ、灰にしてから処分ずみだ。
そして、まるで何事もなかったかのように自宅へもどり、妻——ローレンのねむるベッドの上で、エヴァンは妻を優しく抱きしめた。慈しみのこもった、あたたかい腕で。
「どこに行ってたの?」目をつむったまま——移民ふうの浅黒い肌をした優美な女性——ローレンがたずねた。
「気分転換にドライブしただけだよ」囁くように言ったエヴァン。
ローレンは黙ったまま、エヴァンの温かい手をにぎって抱きしめたのだった——。
第三章:薄情と裏切
《〜〜🎵〜〜》着信メロディーが鳴りだした。
ロング丈の黒いレイン・コートを着ているエヴァン(三十代)——映画『エボリューション』にも出ていた “ショーン・ウィリアム・スコット” 本人——は、携帯を耳に当てるとどうじに、右手に持っているナイフを男の口にくわえさせた。「——どうした?」
『エヴァン、今、どこにいるの?』キューバ系の浅黒い肌をした美女——妻のローレン(二十代)が不安そうにたずねた。『アンドリュー(息子)だけど、四〇度いじょうの熱があるの。いまから、病院に行ってくるから』
「わかった、落ちついて。すぐに向かうから」目のまえに拘束している男を見下しながら、平素をよそおってうまく応えたエヴァン。咥えさせていたナイフを男の口からはずすと、凪いでいたエヴァンの心が波だちはじめる。
——いますぐ病院に向かわないとローレンに怪しまれてしまう。相談にのっている一五歳の少女——自分の叔父から虐待を受けているとサインを出していた——に性的暴行を繰りかえしていたこの男を埋めて、証拠をきれいに処分する暇なんかはないぞ……どうする?……。
「クソッ……マジかよ……」つねに飲んだくれていそうな——社会の落伍者ともいえる——口髭げを生やした男が言った。タンクトップのお腹あたりを真っ赤に染めながら……。彼れはまさに、前回のルイスどうようの場所で、おなじように椅子に拘束されており、二人の会話はすべて、ボイスレコーダーに記録されていた。
「予定変更だ」すると、必死に命乞いをしていた男の言葉なんて聞こえないと言わんばかりに、エヴァンは二十回ちかくも突き刺した! とても事務的で、迅速に——。
「どこに行ってたの?」┫字のロビーにある右側のソファに座っていたローレンがたずねた。夫のエヴァンが、さっき、着いたのだ。
「眠れないからドライブに行ってた」自分の母親——マリー(五十代)——悲壮感のただようブロンドの “デイル・ディッキー” 本人——が右隣りでもたれているソファに座りながら、エヴァンが答えた。ローレンは壁から少し前のほうに椅子をずらしており、マリーはちょうど、ふたりに挟まれている状態である。
「マリーが気づいてくれたのよ」と、彼女をみやったローレン。
「当然のことをしたまでよ」とマリー。
「きっと、大丈夫」前のめりで座りながら、エヴァンが言った。
「どうして、あなたにわかるのよ?」大事なときに側にいてくれなかったことへの不満をぶつけたローレン。
「……」エヴァンはなにも言いかえさず、だまって深く腰掛けた。
すると、スタスタ……と歩いてくる担当医と看護師がやってきた。
「大丈夫ですよ、ただの風邪です。解熱剤をあたえましたので、検査したら帰れます」手術着のうえに白衣をはおった担当医が言った。そのよこで、あおい看護衣を着た小児科の女性看護師は、しかめ面でカルテをみている。エヴァン家族をあんしんさせると、その看護師をのこして女性の担当医はもどっていった。
すると、カルテを閉じた女性看護師——“ヘレナ・ボナム” を若くしたような面貌で、かなり根性がよじれていそうな感じがいなめない——が言った。「あー、赤ん坊はよく熱をだすものなの。いちいち騒がないでちょうだい」そう冷たく言うと、看護師は相手の反応を気にすることもなく、すぐに振りむいて戻っていった。
彼女は母乳の出がわるかったローレンに、人工ミルクは良くないから自力で与えなさいと、散々いびりつけていた看護師である。アンドリューの扱いかたも荒っぽく、まるで物のように赤ん坊の頭をつかみ、強引なかんじでローレンのおっぱいを飲ませていたこともあったのだ。
エヴァン家族は、その思いやりのない看護師の態度に、目が点となっていた。
その後、アンドリューを連れて帰ったエヴァンは、また、ローレンが寝たころあいを見はからって、トランクに積んでいた遺体を埋めたのだった。あの時、もしもマリーが付きそっていなかったら、トランクからはみ出していた——血のついたビニールを不審におもわれていたことであろう。先に気づいたマリーが、うまくローレンを誘導してくれていたのだから。
《——ヴゥ”ーッ、ヴゥ”ーッ!——》携帯が鳴りだした。夜おそく、子ども部屋でアンドリューを寝かしつけていたエヴァンは、ズボンのうしろポケットから携帯をとりだした。「……もしもし?」
エヴァンは “話しを聞いてほしい” という生徒からの電話で、すぐに家をあとにした。

「ボクのせいなんだ」コンビニの蛍光灯に照らされているパーキング・ブロックに腰掛けながら、生徒のクリス(一七)——数学が得意で、奨学金が受けられることも決まっている優等生の少年——が言った。「母さんと話しているときに横槍をいれたから……。父さんが家にもどってきてて、台所にいたんだ。半裸のじょうたいでね」となりで黙って聞いているエヴァンに一瞥をやったあと、クリスはつづけた。「はじめは普通に会話してたんだけど……ふたりが揉めだして、母さんがやられそうになっていた……。だから、父さんを怒鳴りつけてしまったんだ……」
エヴァンはクリスの右目から頬にかけて、乾いた血の痕をかくにんした。「キミは悪くない。きっと、すべてうまくいく。僕が保証するよ」
そのあと、エヴァンは彼れを家まで送りとどけてから帰宅したのだった。
「ゆうべも外出したの?」ダイニングで朝食のコーヒーを入れてあげながら、ローレンが訊いてきた。
「ああ。クリスに呼ばれたんだ」テーブルの席についているエヴァンが答えた。
息子のアンドリューもバウンサーに乗せられた状態で、ダイニングに同席している。テーブルのうえに置かれているので、目線のたかさもエヴァンとさほど変わりはない。
「学校じゃダメなの?」最近、外出することの多いエヴァンをしんぱいしたローレン。
「彼れは特別なんだ。父親から暴力を受けている」エヴァンはシリアルを一口たべた。
「……アンドリューが熱を出した、あの晩も?」席についたローレンが怪訝にたずねた。
「……」
すると、沈黙をやぶるように姑のマリーがやってくる。「おはよう。今日は良い天気ねぇ」息子のエヴァンの肩に手をやった。
「もう行くよ」そう言うと、朝食を残したまま、エヴァンは仕事にでかけていった。
ローレンは何もいえず、ただ不安そうに見おくっていた。
「自分の時間がほしいだけよ」エヴァンの座っていた席につくと、マリーは彼女を宥めるように言ってあげた。
「ありがとう。うちに居てくれて、ほんとによかった」それは、真意からの言葉であった——。

面談の時間になっても現れなかったクリスを懸念して、エヴァンは学生相談室のデスクから彼れの携帯にでんわした。
『もしもし?』
「やあ、クリス。エヴァンだ。今日の面談に来なかったみたいだけど」
『あ、すみません。すっかり忘れてました。今日は父さんと映画に行ってたんです』
「そうか。昨夜のことが、すごく、気になってたんだ」
『だいじょうぶです、先生。父さんは薬をやめてくれたんです。ちゃんと謝ってくれたし、もう一度、信じてみようと思いました』
「……」
『じゃあ、また。もう切ります』
エヴァンはその夜、また、ボストン・バッグを持って出かけたようだ——。
「なあ、……腎臓結石なんだ。オピオイド系の鎮痛薬を処方してくれないか? あそこで、死んじまうよ」カーキ色のジャンパーにニット帽をかぶったホームレス風——四十代の男が、夜おそい時間帯に救急外来の受付窓にやってきた。すごく逼迫したようすで。
男の要求にこんわくしていた受付スタッフのところに、あの冷然たるふるまいでローレンの心をズタボロにしていた女性看護師がやってきた。「帰ってちょうだい! 警察を呼ぶわよ!」相手を威圧するように、睨みを利かせた。
「おい、ちょっと待ってくれ——」男は怖気た。
「いいから、出てって——!!」さらに凄みのある眼光をとばしながら、出口のほうを指して言った。
すると、ホームレスふうの男はおとなしく帰っていった。
「はあ……、夜はやっかいね」同年代くらいの受付スタッフをみやって言った女性看護師。デスクに着いているスタッフがうなずくと、「わたしは、もう上がるわね」と言って、看護師は照明のついてる受付の場をあとにした。
が、そのロビーの椅子に——本を読んでるふりをしながら——座っていたエヴァンが動きだす。本をマガジン・ラックに戻すと、ひそかに後ろをつけていったのだ。
《——ガチャン——》観音開きタイプのドアがひらかれる。照明度のうすぐらい病棟内の廊下をスタスタ…と、疲れきったようすで歩いていく若そうな女性看護師は、ようやっと、めんどくさい患者たちから解放され、夜勤疲れのカラダをシャワー室で洗いながそうとしていた。ボールペンをうしろで簪のように差した——首から聴診器をぶら下げながら——二十代後半くらいにみえるブロンドのわりと美しい女性は、首を左右にコキッ…コキッ…とかたむけた。
そう——シャワーを浴びているさいちゅうに、グサッ!…と刺された女性がこの人なのだ。
しかし、エヴァンは秩序にこだわろうとする典型的なシリアルキラーである。自分をひどい目にあわせた父親への激しい怒りを、その面影をのこすほかの父親に転移させていたわけだが……看護師は父親でもないし、このパターンにも当てはまらないではないか……。
もしや……
女性看護師は後ろをつけられていることに気づいてはいない。これから起ころうとしている悲劇にも……。
エヴァンも薄暗いロビーを足音もたてずに進んでいく。
一瞬、看護師に気づかれそうになったが、シャワー・ルームに入ったのを確認した。
エヴァンは扉のまえで、タイミングを見計らっている。
看護師はシャワーを浴びだした。
そして、とうとう……
「おい!」エヴァンが声をかけた。
とつぜん入ってきたエヴァンに、慌てふためくホームレスふうの男。「ッ!? あ、あの……じつは……探しものをしてて……」
男は帰らずに、関係者用の給湯室へしのびこんでいたみたいだ。
「シ〜〜」そう言うと、エヴァンは自分の鎮痛剤をわたしてあげた。そして、その薬にがっついたホームレスふうの男が背中をむけると、隠しもっていた鈍器でエヴァンはそいつの頭を打撃した。
そのころ、看護師の首をためらわずに切り裂いたエヴァンの母親——マリーは、布で覆った遺体をキャスター付きの担架にのせると、泰然自若といったおももちで安置所に放置したのだった。
「……!? どこだ、ここは? おい、なんだよ、これは?」空き家となっている いつものテラスハウスで、同じように拘束されているホームレスふうの男——マーク(四十代)が目ざめた。スタンド・ライトの照明を直に向けられているため、とても眩しそうに目を細めている。「なんのつもりだ? オマエは誰れだ?」
「“薬をやめた” と言ったのは、ウソなんだな?」照明の影から、エヴァンが静かに言った。
「なにを言ってる……?」とマーク。「頼む。かえしてくれ。このことは、誰れにも言わないから」
エヴァンはバッグからナイフを取りだした。それを見たマークは一気に顔が強ばり、ウソが通じないと悟りだす。じぶんがここで殺されるということも……。
「……フゥ〜……初めてじゃないな……」抗しがたい恐怖をかんじながら、マークは言った。「何回目だ?」とエヴァンをみやって。
すると、エヴァンはフックに近い右パンチをあびせた。「どうでもいいことだ。クリスを殴ったんだろ?」
マークは暴れたことを薬のせいだと言い訳した。
「いいことを教えよう。依存症の会なんて、無意味なんだ。クリスが求めているのは、父親からの愛だ。なのに、あんたは何度もなんども裏切ってきた。ハイになりたいがためにな」
息子を愛してるんだと宣うマークの腹を、エヴァンはゆっくりと突き刺した。すると、マークの服が赤くにじみだしてくる。
「……あんたも父親なら分かるだろ? 金目的でもどったんじゃない……」声を震わせ、涙目でマークは言った。
「金ってなんだ?」とエヴァン。
「……聞いてないのか?……女房が叔父の遺産をうけとったみたいなんだ。このとおりだ、頼む、やめてくれ」
そのとき、エヴァンは自分の父親を思い出していた。
「……フゥ〜……あんたみたいな奴は、ムショに大勢いる」どうせ殺されるなら威勢のいい姿を奴の目にきざんでやろうと思ったマーク。「日常にひそむ怪物だ。あんたは父親にもなれない。なぜなら人を愛せないからだ。……家族に正体がバレたらどうする気なんだ? え?」
「……よく話してくれた」エヴァンはマークの首を切り裂いた。大量の血飛沫を顔にも受けながら。すると、過去の忌まわしい記憶が脳裡によみがえってきたのだ。とんだ荒くれの父親を——“遺体を埋めているところを見たぞ” と母のマリーを脅しつけ、無理やり自分と母さんを引き離そうとした——まだ小さかった自分が手にしたナイフで、その首を切り裂いたという過去を……。
殺人鬼の血は、マリーから受け継いでいたのだ。
ローレンとアンドリューの眠る自宅にもどったエヴァンは、子ども部屋でアンドリューを抱きながら、自分の首に付いていたマークのを返り血を、おなじく帰宅してきたマリーに拭きとってもらっていた。
彼れらは——
不思議な親子愛でむすばれていた——。
第四章:勘づく者達
息子のアンドリューをベビー・ベッドにもどしたエヴァン(三十代)は、妻——ローレン(二十代)の眠っている寝室のベッドにおちついた。月明かりの差してくる窓のほう向いて、横になっているローレンの体をやさしくエヴァンは抱きしめる。そして、安心したように目を瞑った。
「……今夜もドライブに行ってたの?」起きていたローレン——キューバ系の浅黒い肌に 長い黒髪みをした、なんとも艶かしい優美な女性——が言った。
「……うん……」ほんの少し目を開けると、エヴァンは遠くをみながら答えた。
「あなたのことが心配……」天井をみつめながらローレン。
「ストレスがたまってた。でも、もう大丈夫」
「……あなたを失いたくないの……」
ローレンを自分がわに振りむかせたエヴァンは、言葉ではなく、唇をつかって「大丈夫だよ」と伝えた。
やがて、ふたりのキスは情熱的なものとなっていく。
ローレンの杞憂にちかい不安は、このとき晴れていた。
翌朝、キッチンでコーヒーを入れてるキャミソールすがたのローレンに、エヴァンはうしろから近づき、抱きしめた。彼女の頬にキスをくれて。
幸せそうな笑顔をみせていたのも束の間、リビングのほうから聞こえるテレビの音が気に障り、ローレンは言う。「エヴァン、テレビをみながら子守りをしないでって、言ってくれた?」
「言ったよ」とエヴァン。「もういちど言ってくる」
ふたたび、妻の頬にキスをすると、エヴァンはマリーのいるリビングへと足をはこんだ。また、此間みたいに注意するつもりだったが、エヴァンは今ながれている報道ニュースに目が留まる。
『——続いて、速報をお伝えします。市内の開発予定地区から、男性の遺体が発見されました。犬を散歩ちゅうの女性から通報があり、敷地内から——』
「お母さん」エヴァンが何も言わないから、ローレンが直接注意した。「テレビを消してください」
ソファでアンドリューをあやしていたマリーは、呆然と立ちつくしているエヴァンのほうを見遣っていた。「ごめんなさい。気をつけるわね」と言って、テレビを消した。
となりにいるエヴァンと、ソファに座っているマリーをちらちら一瞥し、ローレンは言った。「いいんです。ありがとう」マリーからアンドリューを受けとり、ふたりに怪訝そうな目を向けたあと、ローレンはベビー・ベッドに歩いていった。
報道によると、敷地内から三人の遺体がみつかっている。息子たちに暴力をふるっていた——刑務所あがりの大柄な父親——ルイス。また、自分の姪である一五歳の少女に性的暴行を繰りかえしていた男——フレデリック。そして、薬物依存で息子のクリスをなんども裏切っていた父親——マーク。
このニュースは、エヴァンが面談を行っている生徒たちにも知れ渡っていた。それを受けて唯一、笑顔をみせていたのはレイプ被害者のケリー(一五)だけである。不適な笑みではあったが、殺人犯に感謝の念をかもしだしていた。
いっぽう、父の死に納得できないでいるクリスはというと……
「……酷い父親でした……でも、変わろうとしてたんです」エヴァンが対面にすわるまえで、クリスは悔恨の情をあらわに言った。「父さんを知りたかったのに、そのチャンスを奪われた……」
「クリス」エヴァンは言った。「お父さんは薬を絶っていたかわからない。今は悲しい思いでいっぱいなだけだ。でも、不幸中の幸いなんじゃないのか?」
自分の父親がダメなやつだとわかっていても、クリスは最後まで憎むことはできなかった。父の愛をもらっていた思い出もあったからだ。そんな父が殺されて、幸せだと思えるわけがないじゃないか。
「どうしてそんことを?」悔し涙を浮かべながら、クリスは言った。
「お父さんみたいな人をたくさん見てきた。僕もキミと同じ目に遭ってたんだ。……お父さんは変われない」自分のやってきたことを否定されたくなかったエヴァンは、クリスに理解をうながした。が……
「ちがう……依存症の会に参加するんだって、言ってました」拒否の姿勢に転じたクリス。
「嘘に決まってる」珍らしく感情的なエヴァン。「お母さんが遺産を手にしたから、それで都合よく現れたんだろ?」
「……」壁の窓のほうに頭を向けていたクリスは、流し目でエヴァンを見遣りだす。怪訝なおももちで彼れは言った。「どうして遺産のことを?」
しまった……と思ったエヴァン。「まえに来たとき、キミが話してくれたろ? 忘れたのか?」沈着と。
「……いいえ……覚えていません……」口がぽかんと開いていたクリスの涙は引いていた。「すみません。失礼します」と立ちあがる。
「クリス」エヴァンも立ちあがった。「まだ、終わってないぞ」
「……ごめんなさい、先生。ちょっと気分が」急によそよそしくなったクリスは学生相談室を後にした。
《コココ コン!》
リビングのソファで一緒にくつろいでいた姑のマリーと嫁のローレン、そして、赤ん坊のアンドリュー。ドアを叩く音に、おくれ毛がコケットな お団子ヘアーにしているローレンが向かった。のぞき穴から相手を確認すると、ドアをガチャっと開けた。
「失礼します」エヴァン家族が住んでいる平屋をたずねてきたのは、口周りからエラ頬にかけてワイルドに髭げを貯えている黒人男性だった。「刑事のオーバー・ストリートです」そう言うと、ローレンに警察手帳のバッジをみせた。歳は三十から四十ほどで、どことなく手強そうな印象がつよくでている。

「エヴァン・コールさんのお宅ですか?」とストリート刑事。
「……はい」腕をくみ、警戒しながら答えたローレン。
「奥様かな?」
「ええ、なんですか?」
「あなたのご主人と話したいんですが……いますか?」
「……いいえ。でも、すぐ戻ります」
「では、待ちます」と、ローレンがまだ許可もだしてないのに、ストリート刑事は家に入っていった。
「コールさん、あなたは開発地で発見された事件のことは、もう、ご存知ですよね?」戻ってきたエヴァンにたずねたストリート刑事。
二人は今、ダイニング・テーブルに着いて向かい合っている。疑いの眼差しを向けているストリート刑事に、いっさい、動揺するようすをみせないエヴァン。「ええ、聞ました。ひどい話しです」
ストリート刑事は、被害者の共通点から身内の子どもたちが同じ高校に通っていることを突き止めていた。そして、おなじソーシャル・ワーカーと話しをしていたことも。
しかし、するどい質問にもエヴァンは淡々と答えてみせた。
すると、エヴァンに自分の名刺をわたしたストリート刑事は、マリーとローレンが不安そうに見守っているリビングへと戻っていく。
「あ、奥さん」ストリート刑事が言った。
「!?」後ろから呼ばれて、ビクッと驚いたローレン。
「ご主人ですが、深夜に外出することはありますか?」
ローレンが答えるまえに、アンドリューをかかえているマリーが口をだす。「まさか。そんなことしないわ、刑事さん。息子はよき父親で、よき夫です」
「……どうです? 奥さん」マリーから視線を離さずに尋ねたストリート刑事。
「……いいえ。まったくありません」自信なさげに答えたローレン。
すると、ソファに座っているローレンのほうまで前屈み、ストリート刑事は言った。「あなたは眠りが深いんですか? 奥さん」
大事な息子のピンチに、マリーはカウンターの鈍器になりえる調度品に視線をむけていた。いざとなったら、それで刑事の頭をなぐる覚悟をきめていたのだ。が、今はそれも難しい……アンドリューを抱えているにくわえ、その調度品はストリート刑事の後ろにあったからだ。
すると、アンドリューがいいタイミングで泣いてくれた。ローレンがあやしに子ども部屋へ連れていくと、漠然たる疑いをのこし、ストリート刑事は帰っていったのだった。
その日からだった。繊細なあのローレンが、自分の夫に不信をいだくようになったのは。刑事が帰った夜、子ども部屋にやってきたエヴァンのキスを「やめて」と、避けていたローレン。それを、客間の寝室にある椅子から、マリーは窺っていた。まんがいち、真実を知っても味方をつらぬいてくれるのか、それとも敵にねがえるような不義をはたらく女性なのか。そんなことを想念しながら。
翌朝、また、あのストリート刑事が訪ねてきた。なにか知ってそうな気がするという、刑事の勘ともいうべきものなのか。彼れはローレンと話したいと言って、エヴァンのことを追窮した。
が、ローレンはストリート刑事の期待をうらぎり、夫をまもる姿勢をくずさなかった。“もう、時間の問題ですよ” と言われても、頑なにエヴァンの肩をもってみせたのだ。
その夜——。
夕食を終えたばかりのエヴァンとローレンが共に食器を洗っていると、また、リビングからテレビの音声が流れだす。手を止めたローレンは、となりのエヴァンに目で訴えた。
「僕が話してくるよ」そう言うと、エヴァンはリビングのほうに歩きだす。「母さん——」
『——小児科に勤務する看護師——キャロライン・ハリントンが、遺体安置所の外で遺棄されているのが発見されました——』
ソファでアンドリューをあやしているマリーと、立ち止まったエヴァンが目を合わせた。
「……消してくれ」エヴァンが言った。
「そうしましょうね」家族を脅かすものは排除すべき。そういう意味でマリーは言った。

寝室でぐっすりと寄り添って寝ているエヴァンとローレン。
突如、《ドドドド ドンッ!》と玄関が叩かれた。
「コール先生! 出てこいよ、コール先生——‼︎」
憤怒の叫び声をあげていたのは、生徒のクリスだった。なんども激しく扉をたたきつけ、エヴァンを呼んでいる。
「! なんなの?」眠りから起きたローレンが言った。
「……クリスの声だ」エヴァンはベッドから起き上がる。「僕が出てくる」付いてこようとしていたローレンを止めた。「大丈夫。まかせて」
エヴァンは玄関の扉を開けた。すると、お酒を飲んでいたのか、クリスがおぼつかない足で勢いよく家のなかに入ってきた。
「クリス、どうした?」エヴァンは落ち着いていた。
「あんたなんだろ?」直結しているリビングのところで、クリスがたずねた。
「なんのことだ?」とエヴァン。
「……父さんを殺した……」
今のクリスの精神は かなり不安定なじょうたいであった。
「クリス、酔ってるな?」エヴァンが訊いた。
「遺産の話しはしてない! 父さんから聞いたんだろ?」クリスはズボンに忍びこませていた銃をエヴァンに向けた。「本当のことを言えよ、先生」
「……そんなことするはずないだろ」両手を開いてみせながら、クリスに少しずつ近づいていく。「キミを息子のように思ってる。いつでも力になってやりたい」
すると、赤ん坊をかかえながら、おずおずとローレンが声をかけてきた。クリスは声のしたローレンのほうを見遣った。
「大丈夫だ」とエヴァン。「部屋にもどってて」まだ近くにいる妻をあおる。「ローレン!」すぐ目のまえのクリスに視線を留めたまま。
ローレンは黙って寝室のほうに下がっていった。
すると、いっしゅん緩めたクリスの隙をついて、エヴァンは手練のごとく、銃を奪いとる。次いで、クリスの背後にまわり、抱きしめた。「落ちつけ。いいんだ、クリス。僕はキミの味方だ」
クリスは両手で涙を拭っていた。
「シ〜〜、シ〜〜、大丈夫。気にするな」
抱きしめられているエヴァンの左手をつかみ、クリスは悲嘆の涙をながしている。奪われた拳銃でエヴァンに後頭部を狙われているとも知らずに……。ローレンは、そのようすを遠くから息を殺してうかがっていた。
「シ〜〜、もうーいいんだ」そう言いながら、エヴァンは巡らせる。ここでクリスを殺すべきかどうかを……。すると、エヴァンは銃を下ろした。それをカウンターの上におくと、クリスを家まで送り届けようとする。
「——触んなよっ!」クリスはエヴァンを突き飛とばし、一人で立ち去っていった。
エヴァンはクリスに疑われていても動じることはなかった。おそらく、宥めすかす自信があるからなのだろう……いや、しかし……これまでに焦燥して動顚するといったことが、あったのだろうか……?
寝室の椅子にもたれながら、不安そうにアンドリューを抱いているローレンのところに、エヴァンがやってきた。
「すまなかったな」ローレンのとなりに腰掛け、エヴァンが言った。「彼れは今、精神的に参ってる状態なんだ」
ローレンは、エヴァンを見遣ることもなく、ただ、黙ってアンドリューを抱きしめている。マリーが廊下から心配そうに覗いていたのだが、気づいていたのはエヴァンだけだった。
ほとぼりが冷めると、ローレンは深く言及することもなくエヴァンと寝室を共にしていた。すると、子ども部屋にいるアンドリューが泣きだした。
「見てくる」ベビー・モニターを手にしたローレンに、エヴァンが言った。「寝てて」
あやしに向かったエヴァンは、アンドリューに哺乳瓶のミルクを与えながら、ロンキング・チェアをユラユラと揺蕩わせている。「パパは人を助けてるんだ、アンドリュー。人生の窮地に追いやられている子どもたちを。……フ……わからないようなぁ、まだ、おまえには。——」
エヴァンの独り言にちかい呟きを、壁に設置してあるベビー・モニターがひろっていた。
それを聞かずにはいられなかった——
上体を起こしていた——
妻のローレンは……。
最終章:親子の忠誠
深いねむりについた夫のエヴァンを確認すると、妻のローレンは物置部屋をしらべにいった。エヴァンはよく、家事を手伝っているときにウォークマンを聴いていたのだ。どうやら、それを思い出したらしい——あれは本当に音楽なのか、と。
キャビネットの引き出しや、小物入れの棚まで、ローレンは隈なくさがした。そして、ついに分厚い本の中から——ページはダミーで中が空洞になっていた——エヴァンのMDウォークマンをみつける。
再生ボタンを押したローレンは、ポロッと涙を流していた。
気づけば、すでに明朝。ローレンはキッチンとダイニングのあいだに置かれたゴミ箱の中から、新聞紙を取りあげた。そこには、開拓地でみつかった被害者三人の名前えが載っているのだ。案の定、殺された男たちと、録音に入っていた男の名前えは一致していた。
——彼れらを殺したのは……エヴァンだ……。
ローレンは愕然と記事をみつめていた——と、そこに!
後ろを振りかえると、アンドリューを抱えているマリーが立っていた。
「お腹が空いてるみたいよ」マリーが言った。「ほら、ママよ」アンドリューをローレンにたくした。
すると、手の空いたマリーはキッチンに向かいながら、ローレンに言う。「今、エヴァンは追いつめられてるわ。そうでしょ?」
アンドリューを抱っこしているローレンは、テーブル席に着いて、マリーに耳をかした。
目線の位置にあるウォール・キャビネットからカップを取りだし、コーヒーを入れながら、マリーは息子のエヴァンのことを話している。「——辛い経験をとおして、子どもは、守られるべきと学んだのよ——家族を——守られるべきってね」スプーンやフォークの入ってる引き出しをあけた。そこには、一丁の包丁が入っている。その腹を、マリーはさすった。「でも、ときには守るための代償もひつようよ」スプーンを取りだしたマリーは、砂糖とクリープをいれて混ぜた。カップを両手に持つと、戦々恐々としているマリーの対面に座った。「あなたも辛かったでしょうね。幼かったころから、家族がいなかったんですもの」
「……わたしも……いろいろありました……」とローレン。
「アンドリューは、そんな思いをしなくて済むわね」
穏やかにゆっくりとマリーは話しているが、その目は得もいわれぬ凄みをやどしていた。
「おたがい、家族のためなら何でもする。……そうよね? ローレン」
「……」
《——ヴゥ”〜——》携帯バイブ音が鳴った。
「やあ、ローレン」学生相談室のデスクからエヴァンが出た。
『エヴァン、お願いがあるの』
「なんだい?」
『アンドリューを頼める? 気分転換に二、三時間、家を離れたいの。服を買いに行ったり、スーパーに行ったり』
「わかったよ。すぐに戻るから」
『ありがとう。寝る時間には帰る』
電話を切ったローレンは、すぐに、また違う番号にかけた。彼女は今、自宅の物置部屋にいる。エヴァンのウォークマンをみつけた場所だ。アンドリューをあやしているマリーを気にしながら、そわそわと。
「コールの妻のローレンよ。——こんにちわ。——昨夜、話しが聞こえたの。あなたを信じる。——ええ。証拠もあるわ——」
荷物を積んだローレンは、カジュアルな格好で車を走らせた。
入れ違いでエヴァンが自宅に帰ってきた。
「ローレンは出かけた?」リビングのシングル・ソファで、アンドリューを抱えてるマリーに、エヴァンが訊いた。
「“買いものへ行く”って」とマリー。
「ああ、一人で外出したいって言ってた」
「彼女を信じるの?」アンドリューと一緒に、エヴァンを見遣ってたずねた。
「……ローレンは裏切らない。この家族がひつようだ」
「……あの少年(クリス)は?」
「……」

エヴァンはクリスの自宅前で車を停めた。
すると、平屋タイプの家からクリスが一人で出てきた。ラフな格好で車に乗ると、どこかへ走っていく。
エヴァンもクリスの後を追いかけた。まだ昼間で車の通りも多いなか、意識を彼れの車に集中させて走らせていく。
着いた場所は、あの開拓地。まだ、舗装もされていない砂利道を歩いたクリスは、誰れかと合流するようだ。エヴァンは、それを車内から怪訝に窺っている。そこは、“KEEP OUT” と書かれた黄色のテープで囲まれている場所——クリスの父親の遺体がみつかったところだ。
そのテープをくぐっていったクリス。
エヴァンも車から降りて、距離を保ちながら観察した。
「コールさん」林のみえるフェンスのまえに立っていたローレンに、声をかけたクリス。彼れは Tシャツに パーカーを羽織った姿で近づいた。「やっぱり、先生が?」
「ええ。夫のしわざよ」ブルゾンを羽織ったローレンが答えた。なぜか、その手に革手袋を装着させて。
クリスは、どうして落ち合う場所が遺棄現場だったのか、怪しむこともなかったようだ。まあ無理もない——まだ、未成年なのだから……。
「でも、悲しいことにね——」ローレンは腰からクリスの拳銃を取りだし、彼れの手に握らせた。「あなたのタメだったのよ」美しい眼差しで彼れをみつめながら、その拳銃をクリスの顎下に突きつけた。「ごめんなさいね」と、それは鳴った!
《——ッバァ——ンッ‼︎——》
はじめはそのようすを唖然と見ていたエヴァンだったが、しだいに口元が微笑みだした。
——カ ン ペ キ な 嫁 だ。
撃った拳銃をクリスの手にもどしたローレンは、偽装した遺書をメールに書きこんだ。
クリスの携帯で。
そして、その携帯をクリスのカーゴ・パンツのポケットにもどしたのだ。
「ローレン」
「!?」すぐ後ろに立っていたエヴァンを見あげた。
『昨夜おそく、SNSに投稿された自殺の告白のなかで——名門大学の奨学金を取得した——クリストファー・ウェルズが、実の父親をふくむ三人の殺害を明かしています——』
朝方、エヴァンとローレンは寄り添いながら、リビングのソファで報道ニュースをみていた。とても——とても初めての殺人とは思えないほど——“ P T S D ”に苛まれることなく——ローレンは凛々しかった。そして、さらに美々しくなっている。
《コココ コン》玄関のとびらが叩かれた。
エヴァンの手をどけて、ローレンが扉をあけた。「ああ、刑事さん」
訪ねてきたのは、オーバー・ストリート刑事だった。
エヴァンに容疑をかけていたストリート刑事は——どこか不服そうでありながら——事実を伝えるべく、キッチンで作業しているマリーをうしろに、ダイニングの席にすわって語りだす。「近頃は変わりました……今の子は、なんでもネットにあげる……。彼れはどうやって、あなたの資料を手に入れたんでしょう?」
ストリート刑事の対面には、エヴァンとローレンが並んですわっている。
「親しくなりすぎたんです」エヴァンが言った。
ローレンは黙って夫の手をにぎり、それをストリート刑事にみせつけるように置いた。
「彼れは、よく現実逃避のために、よくオフィスに来てました」とエヴァン。「僕があまかったんです」
後ろでコーヒーをすすっていた——マリーにも視線をむけたあと、ストリート刑事は言った。「今回は本人が自供して、じぶんの銃で自殺しました。……もう、調べようがない。……お気の毒でした」エヴァンを見遣って言った。
「ありがとうございます」
「……じゃ、私しはこのへんで」ストリート刑事は立ちあがって言った。「見送りは けっこうです。では」
警鐘の音は聞こえていても、手がかりがないんじゃその場所まではわからない。どこで鳴っているのか。だれが鳴らしているのか……。
ストリート刑事は帰っていった。とちゅう、カウンターに置かれていた——まな板のうえにある——意味深な包丁に目もくれずに……。
それは、もしものためである。
いちばん恐ろしいのは、マリーのほうなのかもしれない。そのために、キッチンから動かなかったのだから……。
マリーは二人に言った。「パンケーキは(いかが)?」
ローレンを後ろから抱きしめながら、エヴァンはふたりでベビー・ベッドのアンドリューを眺めている。
子どもからの夢だった理想の家庭——
同じ罪を共有する強固な絆——
家族愛。
自分たちと同じ思いはさせまいという——
子どもに希望を託す——
親子愛。
この家族は持っていた——
奇妙な愛で——。

————————
————————
——おわり。
「人間の中で最良のものは家族の愛である。
それは安定の尺度で、忠誠心の尺度でもある」
詩人 ハニエル・ロング
あなたのサポートが何よりの励みになります!もっともっと満足していただける記事を書いていきたいんでサポートのほど、よろしくお願い致します
