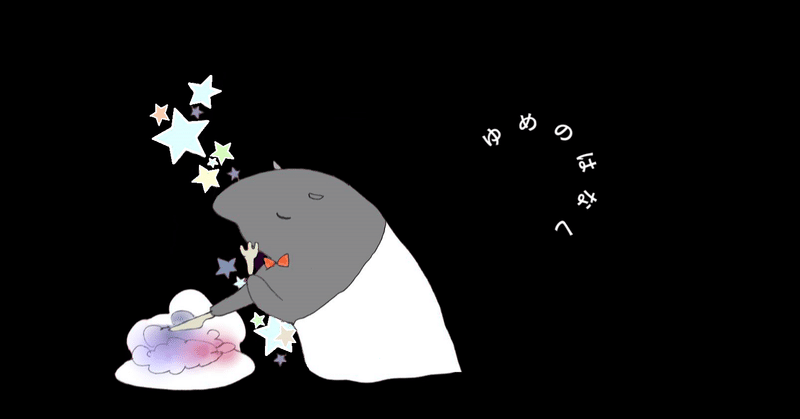
[小説]しらあえ「ゆめのはなし」
きっとすぐに忘れてしまう。
*
わたしは、いい子だから夜の十時にはおふとんに入る。おとうさんとおかあさんはもう一緒に暮らしていないけれど、誰に言われるともなく、かってに体がおふとんに吸い寄せられてくの。
みずいろのシーツと掛け布団は、海みたいでお気に入り。いつだっけ、昔、青いふとんの上で泳ぎの特訓をする親子の本を読んだことがあったなあ。おそらくそれ以来、わたしは寝床を海に見立てるのがすきなのだ。
白いまくらに顔をうずめると、ふとんから声がした。
「やあ、おはよう。といっても、きみはおやすみ、だね」
おふとんの下のほうからだ。わたしは、声を手繰って、えい、と声の主をひっぱり上げた。
ばくくんだ。
「ばくくん、きょうはなんだかいい夢を見れそう。星が白々と冴えていたもの。きっと、静かな美しい夢を見ることね」
ばくくんは、あくびをひとつして、わたしの手から降りて行った。
おふとんのわきの読書灯を消すと、部屋は青い暗闇にしずんだ。
「おやすみ、ばくくん」
夜が来ると、わたしは眠り、ばくくんは起きる。朝が来ると、わたしは起き、ばくくんは眠る。ではふたりが一緒に起きている時間が全くないのかというとそうではなくて、早朝の白い光がさしている時間だけは、一緒に起きて、ゆめのはなしなんかをする。
「おはよう、ばくくん。いい朝だね」
「おはよう。静かな美しい夢は見れたかい」
「……知ってるくせに」
ばくくんは、わたしの夢の内容を知っている。だから、わたしは、ばくくんと二人でおなじ夢を見ていることになるんだけど、わたしが、夢を現実と区別できないほど生々しく感じるのに対し、ばくくんはあくまで、テレビを見ているような感覚らしい。
昨晩の夢は、小学校の屋上で大きな大きなプリンを食べる話だった。
ちょっとした丘ほどの大きさのプリンを、いかなる手段を用いたのか、一人でつくりあげたわたしは、大きなスプーン片手にそれをひとりじめしたのだった。
「しかし、お椀にカラメルソースを入れて、それにすくったプリンをつけて食べるなんて、発想がすごいね。さすがくいしんぼうだ」
「う、うるさいなあ」
ばくくんは、おおきなあくびをすると、布団の中にもぐっていってしまった。
白い光の中にとりのこされたわたしは、まだ、卵とお砂糖の甘い匂いがする気がして、目を閉じて何度か深呼吸し、しばらく、うっとりとした幸福感にひたっていた。
ばくくんは、ユメクイ族のなかでも優秀な獏らしい。むかしは、どの獏も夢を食べる能力を備えていたのだけれども、今となっては、ごく一部の獏だけが夢を食べることができるそうな。
「最近は、いい夢をも食い散らかす悪食が増えてね。ユメクイの品位を下げるからやめろってのに。ぼくは、悪い夢しか食べないよ」
ばくくんは、悪い夢を食べて生きている。だから、わたしがいい夢ばかり見ると、すこしやせる。悪い夢を見続けると、恰幅がよくなる。
「きみは、悪い夢を安定供給してくれるから助かるよ」
ばくくんは、わたしのもとにやってきたときは、やせ細っていた。前の夢主の夢見がよくなりすぎちゃったんだって。わたしは、むかしから夢見が悪いのが悩みだったから、ばくくんが来てくれてたすかった。
ばくくんに悪い夢を食べてもらうと、起きるころには忘れてしまう。後に残るのは、かすかな夢の手触りだけ。
「きょうも、おいしくいただきました」
満足そうなばくくんの顔。わたしは今日、悪い夢を見たらしい。
どんな夢だったのかは覚えていない。でも、胸を突き刺す痛みだけがすこし残っていた。
夢の中で負った傷は、痛みだけ残して消えてしまう。傷跡がどこなのか目を凝らしても、みつからないままだ。
「ばくくんの、『悪い夢』の基準って、何なの」
ある朝、雨がしとしと降る音をききながら、わたしはおふとんの中でばくくんに訊いた。
「いろいろあるけど、きみの心拍数が一定以上はやくなったり、きみがうなされたりしたら悪い夢だと思ってるよ」
「きょうのは、悪い夢じゃないの?」
きょう、わたしは、青い夢をみた。
ただひたすらに、青い絵の具でぬりつぶした様な世界を泳ぐ夢。泳いでいたか歩いていたか定かではないけれど、わたしはその世界をどちらかの方向へ進もうとしていた。明確に覚えているわけじゃない。ただ、起きたとき、胸の奥が凍りついたようにつめたくて、なんとなくそれは青のせいだ、と思ったのだ。
「きみは静かに眠っていたよ」
「でも、青かった。青くてすごく、つめたかったのよ」
「知ってる。青くてひどくつめたく、よく冷えたソーダみたいにおいしそうだった」
ばくくんは、それだけいうと、空腹のおなかを抱えて、眠りに入ってしまった。
胸の奥はまだ青の感触に冷えていた。
「覚えている価値のない悪い夢は、ユメクイが食べる。それ以外は、きみのなかにしまうんだ」
ばくくんは、そういって、ある日はじめてわたしの寝床に現れた。
わたしは、家族と離れ、悪い夢を見ても話すひとがいなかったから、ばくくんの訪問をうれしく思った。
「ぼくが食べた夢は、なかったことになっちゃう。だから、覚えていなくちゃいけない良い夢は、ぼくらユメクイは食べない」
「覚えていなくちゃいけない夢? でも、夢なんて、すぐ忘れちゃうわ」
「忘れているんじゃない。脳で見た夢は、眼と心の奥のほうにしまわれていくんだ。だからすぐには引っ張り出してこれないだけさ」
ばくくんは、つぶらな瞳をぱちぱちさせながら、当然のようにわたしの枕元に座り込んだ。手のひら大くらいのちいさな体、けれども、これまで幾千幾万もの夢を喰らってきたそのしろくろのからだは、やけにたくましくみえた。
「痛くても、つめたくても、涙が出るくらい苦しくても、忘れちゃいけない夢はあるんだ」
「ばくくんは、いつから生きてるの」
冬の朝はまだ星が瞬いている。わたしは、悪い夢を見て冬だというのに寝汗をかいていたので、すこし外気にあたろうとベランダに出て星を見た。肩にばくくんをのせて。
「さあ。人の夢のあるときからかな」
「いつか死ぬの」
「ひとが悪い、くだらない夢を見なくなったとき」
体の中の熱が、白い息になって夜空に溶け出ていく。ばくくんをのせている右肩だけがあたたかく、それ以外の部分が、青白い明け方の空気に晒されて、しだいに感覚がきえて、透けていく。
「とうめいにんげんになっちゃいそう」
ばくくんは、悪い夢をばくばく食べる。わたしが、新しい夢を見ているとき、同時進行的にうしろからついてきているんだって。
「だいたい、きみが見た夢を三秒差くらいで食べてる。かなり早いほうだよ、ユメクイのなかでも」ばくくんは、すぐ自慢する。
「おいしい夢とおいしくない夢って、あるの?」
「そりゃあ、ある。悪い夢であればあるほど、おいしい」
ふくざつだ。わたしが夢の中でうなされればうなされるほど、ばくくんのおなかは満たされるわけだ。そういうと、ばくくんはこう反論する。
「ぼくだってそうさ。自分が満たされるためにはきみの不幸を願わなくちゃいけない。だから夢主には情は移せない」
あくまでビジネス、さ。今風に言えばね。とばくくんはすこし誇らしげに鼻を上に向けて言った。
ユメクイはそういうふうにできているんだそうだ。ひとりの夢主に執着し続けることは、効率がいいとは言えない。だから、悪夢を高い頻度で産生する夢主のもとを渡り歩く、いわば流浪の一族。そうあるために、夢主には情が移らないように進化してきたんだって。 ということは、わたしのもとからも、いずれはばくくんは去ってゆくことだろう。
「でも、きみは稀にみる悪夢体質だね。当分ここにいるよ」
「ほんとう?」
「うん。ぼくがいなくなるのは、きみが人並みにしか悪夢を見なくなったときだね」
とてもしあわせな夢を見た。
細部まできちんと覚えている。ばくくんはこの夢に、まったく手を付けていないみたいだった。
「ねえ、ばくくん。すっごくしあわせな夢をみたの」
「うん、知ってる」空腹のせいか、声が低くか細い。
「すきなひとと、一緒にいるの。なにもいわないんだけど、あったかくて、気を抜くと眠っちゃいそうなくらい安心してて、くるしいくらい幸せなの。ねえ、ずっとここにいたいって思っちゃったよ」
お日さまの光があたたかい。まだ日はそんなに高くまでのぼっていないはずだけれど、よく煮込まれたスープのような、とろみのついたあたたかさが部屋に満ちていた。
「でもね、なぜだか、胸がくるしい」
ばくくんを、ふとんのなかから取り出して、枕元に置く。ふりそそぐ朝日から目を覆うように、ばくくんは短い前足で目をおおった。
「かなしい夢をみたときより、ずっとくるしいよ。どきどきする、恋みたいなやつのくるしさじゃなくてね、どうしてだか、世界が終ったあと、一人でアルバムを見てるみたいな気持ちなの」
カーテンの下に溜まる紫色の影は、軟いえんぴつで描いたみたいに柔らかくまるい。ばくくんをそこにおいてあげると、かれはそっと目を開けた。
「なんでだろう。食べてくれる? この夢」
「いやだね、幸せな夢なんて食べられたものじゃない」
「どうして」
わたしの頬はほんのちょっとひかっている。ほんとうにわけがわからないことに、だけれど。
「ユメクイにはひとの気持ちなんてわからないよ。さあ、もうゆめのはなしは終わり。いっておいで」
ばくくんは、そういうと、ちょこちょこと短い足を精一杯動かして布団の中にもどって行ってしまった。
未だ乾ききっていない水跡を指でなぞると、ふと夢の感触を思い出したので、ああと息を吐いて枕に顔をうずめ眠るふりをした。
*
一日限りの、ゆめのはなし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
