
Photo by
shikibufree17
読書の記録 生き物の死にざま はかない命の物語
稲垣栄洋さんの『生き物の死にざま はかない命の物語』を読みました。『生き物の死にざま』の姉妹編です。
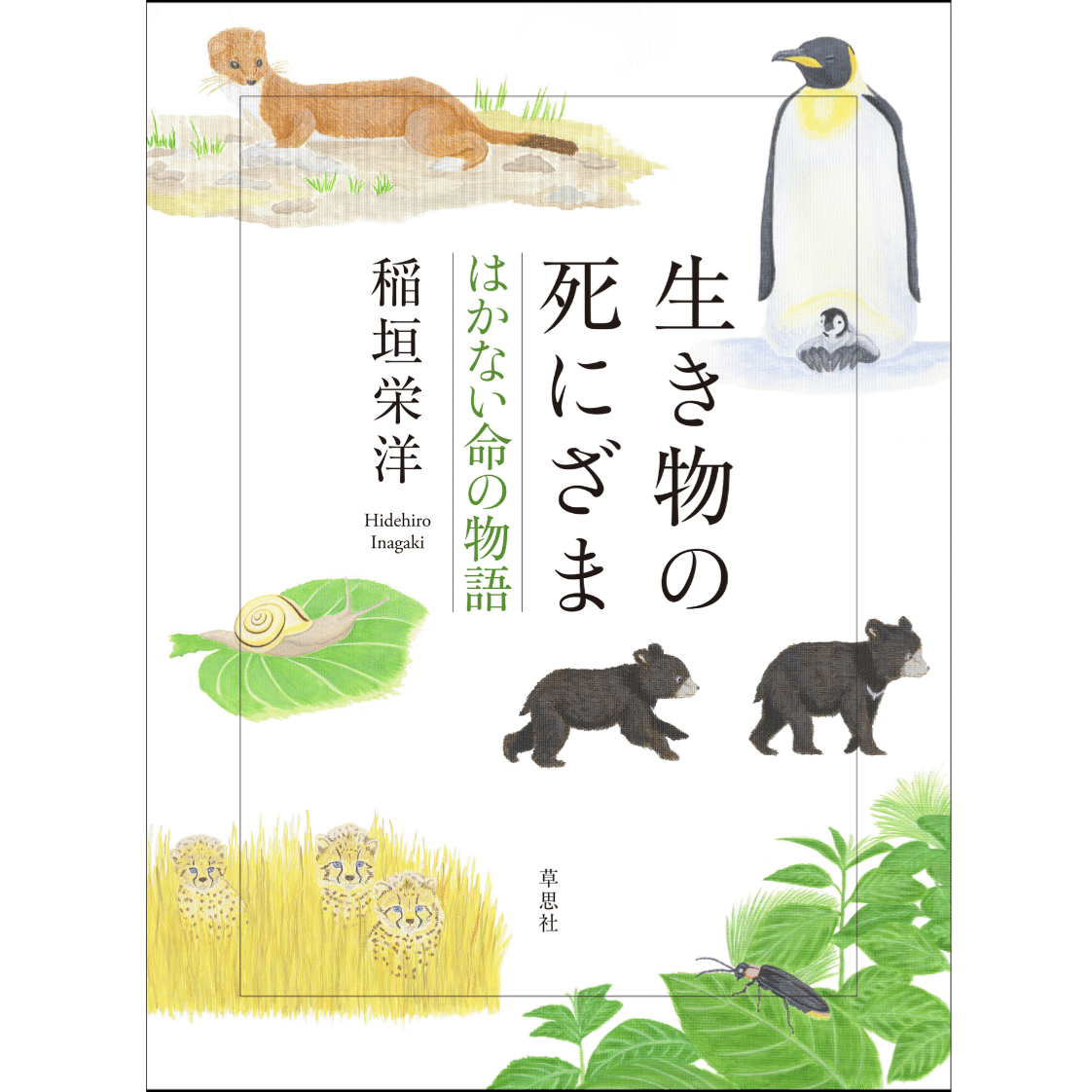
今回も多様な動物から草木まで、幅広く書かれていて、おもしろかったです。
気になったのはもちろん、恐竜好きにはたまらない『オビラプトル』の章。
『オビラプトル』は、プロトケラトプスの卵の化石が多く発見されることで知られるモンゴルのゴビ砂漠で、卵が並べられた巣の中で最初に発見されました。そのため、「卵泥棒」と名づけられました。
しかし、これは誤解で、卵の化石の中は、『オビラプトル』の胎児が入っていたそう。巣の中で発見された『オビラプトル』は、卵を抱いたまま化石になったのです。
化石となる条件は特別で、陸上に棲む生き物が一気に土砂に埋められるなどしないとならない。その条件に当てはまるのが火山の噴火や洪水によるもの。
『オビラプトル』は、卵を抱いたまま化石になったと考えられているそうです。卵泥棒どころか、卵を守り続けたまま化石となった愛情深い恐竜でした。親の愛というものを考えさせられます。
想像力のある人間は、いつくるともわからない死を恐れます。それは人間だけで、他の生き物は、みな「今」を生きているそうです。
想像力の発達で、文明や科学を発展させることができましたが、「今を生きる」ことを忘れてしまった。
でも、未来を想像することで、希望を持ち「今」を大切にすることもできる。
死にざまを知ることで、生きることを考えさせられる素敵な本でした。生きていることに悩みや迷いを持ったら、読むと気持ちが楽になりそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
