
『商業空間は何の夢を見たか 1960-2000年代の都市と建築』
僕のような地方民にとってパルコの時代については語る言葉を持ってはいないが、都市設計の官の発想が面白い。
国、自治体のコミュニティを重視した都市設計では、人々は“広場・市庁舎・公会堂・教会”に集まり、流れ、広まっていく、“都市の核”という中世の考えがあるという。されど人々は公共施設には集まらず、実際に集まったのは商業施設だった―という解説に、なんとも地元の公共施設を思い浮かべてしまってニヤリとする。
しかし若い人を中心に消費欲求という意識自体が見直されてきている現在はどうなのかという疑問が湧いてくるが、そのあたりは、屋台をやりたがる若者が多く「屋台でコーヒーとかを配って、そこで発生する会話にすごく癒されるらしいんです」というところで回答を得られて腑に落ちる。
こうした露店商、小商いへの回帰は、実はバブル前夜、60年代ごろの商空間と似ているという。
また、埼玉県新所沢パルコなどの郊外を設計したアーバンデザイナーが、「郊外の人は一本道しかなくてかわいそうだから、せめて二本の道を選べるように作った」と言ったことを例に、当時の設計者は郊外へのシンパシーもなく、誰も本気で郊外に敬意を払って計画した人はいなかった。など、80年代の都市設計者の思想にもふれていて興味深い。
翻って、僕が住んでいる地方はどうだろうかと考えを巡らせると、核となる場所に人びとが集まり形作られる「都市」または「街」というものは、90年代末で霧消し、新しく生まれたのはイオンモールなどを代表とする郊外の大型の商業施設の集合体だった。
いまや週末ともなるとその巨大な商業施設に家族で車で出掛け一日を過ごす。いわゆるショッピングモールが地方にとっての「疑似都市」となっていて、ハロウィンやクリスマスの飾りで彩られていた本当の街が失われたいま、もはや商業施設内を歩くことでしか「街歩き」を体験することができない。
そんな商業施設への移動には車が不可欠だ。その「街」までは免許のない子供たちは親と一緒に移動を余儀なくされ、その「疑似都市」での「生活」は同世代や友人らとではなくなっている。ドラマでよく見るような、イルミーネーション煌めく街中でばったりと出会う男女には、地方ではもれなく親も付いてくるのだ。
しかしそういった現代の巨大商業施設にはモノも雰囲気もあるものの、過去の「都市」や「街」にあって、この疑似都市には決定的に欠けているものがある。
商いの側の「生活感」だ。
過去、買う側と商いする側は生活感を共有し、夕飯の相談をお店の人としたり、同じ中学校に通っている子供の学校話をした。そこまで密ではないにしろ、お店の人も昼食を食べ、子どもを送り迎えし、夕飯の買い物に出かける。そういった商いする側の生活感は、現在の商業施設では徹底的に排除されている。そしてそれは客である我々も、商いをする側への「生活」の想像力を働かせてはいない。
これは消費行動のエンタテインメント化、レジャー化が原因ではないかと思われる。
ディズニーランドの大ファンが、ユニバーサルスタジオジャパンに行って「ビルが見える」と不満を口にする。いまやディズニーランドの非日常感の徹底が、レジャーランドのスタンダードになっている。そのようなディズニースタンダードを長年かけて商い側も消費側も受け入れ、サービスの成熟が進んだ結果、そういった非日常感、レジャー感を意識的に演出し、遠方から足を運んでもらうショッピングモールの疑似的でファンタジックな都市空間が生まれた。
しかし一方で、生まれたときからそういった疑似都市空間で育った若い人々が、屋台など小商いでお客とコミュニケーションを交わすことに意義を見いだすというのがなんとも面白く、これからの商業施設の役割にも考えを巡らせる。
生活や文化など、様々なことに考えを馳せてしまう都市論や建築論は、なんと魅力的なテーマなのだろう。
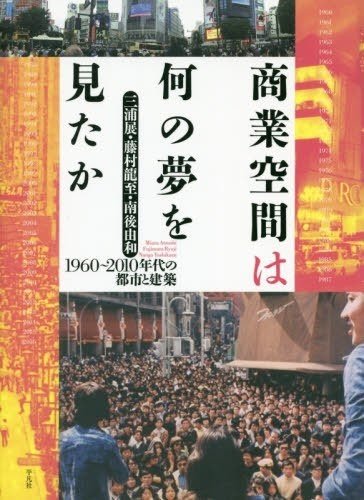
商業空間は何の夢を見たか 1960~2010年代の都市と建築
三浦展/著 藤村龍至/著 南後由和/著
平凡社 2,484円
ISBN:978-4-582-83739-1
2016年9月発行
最後までお読みいただきありがとうございました。 投げ銭でご支援いただけましたらとても幸せになれそうです。
