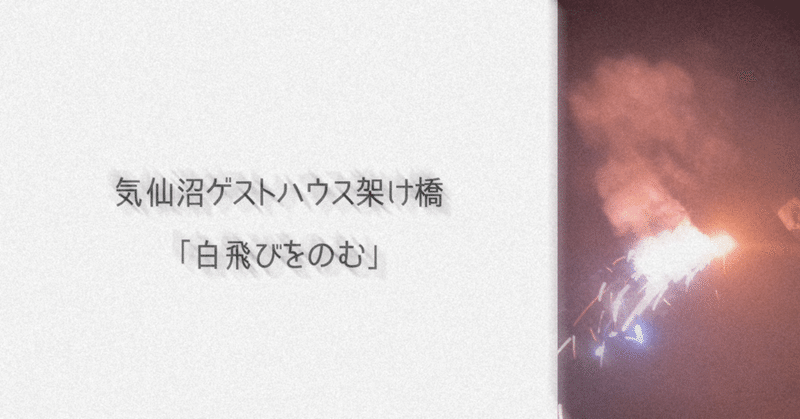
白飛びをのむ
題:夏のはじまり
書:ぬ
------
忘れられない味がある。
と言っても、大切な人の手料理とか、閉店したお店の古い思い出の味とかではない。
何年前の何月かも覚えてないくらいの、ほんの小さな味覚。
いつの出来事だったかを書き記そうとすると、わたしの頭の奥の方に申し訳なさそうに居座っている視覚と味覚の記憶を言語化する作業になる。
白飛びの中にある光景を濃くなぞっていくような作業だから、もしかしたらいつの間にか幻覚をなぞっているかもしれない。ご了承。
・
中学生か、いや、小学生か。いや、やっぱり中学生か。暑い日で、のんびりした時間を過ごしていた。思い出すと胸の内側から鼓動が漏れ出てくるような感覚になるから、もしかすると普通の休みではなく特別な休みの日だったのかもしれない。わくわくする暑い休日ってなんだろう、夏休みかな。
そのくらい曖昧で些細な出来事。
確かあれは昼下がり、太陽と南の窓越しに目が合う頃。
お昼で仕事を終えた母が、帰りに紙パックのジュースを買ってきてくれた。何の味だったか。パッケージを見ただけで、甘酸っぱい香りが口内に再現される果物。それに加えて、だらりと汗が流れる季節の中で一瞬でもオアシスを独り占めできた気分になれる水分感。合計するといわゆる柑橘系。そんな爽やかな味だった気がする。
冷やされた空気と共に部屋に詰まっていたとはいえ、外の怠さと日射しにつられてだらだらとしていた身体は更なる涼しさを求めていた。
母から紙パックを受け取ったわたしは喉に急かされるがままストローで勢いよく穴を開け、それとほぼ同時にジュースをごくんとひとくち飲んだ。
その瞬間口いっぱいに広がったのは、期待通りの軽やかで爽やかな酸味と清涼感のある香り。飲んだだけで身体を縛る熱を解く、魔法がかかったように美味しい飲み物だった。
と、いうことは一切なく。
わたしはジュースを口に含んですぐに、トイレの味だ、と思った。ちょっと背伸びした清潔感を漂わせる、トイレの味。勿論それを実際に味わったことはないが、よくトイレに置いてある柑橘系の芳香剤の香りから想像される味だった。
正直に感想を言ってしまえば、不味い。
頭の中にこのジュースはトイレであるという情報が書き加えられてしまったら最後。そう簡単に払拭できるほどの、それを上回る素敵な感想がわたしの元にやって来ることはなかった。
飲み干したのか、残したのか。それすらも覚えていない。
ただ、仕事終わりの母が家で待つわたしの為にわざわざ買ってきてくれたものが不味かった、という事実に困惑していた。せざるを得なかった。
味の感想を求める母に、飲食物の印象とかけ離れたトとイとレが連続した単語を伝えなければならない。わたしがこの味に似た芳香剤を知ってしまっているが故に、母の善意を折り曲げてしまう。どうしよう。
結果、トイレの味がして不味いと正直に答えた。母はなんだか残念そうな、理解できていなさそうな表情をしていた気がする。
紙パックのジュースと少しの罪悪感。
何年か前の、そんな、夏。
・
今年もまた、夏が来る。
帰省する時は、わたしが帰るのを家で待つ仕事終わりの母の為に、美味しい柑橘のジュースを買って帰ろうと思う。
------
跋文 かわず、せみのように
爪先立ち、忍び足。夏が静かに、でも確実に近づいている今。「夏のはじまり」というテーマで書くと決まったとき、この記憶が真っ先に舌に蘇ってきた。
夏という季節を、言葉を、意識するたびに今まで幾度となく思い出してきた記憶。特別な出来事だったわけではない。たった一度だけ飲んだ名前すら覚えていないジュース。
木漏れ日が白飛びしながら揺れているような、白い霧が視界を覆うような。はっきりしない光景でしか思い出せない。もしかすると、そんな出来事は存在しなかったのかもしれない。
考えれば考えるほど、蒸し暑さを加速させるくらいのべたべたとしたもどかしさが支配してきた。
恐らく下の姉もあの場に居て一緒に同じジュースを飲んでいたはずだから、これを機に確認してみよう。
わたし「何年も前の夏に(中略)ジュース覚えてない?」
姉「えー記憶にない…」「よく覚えてたね、ってかよく思い出したね」
あの衝撃的な出来事を、味を、姉はこれっぽっちも覚えていなかった。
世界中でわたしだけが、何年も前のジュースがずっと舌にこびりついていて、不味かった。
・
ここまで書きながら薄々勘付き、読み返して確信を得たことがある。
思い出の内容が無い。
あの出来事は日常でしかなかった。ジュースが不味かったという、有りがちな、たったそれだけのことだった。意識しないと一瞬で過ぎ去ってしまうような出来事。
でもそれは、夏がはじまろうとしている今を表しているようだ。
気を抜いたら一瞬で時間は過ぎていって、いつの間にか夏に囲まれていそうな今の季節。後で思い返そうとしても断片的にしか記憶を拾えなくて、思い出が日常に溶け込んでしまう。
・
夏のはじまりに、蛙の鳴き声を浴びた。花火をした。流れ星を待った。扇風機を味方につけた。バーベキューをした。蚊の羽音に耳を塞いだ。砂浜を踏んだ。半袖を着た。紫陽花を見た。ラムネを飲んだ。
夏季限定ハッピーセット、パイロット版。
ちゃんと自信を持って思い出せるように、今はそんなものを本気で試してみている。
これがわたしの、夏のはじまり。
