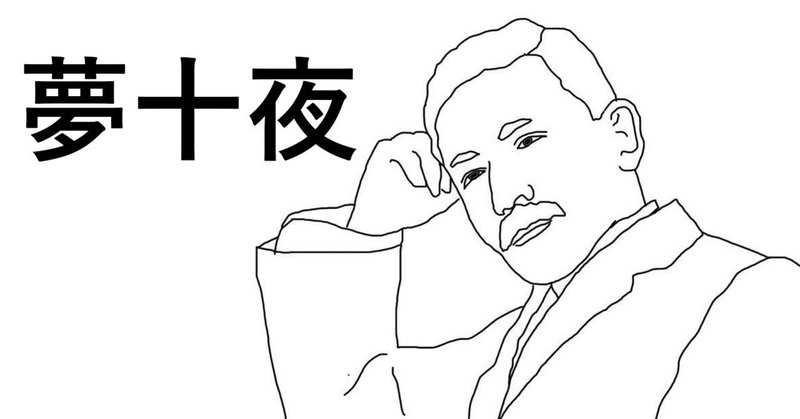
『夢十夜』夏目漱石 「日本で一番美しい夢の話」
このnoteは、まだ本を読んでいない人に対して、その本の内容をカッコよく語る設定で書いています。なのでこの文章のままあなたも、お友達、後輩、恋人に語れます。 ぜひ文学をダシにしてカッコよく生きてください。
『夢十夜』夏目漱石
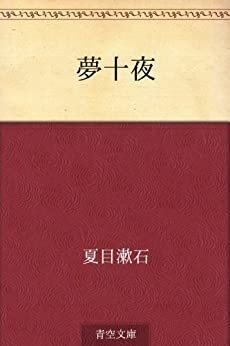
【夏目漱石の作品を語る上でのポイント】
①「漱石」と呼ぶ。
②「余裕派」の作風を解説する。
の2点です。
①に関して、どの分野でも通の人は名称を省略して呼びます。文学でもしかり。「漱石」と呼び捨てで語ることで、文学青年感1割り増しです。
②に関して、物事に余裕を持って一段上からゆったりと眺めるような文学を余裕派と言います。夏目漱石はその代表として語られます。詳しく知らなくても「○○派」という名称だけ言ってれば大丈夫です。
○以下会話
「不思議な感覚になる小説か。そうだな、そしたら夏目漱石の『夢十夜』がオススメかな。読んだことある?たぶん高校の現代文でやったと思うから何となくは覚えてるかな。「こんな夢を見た」という文章から始まって、主人公が見た10個の夢を語る短編小説だよ。一番有名なのは第一夜の話で、美しくて静かな雰囲気がとても良いんだよ。第一夜は、主人公と女の間の淡いお話なんだ。
主人公が座っていると、そのすぐ横で寝ている女が「もう死にます」と言ってくる。顔色を見るにどうも死にそうには見えないんだ。女は、「私が死んだら真珠貝で穴を掘って私を埋めて、星のかけらを上においてください。そして百年まってください。また会いにきますから」って言うんだよ。主人公が「まっているよ」と言うと、そのまま女は目を閉じて涙を流して死んでしまったんだよ。
主人公は女が言った通りに真珠貝で穴を掘って女を埋めて、星のかけらを土の上にそっと置く。そして座って百年待つことにするんだよ。日が東から登り西へ沈み、また東から登り西へ沈む。まってもまっても百年は過ぎていかないことに途方のなさを感じて、自分は女に騙されたのではと思うんだよ。
すると、星のかけらの下から茎が伸びてきて、ふっくらと真っ白なゆりの花が咲くんだよ。ゆりの良い香りを感じて、その花びらに接吻をして、空を見上げると、夜明け前の空に星が一つ輝いていて、「百年はもうきていたんだな」って気づく、というお話なんだ。
関係ないけど、夏目漱石は美人な女性を小説で登場させるとき、「瓜実顔の色白のおちょぼ口の女性」を描くんだよ。『夢十夜』のこの女も瓜実顔で色白なんだ。夏目漱石の好きなタイプなんだろうね。そして僕もこの「瓜実顔の色白のおちょぼ口」が好きなんだよね。
■世界で一番聞いてられる夢の話
人から聞く夢の話ってびっくりするほどつまらないよね。なんであんなにつまらないんだろう。「昨日の夢がヤバかった」とか言ってとうとうと夢の話をされると、早く終わらないかなって気持ちがいっぱいになるよね。ただ例外として、その夢に自分が出てきたって言われると、なんだか嬉しくなるよね。不思議だ。
とにかく自分が出てこない夢の話はつまらないんだけど、この夏目漱石が見た夢の話としての『夢十夜』は、唯一楽しんで聞いてられる夢の話だと思うんだ。自分は登場するはずもないんだけど、この幻想的で美しくて絵画のような世界を、ずっと眺めていたいなって思えてくるんだよね。
■「夢」という設定の妙
『夢十夜』はタイトルの通り、主人公の見た夢の話をしているけど、この「夢」という設定に夏目漱石の手腕が見て取れるんだ。
例えば童話をたくさん書いた宮沢賢治が、『夢十夜』と同じ世界観の話を書くとしたら、「こんな夢を見た」という一文は入れないと思うんだ。わざわざ夢という設定にはせず、「こういう世界観です」って当然のように主張するんだよ。そして読者は「賢治ワールド」に浸ってそれなりに楽しい読書体験をするんだと思う。多分。
小説というのは架空のお話だから、動物が言葉を喋ったり、ひとが空を飛んだりしても良いよね。だから『夢十夜』の世界観を、わざわざ夢だと断る必要はないんだよ。でも夏目漱石はそういったおとぎ話の世界ではなく、夢という設定を使って、現実と地続きにある世界としてこの物語を描いたんだよ。
この設定によって、『夢十夜』を読むとき、読者はそれぞれが体験してる夢の不思議な感覚を思い起こしているんだよ。輪郭がぼやけていて、なんでも素直に受け入れてしまって、体がすっと軽い感じ。そして目覚めたら夢のストーリーの不自然さに笑ってしまう感じ。その不思議体験をこの小説に重ねて読ませることで、『夢十夜』の幻想的な白く濁ったしずかな雰囲気が作られているんだ。
そして『夢十夜』の中で起きた出来事についても、おとぎ話の世界観で『夢十夜』を書いてたら、「あー、なんかよく分からないけど、そういうことが起きる世界なんだね」って自分をむりやり納得させて通り過ぎちゃうと思うんだ。
夢という設定にしたことで、僕らが今いる現実世界の「常識」を物語に当てはめようとして、「本当に百年待ったの?」とか「最後のゆりの花は何?」とか「二人はどういう関係?」とか、いろんな疑問が出てきて、そこがこの小説の持つ力にもなっていると思うんだ。そして教科書にも載るくらいの価値がつけられたんだよね。設定の妙だよね。
■夢の世界の描き方
夢という設定を導入するのは良いとして、単に「こんな夢を見た」って書けば、後に続く文が夢の世界に感じられる訳ではないんだ。「ここは夢の中の話なんだ」って読者に感じさせなければいけない。夢の中だと思わせるために『夢十夜』では色んな世界観の作り方をしているんだけど、その一つが瞳と涙の見たままの描写の仕方なんだよ。
主人公が女の顔を覗き込むシーンで、黒目のことを
大きな潤いのある眼で、長いまつ毛に包まれた中は、ただ一面に真黒であった。
そして女が死んで涙をなすシーンで、涙のことを
黒い瞳のなかに鮮やかに見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて来た。静かな水が動いて写る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。
って表現しているんだ。黒目とか涙という言葉を使わず、女を観察して受け取った印象を素直に表現しているんだ。これは見たものを見たままに素直に受け入れてしまう夢の中の感覚を描いているんだよ。夢の中になると、ありえない設定とか不思議な現象をそのまま何の疑問も持たずに受け入れることってあるでしょ。女の客観的な印象をそのままに書くことで、夢の中の幻想的なしずかな雰囲気を演出しているんだよね。美しい表現だよね。
第一夜はこういう話だけど、これが第十夜まで続いて、それぞれに違った楽しみ方ができるから是非他のも読んでみて。」
お賽銭入れる感覚で気楽にサポートお願いします!

