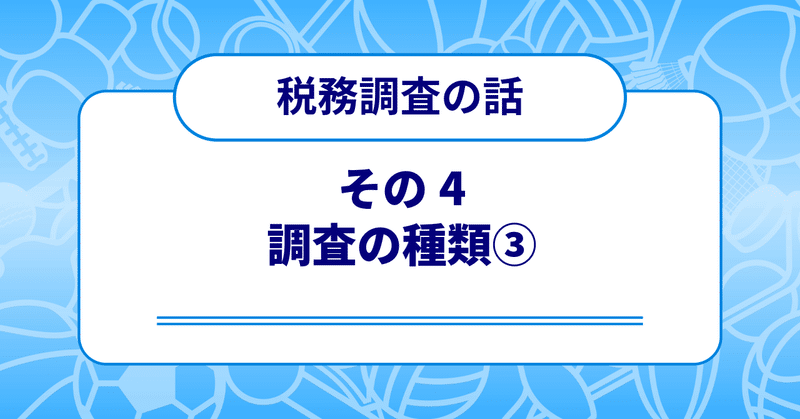
税務調査の話 その4 〜調査の種類③〜
元国税職員による税務調査のあれこれ。第4回も調査の種類の整理の続きです。
前回の記事
今回は取引先の調査です。
反面調査
調査の対象となっている納税者から見た売上先、仕入先、外注先等に臨場し、取引の実在性(除外、架空計上がないか)、取引金額の整合性(一部除外、水増しがないか)について確認する調査を反面調査といいます。
仕入や外注費については、帳簿に記載されているので容易に反面調査先の把握が可能ですが、売上については、除外したものは帳簿に記載されていないので、事前に資料せん(前回記事参照)等により把握している場合に裏付け調査として行われます。
反面調査は、前記のとおり、取引先の事務所等に臨場して行うため、それなりに工数が掛かります。このため、闇雲に行うわけではなく、ある程度的を絞って行います。例えば、仕入・外注費については、提示された請求書・領収証に不審な点がある(取引金額が大きいのに文房具屋で購入した領収証である→偽造の疑いがある)場合や一人親方に多額の支払がある(相手の所得税の確定申告よりも大きい→水増し・架空計上の疑いがある)場合等です。後者の場合、相手側の過少申告又は無申告ということもあるので、反面調査をすれば何かしらの結果が出ます(ただし、一方は法人、もう一方は個人で、なき別れになってしまうと、税目別の縦割り組織なので自分の手柄にならないことも…)
なお、端緒を掴んでいなくても、ある程度金額が大きい相手先には反面調査を行うということもありますので、ケースバイケースです。
ちなみに、意外に思われるかもしれませんが、取引先が反面調査を拒否することは、合理的な理由がない限り認められません。"調査の種類①"の記事にも記載した国税通則法に基づく質問検査権は、取引先にも及んでいるため、反面調査を忌避すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。すなわち、取引先にも調査の受認義務が課せられます。なので、取引関係にヒビが入るので反面調査はやめて欲しいと思っている人も少なくありません。ということで、通常は、誰との取引を調査しているのかは説明しません(調査官に提示する書類から普通に特定できてしまいますが…)
銀行調査
これも反面調査の一種ですが、少し毛色が異なるので、項目を分けてご説明します。
銀行調査では、主に預金取引を中心に調査します。例えば、調査対象の納税者の事務所の近くに所在する銀行/支店に預金口座(社長やその親族名義を含む。)の有無を照会します。通常は、当該銀行の全支店分の照会を行いますので、網羅的に簿外預金の有無が把握されます。
ここで法人名義の簿外預金が見つかれば、売上除外の可能性大ということになります。また、社長やその親族名義の預金元帳を数年間分復元し、売上の入金がないかくまなくチェックします。
銀行調査も反面調査の一種なので、質問検査権とその受認義務については前記と同様です。
なお、預金取引の照会については、これまで銀行窓口に赴いて行ったり、郵送により行ったりしていましたが、オンライン化が検討されているところです。照会事務が効率化することで、これまで以上に脱税が見つかりやすくなるでしょう。
おわりに
以上で"調査の種類"の記事は終了です。次回は調査対象の選定についてです。お楽しみに!
次回の記事
お仕事のご依頼はこちらまで
最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。
