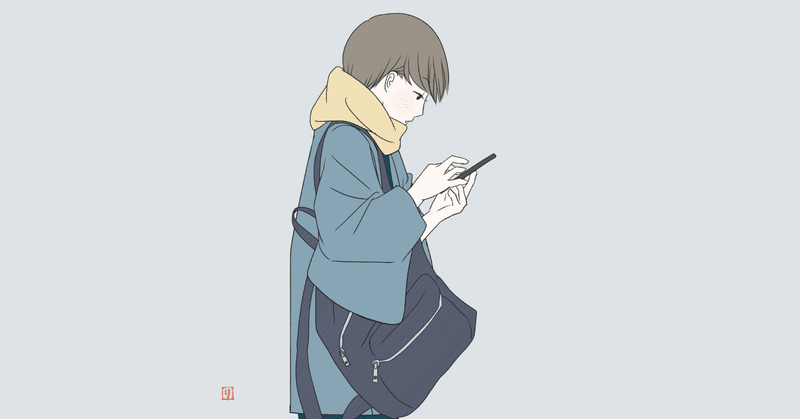
『正月気分』
冬の玄関なんて普通に寒いものだけれど、今朝はとくに冷えた。冷気が鋭く床から突き上げてくるみたいだ。
ここ数日は家でだらだらしていたし、僕のブーツもそれなりに邪魔だったのか、僕から見て奥、つまり玄関の入り口付近に追いやられていた。僕は靴下のまま爪先立ちで降り、母さんに見つからないよう急いで足を突っ込んだ。
「冷たっ」
ブーツの中まで凍っているのかと思った。僕は予想以上の冷たさに身震いしながら、いつもよりちょっときつめに紐を締めた。
グレゴリオ暦で生活している人類は僕の寝ている間に新年を迎え、それから幾日かが過ぎている訳だけれど、もし僕だけがそれを知らずに過ごしていたらどうなるんだろ?
「別に知らなくったって、なんにも変わらないよな」
そう独り言を云いながら特に用事もないまま家を出た。
外はなんだか、まだお正月の空気。
少し歩いて大通りまで出た。
ビルのエントランスやショップのウィンドウ越しには迎春だとか新年の挨拶が書かれた張り紙や立て看板が置いてある。漢字やアルファベット、それに数字。そのどれもが勢いのある書体──と云うよりはフォントだろう、何処のも似ていて少し侘しい気分になる。
肩を竦めるように建つ古びた民家の軒先には正月飾りが見えた。ビルの谷間にあってもそれなりに存在感のある家だから、何か歴史だったりがあるのかもしれない。普段は気にも留めないけれど、今朝はやけに目についた。
「大体、お正月っていつまでなんだろ?」
三日、七日、十一日、いや、二十日までだったかもしれない。
僕は周りをぼんやり流し見しながら少し離れたコンビニに向かった。歩道の脇には昨日降った雪が少し溶けた形のままで固まっていた。踏み締められた部分はまるで潰れた水饅頭みたいにてらてらとしていかにも滑りそうだ。でも、放射冷却でよく冷えた今朝は思ったほど滑らない。ビブラムのソールは、きゅっと氷った地面に吸い付いた。
連れ立って歩く人がちらほらと見えた。まだデパートも開いていないこんな朝から出掛ける用事なんてそうはないと思う。皆、よそ行きに引っ張り出してきたようなコートやダウンを着込んでいる。
通りから人気の無い路地を覗き見ても、やっぱりそこにもお正月の雰囲気が漂っている。
「なんだか不思議な感じ。僕の気持ちだったりがそうさせているのかな?」
僕だけじゃないと思う。人の気分がそういう空気をつくっている。そんな気がした。
コンビニのずっと手前、灰色の鳥居のすぐ下で僕は足を止めた。参道の奥に屋台店らしき奇抜な暖簾が見えたからだ。その近くには艶やかな晴れ着こそ見えないけれど、黒や茶色の上着が見え隠れしている。大人ってどうしてこう地味と云うか無難な服装ばかりをするんだろう、そう思いつつ僕の足は自然とそちらに向いていた。
「確か総社宮だったよな。あの人達はここに向かってたんだ」
いつもは素通りするばかりの小さな神社はさっきの民家と同じように、今朝はその存在感を増していた。
「初詣か──」
晴れやかな気分だったり、願いや感謝の想いは別に期間限定じゃない筈だけれど、正月だからあらためて、と云うことなんだろう。
そんな予定はしていなかったけれど、僕もそのまま境内に入った。そして、人の流れに添って歩き、やがてお賽銭を投げ入れ鈴緒を左右に揺らし、柏手を打った。
「昨年はありがとうございました。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします」
初詣なんて何時ぶりだろう。願いよりは感謝を伝えるものだったと思う。
僕は参拝を終え、社務所前のテントで適当にお守りをひとつ購入した。
「ようこそお参りくださいました。お車でなければ、あちらにお屠蘇もございますので──」
──僕、車に乗ってるように見えるのかな?
見ると本職なのか助務なのか判らないけれど、隣の巫女さんが笑顔と一緒に盃を手にしている。僕はちょっと恥ずかしくて、何故か新年らしい挨拶を云いながらそれを恭しく受け取った。
──あと半年は未成年だけれど、お正月だし。
くいと喉に流した。ほんのりお酒の香りと、何だか体に良さそうな味がした。
「あ、お酒じゃないんですか?」
「はい。少しは入っていますけれどね」
そう返事をしながら巫女さんはまた微笑んだ。
総社宮と云うのは、いわゆる合祀神社なのだと最近になって知った。実際に祀られている神々が幾つなのか何なのかを僕は知らない。皆、総社と呼んでいるから、ずっとそう云う名前の神社だと思っていた。見た目で唯一分かるのは境内の端にあるお稲荷さんくらいだ。後でこの神社のことを少しは調べてみようと初めて思った。
あらためて巫女さんをそれとなく眺めてみる。以前、大学の友達に巫女装束について聞いたことを思い出したからだ。
「コスプレのいわゆる巫女服とは違うんだよ」
彼はそう云っていた。それはお札や護符と扱いを同じくするとのことで、投げたり、跨いだりはもちろん、雑な扱いをしてはいけないのだそうだ。だとすれば、目の前の巫女装束が有り難くない訳がない。僕は柏手を打った時よりも、現実感のある巫女装束を前により厳かな気持ちになっていた。
「ありがとうございました」
盃を返し、もと来た参道を帰る。屋台でたい焼きを買った。あんことカスタードをそれぞれ一つずつ。特に甘いものが食べたかった訳ではないけれど、縁起が良さそうだったから買ってみた。
持ったままだったお守りを仕舞うついでに袋から出して見た。それは安産祈願のものだった。
「ま、まさか、僕じゃないよね。お姉ちゃん、結婚でもするのかな?」
僕は苦笑しながらお守りをバッグに仕舞うと、鯛焼きで暖を取りながら神社を後にした。僕にしては随分とまし──と云うより出来すぎた年の始めだ。
──あれ、僕、何しに来てたんだっけ?
まあ、いいか。今年はなんだかいい年になりそう、そんな気がしてきた。そう思いながら僕はコンビニの前を通り過ぎていた。
──正月気分も悪くない。
僕はあと少しだけこの気分を味わっていたくて、このままもうしばらく歩いてみることにした。
〈了〉
あなたのサポートを心よりお待ちしております。新しい本を買うことができます。よろしくお願いいたします。
