
『ヘンデル回想録』日本語訳(一部)
以下は John Mainwaring, Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel (1760) の冒頭部、全体の1割ほどの翻訳です。とりあえず訳してみた分だけを。
これはヘンデルの最初の伝記であり、また作曲家個人について書かれた伝記としても史上初のものです。しかしながら未だ全体の日本語訳は出版されていないようです。
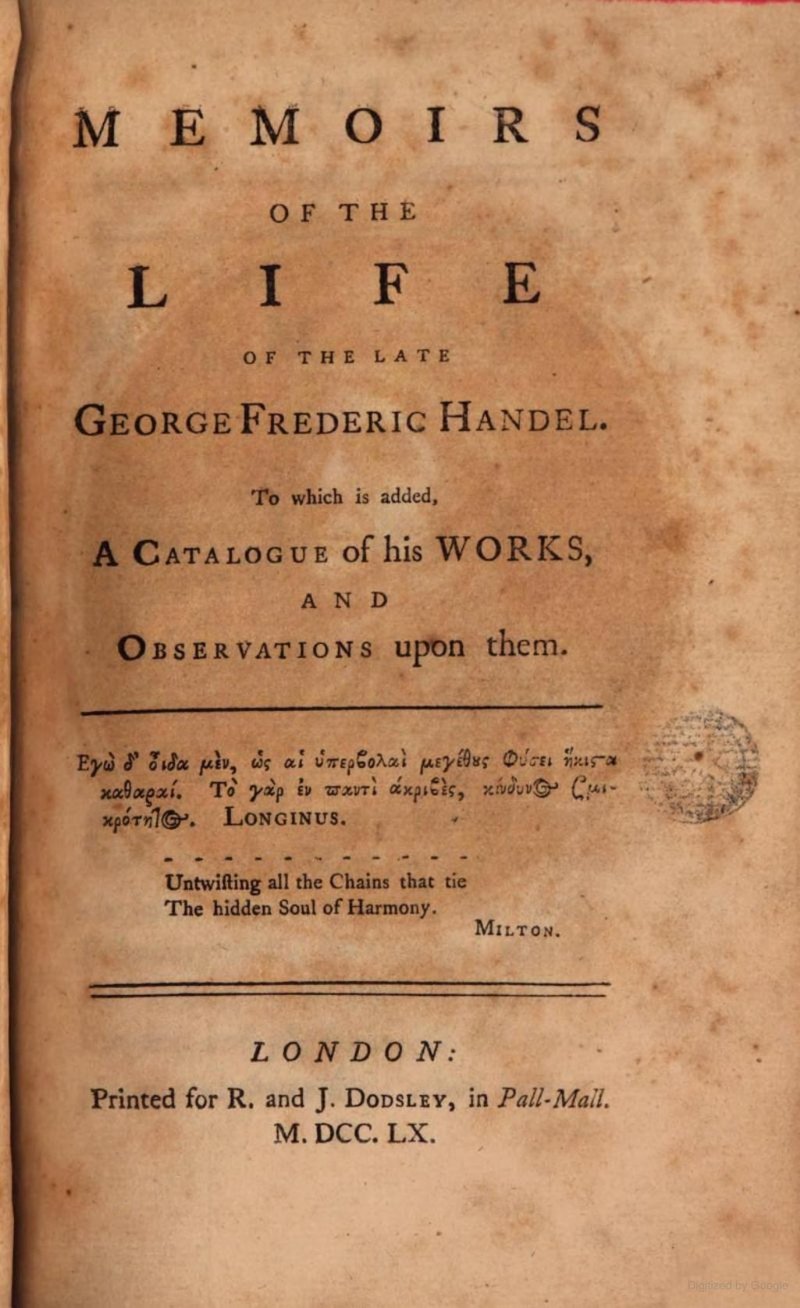
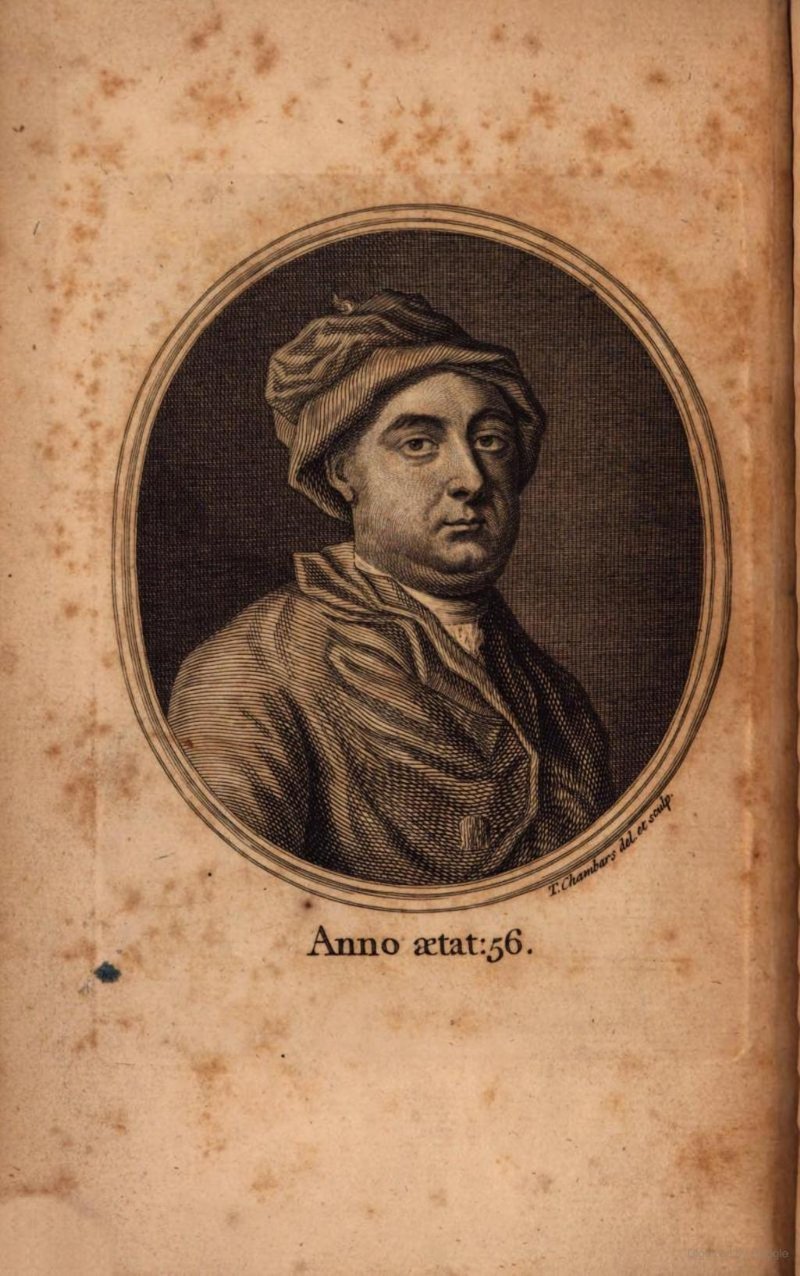
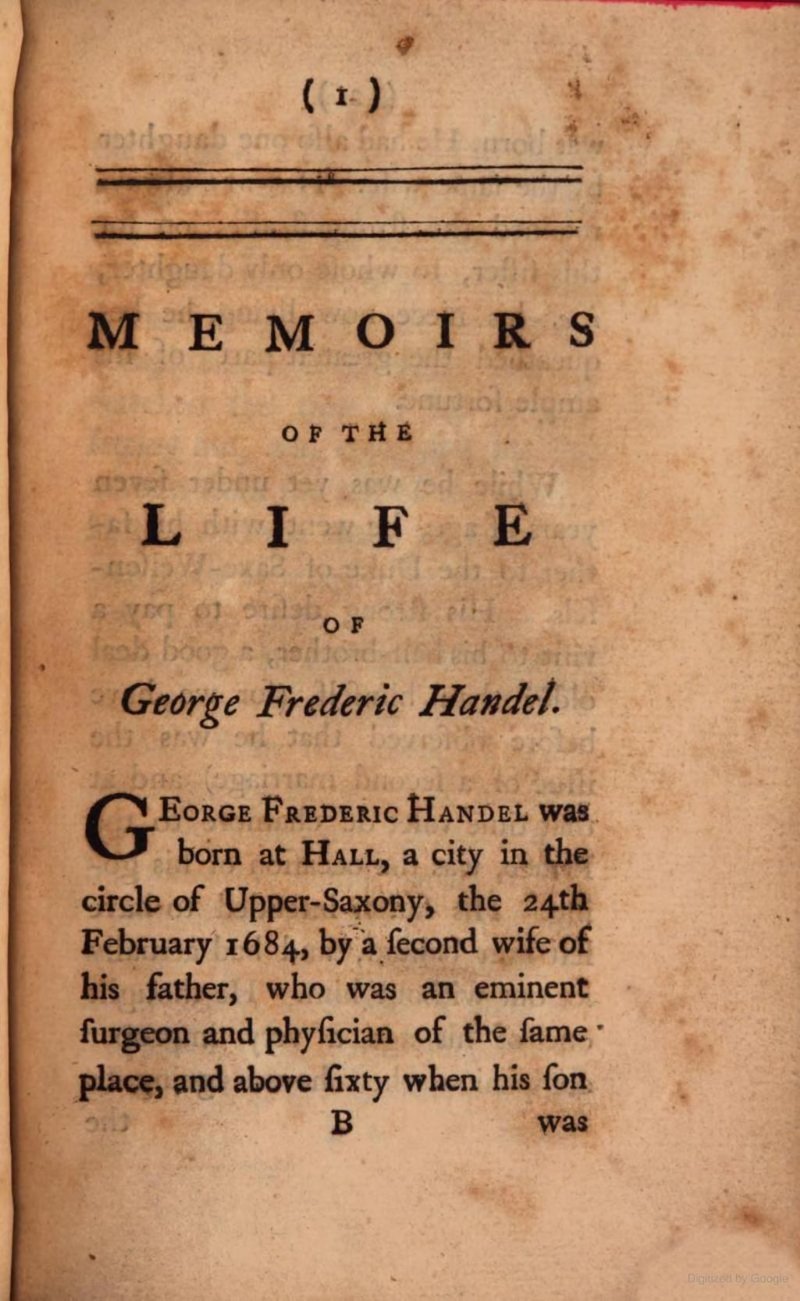
ジョージ・フレデリック・ヘンデルは1684年2月24日に彼の父の二番目の妻の子として上ザクセンの都市ハレに生まれた。彼の父は同市の高名な理容師にして医者であり、かの息子が生まれたときには60歳を超えていた。彼には同じ妻による娘も一人あった。ヘンデルはこの妹に常に最も強い愛情を注いでいた。そのため、彼の姪である未だ存命のその一人娘には、彼の遺産の最大の部分が与えられている。
ヘンデルは7歳にもならないとき、父親についてザクセン=ヴァイセンフェルス公のもとに行ったことがあった。その頃公爵の従僕をしていた腹違いの兄に会いたいがためである(前述のように彼は後妻の子である)。
父親は彼を連れて行こうとは思わず、そのとおり彼を置いていった。彼は幼すぎ、公爵の宮廷で職務を果たすのにはまったく不適当な同伴者であると考えたのである。どう頼んでみても無理と判断したその少年は、願いを叶えるための最後の方法に訴えた。父親の出かける時間を見計らい、家族の目を盗んで徒歩で追いかけたのである。
そしておそらくは道の荒れ具合いのためか、あるいは事故でもあったのだろう、彼は町からさほど離れていない所で父親に追いついてしまった。父親は彼の勇気に驚き、また彼の頑固さを些か不愉快に思いながら、どうすればよいか決心が付きかねた。そして、あんなにはっきりと断ったにも関わらず、どうして付いてきたのかと問い詰めると、彼はその質問には答えず、再び切迫した様で懇願を新たにし、そして抗うにはあまりにも感動的な言葉で嘆願した。
かくして彼は馬車に乗せられて宮廷に連れて行かれ、それまで会ったことのなかった上記の兄に出会い、言いようのない満足感を覚えたのであった。
ヘンデルはごく幼少の時から音楽に強いあこがれを抱いていた。そのため彼に民法を学ばせようと考えていた父親はこれを警戒し、その傾向がさらに強くなることを察知すると、あらゆる手段でこれに対抗した。楽器に手を出す事を厳しく禁じ、その種の物は一切家に置かないようにし、そのような調度品が使われている場所に行くことも許さなかった。しかしこのような警告や作為は彼を抑制するどころか、むしろ情熱を増大させることになった。
彼は密かに小さなクラヴィコードを手に入れ屋根裏部屋に持ち込んだ。家族が寝静まった頃、彼はいつもこの部屋に忍び込んでいた。音楽が禁止される前から彼はある程度に上達しており、その後は就寝時間に熱心に練習することによってさらなる進歩を遂げた。彼の将来の偉大さの兆しに気づく者もないままに。
ここで読者には面白くないこともなかろうと思われることを述べると、このくだりは有名なパスカル氏について彼の姉が書いたものと驚くほど似ている※。両者とも幼少期において成年期を凌ぐ努力を捧げ、一方は比類なき数学への偏向を示し、一方は音楽への偏向を示した。彼らは何の援助も受けず、両親の意向に反して、そしてすべての反対にもかかわらず、それぞれの学習を追求したのである。(※ティコ・ブラーエもまたこの種の例である)
さて、我々の小さな旅行者は、父親とともにザクセン=ヴァイセンフェルス公のもとに到着したところであった。このような状況では彼をハープシコードから遠ざけておくことは容易なことではないし、父親は忙しくて家でしていたように注意深く見張ることもできなかった。
父親はしばしば友人に、息子のこの御しがたい気質について述べ、それを抑えるのに大変な苦労をしているが、ほとんど成功した試しがないと語っていた。そして、もしこの気質をすぐに抑えられなければ、彼の学問の進歩が妨げられ、彼の教育のための計画が完全に狂ってしまうことは必至だと言うのだった。
このような懸念は、前述の計画を遵守することが決まっているのならば、それは誰もが当然と認めるところだろう、しかしそのように固執することが賢明であるかについては多くが疑問視していた。自然がこれほど強い態度で自らを宣言しているようなところでは、抵抗はしばしば実を結ばないばかりか有害であると考えられたからである。
その説明を聞いて、彼の症状は絶望的で指を切り落とす以外に演奏を止めさせる術は無いと言う人があり、それを何としても妨げるというのは可愛そうだと主張する人もいた。このような医師の友人たちによるその息子についての感傷や陳情は、次の事件がなかったら大きな影響をおよぼすことはなかっただろう。それが彼らの忠告に重みと権威を与えることになったのである。
それはある朝のことであった、礼拝が終わった後にヘンデルはオルガンを弾いていた。その弾きぶりには教会に居合わせた公爵の関心を強く惹くものがあった。公爵は帰ってすぐに、オルガンを弾いていた者は誰なのかと従僕に尋ねた。従僕は、それは私の弟ですと答えた。公爵は彼に会ってみることにした。
公爵はヘンデルに会い、趣味と眼識を備えた人ならばこのような場合にするであろう質問を残らずした後に医師に述べた。子をどう育てるかは父親の決めることではあるが、私としてはこのような新進の天才をこの世から剥奪することは、公共と後世に対するある種の犯罪行為であると考えざるを得ない、と。
老医は息子に民法を学ばせたいという望みを未だ持っていたが、もはや息子の性向に譲歩することはやむを得ないと覚悟していた(公爵の助言と権威に従うことは義務であると思われた)。とはいえそれは実に不本意なことではあった。
彼は公爵が息子を気遣い、最善の教育法に付いて意見を述べてくれたことには感じ入っていた。それでも彼はこう言った、恐れながら閣下、音楽は優雅な芸術で素晴らしい娯楽ではありますが、職業としては尊厳に乏しいものでございます、息子がそのような職業でいかに出世したとしても、他の多くのものでそれより劣るほうが好ましいでしょう。
公爵は、人間に偉大な栄誉を与えるもののなかでも大いに卓越したものである音楽家という職業を、かくも見下し蔑む意見には同意できなかった。収入に関しても、彼が自然と摂理の定めた道に進むことが許されたなら、情熱をもたないどころか嫌悪している進路を強いられる場合より、よほど大きな成功が望まれるものと思われた。
彼は結論付けてこう言った、私は何も両立可能な言語や法律を学ぶことを排除してまで音楽を勧めているわけではない、私が望むのは、全てを公正に無理強いすることなく、少年が何であれその天賦の才に従う自由が与えられることである
これらのすべての間、ヘンデルは彼の心強い弁護人をしっかりと見据え、彼の耳は公爵の父親に対する演説の効果を注意深く観察していた。
議論の結果、音楽が容認されただけでなく、ハレに戻ったときには彼の進歩を促進し支援する教師を雇うことが同意された。ヴァイセンフェルスを立つ際、公爵はヘンデルのポケットにお金を忍ばせ、微笑みながらこう言った、お前が自分の勉強に関心があるのなら励ます必要もないだろう。
ヴァイセンフェルスの宮廷で受けた多大な厚意や、前述の議論の成果もさることながら、とりわけ公爵から受けた友好的で寛大な赦免はしばしば彼の心を捕らえた。これらの幸運な出来事は彼の生来の向上心を煽り、この早い段階でも彼の中に容易に見いだせた野心に火をつけることになった。
ハレに戻って父親が最初にしたことは、ヘンデルを大聖堂のオルガニストであるツァハウのもとにつけることであった。この人物は自らの専門に大いなる能力を有しており、期待に満ちた生徒を正しく導くにあたって適役以上であった。ヘンデルは彼を大いに慕っており、自分はけして彼には敵わないと思っていた。
ツァハウの指導の第一の目標は、和声の基礎を叩き込むことであった。その次にはイマジネーションを開拓し、良い趣味を身につけさせた。彼はドイツやイタリア音楽の膨大なコレクションを所有しており、ヘンデルに国による様式の違いや、個々の作曲家の長所と短所を示してみせた。そして実技においても上達するよう、頻繁に課題を与えたり、写譜して演奏させたり、自分に代わって曲を作らせたりした。そうしてヘンデルは同年代の通常の生徒ではありえないほどの研鑽を重ね、経験を積んだ。
ヘンデルはハレ周辺や遠方から訪れた人々の注目を集めるようになり、ツァハウはその弟子を誇りに思った。そして彼は類まれな才能を持つ助手ができたことを喜んだ。彼は仲間とグラスを傾けることを愛し、しばしば留守にすることがあったが、そのような時に彼の代わりを務めさせることができたのだ。
これは7歳の助手の話としては奇妙に思えるかもしれないが、実際それがヘンデルがツァハウに師事し始めた頃のことであれば、そのぐらいの年齢であったはずだ。しかしこのことはさらに奇妙であるだろう、すなわち彼は9歳にして教会の礼拝のための声楽と器楽の作曲を始め、そしてその時から3年の間、毎週かかさず礼拝の音楽を作曲し続けたのである。
しかしながら、彼が父親に注意され、あらゆる楽器に触れることを禁じられる以前に、すでに独学で進歩していたことを忘れてはいけない。そして厳しい禁令の出た後にも、目を盗んで行われたクラヴィコードの練習によってさらなる上達があった。その後ヴァイセンフェルスの宮廷でのささやかな滞在を最大限に活用し、彼はそこで多くの楽器と称賛とを見出したのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
