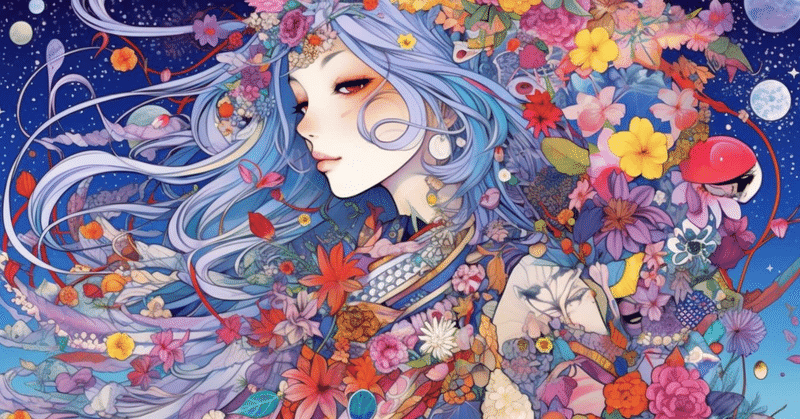
【シロクマ文芸部】文芸部員に僕はなれない
我が校に文芸部が存在すると知ったのは、高2の学園祭の時である。そんな部が存在するとは露ほども知らなかった。
彼女に連れて行かれた先の教室に冊子が並べてあった。年に1回、作品を部費で製本しているようだが、今まで見たこともない。おそらく、各クラスに配布するほどの数は作っておらず、自分たちの分と余分の数冊程度だろう。同じ号がいくつかある。手にとってパラパラ眺める。
「読んでみてよ。」と勧められたので椅子に座って読む。彼女は文芸部の売り子とは知り合いらしく楽しげにおしゃべりを始めた。
担任の国語教師の作品もある。日常を陰鬱なタッチで描いた作品は、日頃の温和な姿からは意外だったので今でも覚えている。生徒の中で、なんとか作品とよべるものを書いていたのは一人きりだった。何となく書いたのは女子だろうと思った。次の号からは彼女の作品だけを読んだ。
完成度は低いが、繊細で読みやすく書き慣れている感じがした。挿絵も描いていたが文章より絵の方が抜群に上手いと思った。
「この人、上手いね。」と名前を指さすと売り子はぱっと顔を輝かせた。なんでも一つ上の先輩で、彼女がいかに優秀で才能があるかを我が事のように滔々と語った。
「気に入ったら買ってくれないかな。その先輩の書いたのももっとあるし。」
そう頼まれて断りきれず1冊買った。もっとあるから、とは言われたもののそれ以上は断った。
冊子は引越しの際に処分してしまった。先輩と呼ばれた彼女の絵も作品も今となってはまったく覚えていない。ただそのペンネームだけは今でも覚えている。
夢魔。
夢魔先輩、夢魔先輩と売り子の部員が何度も口にしていたから覚えていた。それがペンネームであり、本名ではないことがとても奇異に思えたので記憶に残った。
「普段からペンネームで呼んでるの?」と聞くと売り子は至極普通にそうよ、と言った。
「作家は皆ペンネームを使ってその名で呼ばれているのよ。当たり前じゃない?文芸部員は未来の作家なんだから。」
ああ、そうなんだと僕は少々鼻白みながら返事をした。ちょっと夢見てるみたいで気持ち悪いな、と思った。その世界に入ったいくには僕はあまりに夢を持たず現実的だった。夢見る能力のない人間はきっと夢を構築できないのだろう。
文芸部との関わりはここでぷつりと切れる。しかし、何の因果かはわからないけれども、この先僕は何度か文芸のサークルに足を踏み入れそこで物語を書き、失望しては脱退するという行為を繰り返すことになる。
自分をも騙すようなリアリティのある嘘を書かなければ他人をその世界に引き摺り込むことはできない。自分の顔面に相手が迫ってくるような内容でなければ相手の世界に入れない。
夢見る能力のない僕は出来損ないの魔法使いのように夢の世界を作り出そうと試みては失敗を繰り返し、相手の世界に同化しようとしては弾き返される。そんな不全感を抱きながらも夢見ることをやめられない。まさに「夢」であり「魔」だ。
僕は文芸部員になれない。
(終わり)
*次の企画に参加させていただきました。すっかり忘れていた記憶を掘り起こして書いたフィクションです。うまくまとめられなかったので他の人の作品に期待しちゃいます。他力本願。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
