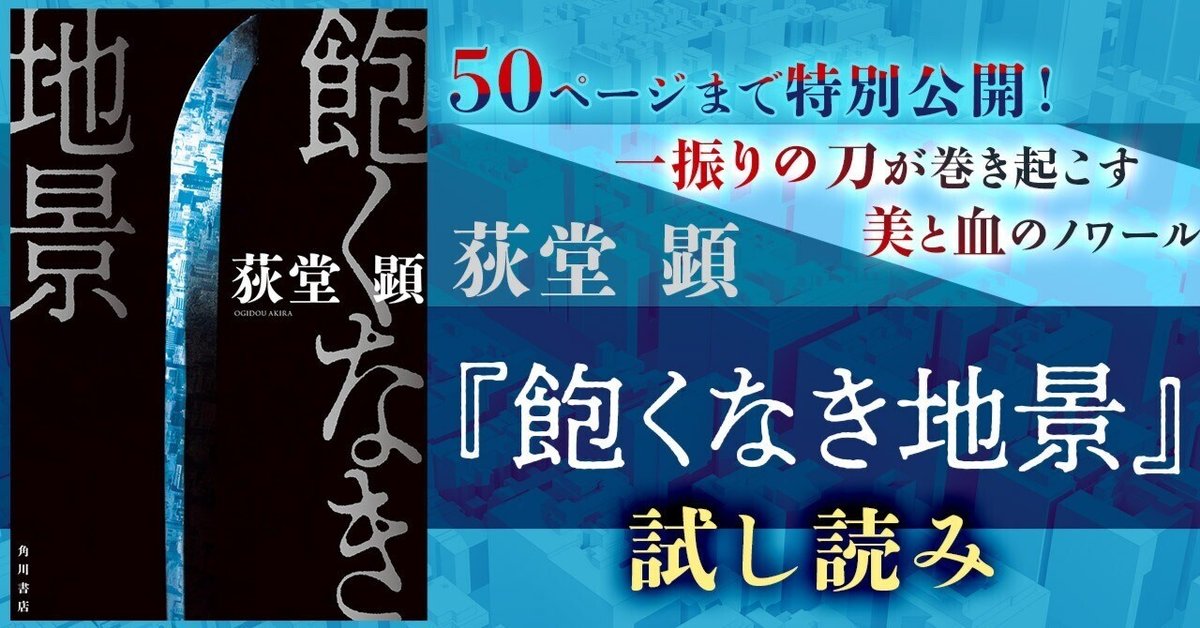
【試し読み】荻堂 顕『飽くなき地景』冒頭特別公開!
歴史ハードボイルド超大作『不夜島(ナイトランド)』(祥伝社)で「第77回 日本推理作家協会賞 長編および連作短編集部門」を受賞した作家・荻堂 顕さん。
受賞後第一作となる長編小説『飽くなき地景』(KADOKAWA)の刊行を記念して、50ページまでの大ボリューム試し読みを特別公開します!
物語の冒頭をどうぞお楽しみください。
あらすじ
土地開発と不動産事業で成り上がった昭和の旧華族、烏丸家。その嫡男として生まれた治道は、多数のビルを建て、東京の景観を変えていく家業に興味が持てず、祖父の誠一郎が所有する宝刀、一族の守り神でもある粟田口久国の「無銘」の美しさに幼いころから魅せられていた。家に伝わる宝を守り、文化に関わる仕事をしたいと志す治道だったが、祖父の死後、事業を推し進める父・道隆により、「無銘」が渋谷を根城にする愚連隊の手に渡ってしまう。治道は刀を取り戻すため、ある無謀な計画を実行に移すのだが……。やがて、オリンピック、高度経済成長と時代が進み、東京の景色が変貌するなか、その裏側で「無銘」にまつわる事件が巻き起こる。刀に隠された一族の秘密と愛憎を描く美と血のノワール。
『飽くなき地景』試し読み
「ある夏の午後、ゆったりと憩いながら、地平に横たわる山脈なり、憩う者に影を投げかけてくる木の枝なりを、目で追うこと」
「かつて斜面を飾る栗林や雑木林の光と陰との対照で感じていた美よりも、道が歩く人の努力の節約の跡を示して、斜面の裾の自然の形をなぞっているのが、美しく思われた」
プロローグ 一九四四年
1
祖父は僕に、覚えきれないほど多くの教訓を授けてくれたが、その授け方はいつも風変わりだった。この国でも有数の、美術品の優れた蒐集家だったから、その感性が年齢に比して若々しく、同時に、エキセントリックだったのも一因だろう。しかし、それ以上に、彼の自尊心が受け続けた苦しみが、彼をおのずから風変わりへと仕向けていたのだと僕は後年に気付いた。
それ自体もひとつの教訓に違いなかったが、祖父が僕に授けた最も大きな教訓は、背筋のよい人であれ、というものだった。優れた剣士が剣術の鍛錬のさなか、彼が握る竹刀を通じておのれの精神性を磨き上げていくように、祖父が言ったところの背筋のよさとは、すなわち、世間と向かい合う際の心の置き方で、我欲、卑しさや浅ましさとは無縁の佇まいを指していたと思われる。もっとも、まだ八つの僕には理解できないと判断したのか、あるいは、そうした態度は言霊で伝えられる類のものではないと考えたのか、祖父は物理的な手段で僕の姿勢を矯正しようと試みた。用いられたのは八畳の茶室だった。
使用人よりも早く起きるため、彼らはさらに早く起きねばならず、結果的に多くの者が睡眠不足に悩まされているということをこの屋敷のなかでただひとりだけ知らない祖父は、土曜の早朝に僕を離れの茶室へと連れ出し、客畳へ正座するよう命じた。命じると言っても、祖父は誰に対しても、それが使用人であろうと僕であろうと敬語で話し掛けるのだが、その声に含まれているのは、この世に生を受けてから今日まで、一切の不自由というものを知らずに生きてきた者だけが持つ無垢な余裕であり、老齢まで保たれた無垢さは傲慢とは無縁だった。
母が当時の日本人女性にしては珍しく五尺七寸もあったおかげか、僕の背は八つの時点で小柄な祖父を追い抜いていたが、生まれつきの胃弱が原因で体躯は貧相このうえなかった。日増しに高くなっていく背丈を支えられるだけの筋力を持ち合わせておらず、物心付いた時には、体を折り曲げるように歩くのが癖になっていた。揶揄われるのには慣れていて、僕としては別段困ってはいなかったが、学校の先生が家に来た時、「せっかくお父上のような大人物の種が蒔かれても、土や水が悪ければ、あっという間に枯れてしまう」と言って母を叱責したことがあった。その日の夜、僕は母に「ろくに妻子にも会わず、たまに帰って来ても、若い女中と何かよからぬことをしている男など、初めから腐った種だ」とはっきり伝えた。代用教員風情の叱責など気にする必要はないということを伝えたかっただけなのだが、母は吸い止しの煙草を灰皿に置き、ずんずんと歩み寄ってくるや否や、僕の頬を思い切り張った。五尺七寸に見合う力強い一撃だった。
茫然自失となって母の部屋を飛び出した僕は、玄関に蹲って涙を流した。痛みのせいだったのか、好意をはたき落とされたからだったのかは、自分のことながら今でも判然としない。その後、食事の準備ができたことを告げにきた母は、張り手をしたのと同じ手で僕の頭を撫でてから、盗み聞きしていたことだけを叱った。それきり、その話題が母と僕の間で持ち上がることはなかった。もしかしたら、ずっと気に病んでいた母が、とうとう祖父に相談したのかも知れなかった。母にとっては義理の父親であったが、滅多に父が帰ってこない我が家においては、父親の役目を果たすことができるのは祖父だけだった。
とは言え、ただ正座するよう命じられただけで、祖父は何の助言も与えてはくれなかった。茶室には時計がなかったが、物事の終わりを予想することだけは正確な幼年期の体内時計は、すでに一時間が過ぎているはずだと教えてくれていた。足の痺れはもとより、肩と腰が疲れを訴え、前に引っ張られるように姿勢が崩れ始めた。背後には祖父が佇んでいて、僕は頬を張った時の母の顔を思い出しながら、張り替えられたばかりの畳ではなく、ぼろぼろと剥がれ落ちて来そうな土壁を睨もうとしていた。祖父の息遣いを除けば、音らしい音は何ひとつ聞こえず、背筋を伸ばすことに集中すればするほど、体幹ではない他の感覚、特に嗅覚が過敏になる。最も強く感じたのは、土壁に染み付いているのであろう葉巻の匂い。外国人の来客があった時、父はいつもこの茶室を使っていた。靴を脱ぐ習慣がない外国人を気遣い、彼らを土足のまま畳に上がらせ、にわか仕込みの茶道を披露しながら葉巻片手に密談するのだという。そして、祖父は実の息子である父を咎めず、懇意にしている浅草橋の畳屋を呼んでは、汚れた畳を張り替えさせる。
「一体どう座れば、背筋がよくなるのですか?」
まさしく痺れを切らして、僕は訊ねた。背丈ばかりが育っていたが、その頃の僕は八つという年齢相応に幼く、背筋さえよくなれば、生じている様々な問題が一挙に片付くかも知れないと期待していたのだ。父は毎晩家に帰るようになり、押し殺したような母の泣き声が夜中に聞こえてくることもなくなるのだと。
「貴方の前に座って、正しい座り方を教えることは容易いのです。頭のいい貴方ですから、その真似をすれば当然、背筋の伸びた正座ができるでしょう。しかし、貴方が真に取り組むべきなのは、うわべを飾るような見様見真似ではありません」
振り返るのは失礼に当たると思い、土壁に目を遣ったまま、僕は「すみません」と声に出した。それ以上のことを口にしなかったが、おそらく祖父は、僕が習得すべきなのは方法や技術ではなく、精神の在り様だと言いたかったのだろう。背筋よくあろうとする心持ちがなければ、どれだけ座法を磨いたところで、日常の生活には決して反映されない。学ぶのよりも先に分かれ、という祖父の態度からは、技法だけでは説明することのできない精神的な美徳を鑑賞することに長けた審美眼の持ち主ゆえの、人間の佇まいに関する独特の美学のようなものが垣間見えた。
摺り足の音が聞こえ、祖父が茶室を出ていくのが分かった。すぐにでも正座を崩したかったが、誰かの目がないのを好機と捉えて休もうとする態度こそが、僕の貧相な体躯に象徴される惰弱さなのだろうと考え、痺れと痛みに耐えながら座り続けた。ただし、首を支えるのはもはや困難で、目に入るのはざらざらとした土壁ではなく、どこまでも均一な畳目だった。これが手縫いによるものだとは、到底信じられない。普段生活している別館の客室には、父がどこぞからもらってきたらしい上等なペルシャ絨毯が敷かれているが、同じ手縫いでも、ただ見栄えがいいだけで、均整の取れた美しさは畳の足元にも及ばなかった。眼下の畳目は僕に、去年の十月に母に連れられて見に行った明治神宮外苑競技場での壮行会を、そこで目にした戦地に赴く学生たちの隊列を思い出させた。尽忠報国の精神を体現した一糸乱れぬ凜々しい整列を眺めながら、僕はそこに加わる自分の姿を想像しようと努めていた。僕も同級生も、まだ戦争に行ける年齢ではなかったが、「徴兵検査では丙種がいいところだろう」というのが僕に対する揶揄の常套句だった。母から「お前は立派な学者になればいい」と言って慰められるたびに、僕は同級生たちの揶揄を思い出し、この体に押されている役立たずの烙印が悔しさの熱を帯びた。
祖父が戻ってきたのを悟り、慌てて背中と腹の筋肉に力を込める。自分では懸命に込めているつもりなのだが、細長い枝がよく撓るように、体はぐにゃりと曲がってしまう。ただでさえ少ない力も、上手いこと一箇所に留まってはくれず、四方八方に散ってしまっているらしい。ふざけているのではないと弁解しようとした矢先、ふたたび僕の背後へとやってきた祖父が「目を瞑ってください」と言った。口調こそ静かだったが、その内側で働いている鋭い意志の力のようなものを感じ取って、僕はすぐに目蓋を閉じた。暗闇のなかでは、より一層、葉巻の残り香が鼻を掠めた。
「いつまでこうしていればいいのですか?」
数分も経たないうちにそう訊ねた。周囲からは殿と呼ばれ尊敬されている祖父だったが、僕にとっては愛情深い好々爺で、決して言葉を返し辛いというわけではなかった。考えあってのことだとは分かっていたが、それを教えてもらわないうちは、最近習った故事で喩えるところの、象を撫でる盲人に等しい。他所の家で寝泊まりするような居心地の悪さを覚えながら、僕は祖父の言葉を待っていた。
自身の息遣いが耳に障り、口ではなく鼻で呼吸することを意識し始めていた時、丸まっていた背中に感じるものがあった。腰から肩に掛けて平行に伸びている二本の筋肉ではなく、ちょうどその間にある背骨に沿うように当てられていた。その時僕は、自分の背筋がまっすぐに伸びているのを理解した。これまでにやったことがない未知の動きに驚いた筋肉が、外部から導かれた形を受け容れ、自分のものとしようと躍起になっていた。初めて感じる熱が、全身を駆け巡っていた。もっともこれは、後年に得た知識、筋力という概念によって、いかにも現実的に説明しようとしているに過ぎない。本当に正しく言い表すのなら、その日まで背骨を持っていなかった不定形の軟体動物に、ぐさりと背骨が差し込まれたような感覚だった。人間が、その個人が、自分が人間であるという実感をその手で得るのは、果たしていつのことなのだろう。柔道や剣道など、誰の力も借りずに目の前の相手と戦わねばならない競技に幼い頃から邁進している男子であれば、おそらく、四つか五つのうちに、その片鱗に触れ始めるのだろう。僕の場合は、八つにしてようやく、数多の困難が待ち受けている遠路の始点に立ったのだった。
「治道さんは、背筋のよい人になってください」
祖父は言った。名前を呼ばれたことでつい振り返ってしまった僕は、祖父が流麗な手捌きで白鞘に刀を戻すのを見た。それで、背中に当てられていたのが刀の棟だったのだと知った。
「折れることのない、強い人になってください」
そう告げた祖父の声はどこか物悲しく、まるで、寒い朝に蘇る古傷の痛みを堪えているようでもあった。子供にはどうすることもできない、まだ僕の手の届かないところにある苦しみを。僕は膝の向きを変え、茶室を出ていく祖父に深く頭を下げた。背中に当てられていた硬さは消えていたが、その日を境に、僕の背筋のよさが変わることは二度となかった。
2
祖父は外を歩くことを好んでいた。散歩と呼ぶにしては時間も距離も長く、闊歩という言葉が大袈裟ではなく似合っていた。父の会社は数台の自動車を持っていて、そのうちの一台は家族用に宛てがわれていた。明治神宮外苑競技場に行った時も若い社員が運転してくれたが、それを断ってひとりだけ歩いて向かってしまうほどの健脚の持ち主だった。口には出さなかったが、祖父は自動車を嫌悪していた。東京という町を隅から隅まで知り尽くしていた祖父にとっては、邸宅の外を歩くのと、邸内の庭に出て池に放たれている錦鯉や梅の老木の様子を見て回るのとの間には、たいした違いはなかったのだろう。
姿勢の矯正をされてから数日後、僕は久しぶりに闊歩の助手を任された。少し前までは刀剣関係の友人や歌会の参加者を連れて歩いていたが、時勢が時勢だけあって、最近は使用人がお供をするようになっていた。コースは決まっていて、邸宅のある高田老松町を出ると神田川に沿って本郷まで歩き、東京帝大のキャンパスを抜け、不忍池の方から上野恩賜公園へと入る。明治維新の立役者である西郷隆盛の像には目もくれず、その像の裏手、日陰にひっそりと置かれている墓碑に手を合わせるというのが祖父の日課だった。気になって、「これは誰の墓なのですか?」と訊ねたことがあったが、祖父は答えてくれなかった。
往復で十二キロの行軍を終えて邸宅に帰った僕は、疲れのあまり腹が空かず、勉強をすると言って自室に戻った。その実は机に頬杖をついてうつらうつらとしていただけだったのが、小一時間ほど経って、使用人のひとりが「お勉強中のところ申し訳ございません」と畏まりながら入ってきて、祖父が呼んでいると教えてくれた。その時期、僕たちは敷地のなかにある別館に住んでいた。本邸は父が陸軍に貸し出していて、近衛文麿や鈴木貞一など高名な軍人や政治家が訪れることから迎賓館と渾名されているらしかった。貸し出しが急に決まったこともあり、二階にある十二帖半と十帖の広い和室が、本邸から移動させた大量の美術品を置くための倉庫として使われ、祖父は一日の大半をそれらの品の手入れに費やしていた。
襖を開けると、奥の十帖の方に座卓が用意されているのが見えた。祖父はすでに上座に腰掛けていて、僕は勧められるのを待って座布団に正座した。祖父が口を開く前から、卓上に置かれている四本の刀に目が奪われていた。その頃はまだ、刀を一振り二振りと数えるということさえも知らなかったのだ。
先日見た白鞘ではなく、きちんとした拵えを身に纏った日本刀。いずれも、祖父がその生涯を懸けて蒐集した名刀で、迎賓館を訪れていた陸軍の将校が、わざわざ別館まで足を運び、「どうしても見せていただきたい」と祖父に懇願しているのを目撃したこともある。その気になれば接収することも容易かっただろうに、胸元に勲章を幾つも付けた立派な軍人が、ただ刀を見るためだけに祖父に頭を下げていたのだ。
僕の注意が卓上に向いているのを確かめると、祖父は右から順に一振りずつ、刀を鞘から抜いていった。鯉口を切る音が聞こえるのに合わせて、僕は無意識のうちに顔を伏せていた。自分のような若輩者には宝刀を見る資格がないと、幼い子供なりに考えたのだ。あの時代に教育を受けた者はみな、自分よりも高位の存在を前にする時に、自然と、御真影の前で取るような厳粛な態度を反復していたはずだ。
「過日、貴方の背筋に当てた刀がこのなかにあります」
鞘は傍らに置かれ、僕と祖父の前に四本の抜き身が並んだ。鍔と鋒の二点で支えるように机に置かれ、刀身が僕の方を向いている。刀を飾る時は差表で刀掛けに置くのが定石で、祖父がそれを持っていないはずがなかった。おそらく祖父は、僕が恐縮しないように、あえて乱雑な置き方をしてみせたのだろう。
「どれがその刀か、分かりますか?」
内緒話のように小さな声で祖父は訊ねた。今ならそれが、飛んだ唾が錆びの原因となるのを嫌ったからだと理解できるが、僕はその密やかさを、試されているのだと解釈した。
「背中に当ててもよいのですか?」
「しっかりと見れば分かります。見て分からなければ、分からないのと同じことです」
そう言われても、僕は茶室で、白鞘に収められていく刀をほんの一瞬眺めたに過ぎなかった。一応は訊ねてみただけで、背中があの刀の反り具合を記憶しているわけでもない。大人になった僕があの場にいれば、どれがあの時の刀だったのかだけではなく、四振り全ての出自を造作もなく言い当てられただろう。拵えを外され、茎の銘を隠された状態でも、刃文と地鉄を観察するだけで、いとも容易く刀工を判別できる。しかしながら、どれほど蓄えた知識も時を遡ることだけは叶わず、姿勢だけが立派になった痩せぎすの僕には、目の前にある日本刀が、どれも似たように見えていた。肥後守は持っていたし、包丁を扱ったことも何度かあったが、同じ刃物でも、それらを等倍に大きくしただけのものではないということは理解していた。日常生活で使われる一介の道具ではなく、東京がまだ江戸と呼ばれていた頃までこの国に群雄割拠していた武士たちの命であり、人を殺めるための武器であった。
畏れ多いという気持ちが消えたわけではなかったが、若さは自制を知らず、徐々に好奇心が湧き上がってきていた。祖父はすでに拝謁の許しを与えてくれている。僕は伏せていた顔を上げ、手前にあった一振りを凝視した。まず初めに見えたのは線だった。反り具合はどれも異なっていたが、日本刀の佇まいは、しなやかな曲線と冷徹な直線を一所に備えていた。本来は同居し得ないはずのふたつの要素が、互いを脅かすことなく、かと言っておもねることもなく、堂々と屹立している。矛盾めいた共存は、他にも見て取れた。たとえば、刃と棟がそうであり、夜空に浮かぶ星のように輝く刃文と、吸い込まれそうな暗さを湛えた地鉄がそうであり、そもそも刀は、灼熱のなかで焼かれたのちに水で冷やされることでその相貌をあきらかにしていく。
人間とは似ても似つかぬ姿形をしているのに、僕には刀が、ひとつの美しい肉体のように思えてならなかった。祖父と過ごした日々を思い出すことには、どうしても感傷が付き纏い、あの想いをそっくりそのまま取り出すことは難しかったが、自分の感情を再解釈することが悪徳でないのなら、僕はきっと、混じり合うことのないふたつの要素を平然と兼ね備えていた刀に、慈愛と憎悪を併せ持つ人間の心を重ねたのだろう。
おかしな言い回しかも知れないが、僕は結局、自分が最もなりたい姿をしている刀を選んだ。その刃先に触れてみたいと思う刀を、指差すことは躊躇われて、代わりに視線で指し示した。残りの三振りを洗練された手付き、刀剣愛好家特有の仰々しいものではなく、剣士のように実用的な所作で鞘に戻すと、祖父は僕が選んだ刀を手に取った。
「これは私が最初に手に入れた刀です。烏丸家が所蔵する刀の手入れをしていた老人から刀剣鑑賞の手解きを受けた私は、十五歳の時に立ち寄った鑑定会でこの刀に偶然出会い、どうしても欲しいと思ったのです。当時の私は病気を理由に休学していた身で、烏丸家の家令が『この子はいつまで生きられるか分からないから買っておやりなさい』と私の父に助言してくれたおかげで、買っていただけたのです」
祖父は小槌に似た目釘抜きを使い、茎と柄とを留めている目釘を押し出した。柄は握ったまま、その手がもう片方の握り拳でトントンと叩かれ、固定されていた刀身がおもむろに浮いてくるのが分かった。刀から柄を外し、続け様に鍔と鎺も外してしまうと、祖父はあらわになった茎を僕の方へと向けてみせた。その刀は無銘であった。
「戦勝祈願のために二振りの刀を神社に奉納した太田道灌が、最後まで手放さなかった一振りだと言われています。銘こそありませんが、その作風からして粟田口、なかでも久国の手によるものだと考えてよいでしょう」
太田道灌の名前には聞き覚えがあった。江戸城を築城した武将で、優れた歌人でもあったという。祖父も歌を詠むから、それで耳にしたのだと思う。粟田口や久国の方は、何のことかさっぱりだった。
「幼い私の我儘によって迎えたものですが、この刀は、烏丸家の繁栄を見守ってきました。私の弟が亡くなるまでは、彼の部屋に飾らせていました。土木建築請負業で身を立て、東京の発展に貢献し続けた弟に、道灌の姿を重ねていたのかも知れません」
祖父の弟、僕にとっての大叔父は、烏丸家の歴史においては異端児で、小学校を卒業するのと同時に土木の世界に足を踏み入れ、二十四歳の若さにして会社を興したらしい。本領安堵によって伝来の土地こそ守られたものの、財産の多くを失った烏丸家が没落の憂き目に遭うことなく旧家としての栄華を保つことができたのは、ひとえに、大叔父が興した烏丸組の成功の賜物だった。大叔父は志半ばで病死してしまい、会社は僕の父が、烏丸建設と名前を改めて引き継いでいた。
「貴方の父親も、幼い頃は姿勢が悪かったのです」
「あの父が、ですか?」
「ええ。貴方よりも悪かった。あれは私譲りで背も低かったので、蚤と揶揄われていました」
耳を疑わずにはいられなかった。父は四尺三寸と背丈こそないものの、柔道で鍛えた体は分厚く、その背筋は、シャツの内側から鉄骨のように迫り上がっている。また、恰幅のよさに加えて、実際よりも大きく錯覚させてしまうような覇気も持ち合わせていたので、背の高い外国人連中に交じっていても不思議と見劣りはしなかった。そんな父が、丙種よりも酷い渾名で馬鹿にされていたとは、今の父しか知らない僕からは到底信じられない。
「あれにも、貴方にしたのと同じことをしました。海軍学校で気を著けの姿勢を訓練するのに鉄の物差しを使っているという話を聞いたのですが、我が家には鉄の物差しがなかったので、代わりに刀を使ったのです」
「……それで、父も今のようになったのですか?」
話の流れを考えれば当然そうなのだが、予想に反して、祖父が頷くことはなかった。祖父と父が不仲であることには、子供なりに薄々勘付いていた。学問で身を立てることを拒み、旧制高校へは行かずに大叔父の会社に入った父は、血縁の者であっても特別扱いはしないという大叔父の方針のもと、他の社員よりも厳しく育てられた。父もまた、自ら茨の道を進むことを望んだようで、陸軍から要請された工事のために大陸へ渡ることを志願し、幾度となく死線を彷徨った。父が帰国を命ぜられた時、病床にいた大叔父の胸中では、この頑固な甥が他の社員たちから二代目として認められるだけの信用を勝ち取れている、という判断が下されていたのだろう。つまり父は、祖父の風変わりな矯正法ではなく、自らの弛まぬ努力によって、醜く縮こまっていた背筋を伸ばしたのだ。
「あれは私の話には少しも興味を示しませんでしたが、ある時、この刀を見るなり『子供の頃に俺の背中に当てたのはこの刀だろう』と言ったのです。なぜ分かったのかと問うと、つまらないことを訊くなよとでも言いたげな顔で、『見れば分かる』と答えたのです」
そう述懐した祖父の顔付きは、張り替えられた真新しい畳を眺めている時のような寂しさを滲ませながらも、ほんの少しだけ、誇らしげであった。膝元から白鞘拵えを取り出した祖父は、慣れた手付きで柄を嵌めて目釘を差し、久国の刀をそっと鞘に戻した。僕から言い出すわけにはいかなかったが、当然持たせてくれるのだろうと思っていたので、味わうことになった落胆は相応に大きかった。
「この刀は烏丸家の守り神です。我が家を震災から守り、弟の会社を幾度も倒産の危機から救い、貴方の父親を無事に大陸から帰らせた。弟の病気が発覚したのは、本社を建て替えるからと言って、この刀を私に返した次の日のことでした。……治道さん、貴方がこの刀に報い続ける限り、この背筋のよい刀は貴方を守ってくれるでしょう。これから先の苦しい時代から、貴方と烏丸家を」
祖父がさらりと口にした苦しい時代という言葉に、僕は言い知れぬ不安を覚えた。ここのところ、本邸に軍人の出入りが増えていた。父に用があるということは、すなわち、何らかの密命が下されているということだったが、父がふたたび大陸へ渡る気配はない。だとすれば、工事は国内で行われていて、来るべき本土決戦に向けて軍備を増強しているに違いない。増強できるだけの余力があるのだから、戦況は有利なはずだ。その時の僕は、幼気にもそんな推測を働かせていたので、博覧強記であった祖父がこの国の未来を憂えたのを聞いて、足元がぐらぐらと崩れていくような気分にさせられた。
「日本はどうなるのですか?」
堪らずそう訊ねてみると、祖父は僕から視線を逸らし、目釘抜きを手にしたまま立ち上がった。床の間の手前に籐製の肘掛椅子が置かれていて、祖父はそこに腰を下ろした。振り返れば、その時すでに、祖父は膝の調子が悪かったのだと思う。それでも闊歩の習慣を止めなかったのは、今日が最後になるかも知れないと思えばこそ、墓参りを欠かしたくなかったのだろう。
「朝夕に音のみし泣けば焼き大刀の」
聞こえるか聞こえないかのか細い声で呟き、祖父は目蓋を閉じた。
利心も我れは思ひかねつも。
その歌が万葉集から引用されたものだと知るまでには、長い月日を要した。
午睡に入ってしまった祖父に一礼し、僕は部屋をあとにした。その日は曇りで、ガラス窓から日の光は差し込んでいなかったが、僕の目には、あの刀が反射した光が焼き付いているような気がしていた。祖父の不穏な態度よりも、自分が祖父の審美眼を受け継いでいるという事実に、密やかな興奮を覚えていたのだ。そしてそれは、ほとんど話したこともない父にも遺伝している。僕はその時、自分と父が紛れもなく親子であるということを、名前に共通する道という文字を除いて初めて認識し、これまでずっと憎んできた父に、怒りや蔑みを向け続けてきた父に、温かい情を抱いた。
一連の出来事を母に話すか迷ったが、男だけの秘密にしようと決め、ついに明かさなかった。しかし、いつも気難しい顔をしている僕が珍しく上機嫌だったからか、その日の母は、いつもより優しかったように思う。夕食を終えたあとは部屋に招かれ、付きっきりで勉強を見てくれた。母のしなやかな腕からはフランス製の香水の匂いがしていた。窓際に置かれていたラジオから玉音放送が流れるのは、それから一年半後のことだった。
第一部 一九五四年
1
左手は順手に、右手は逆手にして握り込む。
目一杯息を吸い込み、呼吸を止める。臀部を後方に突き出し、上体を前傾させていた僕は、床に置かれているバーベルを威勢よく引き上げた。軽く曲げていた背中がしっかりと伸び、床と垂直になったところで一旦静止し、重力に任せてしまうことなく、ゆっくりとバーベルを下ろしていく。床に着いたところで、ようやく息を吐ける。ふたたび肺を膨らませ、今の動作をもう一度繰り返す。背中の筋肉よりも先に握力に限界が訪れ、五回目を終えたところで、僕はバーベルから手を離した。あともう一回できそうな心持ちではあったものの、体の方が追い付かず、前回の記録との変化はなかった。ぐったりとしている僕に代わって、先にセットを終えた重森がバーベルを持ち上げてフックに戻してくれた。
「あともう一回が遠いね」
二十キロのプレートを外しに掛かっている重森に、そう声を掛ける。去年に購入されたばかりだというプレートは早くも汗で錆び始めていて、トレーニングが終わるといつも、手のひらや指が煤けるように汚れた。
「運動歴のない坊ちゃんにしては上出来だ。上背もあるんだし、今からでも何かやったらどうだ?」
「これが性に合ってるんだ。君こそ、戻らないのか?」
やっと落ち着いてきた僕は、急いでバーベルから二枚のプレートを外した。パワーラックの反対側にいる重森は、すでに作業を終えていた。
「おれの場合は馬が合わなかったんだ」
「村松さんも元は国体選手だったんだろう? 喧嘩とはいえ、それを投げ飛ばしたんだから、君はたいした才能の持ち主だよ」
「あいつは強くないさ。それに、喧嘩が強いくらいじゃ、今の時代は飯なんか食えない」
「プロレスをやれば、いくらでも食えるじゃないか」
薄い唇を閉じて苦笑いを浮かべた重森は、力道山の空手チョップを真似ている僕を横目に、出口を顎でしゃくった。トレーニング室は地下にあり、常に立ち込めている若い熱気も相まって、とにかく酸素が薄かった。一刻も早く外の空気を吸いたいのは僕も同じで、手早く着替えを済ませて階段を上り、僕たちは地上に舞い戻った。提げていたのは数冊の教科書が入っているだけの靴袋なのに、まるで重りのように感じられ、爽やかな外気を楽しむ余裕もなかった。筋肉が正しく疲労していることの証だったが、僕と同じ量のトレーニングを僕よりも重い重量でこなしていたはずの重森は、学生服の懐から取り出した煙草に火を点けている。彼曰く、きつい修行を終えたあとの一服は格別なのだという。スポーツマンとしては失格だが、重森はむしろ進んで、その道からドロップアウトしていた。郷里では名の知れたレスリング選手だった重森は、入部から一ヶ月もしないうちにレスリング部を去ってしまった。本人によれば、監督である村松氏との政治思想上の対立が原因で、それからは、大学生らしく酒や麻雀に明け暮れた。もっとも、村松氏の監督下に置かれるのが我慢ならないので辞めたというだけで、運動への意欲までは捨てていなかった重森は、自然とトレーニング室に出入りするようになった。そこで僕は、彼と出会ったのだ。
僕たちが入学するちょうど一年前、うちの大学には日本初となるボディビルディングのクラブが創設され、体を鍛えることに興味があった僕は見学に行こうと思っていたのだが、なかなか勇気が出ず、実際に足を運ぶまでに一ヶ月を要した。その遅れを取り戻すべく、毎日のようにトレーニング室に通い詰めていると、決まった曜日に鉢合わせする新入生がいることに気が付いた。耳が潰れた逞しい青年は、日頃の鬱憤を鉄にぶつけているかのような荒々しい所作でベンチプレスに励んでいた。その時僕は、彼の隣でスクワットをしていた。前の週にクラブの先輩から「君は細いので、まずは大きい筋肉を鍛えるといい」と助言され、フォームのレクチャーまでして頂けたのだが、僕はたった二十キロのバーベルを担いでしゃがむのにも難儀していて、創設されて間もないとは思えないほど筋骨隆々とした部員たちのなかにいるのが恥ずかしかった。それで、トレーニングの合間には、これみよがしに『文藝』なんかを読んでいた。面倒な気取り屋と思われれば、面と向かって揶揄われはしないだろうと考えていたのだが、ある日、つかつかと寄ってきた重森が開口一番に「火野葦平は読むか?」と訊ねてきた。僕と彼は互いに汗を流しながら、連載中の小説について意見を交わし、それ以来、会えば必ず話すようになったのだった。
「講義は?」
「今日はもうないよ」
「なら、飯でも食おう」
短くなった煙草を放り捨て、重森が歩き出す。トレーニングを終えても、最中に感じていた吐き気のような不快感は当分消えず、一、二時間は何も食べる気にはなれなかったのだが、この男はそうではないらしい。こういう部分ひとつとってみても、重森は僕にはない生き物としての強さを持ち合わせている。
「まだ腹が減ってないんだ」
「食わなきゃ、せっかくの運動が無駄になるぞ」
重森は都電の早稲田駅の方へと歩いていて、行き先には見当が付いた。五分ほど歩いたところで、「金城庵」の青い暖簾が見えてくる。昼飯時で店内は混み合っていたが、ちょうどふたり出ていったので、僕たちは待つことなく席にありつけた。重森は悩むことなくかつ丼を注文し、僕は彼とは違う理由で、やはり悩むことなくもり蕎麦を頼んだ。
「浮かない顔だな」
「まだ疲れてるんだよ」
「いいや、違うね。心地よい疲労とは無縁の顔だ」
自分で思っているほどに自分のことを知っているわけではないという事実を認められる程度には、僕は大人になっていた。重森は勘が鋭いし、その勘が間違っているか否かをきっちりと確かめる執念の持ち主だったので、僕は早々に白旗を上げることにした。
「……昨日の昼に、兄に会ったんだ」
「おまえ、兄貴がいたのか?」
「兄と言っても、たかだか数日違いさ。それに、母親も違う。一緒に住んでもいないんだ」
余計なことを言ってしまったと、口にしてすぐ後悔した。父は数人の妾を持っていることを隠そうともしておらず、そんな男の名誉を守ろうというのではない。僕たち家族が咎められる謂れもなかったが、伴侶でありながら確固たる他人でもある母とは違い、紛れもなく血を受け継いでいる息子がその事実について自ら口にする時、まるで、その放蕩ぶりまで引き受けたような気にさせられるのだ。僕は父を蔑視していたが、それと似た色合いの視線を、とりわけ目の前にいる友人から向けられたくはなかった。
「会って、それでどうした? 何がいけなかったんだ?」
「向こうは僕の母を、何というか……、おそらく憎んでいるんだ。一応は母が本妻だからね」
「なるほど。待遇に差があったというわけだな」
「詳しくは知らないが、そうなんだと思う。学費くらいは出したみたいだけど」
気遣いのつもりか、重森は僕に煙草を勧めてくれたが、早死にした大叔父が愛煙家だったのもあって、喫煙は絶対にしまいと決めていたので固辞させてもらった。
あの奇妙な昼食会が始まったのは、僕が大学に入る少し前のことだった。祖父、烏丸誠一郎の葬儀から半年が過ぎていて、僕は祖父が遺した数多くの美術品の整理を手伝うことによって、どうにか悲しみとの折り合いを付けようとしていた。GHQは終戦の翌年、この国における武の象徴であった日本刀の没収を決定した。各地の名刀が海外へと流出してしまうことを恐れた祖父は、信頼の置ける刀剣愛好家を集めて会合を開き、反乱を想起させる武器ではなく、あくまでも優れた美術品として価値を認めさせることで、日本刀の所持を許可させることができるのではないかと考えた。迎賓館を訪れていた政治家たちとのパイプが依然として生きていたことと、イギリスに遊学していた経験のある祖父が英語に堪能だったことの二点が上手く働き、祖父たちの献身は見事に実を結んだ。一九四八年には、日本刀を後世まで守り続けていくための組織である刀剣保存協会が設立され、祖父は初代会長となった。今でも、協会の人間が頻繁に屋敷を訪れ、祖父の刀の手入れをしてくれている。祖父は遺書を書いていなかったので、僕も彼らも、これらの刀をどうすべきか処遇を決めあぐねていた。
その日も僕は、本邸にある祖父の書庫に籠もり、蔵書の整理に勤しんでいた。懸命に辞書を引きながら、ドイツ語で書かれた本の題名を解読していると、妙に粧し込んだ母がやってきて、「出掛ける準備をしなさい」と命じられた。すぐに自室に戻って学生服に着替えた僕は、父の部下が回してきた車に乗り込み、何事かと戸惑ったまま銀座へと運ばれた。母の方は事情を知っているらしかったが、訊くことを一切許さないような、鬼気迫る面持ちをしていた。
車が停まったのは、「メイゾン・シド」というレストランの前だった。日本では数少ない本格的なフランス料理を出す店で、そこのシェフと父は戦前からの付き合いなのだと、あとで聞かされた。二枚目の若い給仕が案内してくれたのは奥まったテーブル席で、見知らぬ女性と青年が先に座っていた。一度挨拶をしたきり、母は能面のような顔で煙草を吸い続け、僕はと言うと、若い給仕が偶然を装って向けてくる好奇の視線に、顔を伏せて耐えていた。父は四十分ほど遅れてやってきたが、謝罪ひとつ口にすることなく、席に着くなり葉巻に火を点けた。そして、何口か吸ったのちに、僕の向かいにいた青年を指差して「お前の兄だ」と紹介した。
僕には姉がふたりいる。上とは六つ、下とは四つ離れていて、ふたりともすでに結婚して家を出ていた。父は僕の母が一向に長男を産まないので、業を煮やして愛人を孕ませることにしたのだが、何の因果か、ほとんど同じタイミングで僕と兄が産まれてしまった。僕に兄がいると教えてくれたのは上の姉だったが、直接聞いたのではなく、家を出ていく前日に母と口論しているのを盗み聞きしてしまったのだ。姉は父を「恥知らず」と呼び、自分と一緒に家を出るよう母を説得していた。母は今、僕の隣に座っていて、姉の説得は無意味に終わっていたが、あの晩の哀訴は僕に、父に対するさらなる嫌悪と、父が持つという別の家族に対する本能的な恐怖を植え付けた。忠臣二君に仕えずという言葉があるが、同じ男が別個の家族を同時に持つというのは、これから大人になって所帯を持っていくであろう僕からすれば薄気味悪く思える。この男は、母の前に座っている女性の前では甘えた素振りを見せたりするのだろうか。それとも、我が家にいる時と同じように、何かにつけて手を上げるのだろうか。僕が見たことのない側面が父に備わっていると考えるだけでも気分が悪くなってくるし、他所の家でも微塵も変わりなく傍若無人な振る舞いをしているという想像も、やはり、僕の胃をむかむかとさせた。運ばれてくる料理はどれも見栄えがよかったが、沈黙の苦みが口いっぱいに広がっているせいで、美味しいはずの食事からは何の味もせず、僕たちは課せられた義務を果たすように黙々と平らげ、「次の会議に向かわねば」という父の言葉を合図に解散した。
父にとっては、離れた池で飼っている二匹の鯉を、ふと見比べてみたくなり、同じところにぽんと放ったという具合の、ほんの気紛れだったのだろう。従って、僕と母があちらの家族と会うことはもう二度とないはずだと思っていたのが、奇妙な昼食会は、毎週の火曜日に必ず開催されることになった。先の惨事がお互いの息子の教育によくないと考えたのか、僕の母と兄の母は打って変わったように会話を繰り広げたが、本妻と妾の間に共通する話題はさほど多くはなく、また、何が相手を刺激するかも分からないため、ふたりは他愛もない世間話に終始していた。父は時折、やはりどうでもいい内容の合いの手を入れていたが、僕と兄は、まったく口を開かなかった。窮屈そうな手付きでフォークとナイフを動かしながら、兄は父と僕の母を暗い目で睨み、会がお開きになって全員が席を立つときに、その去り際に、僕をじっと見つめた。言い方を変えたのは、前者と後者で、彼の目付きがあきらかに異なっていたからだ。腹違いとはいえ兄弟としての情があったのか、あるいは、不誠実な父を持った息子としての連帯感を覚えていたのか、どちらにせよ、僕は確かめようとはしなかった。母から聞いた話では、兄は東京大学の工学部建築学科に籍を置いているらしく、もしかしたら、卒業後は烏丸建設に就職するつもりなのかも知れない。祖父が先手を打ってくれたおかげで進路に口出しをされず、父が蛇蝎の如く嫌う文学部に入れた僕としては、少し嗅げば父の匂いがしてくる領域に足を踏み入れるなど、まっぴらご免だった。
「分からないなあ。おれがおまえなら、今すぐにでも働かせてもらいたいがね」
かつ丼を頬張りながら、重森は言った。大抵の人間は、僕が烏丸建設の御曹司だと知るや否や、その態度を一変させてしまう。意地の悪い同級生たちは、落書きをしたノートの切れ端を壁に貼り出し、「治道殿に買ってもらって、立派な家を建てよう」と囃し立てるだけだったが、大人たち、とりわけ学校の先生が他の生徒がいないところで僕に見せる機嫌を窺うような態度には一晩中ナーバスにさせられた。僕の名が姓を飛び越えることは、この先も永遠にないのだと思うと、何をしても仕方がないような気分になる。
しかしながら、重森は僕の素性に対する興味と、僕自身への接し方を完全に切り分けているらしかった。腹の底を隠すのが上手いだけなのかも知れないが、彼が僕を、あくまでも普通の学生として扱い、友人でいてくれていることには随分と助けられている。
「身内だからって特別扱いはされないよ。それどころか、むしろ腫れ物扱いだろう。三代目は滅ぼすってよく言うからね」
「ヘマさえしなければ、クビにだけはならないはずだぜ。定年までの収入源が確保できるんだから、あとの時間は好きなことをし放題じゃないか。今時、そんな職場を探す方が難しい」
「そう言えば、君が何を志望してるのか、訊いたことがなかったな」
「少なくとも、プロレスラーじゃないことだけは確かだ」
こちらが言い出したことだと気付き、僕は軽く笑った。ボディビル・クラブの部員たちの大半はプロレス好きで、かくいう僕も、去年旗揚げされた日本プロレスの試合を観戦していたが、重森はまったく関心がないようだった。本を読むのは知っているし、トレーニング愛好家だというのも分かっているが、重森が何に興味があるのか、僕は少しも知らなかった。訊けば教えてくれるはずだが、僕は向こうが自然と話してくれるのを待つのが好きだったし、重森としても、そういう性分が気に入ったからこそ、わざわざ違う学部の僕とつるんでいるのだろう。
美味くも不味くもない蕎麦を啜っていると、徐々に食欲が出てきた。二、三十分ほどすれば、もっと腹が減ってくるに違いない。
「家業を継がないんなら、おまえは一体何をやるんだ? 作家か?」
「まさか。僕は読む専門だよ。下手の横好きで短歌をやるくらいだ。数年前に学芸員という資格が作られたのは知ってるか? 博物館の運営に携わる専門職なんだけど、僕はそれになろうと考えてる」
「悪いが初めて聞いたよ。となると、国立博物館で働くのか?」
「いや、資格を取ったからといって、誰もが希望する場所で働けるわけではないらしいんだ。博物館は全国各地にあるからね」
「そりゃそうだが、どうして博物館なんかに?」
「祖父の蒐集品をきちんと管理したいんだ。方々から、博物館なり美術館に寄贈してくれないかと頼まれているんだが、僕としては、祖父の愛した物品が散らばってしまうのは悲しいから、うちの敷地のなかに自前の博物館を作りたいんだ。学芸員の仕事は、その下準備になると思ってね」
祖父は生前、文化財保護委員会の委員を務めていて、東京国立博物館はその管理下にある。学芸員を志すようになったきっかけは、祖父と懇意にしていた数人の委員が葬式のあとで屋敷を訪れた際に、日頃から所蔵品を手入れしていた僕の腕を見込み、「その才能を文化国家のために発揮しなさい」と発破を掛けてきたことにあった。委員のひとりに頼みでもすれば口利きしてもらうことは容易いのかも知れないが、僕のなかには、自分の持っている知識は何もかも祖父から譲り受けた借り物だという意識がある。目利きひとつとっても、祖父が下す審判の基準を知っているからこそ、その基準に照らし合わせた評価を口にできるのであって、今の僕は単なる代弁者に過ぎず、美術の愛好家を名乗ることなど断じて許されない。この恥の意識を乗り越えていくためには、祖父の威光が及ばない場所で修行するしかないのだと考えていた。
「随分と具体的な野望があったんだな。ただの坊ちゃんかと思いきや、たいしたもんだ」
「具体的なものか。僕は一生を費やしたって、祖父のようにはなれっこないんだから」
「そう悲観するなよ。重りを持ち上げることに関しては、おまえの方が上だろうに」
重森がそう言ったせいで、僕は頭のなかでバーベルを担いでスクワットをする祖父を想像してしまい、あやうく吹き出しそうになった。すでに食べ終えていた重森は、爪楊枝を煙草のように咥え、厨房で天麩羅を揚げているご主人をぼんやりと眺めている。ぐにゃぐにゃと気の抜けた蕎麦を急いで平らげ、僕たちはお代を置いて「金城庵」を出た。
「君はもう帰るのかい?」
「ああ。その前に早苗にでも寄って行こうかな」
「あんまりのめり込むなよ」
「言われなくても。こちとら苦学生なんでね」
重森が名前を出したのは、南門の近くにある雀荘だ。僕を除いてボディビル・クラブの部員とはあまり交流していない重森の本拠地は、どうやらそちらのようだった。僕は麻雀をやらなかったし、ずぶの素人を真剣勝負の場に交ぜたくないのか、重森から誘われることは一度もなかった。
僕の家までは、キャンパスから歩いて十五分も掛からない。都電の早稲田駅からだとさらに近く、神田川を渡って少し進むだけで烏丸家の敷地が見えてくる。僕たちは店の前で別れたが、数歩もいかないうちに、重森が僕を呼び止めた。
「親父さんとはまだ冷戦なのか?」
そんなに気になっていたのかと驚きながら、僕は頷く。重森は野望という表現を用いて讃えてくれたが、心のどこかでは、父とはまったく違う人間になるための手段とも考えていた。
「祖父君の持ち物を守りたいなら、親父さんとは話を付けておいた方がいいな」
「どうして?」
「守れるようになる前に手放されちまったら困るだろ?」
「まさか。あの人は本気で天目茶碗に米をよそおうとした男だ。自分の興味が向かないものには、そもそも価値なんてないと思ってるんだよ。ガラクタの山のことなんか、気にも留めていないさ」
「ならいいんだがね。ただ、祖父君やおまえとは違って、家はなるたけ空っぽの方がいいと考える人間はいるもんだ。そういう手合いは、よく調べもせずに二束三文で売り飛ばしてしまう」
どうやら、重森は本気で心配してくれているらしかった。確かに父は、祖父の趣味、ひいては人生そのものを快く思っていないようだったが、烏丸家の家宝とも言うべき所蔵品に手を付けるほど愚か者ではないはずだし、第一、金にも困っていない。ましてや、刀剣保存協会や文化財保護委員会のお歴々も出入りしているのだから、その心配は杞憂だろう。僕は重森に感謝を伝え、あらためて帰路に就いた。彼の言葉は、ほどなくして予言として成就することになるのだが、その時の僕は、ひと匙の危機感すら抱いていなかった。
2
東京における進駐軍工事の大半を烏丸建設が請け負っていたこともあり、何かしらの便宜が図られたのか、終戦後も烏丸家の屋敷が接収されることはなかった。別館で暮らしていた僕と母、祖父は本邸に戻り、祖父が亡くなるまでの八年間、以前と変わりない生活を送った。相変わらず父は寄り付きもしなかったが、葬儀が終わり、祖父の関係者の出入りが増えたのと時を同じくして頻繁に帰ってくるようになった。まるで、嫌っていた人間が消えて清々しているかのような臆面のなさに、これまで以上の侮蔑と嫌悪を抱いたのだが、使用人がこっそり教えてくれたところによると、父は別館を改装して何かしらの事業に使う気でいるらしかった。その計画を練っているのか、父は本邸の客間に陣取っていることが多かったので、万が一顔を合わせてしまわないように、僕は使用人たちが使っている庭に面した出入り口から帰るようにしていた。本邸には各階に階段がふたつあり、そのうちの片方は、客間や食堂に素早く給仕するための動線として設けられている。その階段を使えば、厨房や使用人の部屋の前を通るだけで、家族の誰にも会わずに二階の自室まで辿り着けるのだ。
庭には寄らず、まっすぐ本邸に向かって歩いていると、ちょうど玄関扉が開いていて、内側に佇んでいる父の姿が見えた。足が勝手に動き、僕は車寄せの手前に植えられている目隠しの木立に身を隠す。父はシャツにサスペンダーという格好で、出掛ける時は必ずジャケットを着るから、客人を見送るために玄関まで来たのだと分かった。その読みは見事に当たり、父の背後から、サテンのように光沢のあるグレーのスーツに黒いネクタイを締めた男が現れた。三十歳そこそこくらいの若い男で、筒状のケースを肩から下げている。図面を入れるものだとすれば、建築家か何かだろうか。烏丸建設の社員にしては派手過ぎるし、そもそも父が、普通の社員を屋敷に招き入れることなどあり得なかった。旧知の間柄のような馴れ馴れしい握手を交わして男は去っていき、咥え葉巻の父はその背中を見送ることなく屋敷のなかへと戻っていった。僕はその男に見付からないよう木陰に隠れ続け、彼がいなくなるのを待って、本邸の裏手へと回った。こちらの出入り口には、病院の受付に設けられているような小窓があり、その奥の部屋で寝泊まりしている使用人が庭師や配管工などの客人をなかに通す。警備の役割も兼ねているため、ここには最も歴の長い者が置かれていて、小窓を開けた僕を認めると、年嵩の使用人は優しげに微笑んだ。
「おかえりなさいませ。今日も何か召し上がりますか?」
この時間に帰ってくる時は、トレーニングを終えたあとだと知られているのだ。気遣いはありがたかったが、今日に限っては、彼が他の使用人を呼びにいってしまう前に訊ねておかねばならないことがある。
「さっきまでいらしていたのは誰ですか?」
「道隆様のお客様のことですか?」
「はい。烏丸建設の社員には見えなかったもので」
「申し訳ありませんが、私たちも教えていただいてはおらず、丁重にもてなすように、としか言われておりません。送って差し上げろとのことでしたので、今、別の者が車を出していますよ」
父は祖父の趣味が存分に反映されたこの屋敷を好いてはいないようだったが、上等な客間のことは最大限に活用していて、なおかつ、接客にも細心の注意を払い、聞き出した食事や酒の好みを使用人にも徹底的に覚えさせた。その父が名前を明かさなかったということは、身内にも知られたくない相手だったのだろうか。いつもなら社員に運転させるのを、使用人に送らせたというのも気になった。扉を開けてくれていたので、疑問の数々は一旦脇に退け、僕はひとまず本邸に入った。背中の疲労に襲われながら階段を上っていると、三階から下りてくる使用人とすれ違った。
「あら、坊ちゃん。お帰りなさい」
仄かな香水の匂い。母は父が馬鹿の一つ覚えのように贈り続けていたフランス製の香水を長らく使っていたが、実のところは気に入っていなかったのか、彼女に譲ってしまったらしい。母でない女性からその優しい匂いがするのに僕は今でも混乱してしまうのだが、ふと、違うことが気になって足を止めた。
祖父は各階に書斎を持っていたが、三階に関しては、その全てを祖父が占有していた。寝室と、眠れぬ晩に向かう書斎、そして、蒐集した美術品を置くための倉庫。過去に誤った手入れをされてしまったことがあるらしく、祖父は使用人たちに、浴室とトイレ以外には立ち入らないよう厳命していた。現在は刀剣保存協会の人たちが出入りすることもあるため、その戒律も自然と反故になっている。
「上の掃除ですか?」
「道隆様にお茶を用意したので、片付けていたんですよ」
さっきは見落としていたが、わざわざ振り返って教えてくれた彼女は、その腕に角盆を抱えていた。湯呑みがふたつ載っているのに気付いた瞬間、僕は靴袋を放り投げ、全速力で三階へと駆けた。階段を上がってすぐの部屋が所蔵品の倉庫として使われていて、この階の三分の二以上を占めているだだっ広い空間を無数の棚が埋め尽くしている。祖父の背丈に合わせて注文された木製の什器で、高さが五尺ほどしかないため、そのぶん数が多いのだ。棚板は簀子状になっていて、戸は付いていない。碁盤目状に並べられているおかげで、端から順に整理することができるのが特長だった。ざっと一周してみたところ、昨晩の記憶との相違は見受けられない。刀だけは動かしたような形跡があったが、全て揃っていたので、単に見せびらかしただけなのだろう。もしかしたら、あの若い男にも持たせてやったのかも知れない。袱紗が綺麗に畳まれたままということは、素手で触っていたはずなので、あとで手入れをしなくてはならない。
祖父の私室はこの奥にあり、茶を飲めるような場所はそこしかなかったので、断りもなく客人を入れた父に憤りを覚えながら扉を開けた。僕が強く望んだこともあり、祖父の私室は、何もかもがそのままの姿で時を止めている。祖父を慕っていた古株の使用人は、今でも定期的に寝具を洗濯してくれていた。いずれは片付けなくてはならないと理解していたが、当面は、この部屋に主人の息遣いを忘れさせたくなかった。部屋は引き戸で仕切れるようになっていて、庭に面している窓際の方には、書き物をするための机と、中国から取り寄せたという飾り棚が置かれている。棚としては奥行きが浅く、本来は巻き物を入れるのに使われていたらしいのだが、祖父はそこに、一振りだけ刀を納めていた。
粟田口久国の無銘。
烏丸家の守り神であり、祖父は烏丸家の人間以外には、その刀を見せようとはしなかった。生前に命じられたわけではなかったが、祖父の人生を受け継いだ者としての責務から、手入れこそ続けていたものの、刀剣保存協会の人たちに「拝ませて欲しい」と頼まれても、断腸の思いで断り続けていた。
この部屋に足を踏み入れた時からずっと脳裏に浮かんでいた厭な想像を振り払うように、飾り棚の戸を静かに開ける。中は空っぽで、白鞘に収められた久国は、隣に保管してあった拵えごと消え失せていた。
枕花の下で眠っている祖父を目にした時、深い悲しみに包まれたけれど、不思議と喪失感だけは覚えなかった。家庭というものを放棄した父に代わって僕を躾けてくれた祖父は、知識や教訓、思い出、僕の内側に永遠に残る形で、その愛を惜しみなく与えてくれた。それゆえに、たとえ命が失われたとしても、僕と祖父との間にあった結び付きは決して消えないと思ったのだ。何よりも、受け継いでいくと誓ったあの刀が、物的な縁として、僕の手元に残されていたのだ。
想像の再現に驚きは生じず、その代わりに、僕は今更になってようやく、喪失の苦しみに襲われることになった。ただし、この喪失は人間の死とは性質が異なり、あきらかに抗うことができるものだった。蝶番の軋む音さえ立たぬようにゆっくりと飾り棚の戸を閉めた僕は、厳かな足取りで祖父の私室をあとにし、倉庫を通り抜けるや否や、全速力で階段を駆け下りて、一階の客間へと飛び込んだ。
姉たちがいた頃は、誕生日を迎えた学友たちを呼んでは、ちょっとした舞踏会が開催されていた最も広い客間が、今は父がひとりで使う書斎兼応接室になっている。書斎は祖父のものが幾らでもあったが、父はそこを使うことを頑なに拒み、部屋の雰囲気には微塵も馴染まない白い化粧板の長机を山ほど運び込んで円卓のように並べている。現場一筋の父は、座る場所にもこだわりがないらしく、学校の教員室から持ってきたような安い椅子に、その大きな臀部をどうにか納めていた。背丈だけなら僕の方が圧倒的に大きかったし、ボディビルがもたらした筋肉の成長は、本気でやり合えば、いくらかはやってやれるのではないかという自信を与えてくれていた。
顔を合わせるなり、その腐った性根を否定するような一言を吐いてやろうと意気込んでいたのだが、客間へ入ってきた僕に気付いた父は、どうしてか口元を緩め、「もう帰ってたのか」と呟いた。この男は僕に避けられているのを知っているはずだったが、あえて知らないふりをして、喜ぶようなさまを見せてきたのだ。たったそれだけのことで、ぶつけようとした憎しみが、あたふたと行き場を失ってしまいそうになる。この部屋をも侵し始めている葉巻の匂いを嗅ぎながら、僕は背筋を伸ばして父を見据えた。
「あの刀をどうしたんですか?」
「刀?」
「祖父の刀です」
振り返ってこちらを見ていた父は、ぎしぎしと椅子を軋ませながら体を動かして、僕の方へ向き直った。背の低さを忘れさせる体積の大きさは、人混みのなかに突っ込んでくる車のような迫力を備えている。歳を経ても尊大な性格は変わらず、むしろ磨きが掛かる一方で、その強引さに舌を巻いた財界人たちから「一番太刀の烏丸」と渾名されていると新聞で読んだことがある。
「部屋の飾り棚にあったのがなくなっていました。どこにやったんですか?」
「どこにやったって……。お前、親に対してその言い方は何だ」
「あの刀は烏丸家の守り神です。あれを守っていくのが僕の役目なんです」
遺言によって、誰が受け継ぐか指定されていれば、こんなことにはならなかったと歯痒くなる。烏丸家の男は短命なのだと、いつだったか祖父が口にしたことがあったが、死ぬ間際まで日課の闊歩を欠かさず、誇り高く生に挑み続けた祖父は、筆を取ってしまったが最後、死の運命を受け入れることになると考えたのかも知れない。浮世離れしていた祖父の、極めて人間らしい側面に思えた。
「勘違いしてるのかも知れんが、この屋敷は、烏丸建設の社長である俺の持ち物だ。土地も屋敷も烏丸家のものではあるが、他所の成金の手に渡りそうになったのを食い止めたのは先代だ。断じて、烏丸誠一郎の働きではない。……つまりだな」
つまりだな、というのは父の口癖だった。自分がこれから口にするのは、天地がひっくり返ったとしても変わることのない決定だと言い聞かせるように、その先を続けるのだ。父がこれを使う時は一切の反論が許されず、母は決まって涙を流していて、祖父は沈痛な面持ちで唇を結んでいた。しかし、今の僕はそうなってはいけない。
「屋敷のなかにあるものは自分のものだから、どうしようと勝手だと?」
「ああ、そうだ。話がそれだけなら、部屋に戻りなさい」
「あの若者に売ったのですか?」
僕がそう切り出すと、父の目付きは途端に険しくなった。口の堅い使用人たちにさえ素性を伏せていたのだから、あの客人との会合は、よほど知られたくない密会だったに違いない。
「……どうだっていいだろう。お前には関係のないことだ」
「関係ありますよ。あれは僕の刀でもあるんです」
「お前の刀?」
語気を強めた父は、長方形の灰皿で休ませていた葉巻に火を点けた。
「おかしなことを言いましたか?」
「お前も親父から聞かされたんだろう? あれをどうやって手に入れたか。病弱な子供を不憫に思って、親が買い与えてくれたものだと。つまりだな、厳密に言えば、あの刀は烏丸家の持ち物ではあっても、烏丸誠一郎のものではない。もし仮に、俺があの刀を売り飛ばしたのだとして、お前が自分こそが正当な持ち主だと思うのなら、買い戻せばいい。……だが、それはできないだろう? お前は一介の学生で、学費さえ自分の力で賄ってはいない。そんな身分の人間に、自分のものという考えなどあってはならないんだよ」
息子との邂逅を喜んでいた笑みは消え失せ、ひとりの経営者として、烏丸道隆は告げていた。痛いところを突かれているだけに、すぐさま反論は思い付かない。父を嫌悪しながらも、その庇護下にあることをよしとしている僕は、どれほど鍛えようとも、肉体の全てが矛盾そのものだった。
「大体、刀なんか持ってどうするんだ。誰か斬りたい奴でもいるのか?」
「そんなわけないでしょう」
「なら、持たなくていいだろう。刀は武器だ。人間を殺すためにある。それを額縁代わりの台に載せて鑑賞しようだなんて、はっきり言って頭がおかしいんだ。親父も、親父のお仲間もどうかしてる。そんなに俺の家に来たいんなら、いい加減拝観料でも払えと言ってやらないとな」
吐き捨てるように言い、父は手元のグラスを呷った。祖父たちは、アメリカ人に頭を下げる機会を得るために日夜奔走し、命乞いのような真似をしてまでも、日本刀を守り抜いた。その献身を、この国の歴史を築き上げてきた僕たちの象徴を、この男は嘲笑ったのだ。したり顔で洋物のウイスキーなんかを飲んでいるこの男は、祖父の息子でもなければ、僕の父親でもないと、自らの出自そのものを否定してしまいたくなる。
背筋に当てられた刀がどれだったのかを言い当てた僕は、かつての父も同じ試練を与えられ、同じように看破してみせたのだと祖父から教えられた。そう語った横顔は誇らしげで、弟を慕い、本当の父親である自分を毛嫌いしている息子に、それでも祖父は、深い慈しみの情を抱いていた。だからこそ僕は、父と僕の間に、血縁という事実以上の何かが存在すると信じたのだ。そして、それは大きな間違いだった。
葉巻の匂いから一刻も早く逃れたくて、僕は足早に客間を出た。怒りに任せて父を殴ったとしたら、それこそ、あの男と同じ穴の狢になってしまう。父は母を殴る。彼女がその目的のためにこの屋敷に飼われているとでも言うかのように、当たり前に殴った。なぜかは分からないが、父は母を殴る時、いつも必ず他所行きの服に着替えさせた。そこには暗黙の了解があり、家に寄った父の機嫌が悪いのを察すると、母は自ら綺麗な服に着替え、しばらく部屋から出ないよう僕に言い付けるのだ。もし父の機嫌を損ねれば、この生活は取り上げられ、僕とともに路頭に迷うことになると分かっているから、母は一切の抵抗を見せなかった。家長である父と対立するというのは、そういうことだった。僕の気紛れで、母が長年耐え続けていた屈辱を台無しにするわけにはいかない。この怒りは、あの刀を取り返すための原動力にしなければならなかった。
しかしながら、何から始めればいいか、皆目見当が付かない。あの若者の手に渡ったことは確実で、刀を入れていたと思しき筒状のケースは父が用意したものだろう。分かっているのはそれだけで、若者の正体は謎に包まれている。父が頑なに口を噤むということは、他所の女に関連する誰かなのかも知れないが、それを確かめる術はなかった。ただ、急がなくては、取り返す機会ごと失ってしまいかねない。
僕は三階に戻り、祖父の私室に置いてある電話機を手に取った。電話帳で番号を調べて「早苗」に掛け、「重森君がいたら呼んで欲しい」と伝える。知恵と力を借りられそうなのは、彼しかいなかった。卓上に飾られていた磁州窯の陶器を眺めながら、トレーニングをする際の呼吸、大きく吸い込んで止め、ゆっくりと吐き出すのを繰り返す。期待に反して、早鐘を打っている心臓が落ち着くことはなかったが、鼻にかかったような低い声が電話口から聞こえてくると、わずかではあるが安堵が訪れた。
「急にすまない。中断させてしまったね?」
〈抜ける口実ができて、むしろ助かった。それで、わざわざ雀荘に掛けてくるなんて、よほど差し迫った事情か?〉
「ああ、そうだ。……そうなんだが、いざ電話してみると、どう説明したものか。君の力を今すぐにでも借りたいと思って、居ても立っても居られずに電話帳を捲って、そこの番号を探したんだよ」
〈おれの力ってことは、金の用立てじゃないってことだけは確かだな〉
僕を解きほぐそうと冗談を口にした重森は、少し思案したのち、南門通りにある喫茶店の名前を告げた。早大生の溜まり場で、「早苗」のすぐそばだ。
〈席は取っておくから、歩きながら話をまとめろよ〉
「そうさせてもらう。恩に着る」
受話器を置いた僕は、着替える必要もなかったので、学生服のまま屋敷を飛び出した。来た道をそのまま引き返して、南門の方へと向かう。緑色のテント看板は通りのなかでも目立っていて、僕は「ぷらんたん」の扉を開ける。二階は満席だったが、運よく窓際の席を確保できたらしい重森が手を振っていた。差し込んでいる明るさに目を細めながら、腰を下ろす。重森は赤星の大瓶を飲んでいて、こちらが訊ねる前に「勝ち逃げしてきたんだ」と自慢げに言った。テーブルには、封の開いていないピースが山積みにされていた。僕はコーヒーを頼んだ。紅茶党の祖父がコーヒーを毛嫌いしていたので、大学に入るまで食わず嫌いならぬ飲まず嫌いしていたのだが、いざ口にしてみたところ、瞬く間に虜になってしまった。店内は学生ばかりで、試験の話や、休みにどこに出掛けるかなどが漏れ聞こえてくる。コーヒーが運ばれてくるのを待っていたようで、重森は煙草に火を点けた。
「それで、首尾よくまとめられたか?」
「とりあえずは順を追って話すよ」
父が我が家に正体不明の若い客人を招いていて、その客人に祖父の愛刀をやってしまった。烏丸家の守り神であるその刀をどうしても取り戻さなければならないが、祖父を軽蔑していた父が、刀のことなどどうでもいいと考えている以上、僕の独力でやるしかない。しかし、ひとりでは何も思い付けず、藁にも縋る思いで重森を頼った。熱を帯びた当事者である僕と、麻雀帰りの重森とでは、どうしても受け取り方に差が出てしまうので、事実だけを述べるのに徹した。重森は腕組みをして、耳を傾けていた。
「これで全部なんだが、分かってもらえたか?」
「ああ。十分だ。……先に訊いておきたいんだが、その若い男っていうのは、おまえの親父さんの隠し子じゃないよな?」
「とんでもないことを言い出すね。確かに父は、どこで妾を作ってるか分かったものじゃないけれど、僕が長男であることだけは確実だよ。あの男はあきらかに僕よりも歳上だったから」
「兄貴がいるだろ?」
「ああ、そうか。でも、ほんの数日違いだし、本妻の息子は僕だからね」
矛盾して聞こえるかも知れないが、兄弟がいるという事実は受け入れられたが、兄がいると考えることは僕には難しかった。家督云々にこだわるつもりはないが、長男は僕だ。そうでなければ、母が報われない。重森は「今のは忘れてくれ」と前置きしたうえで、話を続ける。
「親父さんとその男の関係は分からないが、あげたにせよ、売ったせよ、ふたりの間に合意があったのは間違いない。要は、お互いがすでに、所有権が移っていると考えてるってことだ。取り返すには、おまえが新たにその男と交渉を始めなくてはならない。……はっきり言うが、思っているよりも大変なんじゃないか」
「交渉ということなら、僕にも考えはあるんだ。もしも、あの男が刀剣の愛好家で、何らかの手段で父と知り合って家に来たのなら、まずはあの刀の出自を伝えて、取引をなかったことにしてくれないかと頼むつもりなんだ。愛好家なら、理解してもらえるはずだからね。それでも駄目なら、他の刀と交換する用意があると話す。粟田口久国とはいえ、無銘の刀には違いないから、より客観的な価値の高い刀との交換を申し出れば、考えてくれるはずだ。できれば避けたいけれど、あの刀を失うよりはましだ」
今の僕に思い付ける最善の手だったが、表情を曇らせた重森は即座に「無駄だ」と告げた。
「ふたりは他の刀も手に取っていたんだろう? ということは、その男は、見比べたうえで祖父君の刀を選んでいるんだ。取り替えたり、取引をなしにしてくれなんて言って、素直に従ってくれるとは思えないな」
重森の指摘は僕を驚かせるばかりか、自分の口から倉庫の刀の件を話したにもかかわらず、そのことに思い至らなかった愚かさを恥じさせた。見比べた末というのは事実と判断していいはずだが、なぜあの男は、銘吉光の短刀や銘助真の太刀ではなく、あえて無銘の刀を選んだのだろうか。紛れもない名刀ではあったが、約んだ地鉄や直刃の飾らない刃文は、派手なスーツを着こなしていた彼の好みとは思えない。父は、かつての持ち主であった太田道灌の話をしたのだろうか。もし、それを聞いて選んだのだとすれば、その感性には一目置いてもいい。
「なら、どうすればいい?」
「今は何を考えようとも机上の空論だ。まずは、その男の素性を知らないと」
「それが分かれば苦労しないさ」
「いいや、苦労はいらない。使用人が送り届けたってことは、その人に訊けばヤサは分かる」
ゆっくり味わおうとしていたコーヒーが、つい熱いまま喉を流れ落ちていく。紫煙を燻らせていた重森は、どうということもないという顔で僕を見ている。さっきもそうだが、当事者である僕が見落としてばかりなのは、この状況に前のめりになっているからではなく、純粋に頭の回転が鈍いのだろう。馬鹿にして然るべきなのに、少しもそんな素振りを見せない重森は、これまでに知り合ったどの同級生よりも機知に富んでいて、僕は彼にあらためて敬意を抱いた。
「ありがとう。戻ってきたら、すぐに訊いてみるよ」
「ああ。作戦会議はそのあとの方がいい。難しいとは思うが、今は落ち着いた方がいいぜ」
コップに赤星を注ぎ、重森はぐいと呷った。こちらの気持ちまですっきりとする飲みっぷりだった。用が済むなり帰るというのは、まさしく父のように傲岸不遜な振る舞いで、「もう一本くらい頼もうと思ってたんだが」と打ち明けた重森が、その実、三本目の大瓶を空にするまで付き合った。下宿先では飲酒と喫煙が禁じられているらしく、こうして外で満喫しておく必要があるのだ。親御さんにはレスリング部を辞めたと伝えていないため、しこたま飲むのは麻雀で大勝ちした時だけと決め、援助を打ち切られた時に備えて金を貯めているという。短い間ではあったが親しくなったレスリング部の先輩に紹介されてムスケルアルバイトもやったそうだが、肉体労働はトレーニングへの気力を失わせるため、重森は今、下宿先の娘さんの家庭教師をやっているという。その高給なことに驚いたものの、肝心の娘さんは頭がいいため、いつお役御免になるか分からないそうだ。
「路頭に迷いそうになったら、親父さんの会社で雇ってくれ」
「本気か? 間違いなく父は君を気に入ると思うけど……」
「半分くらいは本気だ。一本でも命綱があると分かれば、安心してふらふらできるからな」
山積みのピースを懐に詰め、重森は立ち上がった。学生たちの朗らかな喧騒を背に階段を下りて、喫茶店をあとにする。重森が「書くものはあるか?」と訊いてきたので首を横に振ると、彼は一旦店内に戻り、ビラか何かの切れ端を持って出てきた。
「下宿先の電話番号だ。念のために渡しておくよ」
急いで書いたにしても読み難く、上の飛び出た0が6なのか否かを訊ねてから切れ端を受け取った。明日は土曜日で、僕は講義を取っていなかった。重森はトレーニング室に行くのかも知れないが、僕は一日おきに体を休めることにしていたから、月曜日までは会うこともない。わずかに陽が傾き始めていたが、隣を歩く重森の顔は、夜を先取りしたような赤みを帯びてい
た。
3
東京に生まれて十八年も経つというのに、渋谷を訪れるのは初めてだった。東京を隅から隅まで知り尽くしていた祖父の闊歩には、当然ながら渋谷を巡るコースもあったようだが、僕の方に縁がなかったらしく、それを引き当てたことは一度もなかったのだ。
普段よりも早く起きた僕は、昨日あの男を車で送った使用人に声を掛け、「どこで降ろしたか覚えていますか?」と訊ねた。いかにも判然としない様子だったので、「あの人に渡せと言われたものがあったのだが、忘れていた。このままでは父に怒られてしまうから、こっそり送って欲しい」と付け加えたところ、使用人は心得たとばかりに頷き、「急いで用事を片付けるので、お部屋でお待ちください」と承諾してくれた。父の怒りの激しさを知らない者は、この屋敷にはいなかった。
幸い父は家におらず、今日は車が使われる予定もなかったようなので、使用人は僕の学用品を買いに行くという名目で車を出してくれた。嘘を吐くのは心苦しかったが、背に腹は代えられず、刀を取り戻したら一切合切正直に打ち明けようと決めた。
学習院大学の方へと出て、明治通りをひたすらに南下する。新宿御苑と明治神宮、静かな緑
地を過ぎると、途端に街並みが猥雑さを醸し始める。
「この辺りにはお詳しいですか?」
「誠二郎様と道隆様の送迎で、こうして賑わうようになる前の寂しい時代から幾度となく来ております」
誠二郎は祖父の弟で、烏丸組の創始者だ。ふたりで来ていたということは仕事絡みだろう。関東大震災のあとで、青山と代官山に耐震構造の優れたアパートメントが建てられたが、あれに携わったのが父たちだということは、関心を欠落させようと努めている僕でも知っていた。
「彼とはどんな話をしましたか?」
「彼?」
「送って差し上げた方ですよ」
渡すように頼まれたと言っておきながら、相手の名前も知らないというのは不自然極まりなかったが、分からないものは仕様がない。
「それが、とても無口な方で、これと言って何も話しておりません」
「冷たい人でしたか?」
「いえ、物腰は丁寧でしたよ。考え事をしているようでしたので、邪魔しないようにと思ったのです」
他人の車で運ばれている時、大抵の人間は寡黙になるし、礼儀正しく振る舞わない方がよほど難しい。つまりは、使用人の話は、男について考えるうえで何の役にも立たなかった。
渋谷の駅前を過ぎて、井ノ頭通りを進んでいく。こちらは何もしていないのに、わざわざ近寄ってきて「通行の邪魔だ」とばかりに車を睨んでくる男が何人かいた。使用人は彼らを刺激しないよう巧みに無視しながら、ここが宇田川町で、この先にある建物の前であの男を降ろしたのだと説明してくれた。
「そこで停めていただけますか?」
「承知しました。車通りも多くはありませんし、私は下で待っております」
「場所が分かったので、もう大丈夫ですよ。子供じゃあるまいし、ひとりで帰れます」
バックミラーに目を遣った使用人は、細長い鏡越しに、僕と視線を合わせるべく躍起になっていた。そして、こちらにその意思がないのを悟ると、ややきつい声で「渋谷は治安がいい街ではありませんから、坊ちゃんを置いていくわけにはいきません」と言った。
「心配し過ぎですよ。背だけは高いもんで、学生だからと絡まれたりはしないはずです」
「だからこそ、生意気だと因縁をつけられるかも知れないでしょう」
どうやら彼は、本当に僕を待つ気でいるらしい。昨日ここで降りたからといって、あの男が今日もここにいるとは限らなかったし、仮にいてくれたとして、話がどう転がるかも分からない。万が一、こっぴどく決裂することがあれば、近くにいる使用人にその様子を見聞きされるかも知れない。屋敷にいる使用人は皆、名目上は烏丸家に仕えているが、祖父が亡き今は、我が家の当主も、彼らに給料を支払っているのも父で、実質的には父の使用人と呼んで差し支えなかった。使用人が知り得る僕の情報は、今回のような場合を除いて、ほとんどが父に筒抜けのはずで、僕が刀を取り返そうとしていると知れば、あの男は阻止に打って出るだろう。
「……ひとりじゃなければ大丈夫ですか?」
ふと思いつくことがあってそう切り出した僕は、「用事を済ませたら、友人と遊んでいこうかと思っていたんです。彼と一緒なら、待っている必要はないでしょう」と続けた。
「ご友人と言っても、その方も学生でしょう?」
「レスリング部で、元国体選手を投げ飛ばして肩を脱臼させた猛者です」
重森はすでに退部していたし、元国体選手というのは監督の村松さんのことだが、少なくとも事実しか口にしていない。ボディビルを始めたとはいえ、烏丸家の使用人たちにとっては、僕はいつまで経ってもひ弱な丙種で、逞しい友人が隣にいれば安心してくれるはずだった。
「どこかで待ち合わせなさっているのですか?」
「いや、下宿先の電話番号を聞いているから、喫茶店かどこかから掛けようと思っていました」
「では、私がお迎えに向かいます。ここまでお連れするので、そうしたら、おふたりで遊びに行かれるとよいでしょう」
彼なりの折衷案らしかったが、当の本人が今下宿にいるか保証はない。もっとも、迎えにいってくれている間は、何が起きようとも、その顛末を見られずに済む。その間に交渉を済ませてしまえばいいのだと考え、僕は使用人に重森の下宿先の住所を教えた。「武陽興業株式会社」と看板が出ているビルの前で車は停まり、職業的な俊敏さで僕よりも先に降りた使用人が車のドアを開けてくれた。渋谷は危ないというが、この光景を見られる方がよほど危ないはずだ。
「ああ、そうだ。ひとつだけ覚えていることがございます。あの方はソフト帽をお持ちだったのですが、被らずに脇に置いていたのです。舶来品とお見受けする素晴らしい品でしたので、『素敵な帽子ですね』とお声を掛けましたところ、彼は『蓑よりかは、雨を凌ぐのにちょうどいい』とおっしゃいました。あれは、どういう意味だったのでしょうか」
僕にもさっぱりだったが、使用人はその共通点を喜ぶように微笑み、一礼してから車に乗り込んだ。ここから下宿のある西早稲田までは、車なら片道二十分も掛からない。勇ましさではなく、急がなくてはという焦りによって、僕はビルの扉を開けた。窓のない暗い階段を上っていくと、三階にあった一室に、表から見えるのと同じ金文字の看板が出ていた。入り口をノックし、背筋を伸ばして待っていると、少しだけ開いたドアの隙間から男が顔を覗かせた。スポーツ刈りで、柄物のシャツの上からブルーのスーツを着ている。
「どちら様で?」
「急に訪ねてきてすみません。僕は烏丸道隆の使いの者です」
「烏丸? 烏丸建設の?」
「ええ。昨日、こちらの方がうちにおいでになりましたよね? その時に、伝えそびれてしまったことがあるようでして、それをお伝えに参りました」
「へえ。わざわざどうも。で、何を伝えれば?」
スポーツ刈りの男は、頭ふたつ分は下から僕の目をじっと見つめている。目や鼻、顔、体付き、どれを取っても丸っこく、子供の頃が容易に想像できるような外見だったが、喉を使い古したように掠れた声を聞いただけで、その内面に一切の愛嬌が備わっていないのを予感できた。僕が嘘を吐いていると判断すれば、容赦無く追い返されてしまうはずだ。
「直接お話しするよう烏丸道隆から言われているんです」
「誰に?」
「急いでいたので、お名前は伺っておりません。行けば向こうが分かるだろう、と」
ドアが閉められる音が存外に大きく、つい身震いしてしまった。怪しまれるのは当然だが、今の僕に、あの若い男の名前を知る手立てはなかったのだ。手立てのみならず、場合によってはもっと重要な勇ましさすらも持ってこなかったのだが、ここですっぱりと帰るような潔さもなく、消極的に、何かが起きることを祈りながら立ち尽くしていた。
せめて、もう一度くらいノックすべきかどうかと悩んでいた僕は、今度はゆっくりと開いていった黒みがかった茶色のドアの向こう側に、あの男の姿を認めた。屋敷の前にいた時は細部まで観察できず、人相は曖昧だったが、特徴的なグレーのスーツと黒いネクタイは、昨日見たものとまったく同じだった。外国人のように鼻が高く精悍な顔付きで、青年将校のような凜々しさを纏いながらも、どこか女性的な印象を受けたのは、目元に品があったからだろう。僕よりは低いものの、それでも背は高く、突き合わせている顔に続いて、ドアノブを握っている彼の手の厚みに目が行った。何かの拍子に重森が、「漁師の息子とは喧嘩するな」と言っていたのを思い出す。物心ついた頃から網を引っ張っているので、手の筋肉が発達し、掴むのも殴るのも人一倍強いのだそうだ。それは機械的な運動によって鍛えたのではない、大自然に磨かれたタフネスであり、男の手には、その類の力強さが漲っていた。
「烏丸道隆の使い?」
「はい。先日は挨拶もせずに失礼致しました」
「会っていたかな?」
「屋敷から出ていかれる時にすれ違っていました」
「覚えがないな。申し訳ない」
目元から連想される通りの、やや高い声だった。男は疑う様子もなく、僕を室内へと招き入れてくれた。床には緑色の絨毯が敷き詰められ、充満している煙草の匂いも相まって、会社のオフィスというよりも邸宅の喫煙室のような雰囲気だった。並んでいる机こそスチール製だが、卓上ランプやガラス細工のような調度品が置かれ、壁際の書棚も本で埋まっている。スポーツ刈りを含めた四人の男が椅子に腰掛けていて、熱心な様子で帳簿か何かにペンを走らせている。三十を越える者はいないようで、全員が似通った青色のスーツを着ていた。たいした興味もないのか、彼らは僕を一瞥さえしなかった。
男はつかつかと歩き進み、隣の部屋に続いているドアを開けた。そちらは応接室のようで、黒い革張りのソファ二台がローテーブルを挟んでいる。
「座ってくれ。何か飲むかい?」
「いえ、お気遣いなく」
「烏丸道隆の使いに何も出さなかったんじゃ、礼儀知らずの誹りを受けてしまうよ」
冗談めかした口調で言い、男は壁際のキャビネットに向かっていく。戸棚にはステンドグラスが使われ、抽斗の取手には、凝った形をした真鍮の飾りがあしらわれている。おそらくはイタリア製で、祖父の好みではなかったが、趣味のいい家具に違いなかった。
「まったく、空にした瓶をそのままにするなと言っておいたのに。向こうの部屋から取ってくるから、少し待っていてくれるかな」
問い掛けながらも反応は待たず、男はドアを開けっ放しにして、応接室から出て行ってしまった。窓はひとつだけで、昼間なのにカーテンは閉め切られていたから、室内を照らしているのは柔らかい光を落とす電球が四つも五つも付いたシャンデリアだった。白壁には印象派の画風と思しき風景画が飾られている。セザンヌのようだが、複製だろう。来客の目を楽しませることにこだわりがあるなら、あの刀も飾られているのではないかという期待を持ったが、刀掛けやその代わりになりそうな台座は見当たらなかった。
足音に振り返ると、向こうの部屋で椅子に腰掛けていた男がふたりいて、さながら宝蔵門の仁王像のようにドアの左右に立つなり、カーテンの方に顔を向け、気を著けの姿勢をとった。僕を驚かせたことに対する詫びのひとつもなく、そんな男たちが背後にいるのが不気味で、むしろこちらから「ここは一体何の会社なんですか?」と訊ねてみたが、ふたりとも、平然と僕を無視してみせた。ぞわぞわとした不快さを背中に感じながらも、振り返るのをやめて座り直し、こんなことならビルの前で張り込んで出てくるのを待てばよかったと後悔し始めた頃、戻ってきた男が向かいに腰を下ろした。足の付いたグラスと酒瓶を持っていた。
「スペイン人は朝から飲むそうだ。勤め人はこうはいかないね」
男は二脚のグラスを満たしながら、その酒がシェリーという名前だと教えてくれた。重森に付き合ってビールを飲んだことはあるが、僕はまだあの苦さを、苦さ以上の豊かな味わいとして感じ取れはしなかった。漂う匂いからして苦い酒ではなさそうだが、退廃とは無縁の僕は、飲酒への欲求も、そこで得られるという快楽にも、いまいちぴんと来なかった。
(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)
書誌情報

書名:飽くなき地景
著者:荻堂 顕
発売日:2024年10月02日
ISBNコード:9784041150672
定価:2,145円(本体1,950円+税)
ページ数:384ページ
判型:四六判
発行:KADOKAWA
★全国の書店で好評発売中!
★ネット書店・電子書籍ストアでも取り扱い中!
Amazon
楽天ブックス
電子書籍ストアBOOK☆WALKER
※取り扱い状況は店舗により異なります。ご了承ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
