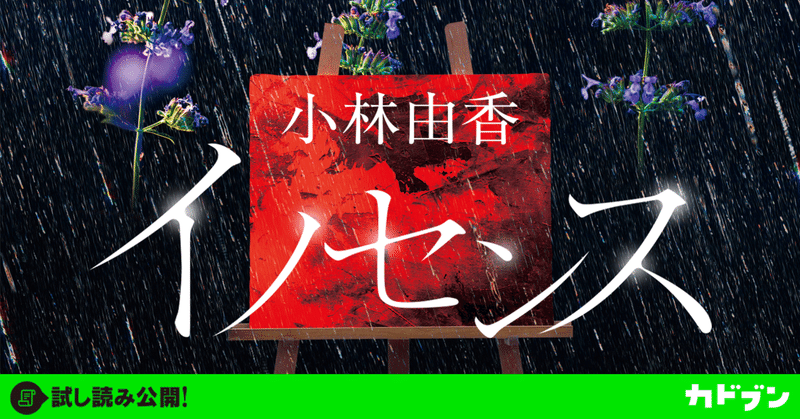
電車に飛び込むなら、夜にやってよ。朝やられると迷惑なんだ/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#1
連載中から賛否両論の嵐。
小林由香『イノセンス』期間限定「ほぼ全文試し読み!」
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、このたびnote上でほぼ全文試し読みを行います。
あなたは、主人公の取った行動は許されると思いますか?
2020年最大の問題作をお見逃しなく!
1
文庫本を開いた瞬間、あっ、という間抜けな声が口からもれた。
まるで押し花のようだった。黄色と黒の縞模様の大きなジョロウグモが紙にべったりと貼りついている。潰されたときに体液や内臓が飛び散ったのか、ジョロウグモの周りは薄汚れていた。
窓から射し込む陽光を浴びながら、音海星吾は震える指でページをめくっていく。頭の中で警報がわんわん鳴り響いているのに、めくる手を抑えられなかった。
潰された虫が怖いんじゃない。恐ろしいのは、誰かの悪意だ。
静かに、赤く揺れる文字。視界がゆっくりぼやけていく。
オマエニコロサレタ
ヒトゴロシハシネシネシネシネシネシネシネシネシネ――。
なにも印字されていないページに、鮮やかな真紅の文字が執拗に書き連ねてある。
筆跡を隠したいのか、文字のサイズは大小ばらばらでひどく拙かった。文末には『2月9日月野木』という暗号めいた言葉が記されている。
涙をこぼしたかのように、ところどころインクが滲んでいるため、真っ赤な血が飛び散っているように映った。
不穏な『シネ』という言葉が胸に染み込み、心の奥深くまで侵食していく。軽い目眩を起こしそうになり、両足に力を込めた。
一度大きなミスをした人間は、死ぬまで許されないのだろうか――。
この類の嫌がらせには慣れているつもりだったのに、手がじっとりと汗ばんでくる。
今朝、部屋の空気を入れ替えようと思い立ち、窓を開けるとベランダに新品同様の文庫本が転がっていた。
タイトルは『罪の果て』。十年ほど前に出版されたミステリ小説で、ドラマ化・映画化されている人気作品だ。父が原作のファンだったので、星吾も中学二年のときに読んだ覚えがあった。
文庫本の表紙には真っ白な傘が描かれ、それを汚すように赤い雨が降り注いでいる。地面に広がる赤い水を眺めていると血溜まりを連想してしまい、慌てて視線をそらした。
胸騒ぎがして、窓の外を慎重に確認してみたが、狭い庭には潰れた空のペットボトルが転がっているだけで、どこにも不審な人物は見当たらなかった。
窓を閉めて鍵をかけると、深く息を吸い込んで呼吸を整えた。心を鎮めてから半年前の記憶をたどってみる。
一度だけ鞄の中に脅迫文が入れられていたことがあった。暗号めいた言葉はなかったが、真紅の文字、カタカナ表記だったのを思い返すと、犯人は同一人物かもしれない。当時は、電車、大学の構内、バイト先のどこかで入れられたのだろうと軽く考えていた。けれど、今回はより悪質だ。犯人は住居を特定していることを知らせたくて、ご丁寧にもベランダに投げ込んだのだ。
昨日、バイトを終えて帰宅したのは夜の十一時。そのときすでにベランダに投げ込まれていたのだろうか。もしかしたら、深夜、在宅しているときにやられた可能性も捨てきれない。
思いだしたくもない『罪の果て』の内容が脳裏に浮かんできて、胸に疼くような痛みを覚えた。物語の概要は、三人の男たちが金ほしさからある青年を殺害し、被害者の父親に復讐されるという話だった。ひとり目の加害者の男は、マンションの建設現場から落下してきた鉄パイプの下敷きになり、ふたり目は車道に突き飛ばされ、三人目はナイフで刺されて殺害された。たしか、復讐を終えた父親がたどり着いた罪の果ては、哀しい結末だったはずだ。ずいぶん前に読んだので記憶が曖昧ではっきり思い起こせなかった。
星吾は怒りにまかせて文庫本をゴミ箱の中に叩きつけた。けれど、乱れた心は正常に戻ってくれない。
ミステリを楽しめるのは、自分が安全な場所にいるときだけだ。
ふと、背後に人の気配を感じて振り返った。
ゆっくり室内を見回してみたが、特に変わった様子はなく、殺風景な部屋はしんと息を潜めている。
部屋にあるテレビやパソコンのモニターには、黒い布が掛けられていた。それらを横目で見ながら部屋を出ると洗面台の前に立った。目を伏せて歯ブラシをつかみ、歯磨き粉を素早くつける。どくどくと鼓動が速まっていくのを感じた。
不穏な出来事が起きると、鏡を見るのが怖くなる。
あの男があらわれるようになったのは、十六歳の秋――。
男は殺害されたのに、いまだに鏡の中に姿を見せる。電源を落としたあとのテレビやパソコンのモニターに、ほんの一瞬だけ映り込むときもあった。
青白い顔の亡者は、いつも右目を大きく見開き、左目を怪しく細めている。
頭がおかしい、と人は言うかもしれない。けれど、微かに腐敗臭が立ち込め、静かな息遣いが近づいてくるのを感じるのだ。冷たい手で心をそっとつかみ、恐怖心を植えつけていく。
泣きながら謝り続けても、あの男にはどのような言葉も届かない。なにを望んでいるか尋ねても返答はなく、薄い笑みをこぼすだけだった。
アパートを出て空を振り仰ぐと、先刻とは打って変わり、低い灰色の雲が垂れ込めていた。梅雨どきの湿気を含んだ空気が身体にまとわりついてきて陰鬱な気分になる。
星吾は微かな苛立ちを覚えながら、大通り沿いの歩道を歩き始めた。
大型トラックの走行音、遠くで響くクラクション、頭上で旋回するカラスの鳴き声、そのすべてが耳障りで鬱陶しくてしかたなかった。
気を抜くと、瞼の裏に『シネ』という真紅の文字がちらついてしまう。
排ガスを含んだ生暖かい風に頬をなぶられ、鼻を歪めた。不快な出来事に遭遇すると、五感が過剰なまでに敏感になってしまう。
こめかみを指で押さえ、どんどん歩調を速めていき、鈍行しか停まらない小さな駅に素早く駆け込んだ。朝の通勤ラッシュの時間帯はすでに過ぎていたため、乗客の姿は少なく、構内は廃駅のように閑散としていた。
鞄から定期券を取りだして改札を抜け、長い階段を下りてホームに出る。曇り空のせいで普段よりも辺りが薄暗く感じられた。心なしか空気も澱んでいる。
いつも乗車する位置まで向かう途中、ふいに視界の端になにか白いものを捉えた。
反射的に視線を移すと、一羽の鳩が舞い降りてくる。一度も傷つけられた経験がないのか、鳩はずいぶん人馴れしている様子で横切っていく。その姿を目で追っていると、ホームの端に奇妙な男が立っているのに気づいた。
年齢は四十代後半くらいで、皺の目立つ灰色のスーツを着ている。肌は驚くほど白く、頬はげっそりとこけ、脂じみた髪がべったりと頭皮に張りついていた。まるで魂が抜けたような顔つきで、身体を少しだけ前後にゆらゆら揺らしている。
一瞬、目を疑った。
色白の男が肩を震わせ、涙を拭うような仕草をしたのだ。
背筋がひやりと冷たくなったとき、静まり返ったホームに急行電車が通過するアナウンスが流れてきた。
泣き顔から一変、色白の男は顔をくしゃくしゃにして笑った。まるで知り合いに挨拶するように、少しだけ右手を挙げている。
反射的に彼の視線の先をたどってみたが、向かいのホームには誰もいない。存在しない相手に笑いかけている姿を見て、ぞっとした。
威圧的な轟音と共に電車が近づいてくる。
その場から遠ざかりたいのに、身体がいうことをきいてくれなかった。
すぐそこまで電車が来ているのに、色白の男はじりじりとホームの際に近づいていく。放心したような顔つきで、靴裏を擦りつけるようにして前へ前へと足を動かしている。まるで誰かに操られているようだった。
次の瞬間、意に反して足は駆けだしていた。
ぞっとするほど細い腕――。気づけば、色白の男が線路に飛び込もうとしたとき、星吾は彼の腕をつかんでいた。男は人形のように抵抗しなかったため、強く引いた勢いで自分もろともホームに倒れ込んでしまった。
顔を上げると、電車が警笛を鳴らし、すぐ目の前を通過していく。
耳を聾する音に心臓が縮み上がり、先ほどまでの焦燥は恐怖に転じた。体温が一気に下がり、血の気が引いていく。速まる鼓動がうるさくて、外界の音が聞こえなくなる。
電車が通過するまで、倒れたまま立ち上がることさえできなかった。
轟音が消える頃、星吾は右腕に鈍い痛みを感じた。目をやると、皮が剥けて血が滲んでいる。傷は浅いが、手首から肘まで派手に擦りむいていた。
「なんの恨みがあって……どうして……どうして」
呪文のような言葉が耳に飛び込んできて顔を上げると、色白の男はこちらを睨みながら「どうして、なんで、邪魔をする」と繰り返しつぶやいている。
彼は全力で声を張り上げているようだが、かすれていて聞きづらかった。目に憎しみの色を滲ませ、血色の悪い唇をわなわな震わせている。
「どうして……どうして俺の邪魔をした」
勘違いしている男の姿を目にした途端、腹の底から激しい怒りが込み上げてきた。
「迷惑なんだよ」
星吾は立ち上がると、苛立ちを抑えられず、吐き捨てるように言葉を継いだ。「そんなに死にたいなら、夜にやってよ。朝やられると迷惑なんだ」
色白の男は一瞬だけ虚を衝かれたような表情を見せたが、しばらくすると頬を引きつらせて忍び笑いをもらした。
「朝は迷惑……そうか……朝は……迷惑……」
男は自分に言い聞かすようにゆっくり声をだした。人間ではなく、まるで壊れかけのヒューマノイドのようだ。
相手をするのも面倒になり、駅員が来てくれるのを期待して周辺に目を走らせると、近くに花束を抱えたひとりの女が立っているのに気づいた。
駆け寄って来る女の長い髪から、ふわりと甘い匂いが漂ってくる。奇妙な感覚に囚われた。どこかで会ったことがあるような気がしたのだ。
同じ大学の学生だろうか――。
大学二年の星吾と歳はそう変わらないように見えた。薄化粧で地味だが、美しく整った顔をしている。黒いワンピースや胸に抱えている白百合の花束が、暗く不穏なものを連想させた。
女は優しい声音で「大丈夫ですか?」と色白の男に声をかけている。
足音がして顔を上げると、通報があったのか、慌てた様子で若い駅員がこちらに駆けてくる姿が目に入った。
近寄ってきた駅員が「どうされましたか?」と尋ねると、色白の男は弱々しい声で「すみません。目眩がしただけです」と嘯き、緩慢な動きで立ち上がった。そのまま、今にも倒れそうなおぼつかない足取りで改札に続く階段に向かっていく。
駅員はこちらに軽く頭を下げると、すぐにあとを追いかけ、男の顔を覗き込むようにしてしきりに声をかけていた。
「夜なら死んでもいいの?」
今度は女が敵意のこもった視線を向けてくる。
星吾は笑いそうになった。
人身事故で長時間電車が止まれば、苛立つ乗客は多い。中には駅員に悪態をつく者もいるというのに、当人を目の前にしたら優しい言葉をかけろというのだろうか。
女の問いかけを無視して、星吾はホームを歩き始めたが、すぐに足を止めた。
背後から「今日の夜、あの人が自殺したらどうする?」という言葉を投げかけられたのだ。その声には上辺だけで心配している人間とは違う怒りに満ちた響きがあり、今にも泣きだしそうに震えていた。
思わず振り返ると、女は薄い唇を引きしめ、真っ赤な瞳でこちらを睨みつけてくる。
他人のことなのに、なにを熱くなっているのだろう――。
内心で舌打ちすると、強い反発心が湧いてきた。
もしも同じ大学の学生なら、悪い噂を流される可能性もある。星吾は白けた気持ちを押し隠しながら、どうにか言葉を吐きだした。
「僕が止めなければ彼は死ぬはずだったんだ。その後の人生は、彼自身が決めることだよ」
一瞬、女の目に増悪の火が灯った。
「それなら、なぜ助けたの」
「遅刻したくなかっただけ」
「自分にメリットがなければ人なんて助けないってこと?」
胸の奥で複雑な感情が芽生えた。いつものように薄笑いを浮かべて流すことができなかった。
女の瞳にうっすら涙が溜まっていたのだ。
色白の男となにか深い関係があるのだろうか――。
なぜこんなにも執着するのか理由が気になったが、もうこれ以上空疎な会話を続けたくないという感情が勝った。都合よく、「黄色い線の内側にお下がりください」というアナウンスが流れ、ホームに電車が滑り込んでくる。
星吾は薄気味悪い女から一刻も早く離れたくて、急ぎ足で車内に駆け込んだ。
空いている座席に腰を下ろし、なにげなさを装いながら周囲に目を走らせた。けれど、車内にもホームにも、どこにも女の姿は見当たらない。冷房がききすぎているのか、少し肌寒さを感じた。
奇妙な夢を見ているような気分だった。
正面の車窓に目を向けると、ジュエリーブランドの巨大な広告が視界に入る。森の中にいるふたりの子どもたち。少年が少女の小さな手を取り、指輪をはめようとしている。店名だろうか、上部にはシルバーの文字で『エバーグリーン』と書いてあった。
突然激しい頭痛に襲われ、星吾はこめかみを指で強く押さえた。
虫が蠢くようなごぼごぼという低い音が響いた直後、高音のキーンという耳鳴りがしてくる。
目の前の景色が歪み、強い息苦しさを覚えた。
首筋の毛が逆立ち、全身が硬直する。
一瞬だが、車窓にあの男があらわれたのだ。
すぐに顔を伏せる。時折、この症状に襲われて苦しんできた。理性で押し込めていた憎しみが今にも爆発しそうになり、慌てて鞄の外ポケットに手を突っ込んだ。瞼を閉じて、お守りを強く握りしめる。冷たい金属の感触が手に広がっていく。社寺では手に入らない大切なものだ。
お守りが熱を持つ頃、緩慢な動きで顔を上げると、そこには亡者の姿はなく、見慣れた景色が広がっているだけだった。
さっきまでは肌寒かったのに、気づけば全身が汗まみれになっている。
ガタンとドアが閉まり、電車はゆっくり動きだした。
氷室慶一郎――。
あの男はもうこの世にはいないのに、いまだに深い憎しみを消せないでいた。
世間の人々は、氷室をヒーローと崇める。けれど、星吾にとっては憎悪の対象以外のなにものでもなかった。
なぜあの日、あの男に出会う運命だったのか、その意味を繰り返し考え続けた。どれだけ考えても答えなんて見つからないのに思考するのをやめられず、最後は決まって運の悪さに泣きたくなる。
あの事件が起きたのは、数ヵ月後に高校受験を控えた十四歳の秋だった。
学校が休みだった土曜、進学予備校に行くと、掲示板には模擬試験の案内に交じって『恐喝犯に注意!』と書かれた紙が貼りだされていた。
予備校の近くの繁華街でカツアゲが横行しているという。
講師や職員たちは、「帰りが遅くなるときは気をつけるように」と呼びかけていた。けれど、生徒たちは、中学生の所持金なんてたかが知れているから、犯人のターゲットにはならないだろうと気にも留めていなかった。
模擬試験を受けたあと、星吾はしばらく自習室で勉強してからエレベーターでエントランスホールに降りた。腕時計の針は、午後五時を指していたのを覚えている。
予備校の外に出ると、いつもより人通りが少なかった。
その日は大型で強い台風が接近していたのだ。
台風の到来は予想されていた時刻よりも、かなり早かった。周囲の木々は強風に煽られ、目の前を壊れた傘が横切っていく。
生暖かい風に誘われて天を仰ぐと、鉛色の分厚い雲が激しくうねりながら動いていた。不気味な空模様に不安を掻き立てられ、心細くなった星吾は駅に続く道を足早に歩き始めた。
電車は問題なく動いているだろうか――。
運行状況を確かめるため、鞄からスマホを取りだそうとしたとき、右腕に強い衝撃を受けた。
それは一瞬の出来事だった。
背後から誰かに腕を強くつかまれ、あっと思ったときには路地裏のポリバケツに向かって投げ飛ばされていた。膝を強く打ったせいで、うまく立てない。生ゴミの異臭が鼻を衝く。慌てて口もとを手で覆いながら顔を上げた。
異様な光景に、ごくりと唾を飲み込んだ。
目の前には、人のよさそうな笑みを浮かべた三人の男たちが立っていたのだ。
ひとりはジャケットにジーンズ姿の浅黒い男。後方には、首にイーグルのタトゥーを入れている怪しげな人物。その隣には、髪をヴァイオレットピンクに染めた中性的な雰囲気の男がいた。
自分の置かれている立場がまったく把握できず、彼らの姿を呆然と見上げていると、タトゥーの男が狡猾そうな微笑を湛えながら近寄ってきた。彼は友だちに話しかけるような軽い口調で「早く財布だして」と、当たり前のように指示してくる。
咄嗟に、予備校で目にした『恐喝犯に注意!』という警告文が脳裏をかすめた。心臓が波打つたび、地面が揺れているような錯覚がして気分が悪くなってくる。
浅黒い男はポケットから折りたたみナイフを取りだし、慣れた手つきでカチリと刃を立て、奇妙なリズムでゆらゆら揺らした。まるで催眠術の振り子のようだった。恐怖を植えつけるようにじっくり見せつけてから、またポケットに戻し、彼は静かに唇の端を吊り上げた。
星吾は今まで暴力的な事件に巻き込まれたことも、殴り合いの喧嘩をした経験もなかった。どう考えても勝ち目はなく、抵抗しても負けるのは目に見えている。しかも相手は凶器を持っているのだ。講師たちの警告にちゃんと耳を傾けるべきだった。強い後悔が押し寄せてきて泣きたくなる。
震える手で鞄を探り、急いで財布を取りだそうとしたとき、大通りのほうからひとりの青年が駆け込んでくる姿が見えた。
「お前らなにやってるんだよ」
それが、氷室慶一郎だった。
彼は白いシャツが似合う颯爽とした雰囲気の人物で、敵は三人もいるのに胸を張り、精悍な顔つきで腰に手を当てていた。まるで体育教師が素行不良の生徒を叱責するような姿だった。
氷室が堂々たる態度で「子どもから金を巻き上げるなんて最低だぞ」と言い放つと、男たちの表情が明らかに険しくなっていくのがわかった。
張りつめた空気の中、星吾は三人の男たちと青年の姿を交互に見やった。
動揺しているのに気づいたのか、氷室はこちらに顔を向けると表情を和らげて微笑んでみせた。彼の鷹揚な態度が、焦燥感をいっそう掻き立てる。
あいつらはナイフを持っている――。
早く伝えなければいけないのに怖くて言葉にできなかった。余計なことを告げれば、犯人を逆上させて自分が刺されるかもしれない。
星吾が鞄の中から財布を取りだし、彼らに金を渡そうとした瞬間、氷室がそれを制した。
「やりたくないことを強要されて、それに従う必要はない」
「あんまりナメないほうがいいよ。俺、前にひとり殺しちゃってるから」
浅黒い男が自慢げに言うと、氷室は毅然とした態度で返した。
「やろうと思えば小学生でも人を殺せる」
「はぁ?」浅黒い男の目が鋭くなる。
「欲にまみれて人を傷つけるのも、人を殺すのも簡単なんだよ。誰にでもできる。だけど、やられた人間には深い傷が残る。それは簡単には消せない。もうすぐ警察が来るから、この子を傷つけるな」
男たちは頬に笑みをのせたまま、青年を取り囲んだ。三人とも目は笑っていなかった。
「俺ら警察なんて怖くないんだけど」
浅黒い男の言葉に賛同するように、タトゥーが口を開いた。
「こいつナメてるみたいだから証明してやればいいんじゃない?」
タトゥーは舌打ちしたあと、首をポキポキ鳴らした。
それが合図だったかのように、彼らは激しい暴力をふるい始めた。
氷室は初めのうちこそ反撃し抵抗していたが、地面に倒されたのを機に、暴力は勢いを増していった。
本気の暴力を目の当たりにし、星吾は死というものを初めて身近に感じた。恐怖で身が固まり、震えながら残虐な暴行現場を見ていることしかできなかった。
氷室は幾度も全身を蹴られ、顔の骨が砕けるほどの強さで踏みつけられて口の中が血でいっぱいになっている。なにか話そうとしているが、はっきり言葉にならないようだった。
あんなひどい暴行を受けたら後遺症が残り、今後の生活に支障をきたすおそれもある。どうして警察は助けに来てくれないのだろう。
次は自分がやられるかもしれない――。
僕は悪くない。最初から金を渡して助けてもらえばよかったんだ。財布には二千円くらいしかないはずだ。勝ち目のない正義をふりかざす意味なんてない。
ここからすぐに逃げだしたい――。
星吾がゆっくり後退りすると、犯人のひとりに気づかれた。
もう終わりだと思った。そのとき、こちらに向かってこようとする浅黒い男の足を、氷室が両手でつかんだ。急に足をつかまれた浅黒い男が前のめりに倒れると、残りのふたりの男たちが氷室を蹴り始めた。その隙に、星吾は逃げるように全力で駆けだしたが、大通りに出たところでバランスを崩して転倒してしまった。
痛みを堪えながら顔を上げると、街路樹が強風に煽られて倒れそうになっている。まるで絶滅した世界のように、まったく人の気配が感じられなかった。
震える足に力を込めて起き上がったとき、短いうめき声が響いた。
星吾が怯えながら振り返ると、すぐ後ろにいるヴァイオレットピンクの男と視線がぶつかった。自分を捕らえに来たのかと思ったが、なぜか彼は青白い顔で唇をぶるぶる震わせている。
嫌な予感がして路地を見やると、タトゥーと浅黒い男もこちらに向かって走ってくる姿が見えた。反射的に身構えると、浅黒い男は興奮した口調で「テメェが逃げだしたせいだからな。逃げたお前も同罪だ。俺らのこと誰かに話したら殺すぞ」と言い残して走り去っていった。
星吾はなにが起きたのかわからず、駆けていく男たちの姿を呆然と眺めていた。ゆっくり首を巡らし、路地のほうを凝視すると、青年が倒れている姿が目に飛び込んでくる。
辺りは薄暗く、不穏な空気が漂っていた。
星吾は路地に足を踏み入れ、倒れている氷室の近くに駆け寄った。
腹からなにか鉄のようなものが突き出ている。それがナイフだと気づくまでに数秒かかった。
氷室は右目だけを見開き、口を微かに動かしている。仰向けになった腹から真紅の血があふれ、あっという間に白いシャツを染めていく。
星吾はあまりの恐怖に腰が抜け、その場にしゃがみ込んでいた。声をだそうとするも、首を絞めつけられるような息苦しさに襲われ、叫ぶことさえできない。
どろりとした血溜まりが、地面にじわじわと広がっていく。
耳の奥から心臓を打つ音だけが響いていた。気持ちばかりが焦るが、身体の自由がきかない。
そこからの記憶は明確に思いだすことができず、曖昧だった。気づけば、土砂降りの雨に打たれていた。
どうして……警察は助けに来てくれないのだろう。
星吾は震える手で鞄をつかむと、スマホを取りだそうとして動きを止めた。
浅黒い男の声がよみがえってくる。
――テメェが逃げだしたせいだからな。逃げたお前も同罪だ。
テメェが逃げだしたせい? 同罪?
自分が逃げだしたとき、男の足をつかんだせいで怒りを買い、あの人は刺されてしまったのかもしれない。もしそうだとしたら、僕もなにかの罪に問われるのだろうか――。
星吾は三者面談のとき、部活動も積極的に行い、成績や授業態度もよく、県内でも屈指の名門私立高校に学校推薦で受験ができると言われた。第一志望の県立高校も今のままがんばれば合格できると太鼓判を押された。それなのに今ここでこんな事件に巻き込まれたら、すべてがダメになってしまうかもしれない。
遠くからパトカーのサイレン音が聞こえてくる。星吾は感覚が麻痺している足で懸命に立ち上がった。きっと警察が助けに来てくれたのだ。安堵を覚え、おぼつかない足取りで大通りに向かって駆けだした。
――俺らのこと誰かに話したら殺すぞ。
このまま現場に留まり、彼らのことを話したら、本当に復讐されるかもしれない。もうすぐ警察が来る。自分は被害者だ。加害者じゃない。逃げてもなんの問題もないだろう。もし警察にバレたら、身を守るために逃げた、そう証言すればいい。またあの男たちが戻ってくる可能性もあるのだ。そもそも最初から金を渡しておけば、こんな出来事はちょっと悔しい経験で終わっていたはずだ。
十四歳の少年には、正しい判断がつかなかった。
自己愛が強く、良心が足りなかったのかもしれない。それとも十四歳では、パニックになり逃げてしまうのは普通の行動だったのだろうか。
事件後、どれほど考えても星吾には明確な答えはだせなかった。
それからの人生は、最悪なものへと変貌していった。
あのとき耳にしたのは、近くで起きた交通事故の現場に急行するパトカーのサイレン音だったのだ。容疑者の供述や司法解剖の結果、氷室がナイフを腹に刺されたのは十七時二十分頃だったという。星吾が逃げだしたあと、氷室を発見したビジネスマンが救急に連絡したのは、十七時五十三分。刺されてから、消防に連絡が入るまで三十三分ほど時間があったことになる。
救急への連絡が遅れたせいで、氷室は出血性ショックにより死亡した。
その後、防犯カメラの映像から身元を特定された星吾は警察に呼びだされ、警察署で事情聴取を受けた。
なぜ現場から逃走したのか尋ねられたが、うまく言葉にできなかった。担当の年配の刑事から「傷はそれほど深くなく、もっと早く救急車を呼んでいれば助かった可能性が高かった」と叱責された。遠回しに、お前は人を殺したのだと罵られた気がして、ずっと震えていた。
やっと口にできた台詞は「僕はなにか罪になるんですか」という自己中心的な言葉だった。年配の刑事は大きな溜息を吐きだしたあと、静かな声で「法で裁かれることはない。だが、あのときどうすべきだったのか、ゆっくり考え続けてほしい」と諭すように言った。
怒鳴られたわけではないのに、涙が止まらなかった。
二十歳になったばかりの氷室は、大学の医学部に通う正義感の強い人物で、多くの人々から愛されていた。情報番組のコメンテーターたちは、こぞって彼を勇敢なヒーローだと称賛した。
星吾は事件から目をそむけたくて、テレビや新聞を極端に避けるようになった。けれど、身近な場所で起きた惨劇だったため、学校や予備校でどうしても噂話を耳にしてしまう。
なによりも衝撃を受けたのは、氷室は十四歳の夏、川で溺れそうになっている小学生を助け、山梨県警察本部から感謝状をもらったという話だ。
同じ十四歳――。
一方は助けてくれた人間を置き去りにする愚か者。もう一方は自分の命も顧みず、溺れている少年を助けた勇敢なヒーロー。
休み時間になると、仲のいいクラスメイトがある動画を見ていた。大学の友人たちが涙ながらに氷室について語っている追悼動画だった。
氷室は中学まで弁護士を目指していたが、川で少年を助けたとき考えが変わったという。川べりで咳き込んで苦しそうにしている少年の姿を目にしても、なにもできない自分自身に不甲斐なさを感じ、なによりも命が大切だと悟り、医師を志そうと決意したらしい。
すべてが完璧すぎて、その完全さに耐えられなくなり、吐き気がした。そんなふうに生きられない人間からすれば、氷室は愚か者を追いつめるだけの気味の悪い存在でしかない。
あいつにも欠点はある。
氷室はひとつだけ大きな過ちを犯していた。
正義感の強い青年は、警戒が不充分だったのか、咄嗟に助けようとして路地裏に駆け込んでしまったのかわからないが、あのとき彼は警察に連絡していなかったのだ。それなのに、氷室の過ちについてはまったく報道されなかった。
三人の加害者たちの名前は非公開。けれど、年齢は公表された。
驚くことに、彼らは十七歳から十九歳の未成年だったのだ。
十九歳の主犯格の男ともうひとりは、刑事裁判を受けるべきだと判断されて逆送が決定し、実刑判決が確定した。残りの十七歳は、少年審判で中等少年院送致の保護処分を受けた。
世間は加害者三人を罵倒したが、それだけでは済まなかった。
犯人のひとりが公判で「逃げだした少年を追いかけようとしたとき、被害者に足をつかまれ、ついカッとなって刺した。少年が逃げなければ、ナイフは使わなかった」と口にしたのだ。追い打ちをかけるように、週刊誌は「被害者の少年は刺された青年を置き去りにした」という記事を載せた。
記事の冒頭には『救えたはずの命』という見出しが躍っていた。
犯人たちに判決が下されると、人々の怒りの矛先は、二度も逃げだした少年に向かった。『少年GK』はインターネットの掲示板やSNSなどで叩かれ始めた。
――『ゲス』『クズ』の『少年GK』。
――犯人がいなくなったのに、なんで救急車を呼ばないの? カスなの?
――クソみたいなクズが生き残って、氷室みたいな優秀な人間が死んだりするんだよな。
――少年GKは生きていてもなんの役にも立たない卑怯者なのに。
――誰か少年GKの本名アップ頼む。
――人間失格。生まれてこなければよかったのに。
もうなにもかもが怖くてしかたなかった。いつか本名を晒される日が来るのではないか、そう思うと不安で眠れない夜が続いた。
救えたはずの命――。
その言葉が心に居座り、胸に深い悔恨の根を張っていく。
中学や予備校で氷室の事件が話題になるたび、星吾は息を潜め、無関係を装ってどうにかやり過ごしてきた。けれど、授業にも身が入らなくなり、成績は急落していく一方だった。
どうにか第二志望の高校に合格できたが、以前の生活には戻れず、家族との関係にも不穏なものが漂い始めた。
父からはことあるごとに「助けてくれた青年の分まで一生懸命生きなければならない」と論されるようになった。
星吾は内心で「父は間違っている」と思っていた。
加害者たちに素直に財布を渡していれば事件は起きなかったはずだ。それなのに氷室は自己満足のために正義をふりかざし、勝手に命を落としたのだ。誰かに助けを求めた覚えはない。けれど、内なる叫びは誰にも届かなかった。
その後、哀しい出来事が次々と家族を襲った。
(#2に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
