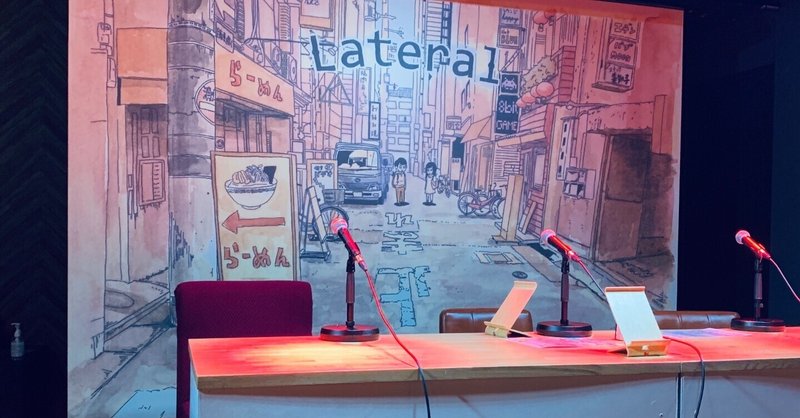
『鬱と本』トークイベントに行った
梅田で開催された『鬱の本』のトークイベント『鬱と本』に行った。
わすれたくないこと書き残し。
配信はなかったので、この話は書いちゃだめだったみたいなのあったら消すので言ってください。
点滅社さんのことは「出版社をつくることにしました」のnoteで知った。
文章を書くのが好きで亜沙さんと本も作っているけれど、元々かんののアカウントは音楽やお笑いやラジオの趣味アカウントだったので、ほとんど物書きの方達と繋がっていない。オカワダさん主宰のアンソロジー集『BALM』で初めて交流があり、すごく嬉しかったのを覚えている。
そんなわたしの元にも、点滅社さん開業の話は流れてきた。
イベントにいらっしゃっていた装画・装丁を担当された平野さんも仰っていたことだけど、いろんな出版社が立ち上がるのを遠くから応援する中で、なぜだか点滅社さんのことは気になっていた。今考えれば、屋良さん自身の魅力だと思う。こまめに更新されるnoteやツイートとその内容の温度感から近い感覚の人が本に携わって今日も生きている、ということがただただ嬉しかった。個人的には屋良さん個人の素直なツイートに毎日力をもらっていた。
梅田ラテラルに着くと、既に多くの人がいて一番前に座ることになった。
点滅社さんのイベント、ということで行った上に会場で本を購入して開場までの時間で読んでいたので、勉強不足で青木真兵さんと鳥羽和久さんのことは知らない状態だった。
もっと言えば、屋良さんがやらさんであることもイベントをやると知ってはじめて気づいた。個人の名前で声をかけそうになってしまった。
青木さんは自宅を開放して人文系私設図書館『ルチャ・リブロ』を営んでいる。図書館を開くことにしたのはパートナーである海青子さんが司書だったから、そして「本が家にたくさんあったから」と話し「じぶんの過剰性を生かす・シェアすること」の話をしていて印象に残った。
その前に「抽象化ってころされた感じになるんですよ」と話す場面があって、わたしは「もうすこし普通に振舞えないものか」と悩んでいる方ではあったんだけど、たしかにそうだなと学生時代の違和感の蓋が開きかけて怖かった。話めちゃくちゃおもしろかった...
鳥羽さんは福岡で小中高生の学習指導をしている。著書を検索すると「君は君の人生の主役になれ」というタイトルの本が出てきて、興味が湧いた。
話を深堀する姿・大袈裟かもしれないけど人間に興味を持っている姿がすごく印象的だった。
(こっから特にかなり覚書です、すいません、素敵な人だったということ)
社会で生きていて、大人は(わたしも大人なんだけど)外に矢印が向いていない気がしていてたまに苦しくなる時がある。三人ともそうだったけど鳥羽さんからは特に人への興味が伺えて、社会捨てたもんじゃないなと思った。手元のメモを書くのにも時間がかかっているんだろうなと思った。あと、たまに会話の中でああ断言できてるんですね、みたいな頷き方をしていて印象的だった。まだわからないものをわからないとしておくことというか、引っ張られない強さというか... 断言できることも、どちらのかっこよさもあった。
「子どもに言葉を与えるのが早すぎるとよくない」という言葉も書き留めておきたい。
他にも二点を行き来して補完(漢字違うかも)する話、その派生での他者ニーズと自己ニーズの話、が興味深かった。イベントが終わる頃にはすっかり二人のファンになっていた。
あと「なんでもひとりでやらないこと」「人と関わること」についても話していた。
実は今回の〇〇×の企画、ひとりでああでもないこうでもないと本の内容を詰めながら、大枠はできた誰かに見てもらって独りよがりすぎていないか知りたいと思った時に見てくれたのが屋良さんだった。
それまでのやり取りはいいねくらいで急に声をかけられて怖かっただろうに、屋良さんは背中を押してくれた。背中を押してくれという気持ちも正直あったと思う、役を買わせてしまった。
申し訳なかったけどありがたかった、今に続いている。要項や説明に書いている「飛行機でたまたま隣に座った人と話す感じ」というのは元は屋良さんの言葉だ。
「ひとりでやらないこと」と話すトークイベントの元となった本には、八十四人もの人が寄稿している。イベント中、目の前の温かみのある装画と目が合う時間が何度もあった。
その後、詳しくは書かないが『鬱の本』のトークイベントであることもあり、身近な人から死にたいと言われたら?という話になった。
いろんな話をした後最後に青木さんが、その死にたいは死にたいって意味ではないかもしれないしという話をしていて、前から風がバッと吹く感じがした。
その言葉に否定が飛ばないこのライブハウス全体というか、考えすぎだよって面倒な顔をされない場所というか、はじめてわかってもらえた気持ちになった。
わたしは言葉の裏を読んでしまう。読んでしまう、が正しい。人と話したり遊んだりするの好きなのにたくさんの人といると(誰に頼まれてもいないのに)全員分のいろいろを考える必要に駆られておかしくなりそうな時もあるし、でも読めないよりいいのかもと思う時もある。コミュニケーションがうまく取れない時も取れすぎてしまってよかったり疲れたりする時もある。総じて面倒だとは思われていて、それを苦しく思っていた。
はじめてわたしじゃない人間から「それって言葉通りの意味で捉えていいの?」という問いかけを聞いて、変だけど泣きそうになった。打っているいまも泣きそうになっている。打ってみて、たったこれだけのことが誰とも共有できていなかったのか?とも思う。
瀬尾まい子の『幸福な食卓』で、だいすきなシーンがある。
主人公の佐和子がお父さんに対して、無意識に酷いことを言ってしまう。ハッと気づいて、じっと次の言葉を待っていると、兄である直ちゃんは「かわいそうに」「そんなことを言うほど、佐和子は傷ついているんだね」と言う。
急に佐和子のことを思い出して、そうだわたしは佐和子に「なんて酷いことを言うんだ!」って言わない大人になりたかったんだ。そして、なれたんだ。思い出していた。

いま一番生でライブを見たい歌手
他にも店内を探索したら、梅田サイファーのポスターが貼ってあったり、岸教授の生活史の本も置いてあったりした。好きで溢れてる。

家に帰って、しばらくは飾っていた。昨日、落合加依子さんのページから読み出した。時間はかかるかもしれないけど、読み進めていく。
当日かかってきた音楽の中で、イベントからリピートしている曲。脳。
行ってよかった!
#イベントレポ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
