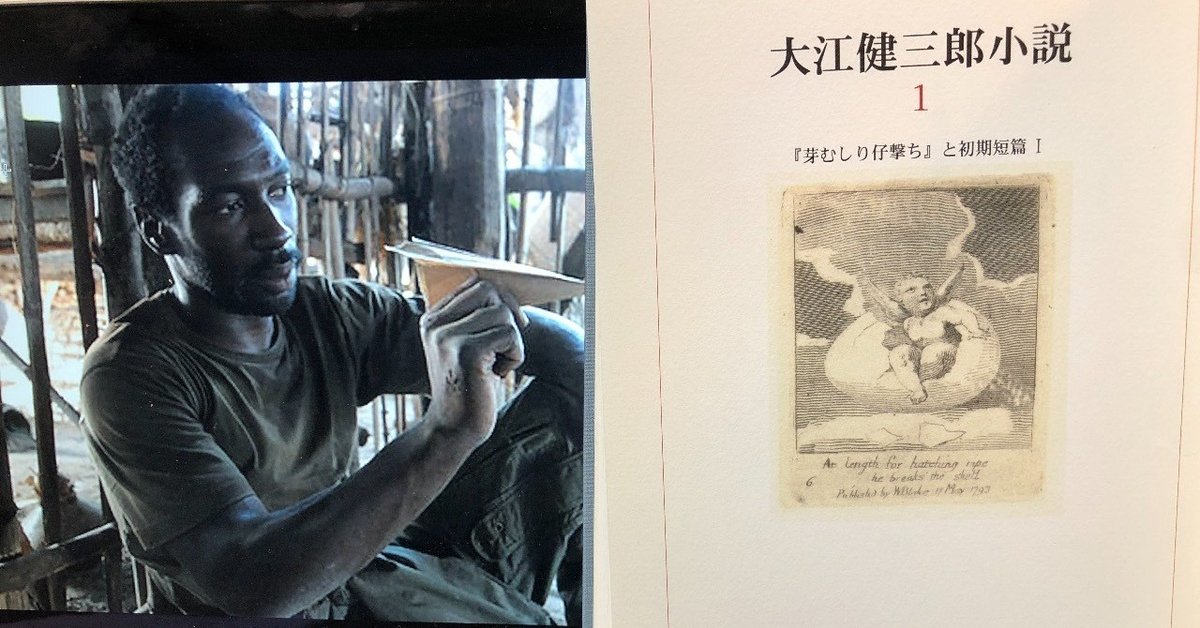
vol.73 大江健三郎「飼育」を読んで
なにやら不気味な臭いと、谷底に誘われるような書き出しに戸惑った。異質な感覚に読みづらさが加わり、どこか政治的なメッセージを勝手に感じた。
1958年、大江健三郎23歳の芥川賞受賞作。「文学を通して、政治に関与する」という新進気鋭の学生作家が描いたむごたらしく、たくましい出来事は、何を表しているのだろうか。

<概要>
戦争中、森の奥の谷間の村に、撃墜されたアメリカの飛行機から、黒人兵が降りてきた。村の大人たちは、捕らえられた黒人兵をどう処置するか、判断できず、県の指令待ちとなった。その間、主人公の少年「僕」の家の地下倉で黒人兵を『飼育』することになる。最初は「獲物」であった黒人兵と「僕」との関係は、やがて食事の面倒を見るうちに人間的な触れ合いになっていく。ある日、県の指令で黒人兵の移送が決まると、黒人兵は「僕」を盾として抵抗する。村人は相談を重ね、やがて「僕」の父が、「僕」を盾にしている黒人兵に・・・。(概要おわり)

かなり丁寧に読んだつもりだけど、一度読んだだけでは何が描かれているのかわからなかった。それでも読み解きを楽しむためにこんなことを考えた。
この『飼育』から浮かんだ言葉は、「死」と「監禁」と「敵」と「裏切り」と…暗いイメージばかり。その背景に大きく「戦争」があった。「戦争」から縁遠い谷間の村に「大人の世界」と「子どもの世界」があった。
突然の黒人兵に大人たちは困り果て、子どもたちは好奇心に湧いていた。「大人の世界」は、何も判断できず、県からの指令に従うだけで、無防備に加害者になることを受け入れる世界。これは当時の日本政府への批判なのか。アメリカにお伺いを立てなければなにも判断できない日本政府への苛立ちなのか。
「子どもの世界」は、野獣のような敵の黒人兵と意思疎通するも、無条件に被害者にされ、理不尽さを浴びながらも、けなげに成長していく世界。これは、何も判断できない日本政府の主体性のなさが、結果的に純真な子どもを被害者にしている現状を訴えているのか。
小説の中で「敵」は「獲物」となり、飼っているうちに「友人」となるが、やっぱり「敵」は裏切った。アメリカは「敵」だった。日本を都合のいいペットにしたく笑顔で近づき、「友人」のように振る舞った。しかし、状況が変わるとやっぱり「敵」は裏切った。
NHKスペシャルで、中曽根、後藤田らと大江が安全保障について議論をしていた。時は日本が自衛隊をイラク派遣した翌日だった。その中で大江は、「政府は国際協調の中でイラク派遣を決めたというけれど、国際協調ではなくアメリカの意向に屈した決定だ。これは将来の子ども達のためにはならない」という旨を主張していた。
なんだか『飼育』で「敵」を「友人」と思い込んだ敗戦国は、「敵」に危険がおよんだ途端に、戦勝国の「敵」は敵となり、未来の子どもが被害にあったことと、重なった。
今また、同じ空気を感じる。
おわり
