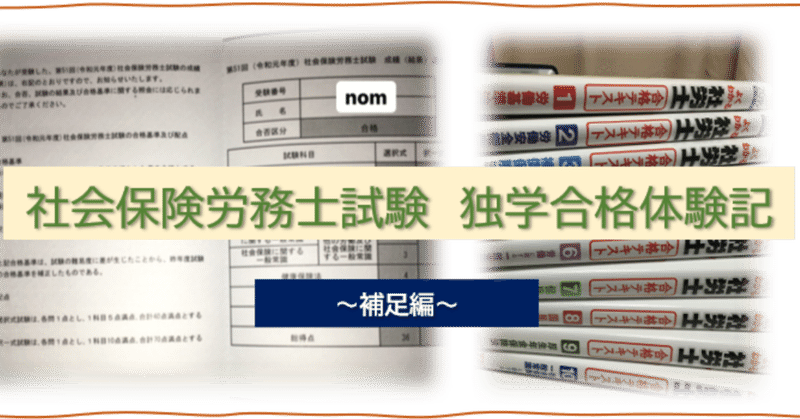
【社会保険労務士試験独学合格体験記 補足編】 テキストの内容を理解するためのポイント①
こんにちは、Nomです!
以前に、社会保険労務士試験の勉強方法や試験対策などを、体験談とともに記事にしています。過去記事はマガジンという形で綴っていますので、下記リンクからご覧ください。
今回の記事は、社労士試験の勉強方法について、テキストの内容を理解するための視点・読み方などのポイントを凝縮して書いていきたいと思います。
(過去記事と同じことを書いている箇所もありますが、何度も言うところは大事なところだと思ってください!😉)
1.最初に”保険”と”労務”
「社会保険労務士」という資格の名称からして、この2つの大きな区分けは簡単に思いつくでしょう。そして、覚えることはこの2つです。
これからこの2つについて、労務→保険という順番で、簡単に書きます。
①労務
会社が、従業員を雇う(=労働契約を結ぶ)。
雇う者(使用者)と雇われる者(労働者)、力関係は上である使用者の暴走を規制するためにあるのが、大きくまとめて労働法です。
その労働法に基づいて労働に関しての事務・管理業務が、”労務”。
労働契約をするということは、労働法の規制を受けるということです。
社労士のテキストを読み進めていくにあたって、だいたい最初にあるのが、
「労働基準法」です。
なので、まず最初にすることが、
従業員を雇う(=労働契約を結ぶ)ところから、クビにすることも含めて働かせるにあたって、雇う者(使用者)の暴走をどうやって規制していくのかという考え方を理解することです。
労働契約を締結したり、解約したり、はたまた解雇したりなどの、労働契約に関することは、労働基準法の他に労働契約法や最低賃金法などがあります。
その労働契約の条件を改善を求める団体交渉に関しては、労働組合法などがあります。
なので、最初の労働基準法を勉強するにあたっては、労働一般常識の科目にある労働契約法や最低賃金法、労働組合法などの法律を関連づけて理解し、覚えるということが大事です。
そして、労働基準法をはじめとする労務系全般にいえることですが、条文そのものを問う問題ももちろんありますが、判例からも出題されます。近年は、判例からの出題が多い傾向にあり、条文の解釈の仕方とその条文がなぜあるのかという背景や理由を問うことで、「考え方がわかっていますか?」と訊いているのです。
②保険(公的保険)
雇った従業員のケガや病気、老後、失業などについて保障をするために労働契約に付随しているともいえる公的保険が、主に労働者災害補償保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険です。
まあ、丸覚えでも何とかはなるところではありますが、覚える量はかなり多いと感じます。
なので、”保険関係に共通した考え方(=保険の原理)”を理解して、それぞれの科目の違いをハッキリ覚えていくことが肝心だと思います。そして、この違いを覚えることが一番難しいといえる箇所で、試験もこの違いを突いてきます。
先述した”保険関係に共通した考え方(=保険の原理)”については、次回の記事で具体的に書いていきます。
今回の記事は以上です。
ーーーーー
このページの"♡"(ハートのマーク)は、"スキ♡"ボタンって
いいます!このボタンは、noteに登録しなくても押すことが
できますので、押していただけるととても嬉しいです😊
また、"フォロー"もよろしくお願いします。
書きたいと思うことを書いています!😉 誰かの何かの役に立ったらとても嬉しいです😄 これからも頑張って記事を書いていきます!💪
