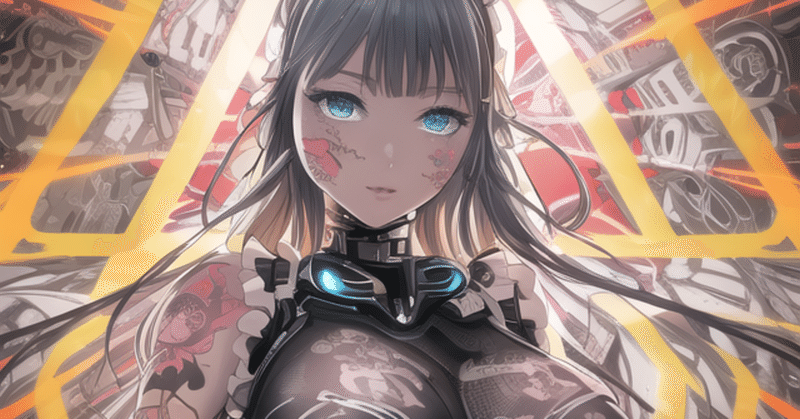
何故、ASDがゲーム依存になりやすいのか?前編。
発達障害の人がゲーム依存になりやすいという話を聞きます。僕もゲームが好きで、独身時代にゲームで遊んでいましたし、今でもスマホのアプリゲームを楽しんでいます。
よく指摘されるのが過集中やこだわりの強さが原因になっているみたいですが、僕はそれだけではないような気もします。僕自身の経験を含めて、ゲーム依存になる原因を考えてみました。
現実逃避の手段。
ゲーム依存になる人は現実で上手くいっていない人が多く、ゲームの世界に逃げ込んでしまいます。ゲームの世界では現実の息苦しい状況を紛らわしてくれます。
以前、テレビ番組でゲーム依存症の人を治療されている医者の方がおしゃっていましたが、ゲーム依存になる中高生は、親が教育熱心で、多大な期待が本人のプレッシャーになり、その現実から逃れるためにゲームに依存することが多いようです。
発達障害の人も現実で上手くいかないという人が多いと思うので、現実逃避手段にゲームにのめり込むことが多いと思います。
ある程度自分でコントールができる。
現実世界の物事はコントロールできないけど、ゲームならある程度はコントロールができます。ゲームのミッションは難しいのもありますが、努力すればクリアできるように設定されています。
現実のミッションは、発達障害の人にとってクリアできるようになっていませんし、ゲームと違いノルマという言葉がのしかかります。
登校拒否になる子供は発達障害が多いと言われていますが、引きこもっていてゲームをやるのは、現実世界と違い自己でコントロールできるのが原因という指摘もあります。
マニュアルがある。
これも大きい要素です。ゲームには必ず説明書がついていますので、それを読めば、ゲームを進めることができますし、最近では、ゲームを始めてすぐにチュートリアルがあり、プレイしながらゲームの流れが学べます。
現実世界になると、就職してすぐに説明があまりなかったり、数日で職場に慣れることを求められたり、面接で説明されなかった仕事を任されることがあり、定型の人でも対応しきれない職場があります。
今回はゲーム依存の話を前編という形をお送りしました。僕もゲームが大好きで、結婚する前はかなりやり込んでいました。発達障害のことを調べていくうちに自分自身がゲームに嵌まる原因がわかってきたので、記事にしてみました。共感できるとありがたいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
