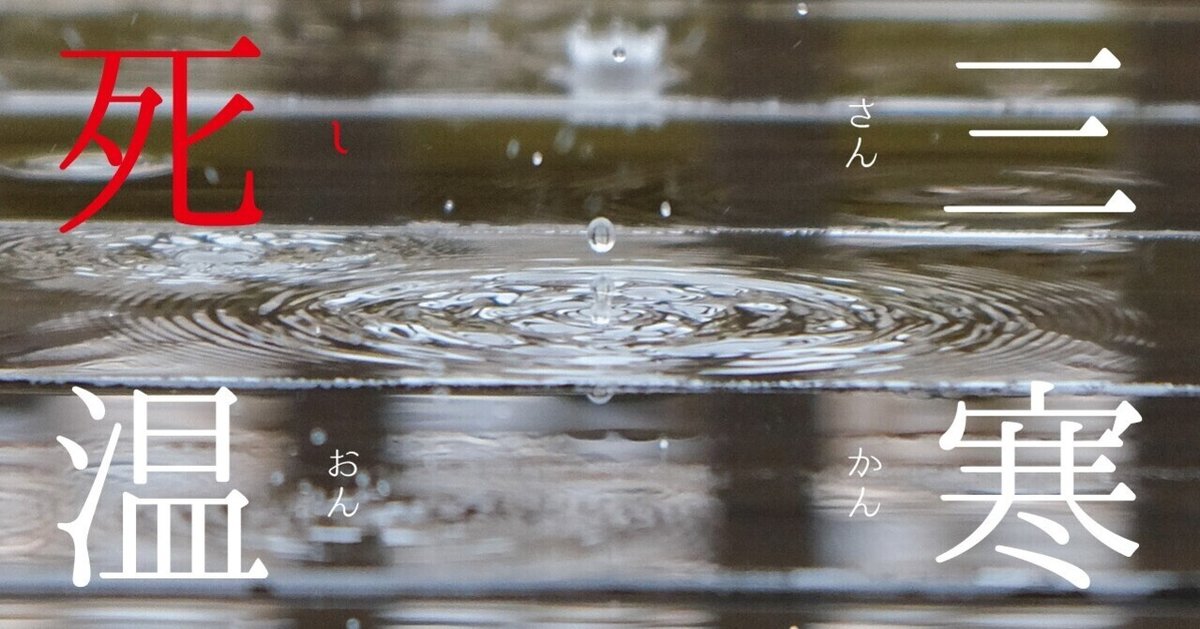
長編小説【三寒死温】Vol.8
第一話 人探しの得意な探偵
【第七章】憧れと戒め
一通り話を終えた私は、不覚にも、涙を流していた。
ここまで歳を重ねると、どうしても涙腺は緩むし、瞼の締まりも悪くなる。もうとうの昔に涸れ果てたと思っていた涙が、まだ熱く滾々と湧き上がる様に、自分の事ながら微かな喜びを感じた。
それでも恐らく、私が涙を流すのはこれが最後となるだろう。
目の前に座る男性に改めて娘の話をしながら、私は、彼女の想い出を黒く艶やかに光る漆塗りの重箱に丁寧に仕舞い、内蓋の代わりに蝋引きの和紙を一段ずつ敷いていった。そして、重箱と同じ墨色の組紐でしっかりと結んだ。
もし次の誕生日まで生き永らえることができたら、私は傘寿を迎えるのだ。これでいい。
そうだと思い、私は想像の中でしっかりと封印した重箱を一度解いてから、金糸雀色の組紐で結びなおした。
途中で意見や質問を挟むことなく、コーヒーに口をつけることもなく、恐らくは姿勢を変えることもなく、じっと動かずに私の話を聞いていたその男性が、呟いた。
「オミナエシは、漢字で書けば『女郎(じょろう)花』。」
そう。だから、憧れと戒め。
私は返事をする代わりに、ようやく涙の引いた瞳をそっと閉じた。
少し間を置いてから、お役に立てずに申し訳ありませんと言ったその男性に、私は労いと感謝の言葉を掛けた。
それはどちらも本心からのものだった。
人に話をすることでのみ、整理することができる感情もある。今、私のこの笑顔は、決してビジネス・スマイルなどではない。
「今日、こうしてあなたが来てくれたことも、きっと何かの縁なのでしょう。失明してからというもの、私は、娘の亡霊に早くあの世に連れて行って欲しいと切望していました。会えない娘を想って死ぬことが、せめてもの償いになる。そう信じていたからです。
でもそれは、どうやら思い違いだったみたいですね。それどころか、とんだ責任転嫁だわ。自分の中で踏ん切りがつかずに引き摺っていただけのことを、まるで自己犠牲のように考えていたのですから。」
その男性は、何も言わずに無言で私の正面に佇んでいた。
私の言葉の続きを待っていたのかも知れないし、何か適切な言葉を探していたのかも知れない。
その時、ふと、その場の緊張の糸が切れるような雰囲気を感じた。
鳴りもしない振り子時計の刻打ちの鐘の音が聞こえたような気がした。
「最後にこれを。」
そう言いながら、その男性はもぞもぞと手を動かし始めた。
絹よりは少しざらつきの大きい摩擦音から察するに、恐らく帆布を使ったショルダーバッグのようなものだろう。小さな鞄を開けて何かを取り出し、丁寧に閉めた。ざぁっ、ざぁっ、というファスナーが走る音が、まるで遠い潮騒のように聞こえる。
最後に、宙を舞う紙風船を赤子に向けてそっと叩くような、慈愛に満ちた音を二回、響かせた。
「実は、奥さまにぜひ読んでいただきたい本があります。短歌集です。残念ながら点字版は出版されていません。ですので、時間のある時にでも、先ほどの使用人の方に音読してもらってください。」
思いがけない贈り物を手にしたまま、しばらくの間、私は言葉を発することができなかった。
「短歌・・・ですか? どなたのかしら?」
どうにか絞り出した私の問いかけに答える声は、もうなかった。
その男性は、もういない。音を立てることもなく、誰に気づかれることもなく、静かに姿を消していた。
私はすぐに使用人を呼び、その男性が残していった短歌集を手渡した。
その本には一か所だけ、付箋で目印の付けられたページがあった。恐らく、その部分を読んで欲しいという彼からのメッセージだろう。
「四篇の短歌が納められています。春夏秋冬それぞれを代表する花と、それにまつわる母親とのエピソードを詠っているようです。ここを読めばよろしいのですか?」
私は音が立たないようアールグレイを一口含みながら、小さく一度だけ、頷いた。
◆ ◆ ◆
桜散る並木 負われし母の背に
偲ぶは 君と離れし憂い
かつて、お母さんに背負われて歩いた桜並木。
私も今、あなたと同じように子を背負い、歩いています。
子どもと離ればなれになってしまう辛さ、今なら理解できる気がします。
向日葵の 照りつける陽に逆らはず
何時ぞ来る日を すがらに待てり
どんなに強い日差しにも顔を背けず、凛と立つ向日葵。
その過酷な環境が、自分を育ててくれると知っているのでしょう。
今はとても辛いですが、あなたに会える日まで、私も待ち続けます。
移ろひて 在りし姿の霞む君
今に重ねし 女郎花かな
私にとって母の面影は、幼き記憶の中で止まったまま。
今、あなたはどこで、どんな風に生きているのでしょうか。
あなたが愛した女郎花のように、美しき女性であって欲しいものです。
冬菊のまとひし 雪の九十九髪
枯れ焚かれなほ 匂い艶めき
生きていれば、あなたはもうお婆さんですね。
私も、少しずつ白髪が目立つ年齢になってしまいました。
枯れて焼かれても素敵な香りを放つ冬菊のように、私も生きたいものです。
◆ ◆ ◆
私の手先から、ティーカップがするりと抜け落ちる。
かつて古いモノクローム映画で観たスローモーション・シーンのような、ゆったりとした時間が流れる。
ようやく、小さな子どもの悲鳴にも似た音を立ててカップが砕け散った。
私の心臓は大きく波打ち、
手の平は冷たい汗で湿り、
指先は小刻みに震えている。
程なくして、アールグレイ独特の柑橘系の香りが、私の全身を包み込んだ。使用人は慌てて片付けようとしたが、私はそれを制して、声にならない声をどうにか振り絞った。
「作者は、どなた?」
からからに干からびた自分の声を聞きながら、私は、見えない目を瞑って遠い昔の記憶を辿っていた。
◆
眼前には、娘が小さい頃に手をつないで二人で歩いた桜並木が伸びていた。歩くのに疲れて駄々をこねる彼女を仕方なくおんぶしたことが、まるで昨日の出来事のように蘇る。
そうそう、あの子は近所の畑に咲いていた向日葵の花が大好きで、泥だらけになってよく摘んでいたっけ。
向日葵にも負けない彼女の笑顔は、太陽よりも明るく輝いていた。
一番好きなお花はなあに?
最初は似ている菜の花と勘違いしていたけれど、きちんと正解の方を覚えていてくれたようだ。金糸雀色に染まる川沿いの土手が脳裏に浮かび、思わず中空に手を伸ばしそうになる。
そして、菊。言うまでもない。私そのものだ。
◆
「高井 椿という女性です。五年ほど前に出版されたものみたいですよ。」
口を開いても、もう声が出ない。
呼びかけるべき愛しい名を、声に出すことができない。
「奥さま? 大丈夫ですか?」
詠み手の筆名は、私が娘を生む前、一緒に暮らしていたほんの数年の間だけ名乗っていた 最初の主人の姓に、 娘の名を付け加えたものだった。
間違いない。
ほんの少し前に、流すのはこれで最後だと心に決めた涙が、もう涸れ果てたと思っていた涙が、光を感じることのできない瞳からとめどなく溢れ出てきた。いつしか私は両手で顔を覆い、その場に座り込んで幼子のように泣きじゃくっていた。
そして今度こそ、涙を流すのはこれで最後だと、今生の誓いを立てた。
第一話(完)/ 第二話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
