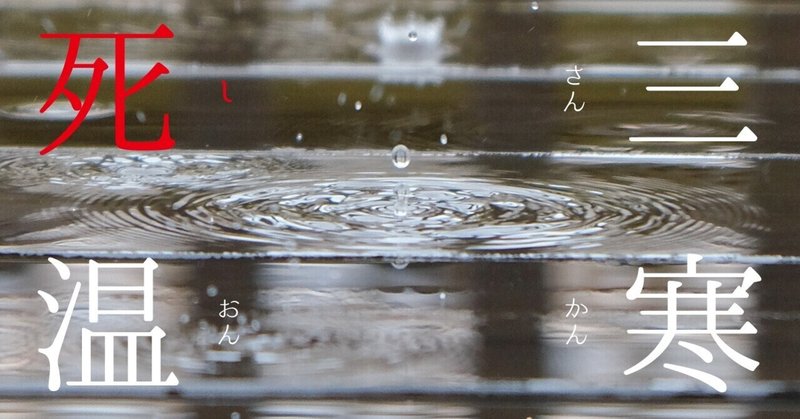
長編小説【三寒死温】Vol.10
第二話 律儀な看護師の旦那
【第二章】慈善事業を勘違いしている
現場に着くと、二人いるはずの保護者も一人しかいなかった。
PTAとて強制ではない以上、場合によってはこのようなケースが出てしまうのも仕方がない。早めに来てよかったと思いながら、私は一人だけで信号機の前に立っていた保護者の男性に「遅くなりました」と声を掛け、横断歩道を渡って反対側の信号機の下についた。
保護者の男性はちらりと私を一瞥しただけで、特に何も言わなかった。
会釈の一つもないのかと思ったが、そういえば、父親が参加している姿を見るのも珍しい。
しばらくすると、その保護者の息子と思しき子どもが、母親に連れられて交差点にやって来た。
黄色い帽子に黄色いランドセルカバー。まだ一年生だ。
子どもを連れてきた母親は、そのまま自転車で駅の方へと向かって行った。
歩行者信号が青に変わるまでの間、父親と息子が仲良く話をしていると、そこへ一人の上級生が近づいてきた。紺色のキャップに、迷彩のジャンパーを羽織った彼は、その親子と楽しそうに笑いながら何かを大声で喋り始めた。
そうか、彼の家もこちらの方なのか。
いつも顔を合わせるのは、私が普段持ち場としている、小学校に近い押しボタン式の信号だから、彼の家の方角までは細かく知らなかった。
ふと、彼の顔が横断歩道の対面に立つ私の方へと向いた。
私と視線が合うと、彼の唇が小さく「あっ」という形に開いたのが分かった。そして次の瞬間には、彼は慌てて顔を反対側に背けていた。
隣にいた一年生の保護者は、私と目が合った途端に口をつぐんだその上級生の一連の仕草を訝しく思ったのか、彼がほんの数秒前まで顔を向けていた私の方をちらりと見やった。そして、信号が青に変わると、横断歩道を進むよう彼と自分の息子を促した。
始業時間である八時近くになって、遠目にも子どもの姿がないことを確認してから、私は再び横断歩道を渡ってその父親に声を掛けた。
「先ほどの一年生の男の子は、息子さんですか?」
すでに自宅のある方向へと歩き始めていたその父親は、「ええ」と言いながら上半身だけよじって、私の方を振り返った。
「一緒に学校に行った上級生の男の子、いましたよね。」
返事をする代わりに小さく頷いた彼は、まだ半身のままで私の方を見ている。
ボランティアとはいえ、私はスクールガードだ。
つまりは、列記とした学校関係者ということになる。
自分の息子が通う学校に関与している年配者に声を掛けられているのに、この父親は、まともに相手の正面を向いて話をすることもできないのか。
そう思うと、全身の血が逆流を始めそうになる。
「彼、六年生の子なんですけどね・・・この辺りじゃちょっと有名な悪ガキでして。」
私がそう言うと、その父親はようやく私の正面を向いた。
眉間には、皺を寄せている。
先ほどの話っぷりからして、きっと親子ともども見知った顔なのだろう。
私は、学校へと続く交差点の先を指差しながら話を始めた。
「この道を行ったり来たりしていつまでたっても学校には行かないわ、平気で歩道からはみ出して車にクラクション鳴らされるわ、同級生だろうが下級生だろうが構わずにちょっかい出すわ、我々が何度注意しても、まったく言うことを聞かないでね。
向こうも私の顔を知ってるから、さっきも慌てて目を逸らしていた。何で今日はこんなところにいるんだ、というような気持ちだったんでしょうな。」
父親は、特に何も言わずに私の言葉を聞いていた。
「女の子の中には、彼と一緒になるのが嫌だと言って、登校する時間をずらす子までいましてね。」
「それを、なぜ私に?」
その父親は、眉間に寄せた皺を解くこともなく硬い口調で言った。
「あ、いや。お子さんがまだ一年生だったもので、何か変な目に合わなければいいなと。注意した方がいいと思ったので。」
実際に何かが起こってからでは遅い。
危険の芽は、事前に摘み取るに越したことはない。
「それはどうも。
ただ、こちらから聞いてもいないのに、初対面の人間に他の家のお子さんの話をべらべらと喋ってしまうのは、いかがなものでしょう。」
少し意外な反応だった。
こういったところは、母親と父親では違うのだろうか。
母親ならば、それこそ食い入るように私の話を聞いてくるものだが、この父親にはそのような素振りはなく、かえって鬱陶しく感じている雰囲気さえ窺える。
「あのね、お父さん。こういう情報は知っておいた方がいいですよ。特にお子さん、まだ一年生なんだから。」
まったく、こちらの親切心も汲み取れないようでは話にならない。
しかも、年配の私の方からわざわざ声を掛けているにも関わらず。
「彼、ご近所さんなんですよ。それこそ、彼がまだよちよち歩きしている頃から知ってるんです。」
「ああ、そうでしたか。」
「申し訳ないが、知っている子の悪口を言われるのは、聞いていて気分のいいものじゃないですね。」
これは悪口ではない。事実なのだ。
この父親は、そこのところがまったく分かっていない。
心地のよい話ばかり聞いて、聞きたくない情報に耳を塞いでいては、肝心なものを見落としてしまう。
そんな説教が喉元まで出かかったが、寸でのところで飲み込んだ。
「いや、悪口のつもりで言ったわけではないんですけどね。」
「少なくとも私の前では、彼はごく普通の、ゲームが大好きな小学六年生です。一緒にゲームの話をしている限り、物知りだし説明も上手だし、うちの子どもにもいろいろ教えてくれています。」
「好きな人に対しては、子どもはみんなそうですよ。私なんてがみがみ言うもんだから、それは嫌われているでしょう。ああやって目を逸らして行ってしまうくらいですから。」
「普通に話せば、聞き分けのない子ではありませんよ。」
この父親は、いたずらっ子の六年生のほかにも何人かの子どもと親しげに言葉を交わしていた。きっと、そんな風に子どもたちから慕われている自分に酔い痴れているのだろう。
だが、それが一体何になる?
大人が子どもに嫌われないでどうすると言うのだ。
子どもと一緒になって同じ目線で話をすれば、それは当然、子どもの方だって寄ってくるだろう。怒られなくて居心地がいいのだから。
しかしそれでは子どものためにはならないし、その結果、子どもに舐められることにもなる。
まさに、いい人、いい人、どうでもいい人。
いてもいなくても影響のない、人畜無害な透明人間。
私は、込み上げてくる嘲笑をどうにか抑えながら言った。
「でもね、彼がいたずらっ子なのはみんな知ってる。やっと卒業してくれるって、みんな喜んでいるんですよ。子どもにはいろいろな側面があるものです。」
実際に私は、そういう立ち話をしている保護者同士の会話を聞いたことがあった。きっと、彼に何かしら嫌な思いをさせられた被害者だったのだろう。だからこそ、私は常に彼に対して睨みを利かせているし、機会を見つけては他の保護者にも注意を促しているのだ。
この父親のように、まだ何も知らない初心者の保護者などは、特に。
「『みんな』ですか。少なくとも、ご近所さんも含めて私の周りにはいませんが。」
「それは、彼の登校時の様子を見ていないからではないですか? まあ、ご存知なくても仕方ないとは思いますが。」
「だいたいの想像はついてますよ。それこそ彼がもっと小さい頃なんて、ウチはよく彼にピンポンダッシュされていましたから。言ってみれば、もうとっくの昔から被害者です。」
そう言ったその父親は、それまで硬かった表情を和ませたかと思うと、薄っすらと笑みさえ浮かべて見せた。
ああ言えばこう言とは、よく言ったものだ。
この父親には、人の話を聞き入れるというつもりなど初めからないのだろう。そこまで言うのであれば、私からはこれ以上、特に何もない。
何かあってからでは遅いというものだけれど、結局、こういった連中は何かが起こらないと分からないのだ。
「彼がどんな家庭環境にあって、普段、どんな生活をしているか、そういったこともすべて理解しています。恐らく、あなたよりも。」
それは当然だろう。私はご近所さんではないのだ。
彼の普段の生活など知らないし、興味もない。
それに、大よそのところは私にだって想像がつく。どうせ片親だったり、育児放棄であったり、そんなところだろう。
確かに不憫な気はするが、だからといって彼が何をしても許されるわけではない。
「詳しい話は知りませんけどね。スクールガードとして、通学路を利用する地域の住民たちや他の児童たちに迷惑が掛かるような行為は、見逃すことはできないんですよ。」
「だったら私などではなく、彼自身に、しっかり説教してあげてください。それとも、近隣の保護者に名指しで問題児だと言って回ることも、スクールガードさんの役割なのですか?」
「周りの親御さんたちが知っていれば、いろいろと守ってあげられるでしょう。何かあって、辛い思いをするのは子どもたちなんです。」
「私は、子どもたち同士のことに口出しするつもりはありません。事前に『誰々には近づくな』なんてもってのほかです。」
最近よく耳にする、自称教育者などの台詞と似ている。
恐らくこの父親も、そんな輩の受け売りだろう。申し訳ないが、聞こえはいいが単に子ども任せにしているだけではないかと思って聞いていた。
だってそうだろう。大人が正しい方向に導いてやらなければ、子どもたちはいったい何を模範とすればいいのだろうか。
返す返すも、そんなことを言っているから、子どもに舐められるのだ。
「彼のことは、お教えいただかなくても存じています。ご心配には及びません。そんなことよりも、まずは時間を守っていただきたいものです。」
なるほど、この父親の一連の尊大な態度の理由は、これか。
「私の持ち場は本来、ここではないのですよ。担当者が来られなくなってしまったようで、急いで応援に来たわけです。」
「別にどなたでも構いません。空白の時間があったのは事実ですので、今後はお気をつけください。」
それでは、これから仕事があるので失礼しますと付け加えて、その父親は踵を返して行った。
◆ ◆ ◆
そんな、小賢しい保護者のことを思い出しながら、私は自分の持ち場である押しボタン式信号機の横断歩道へと急いだ。
その間にも、救急車のサイレンはますます大きくなっている。このままでは、私が到着するよりも先に救急車が通過してしまうかも知れない。
子どもたちが存分に騒いでしまった後では、注意のしようがない。現行犯でなければ、さすがに私でも何も言えなくなってしまう。
しかし、もうそこの丁字路を左折すれば横断歩道が見えるというところに差し掛かった時、不意に救急車のサイレンが鳴り止んだ。
サイレンが鳴り止んでようやく、大勢の人たちが大声を出してざわついているのが分かった。中には、子どもたちが泣いているような声も入り混じっている。ただ事ではない雰囲気が充満している。
丁字路の角を曲がると、救急車の赤色灯が一定のリズムで正面のマンションの壁を赤く染めているのが見えた。
思わず私は、走り始めた。
途中、足がもつれて転びそうになったが、構うことなく走り続けた。
バス通りとの交差点までくると、信号機のすぐ脇に、二台の救急車が後部ハッチを大きく開けたまま停まっていた。目と鼻の先には、転倒した原付バイクが横たわっていた。
ごくりと飲み込んだ唾の通り道が、一瞬にして凍り付くのが分かる。
事故だ。
単独か、それとも複数台か?
歩行者は巻き込まれているのか?
まさか子どもは?
原付バイクの破片は四方のあちらこちらに散らばっているものの、路上に血痕らしきものは見当たらない。
もう一度、交差点の方に目をやると、奥に停まっていた救急車にちょうど怪我をした人が運び込まれるところだった。私からは陰になっていて見えなかったが、どうやら先に到着していた救急車の奥で応急措置が施されていたらしい。
ストレッチャーと救急隊の隙間から、黒、茶色、そして緑色の迷彩柄がちらりと見えた時、私の心臓は大きな音を立てて飛び跳ねた。
「だから、言わんこっちゃない!」
あの、いたずらっ子の六年生が交通事故に遭ったのだ。
私は「大丈夫か!」と叫びながら、救急車の周りにできた人だかりに飛び込んで行った。すでに近所に暮らす住民たちや、騒ぎを聞いて駆けつけた保護者たちが大勢いた。
私がスクールガードのベストを着ていたからか、自然と人だかりに裂け目ができて救急車の後部ハッチまでつながった。
足早に近づいてストレッチャーをのぞき込むと、迷彩柄のジャンパーを着た男の子が横たわっていた。やはり例の、六年生のいたずらっ子だ。
もしかしたら頭を打っているのか、目をつぶったまま動かない。意識がないようにも見えた。
その時、不意に私の後ろからかわいい怒鳴り声が聞こえた。
同時に、膝の裏辺りに軽い衝撃を感じた。
「どこにい(行)ってたんだよ!」
振り返るとそこには、黄色い帽子を被り、黄色いカバーを掛けたランドセルを背負った男の子がいた。
二度、三度と足を振り上げて私のことを蹴飛ばしている。
先々週、父親と共に六年生のいたずらっ子と楽しそうに話していた、あの一年生の男の子だ。彼は続けて、
「ひ(轢)かれちゃったじゃないか!」と言うと、いたずらっ子の名前を大きな声で何度も呼びながら、わんわんと泣き出した。
私がどうにかなだめすかそうと近寄ると、彼は私のことを小さい手で叩いて、後方に飛び退いた。
その後ろに立っていたどこかの保護者らしき女性がその男の子を抱きかかえると、円を描くように周りを取り囲んでいた子どもたちに「ほらみんな、大丈夫だから学校に行くよ。」と大きな声で呼びかけた。
ちょうど生活指導の主任と思しき教員がやって来て、人だかりとなっていた子どもたちを小学校へと向かわせた。
◆
来た時と同じようなせわしいサイレンを鳴らしながら救急車が立ち去ると、先ほど一年生の男の子を抱き上げた保護者が私に話しかけてきた。
何度か顔を合わせたことのある保護者だ。
「今日、こちらを担当する予定だったスクールガードさんですか?」
「ええ。そうです。」
「事故をご覧になっていましたか?」
「見ていませんよ。今、来たところだから。」
「なぜ、いらっしゃらなかったのです?」
「所用があって、今日は家を出るのが少し遅かったかな。」
「遅刻、ですか?」
「もともと何時から何時という、定められた時間はありませんので。」
「でも、いつもなら、いらっしゃる時間のはずでは?」
「そうなんですが、絶対ではないんですよ。」
「つまり、いなかったことに、落ち度はないと。」
「そもそも、ボランティアですから。」
「そうですか・・・」
その保護者はしばらくの間、腕組みをして黙っていた。
それにしても、言うに事欠いて「落ち度」とは何事か。今回の事故を、私たちスクールガードの責任にしようという魂胆が丸見えではないか。
周りには、遠巻きに私たちの会話の成り行きを窺っている保護者のグループが、いくつかあった。決して近くには寄ってこないが、話が聞こえる距離は維持しながら、その場に群れて佇んでいる。
「それでは、学校と相談させていただきます。無報酬だから責任は負えないと言われてしまっては、我々としてはもう、あなた方を頼りにすることはできません。」
そうか、この保護者はPTAの役員の一人だ。最初のスクールガードボランティアの説明の時に、同席していたのを思い出した。
「無報酬だからといって、手を抜いているわけではない。ボランティアとしてできる範囲のことは、しっかりやっているつもりです。」
確かに、私がいつもと同じ時間に来ていれば、防ぐことのできた事故かも知れない。まだ子どもたちが家を出る前から持ち場に来て準備をしていれば。その点に関して言えば、多少の罪悪感はある。
しかしそれは、あくまでも私たちボランティアの善意であって、それを当たり前のものと思って欲しくはない。
何かしらの見返りと引き換えに約束された契約ごとではないのだ。
先日の保護者の父親といい、このPTAの役員といい、慈善事業を勘違いしているのではないだろうか。
「結果的に、事故が起こってしまっては意味がありません。」
「気持ちは分かるが、ボランティアにプロ並の責任を負わされても困る。」
「ですから、学校と相談してみると言っているんです。ボランティアでは限界があるなら、有料サービスの検討も必要かも知れません。」
「そもそも、今日はPTAでも誰か保護者がいるはずでしょう? 月曜日なんだから。」
「今日は延期になっていた三・四年生の校外学習の代替日なので、PTAの見守り活動は明日に変更になりました。ご連絡したはずですが、情報共有されていないのですか?」
そんな話を聞いた記憶はない。
私が知らないということは、ボランティア事務所の所長が我々に伝え忘れたのだろう。もしくは、伝え聞いた仲間が私に言い忘れたかの、どちらかに違いない。
「大切なのは、子どもたちの安全です。私たち保護者からすれば、プロであろうがボランティアであろうが、スクールガードさん個人の立場などどうでもいいことです。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
