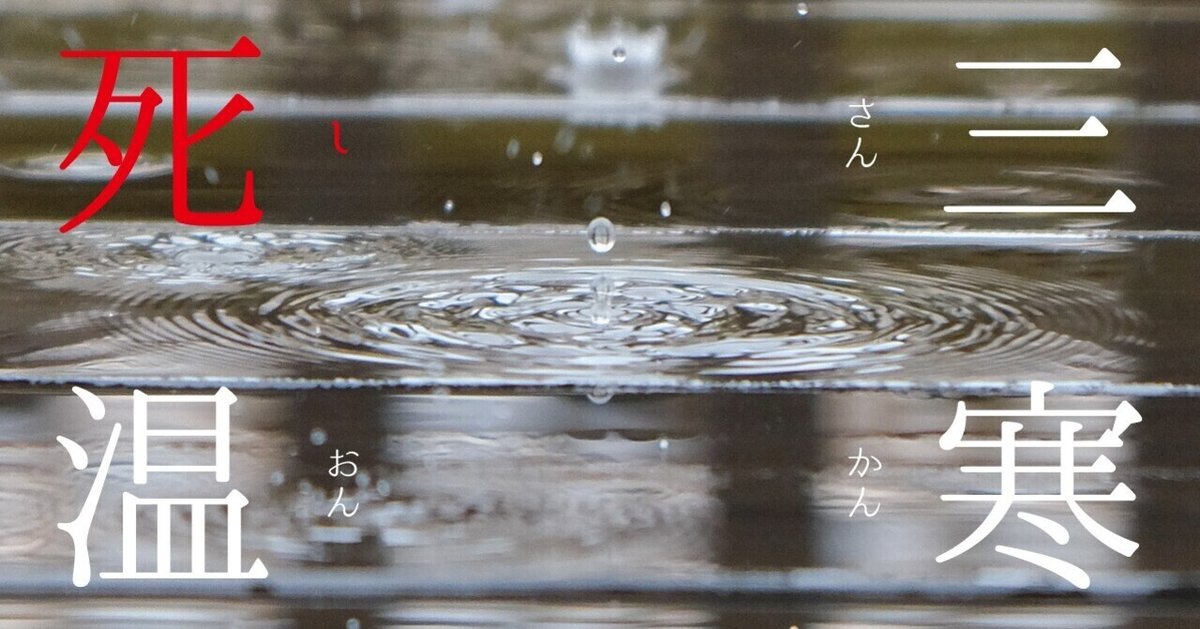
長編小説【三寒死温】Vol.3
第一話 人探しの得意な探偵
【第二章】暗転と終幕
一室だけ洋風に設えられた広い居間には、私以外には誰もいない。
その男性は、ゆったりとした幅の広い歩調を保ちながら部屋へと入ってきた。必要以上に音を立てまいとする彼の足の運びには、いささかぎこちない響きが感じられた。
カーペットの上を靴を履いて歩き回る経験が、あまりないのだろう。
その男性からは、午前中に使用人が漂わせていたような雨の匂いは感じられなかった。その代わりに、微かな土の甘い香りをまとっていた。
「もう、雨は止みましたか?」
「ええ、昼過ぎにはもう上がっていました。」
そう答える彼のしっかりと抑えの効いた声色には、録音された自分の声を聞いているような違和感があった。
骨伝導によって高音部を削り取られた内側からの音に慣れてしまっているせいで、実際の自分の声を耳で聞くと、どこか作り物のような響きを感じる。その男性の声色は、彼の佇まいから放たれる雰囲気に比べてとても低かった。きっと、あえて落ち着いた声を出しているのだろう。
作り込まれた彼の語り口から実際の声を想像するに、年齢は、30代半ばあたりだと思われる。
「お帽子と上着を、こちらに。」
後ろから追うようにして居間へと入ってきた使用人の言葉に従って、身に着けているものを脱ぐその男性からは、大ぶりながらもきびきびとした所作が窺えた。ほとんど音は聞こえてこないけれど、僅かに感じるそれらの着脱の雰囲気から察するに、恐らく、畏まった服装ではない。
帽子といっても、きっと野球帽のようなカジュアルなものだろう。
上着といっても、上等なスーツが奏でる鋭利で威厳に満ちた摩擦音とは少し違う。どこかふわふわとした軽い音は、思いの外寒かった昨晩、慌てて用意した羽毛布団を連想させた。
帽子と上着を脱ぎ終えたその男性が、恐縮したような声で言った。
「すみません。こんなラフな格好で来てしまって。」
慌てて使用人が、
「奥さまは目がほとんど見えませんので」と小さな声で囁く。
「いいんですよ。さあ、そちらにお掛けください。」
「そうでした。すみません。目はまったく見えないのですか?」
「いきなりそんなデリカシーのない質問を。」
実際に、使用人がそう声を発したわけではない。そう心の中でいきり立っているであろう彼女の顔が、頭に浮かんだだけだ。
思わず笑みが零れる。
「光を感じる程度の視力は残っているのですが、ものの形はほとんど認識できません。それでも一年ほど前までは、かろうじて輪郭ぐらいは見えていたのですよ。失明してもまだその先があったなんて、嫌になります。」
その男性はきっと、私の言葉を聞きながら頷いていたのだろう。
「声に出してお答えください」という、使用人の小さな声が聞こえてきた。怒りを押し殺したような、普段はおよそ聞くことができないくらいの低い声だった。
「失礼。分かってはいるのですが、慣れていないもので申し訳ありません。不愉快に感じる言動があったら、言っていただけると助かります。」
恐らく使用人は、彼女自身の表情も、私には見られていないと思っているのだろう。もちろん実際に見ることができないのは確かだが、相手の表情くらいなら声色からいくらでも想像できる。会話の中での間の取り方や息遣いの雰囲気で、相手の感情やその挙動を察することだってできる。
ここまでのところ、この男性からは、噂で聞く自身の能力に対する奢りのようなものは見受けられなかった。言葉遣いにも、必要以上に遜るような慇懃無礼な響きは感じられない。
信用に足るかどうかはまだ判断がつかないけれど、少なくとも、門前払いを喰らわせる必要はなさそうだ。話をして、損はないだろう。
◆ ◆ ◆
娘を探し出すという魔物に取り憑かれてからというもの、私はそれまで心血を注いできた事業に身が入らなくなっていた。
文字通り裸一貫から築き上げた我が帝国に自尊の念は抱いていたが、それでも、かつて幼い娘を手放したことがあるという後ろめたさは、いつまで経っても消えることはなかった。それどころか、世間的な名声を手に入れれば入れるほど、その事実は私にとって大きながん細胞となり、全身を蝕んでいった。
一刻でも早く娘を探し出して、解放されたかった。
しかしそれは、なかなか成果として実を結んではくれなかった。
事業において、常にプロセスと成果との整合性を意識してきた私にとって、結果の伴わない行為を続けなければならないということは、誠に不本意だった。いつ入るとも知れない朗報を待つばかりの日々は、フラストレーションでしかなかった。
そんな私には、さらに追い打ちを掛けるような不運が待ち受けていた。
それは、今から五年ほど前のこと。
私は突然、暗い井戸の中に放り込まれることとなった。
文字通り、暗闇の世界に。
ある日、真夜中に目を覚ますと、消したと思っていたはずのフットライトが点いているのが見えた。
私の「いらない」という意見を完全無視した使用人が、私が暮らしている母屋のすべての廊下と寝室に設置したフットライトだ。
当時、私はこの照明器具の有用性に関して、使用人からさまざまな説得を受けた。その年齢になると、何よりも骨折、特に足腰の骨折は命取りになるのだと諭された。最悪の場合、寝たきりになってしまう可能性もあるのだと脅された。例え寝たきりにはならずとも、完治するまで動けなければ体は衰えてしまう。維持するだけでも大変なのに、減った分の筋肉を取り戻すためのリハビリは容易ではないし、一定期間、横になったきりで過ごすことで内臓に与える影響だって計り知れないのだ。そう滾々と説教された。
そんな風に年寄り扱いされることそのものに最も嫌悪感を抱く私を説得する方法としては、どう考えても非効率的で実現性が低い選択である。
当然、私は使用人の言葉すべてを右から左に聞き流した。
しかし彼女には、私を説得するつもりは初めからなかった。私の理解を得るつもりなど、初めからなかった。
それから数日後、私が仕事で地方に赴き、一泊して帰ってきた時には、すでにフットライトの設置工事は終わっていた。
まさに「有無を言わさず」とはこのこと。
私ですら、仕事でもプライベートでもここまで我を押し通したことはない。他人から見ればどうか分からないが、自分ではそう思っている。
そんないきさつがあったせいか、私は彼女が屋敷に泊まる予定のない日には、極力フットライトを消すようにしていた。初めはまるで幼子のような些細な抵抗のつもりだったが、気がつけばそれが習慣化していた。
その夜も、いつも通りに彼女の翌朝の不在を確認してフットライトを消したつもりだった。しかしどうやら、私は思い違いをしたらしい。
消したという記憶はあっても、それが当日のことだったのか、それとも昨夜のことだったのかと問われると、残念ながら自信がない。
仕事ならこんなことはないのにと、思わずため息を吐いてしまう。
まあ仕方がない。トイレに起きるついでに消してこよう。
そう気を取り直してフットライトに近寄ると、その光はふと消えて見えなくなった。後には、何事もなかったかのように暗闇だけが残っていた。
ちょうど、電球が切れてしまったのかしら。
そう思って何気なくスイッチを押そうとした時、何か違和感を覚えた。
一瞬だけ手を引き戻し、もう一度、スイッチに指先で触れてみたところで、その正体に気がついた。フットライトのカバーに、まるで温かみがない。
初めから灯りなど点いていなかったかのような、無機質な冷たさしかない。
そんな違和感を押し殺しながらスイッチを押してみると、フットライトは小さな音を立てて点灯した。やはり、電源は入っていなかった。
つまり、故障ではなかったわけだ。
それではなぜ灯りが点いていたのだろうと不思議に思いつつも、一晩明けて翌朝には忘れていたのだが、同じことはその後も何度か起こった。
もしかしたら、何か目の病気を患ってしまったのだろうか?
目を上下左右に動かすと、一緒になってゆらゆらと後を追いかけてくる黒い斑点たちがいる。その存在には以前から気がついていた。
蚊か、それもと羽虫か、そんな翅を持った小さな虫が自分の顔の周りを飛んでいると思って手で払っても、少しも遠のいてくれないのだ。
煩わしさのほかにこれといった実害がないのが、かえって気持ち悪い。
ちょうど、慣れないコンピュータを導入した時期でもあったので、その影響も危惧した。
ほどなくして、何の集まりだったかは忘れてしまったが、私は同年代の友人たちと会食をする機会を得た。そして、彼女たちに「それは飛蚊症といって眼球(正確には硝子体というらしい)の汚れが原因だから、あなたもそれだけ歳を取ったということよ」と笑われながら一蹴された。
「私もよ!」
「ルテインが効くらしいけど、本当かしら?」
「あなたのところ、サプリメントは扱っていないの?」
盛り上がる友人たちを見て、特に気にする必要はないと判断してしまった。単なる老化現象の一つとして、頭の隅に追いやってしまった。
実際、飛蚊症のほとんどは加齢や近視の影響から発症するらしく、私自身も症状が極端にひどくなるようなこともなかったので、高を括っていたのかも知れない。
使用人に話してみたけれど、LEDだからそんなに早く切れるはずはないと軽くあしらわれた。この際、眼科に掛かってはどうかと、いらぬお節介までおまけで付いてきた。
◆
しかし、そんな猪突猛進な彼女の言葉も、今の私には空しく響くだけだ。
眼精疲労と老化という、ある意味で都合のいい言葉を鵜呑みにせずに、聞き入れておけば良かった。言う通りにしておけば良かった。
後悔以外の何ものでもない。
半年ほど経った後、あからさまな視力の低下に悩まされ眼科を受診すると、ないはずの光を視界に感じるというのは、その病気の初期症状の一つだったことが判明した。
列記とした「予兆」だったのだ。私の無知により見落とされただけで。
私が患っていたのは、網膜剥離だった。
嫌味な人間ならば、「そら見たことか」と嘲笑していたことだろう。
でももちろん、使用人の彼女はそんなことはしない。
「だから言ったじゃないですか!」
そう大声で怒鳴られた時には少しカチンときたけれど、本気で肩を落としてしずしずと廊下を歩く彼女の後姿を見ると、申し訳ないという自責の感情すら芽生えた。心の底から案じてくれていたからこその彼女の落胆ぶりに、思わず心が熱くなった。
まあ、翌日にはもうケロっとした顔をして、早くも屋敷のバリアフリーには何が必要かとあれこれ頭を悩ませている姿を朧げながらも見かけた時には、思わず苦笑いしてしまったけれど。
昨晩のあの温かい気持ちを返しなさい。そんな台詞が喉元まで出掛かった。
灯ってもいない光を感じる「錯覚」が何度か起こった後、私の目の前で開催されていた華やかな舞台は、何のアナウンスもなく唐突に、しかし確実に幕を下ろした。
そこには演劇の終わりのようなカーテンコールもなければ、コンサートの終わりのようなアンコールもない。
会場全体に口笛や拍手の音がこだまするようなスタンディング・オーベーションもなければ、身を屈めて獲物を狙う獣の唸り声のように地表すれすれを這うブーイングもない。
文字通り、黒い幕が天井から音もなく静かに降りてきただけだ。
そして、一度降ろされた幕が再び上がることは、もう二度となかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
