
【短編】鍵っ子














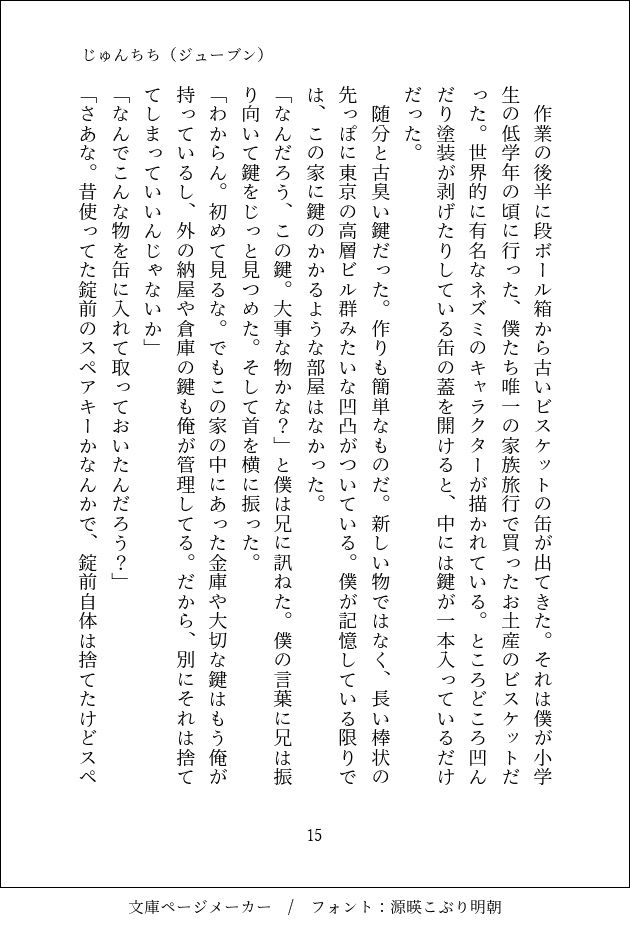






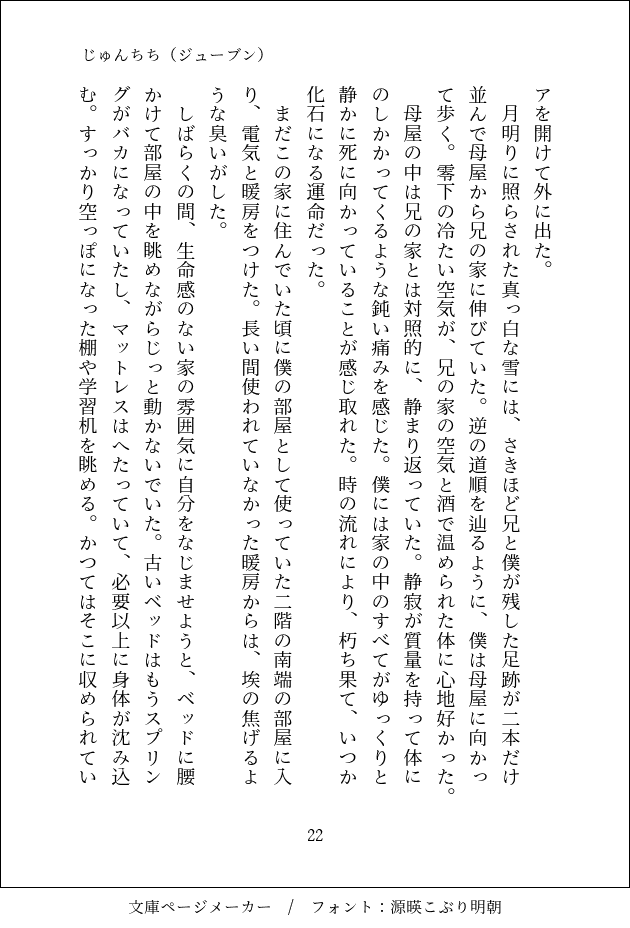


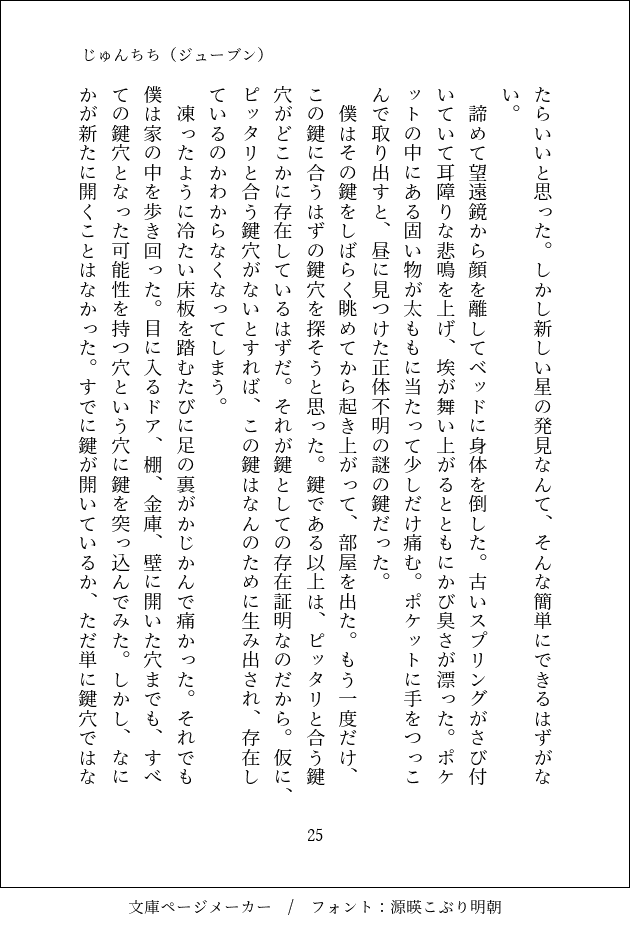















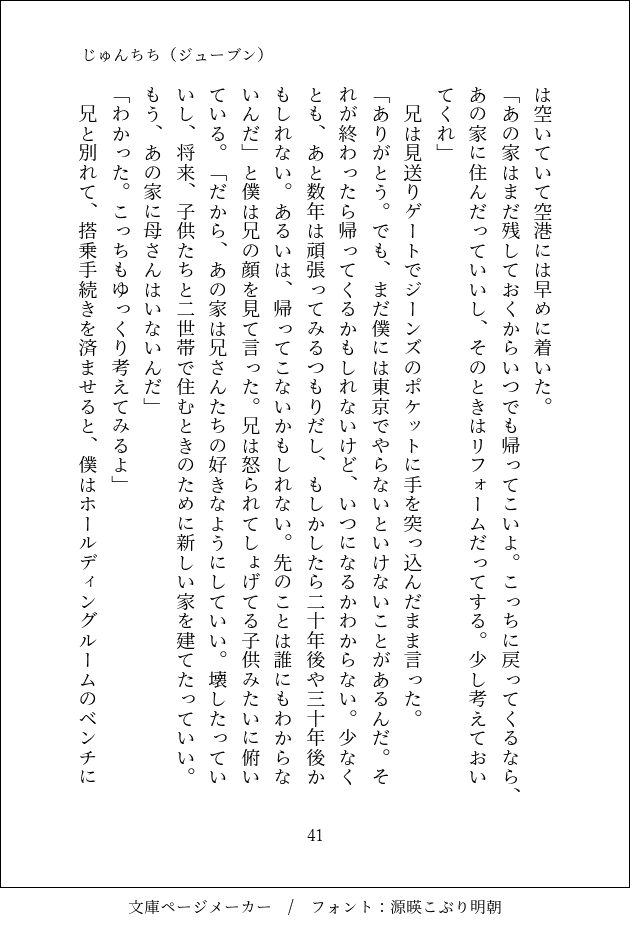


鍵っ子
母が死んだ。時計が壊れた。どちらももう動かない。
「この飛行機はただいまから降下を開始し、およそ三十分後に着陸いたします」とキャビンアテンダントの女性が柔らかな声でアナウンスし、飛行機は旭川空港への着陸態勢に入った。しばらくするとポーンという間の抜けた音と共にシートベルト着用サインが点灯する。それを合図に居眠りをしていた人たちがのそのそと動物園の象のような緩慢さで動き出した。隣の通路側の席に座る頭の禿げ上がった男性は大きな欠伸をしながら四本の手足を伸ばし、肘掛けで仕切られていたはずの僕の空間を侵食してきた。中年男性が持つ特有のくすんだ臭いが鼻に届いて思わず顔をしかめた。その男が持つ、無邪気と呼んでいいほどの無神経さが羨ましかった。
窓側に身を寄せながらシートベルトを着用して五分ほどが経った頃、突然、激しい頭痛に襲われた。それはこれまで経験したことのないような激しい痛みだった。左目の眼球の奥が岩のように硬く重くなり、そしてビキビキと音がして鋭い亀裂がいく筋も走った。瞼に力を込めて目を瞑り、俯きながら体を小さくして耐えていると、いつしかその部分をハンマーで何度も叩かれているような暴力的な痛みに変わった。激しい振動と痛みが頭の中に響く。それはまるで、だれかが僕の頭に直接的に怒りのメッセージを届けようとしているみたいだった。何度も何度も、重く硬いハンマーを力一杯振り下ろして。
僕はとにかく体を小さく畳むようにして黙って耐えていた。それでも猛烈な痛みのせいで、粘り気のあるいやらしい汗がじんわりと額や鼻に滲み出てくる。食いしばった歯の隙間から荒くなった息が漏れた。機内の乾いた空気の中に、僕の湿った吐息が溶けて消える。僕がそんな様子で頭を抱えていても隣の席の男性は一向にこちらを気にする様子はなかった。相変わらず僕の席の範囲にまで、そのでっぷりと肉のついた太く醜い脚を投げ出して欠伸を繰り返している。
飛行機が振動を伴いながら滑走路に着陸し、やがて動きを止めた。シートベルト着用サインが消えると同時に周りの乗客たちは一斉に立ち上がった。隣の男性も先程まで欠伸を繰り返していたのが嘘のような機敏な動きで立ち上がり、頭上の荷物入れからその身体には似つかわしくない小さな鞄を取り出していた。頭痛は少しずつその痛みのレベルを下げていたが、それでも僕は立ち上がる気力がなく、シートに深く体を沈み込ませたまま深呼吸を繰り返した。
「大丈夫ですか?」
どれくらいの時間が経ったのかわからない。気がつくと周りに他の乗客の姿はなかった。二九歳くらいのキャビンアテンダントの女性が先程まで男性客が座っていたシートの前に膝をついて、下から僕の顔を覗き込むようにしていた。その顔には親密さと親切さの仮面が張られていたが、その下にはキャビンアテンダントという仕事に対するプロフェッショナルとしてのプライドが横たわっているのが感じられた。
「大丈夫。母が死んだだけだから」
「御愁傷様です」
「でも、そのおかげであなたみたいな綺麗な人と話せたから」と僕が言うと、キャビンアテンダントはビジネスライクな笑顔の仮面を被った。実に見事な笑顔だった。どこからどう見ても一〇〇%の完璧さを備えた笑顔だった。バランスが取れていて、どこにも歪みや破綻がなく、これ以上は一センチメートルすら踏み込ませないガードの固さがあった。おそらく鏡の前で何度も練習を繰り返して身につけたのだろう。「実は今、頭痛がひどかったんだ。この間、葬儀で帰ってきた時にはこんなことなかったのに。こんなことは初めてだ」
「お母様が亡くなられたのですから。心の痛みは時間をかけてやってきます。その傷が深ければ深いほど、到達するのに時間がかかるものです」
「そういうものかな?」
「私はそう思っています。だから今はお母様のためにも、お客様ご自身のためにも哀しむべき時なのだと思います」
「これから母の遺品整理なんだ」
「大切な思い出を持ち帰ってください。人が死んだ人間に対してしてあげられることは思い出としていつまでも心の中で存在させてやることだけです」
「それはあなたの人生経験から? それとも本や映画で学んだ知識から?」
「両方です。私もすでに父と母を亡くしてますから」
「ありがとう」
女性と話している間に頭痛は治まっていた。先程までの激しい痛みが幻だったみたいに、僕の頭の中には平穏さと静けさが戻ってきていた。長く激しい戦いが終わったペリリュー島の戦場跡のように静かだった。
僕はようやく立ち上がって飛行機の外に出た。一階の到着ロビーの窓から見える景色には色がなく、一面がただただ白かった。空には分厚い雲がかかっていて雪を降らし、地面に音もなく積もらせている。十一月の旭川における、いつもの光景だった。僕が憎んだ、うんざりするほど色も味もない退屈な景色だ。五時間くらい噛み続けたチューインガムみたいだといつも思う。
到着ロビーには僕を迎えに来てくれている兄の姿があった。一八〇センチ半ばと身長が高く、骨太のがっしりとした骨格を持つ兄は遠目でもすぐに見つかった。結婚してから太り、今ではまるで冬眠前の熊みたいに見える。近付いてくる僕に気がつくと彼は右手を中途半端な高さに挙げた。右手はそのまま行き場を失い、中途半端な高さのまま所在なさげに動きを止めている。
「遅かったな。なかなか出てこないから心配したよ。飛行機の時間を間違えたのかと焦った」と兄は安心したように言った。僕が目の前まで来て、ようやく右手を下ろせたことにホッとしたのかもしれない。
「キャビンアテンダントが綺麗な人でね。少しばかり話し込んでいたら遅くなった。待たせて申し訳なかったね」
「お前は相変わらずだな」と兄は大きな声で笑った。やはり熊みたいだった。
人の少ない空港から駐車場まで兄と並んで歩いた。冬の北海道の空気は厳しい。よそ者にはなおさらだ。耳と頬が針で刺されたように痛み、呼吸をすると鼻の中が切れたように血の匂いがする。身長が一七〇センチと少ししかない僕の目の横には兄の髭の生えた顎がある。僕たちふたりを見て、兄弟だとわかる人間は少ないかもしれない。兄は父親似で、僕は母親似だから兄弟なのに似ていない。兄の姿は年々、僕の記憶の中にある父の姿に似ていっている。
駐車場に着いて兄の車に乗った。黒いホンダのヴェゼル。車体のサイドやタイヤには泥のはねた汚れがこびりついていた。助手席のドアを開けて中に入ると、コーンポタージュ味のスナック菓子やチョコレートの甘い匂いがした。後部座席を覗くと、姪のうさぎのぬいぐるみが座っていて、その横には甥の戦隊ヒーローのフィギュアが横たわっている。シートの足元にはお菓子の食べカスがボロボロと落ちていた。車内の暖かさと和やかな雰囲気に安心してため息が漏れる。
「ごめんな、汚くて。掃除しても子供たちが散らかしてキリがないんだよ」と運転席に座る兄がシートベルトを締めながら嬉しそうに言った。
「いいよ。子供はそれくらい元気で能天気なのがいいんだから。子供の特権だよ」
「そうだな。でも、お前ももう少し元気で能天気になっていいんだからな」
「もう十分すぎるくらいに能天気だよ。三十過ぎても独身で、好きなことやって暮らしているんだから」
「そうか。お前が元気ならそれでいいよ」
「元気がどうかは重要じゃないんだ。僕にとってね。自由であれ。それが僕の人生におけるテーゼだ。あるいはアンチテーゼと言ってもいい。どちらにせよ、大した違いも意味もない。自由である分だけ、傷つけられることも多いしタフさも求められるけどね。とにかく僕は東京でそれなりに生きてるよ。今のところはうまくやってる」
兄は僕の言葉に対して笑顔を浮かべただけだった。八歳年上の兄は昔から僕を子供扱いするところがある。僕が物心ついたときからすでに兄は父の仕事を手伝っていた。僕たちの父親は煉瓦造り職人で、小さな工房を営んでいた。職人気質で仕事一筋の父はあまり家庭を顧みることはしなかったし、子供である僕には興味を示していないように思えた。実際、僕にはほとんど父と会話をした記憶もない。だから僕はずっと母と二人で過ごすことが多かった。二人きりの家の中で、僕と母は磁石で引き付けられているかのようにピッタリとくっついて過ごした。
兄は高校を卒業すると大学に進まずに、父の工房を本格的に手伝うようになった。そして僕が十五歳の頃に父が亡くなると兄が後を継いだ。彼の人生において職業選択の自由があったのかは僕にはわからない。彼が自由意志に基づいて父の後を継いだのか、残された母や僕(もしかしたら兄自身も含んでいたのかもしれない)を守るために後を継いだのか、それは兄にしかわからないことだ。兄はそういう事柄を他人に喋るようなタイプの人間ではない。
何れにしても兄は必死に働いて工房を大きくした。法人化して従業員を数人雇うほどになった。別に魔法を使ったわけでもなく、兄には実際的な面での才能があったのだ。煉瓦造りだけではなく、ピザ窯やパン窯、かまどや暖炉などの製作に手を広げて成功させた。もともとの人の良さと、丁寧な仕事ぶりが評判となって旭川市内ではそれなりに仕事を請け負うようになった。試しに旭川市内を車で走り、適当なピザ屋やパン屋に入ってみるといい。おそらくそこの窯は兄が作った窯だ。さらに、この土地では小金持ちが新しく家を建てる場合、暖炉を家の中に作る。その暖炉を作るのも兄だった。そして仕事で懇意にしていた地元の住宅メーカーの社長から娘を紹介されて結婚した。それが彼のこれまでの人生だった。男の子と女の子の子供が生まれて幸せそうに見えるし、幸せであってほしいと思う。
そんな順調で充実したように見える兄の人生と比べて、弟である僕の人生は対照的なもののように思える。僕は大学進学を機にこの街を出て東京に行った。十八歳までの僕は、この街でずっと退屈さと息苦しさを感じながら生きてきた。それは女とセックスをした後にベッドの中で女の胸に顔を埋めているときの感覚に似ていた。
東京に出てからの僕は、とにかく女の世話になって生きてきた。大学の学費は払ってもらっていたが、それ以上は兄の世話になりたくなかったからだった。だから仕送りは断り、知り合った女の家に転がり込んで生活していた。バイトはせずに複数の女から小遣いをもらって遊んでいた。大学卒業後は遊び仲間にいた出版社の人間に仕事をもらい、フリーライターとしてたまに雑誌に記事を書くだけで、女たちの世話になる生活が今も変わらず続いている。もちろん母は、そんな僕の生活を知らず、出版社に社員として勤務していると思い込んでいた。小説が好きな母はそれを殊更に喜んでいたし、いつか僕は自分の小説を書くよ、とうそぶいて母をさらに喜ばせた。兄はそんな僕の嘘に気付きながらも母にはバラさなかった。兄は優しい人間だから、つまらないことで母を傷つけたくなかったのだろう。
車は旭川市中心地に向かう道を外れ、山の方に伸びる道路に入った。だんだんと実家が近づいてきて、懐かしい光景が車窓の外を流れていく。僕はシートに深くもたれかかるようにして座り、左に顔を向けて車窓を流れる景色をただ眺めた。冬の色のない景色を眺めているとどこか遠くに飛ばれされてしまいそうな不安に襲われる。
「母さんの遺品が多くてな。物を大事にする人だっただろう。だから整理するのが大変なんだ。でも、その分だけ懐かしい物がたくさん出てきて楽しいぞ」と長い沈黙のあとで、兄が言った。
「最後に病室に見舞いに行ったとき、僕が幼稚園で作った紙粘土の作品、母親と幼い僕が手を繋いでる姿をかたどったやつだけど、それを飾っていて驚いた。あんな物、とっくに捨ててると思ってたから」
「俺たちに関する物はだいたい取ってあるよ。特にお前のは絶対に捨ててないと思う」
「うん、そうかもしれない」
最後に少しだけ山道を登って、実家に着いた。がらんと開けた敷地の中に母が最後まで住んだ母屋と兄の家族が住む離れがある。古い木造家屋の母屋と洋風の煉瓦造りで洒落た兄の家が並んでいる光景は、どこかチグハグな印象を見る者に与えて僕は空を見上げた。灰色の空からは真っ白い雪が静かに降ってきていた。そのチグハグさは、まるで分別が不十分で紙も生ゴミもプラスチックも金属破片も無造作に詰め込まれたゴミ袋のようだった。その不分別さは雄弁だった。多くのことを物語っていた。だから僕は空を見上げるしかなかった。
それでも仕方のないことだった。誰も責めることはできない。父も、母も、兄も、僕でさえも。僕の実家だけの特殊な事情ではない。日本全国で見られる光景なのだと思う。そして、それは人々がそれぞれの人生を懸命に生きた証なのだ。
車が入ってきた音が聴こえたのか、兄の家族が出迎えにきた。六歳になる甥っ子が駆けてきて車を降りた兄に飛びついた。兄は軽々と抱き上げて空に向かって突き上げる。甥の楽しそうな笑い声が響いた。三歳の姪は義姉に抱かれたまま眠い目を擦っている。
「いらっしゃい。遠くて疲れてるでしょう。昼ごはんができてるから中に入って休んで」と義姉が僕に声をかけてくれた。
「そうだな。遺品の整理は昼飯を食べて、午後にしよう」と兄が肩に甥を乗せながら言った。僕は頷く。寒さが肌を刺す痛みに喋る気力も失っていた。
兄の家の中は暖かかった。身体の先がじわりとほぐれるのを感じる。力が抜けて動きがぎこちなくなり、出来の悪いロボットみたいな歩き方になった。義姉の料理を食べ終わる頃にようやく身体の芯までが温まった。食事の間に、姪はその小さな手で鳥の唐揚げを掴んだまま眠りに落ちた。
食事が終わると少しの間、甥とテレビゲームや戦いごっこをして遊んだ。いつだって彼がヒーローで、最終的には彼が勝った。小さな彼にとってまだ世界は正しい方向に、正しい速度で進んでいる。そのことが僕を安心させた。
午後二時になり、まだ遊び足りずに頬を膨らませながら怒る甥を義姉に任せて僕と兄は母屋に移動した。母屋は驚くほどに寒かった。兄が朝から暖房を入れていたにも関わらず、ひっそりと静まり返り、凍りついたように感じられた。それは単なる室温の問題ではなかった。家の中に漂う空気の質の問題だった。温度計では計れない、感覚的な寒さだった。だからこそ、その寒さは宿命的で本質的に思えた。住む者を永遠に失って時間の止まった家だけが備える特殊な寒さだ。
「相続に関わるような重要書類や貴重品はもうファイリングして俺の家にある。日用品のほとんどは処分した。大きな家具は業者に引き取ってもらう。あとは、細々とした思い出の品々や母さんが大切に使っていた物だけだ」と兄が説明してくれた。
「了解。さっさとやってしまおう。寒くて凍えてしまいそうだ」
「そうか? 東京に行ってから寒さに弱くなったんじゃないか?」と兄は笑った。
僕たちは粛々と作業をこなした。家中の引き出しを開けて中身を取り出して並べ、棚に置いてある物を床に降ろして並べた。そして、それらをいる物といらない物に分別していった。読書好きの母ではあったが、彼女の持っていた本にはそれほど価値のある物は見当たらなかった。どれも一昔前に流行して年月の流れの中で誰からも忘れ去られてしまったような軽い小説ばかりだった。本と比べればCDやレコードの方はマシだった。クラシックやジャズの名盤がいくつかあった。僕はその名盤だけを残して他は捨てることにした。
納戸に積んであった段ボール箱を次から次に開けていった。中身は僕や兄が幼稚園や小学生の頃に工作した物ばかりが入っていた。母以外の人間にとっては大した意味を持たない物ばかりだ。それらは写真に撮って残し、実物は処分することにした。僕と兄、それぞれが自分の作った作品を手に持って、照れ臭いような中途半端な表情を顔に張り付けて写真に収まる。その写真のデータは兄がパソコンで管理してくれることになった。
作業の後半に段ボール箱から古いビスケットの缶が出てきた。それは僕が小学生の低学年の頃に行った、僕たち唯一の家族旅行で買ったお土産のビスケットだった。世界的に有名なネズミのキャラクターが描かれている。ところどころ凹んだり塗装が剥げたりしている缶の蓋を開けると、中には鍵が一本入っているだけだった。
随分と古臭い鍵だった。作りも簡単なものだ。新しい物ではなく、長い棒状の先っぽに東京の高層ビル群みたいな凹凸がついている。僕が記憶している限りでは、この家に鍵のかかるような部屋はなかった。
「なんだろう、この鍵。大事な物かな?」と僕は兄に訊ねた。僕の言葉に兄は振り向いて鍵をじっと見つめた。そして首を横に振った。
「わからん。初めて見るな。でもこの家の中にあった金庫や大切な鍵はもう俺が持っているし、外の納屋や倉庫の鍵も俺が管理してる。だから、別にそれは捨ててしまっていいんじゃないか」
「なんでこんな物を缶に入れて取っておいたんだろう?」
「さあな。昔使ってた錠前のスペアキーかなんかで、錠前自体は捨てたけどスペアだから捨てるのを忘れちゃっただけじゃないか」と兄は言うと自分の作業に戻っていった。
僕は顎に手を当てて鍵をしばらく見つめてみた。しかし、なにもわからなかった。全ては憶測でしか語ることができない。考えることを諦めて、ジーンズのポケットに鍵を入れてから僕も作業に戻った。
作業は夕方の六時頃になってようやく目処がついた。いつの間にか雪は止んでいて、空には丸い月がぽっかりと浮かび、数え切れないほどの星が瞬いていた。東京では星が見えないし、そもそも夜空を見上げるという行為自体が意識されないために忘れていたけれど、空には本当に多くの星が存在していて、それだけたくさんの人が死んでいるのだ。冬の夜は長い。外はもう真っ暗で地面に降り積もった雪が月の光を受けて銀色に輝いていた。僕は形見として、レコードと天体望遠鏡と小さなロケットペンダントをもらい、それらを段ボールに詰め込んだ。その間もジーンズのポケットには先ほどの鍵が入ったままだった。
兄の家に戻ると暖かい夕食が用意されていた。ホワイトシチューとバゲットが湯気を立てながらテーブルに並べられていた。シチューの甘い香りとバゲットの焼けた芳ばしさを鼻から吸い込んで胸に満たした。姪が口の周りにべったりとシチューを垂らしながらも、必死に人参をスプーンに乗せようとしている。甥はその隣でバゲットに噛り付いて乾いた子気味良い音を響かせた。
夕食を終えると兄の家族たちは風呂に入り、兄と僕は酒を飲んだ。兄が竹鶴のピュアモルトの瓶を出して、グラスに注いでくれた。兄のグラスには指一本分、僕のグラスには指二本分の量を神経質と感じられるくらい精確に入れた。まるで実験における薬量を厳密に調整してフラスコに入れている化学者みたいな雰囲気だった。その熊みたいな見た目とそぐわないけれど、この気質が彼を父の後継者とさせ、さらに職人としての信頼に繋がっているのだとわかった。
子供たちがいなくなってしまうと、部屋の中はとても静かになった。二重窓のせいなのか、地面に降り積もった雪が音を吸い込むせいなのか知らないが、外からは一切の音がしない。兄の息遣いまでが聞こえてくると同時に、僕の息遣いも相手に伝わっているのかと思うと気まずくなる。
「最近、仕事の方はどうなんだ? 東京での暮らしぶりとかさ」と沈黙の中で酒を飲み続けてしばらく経った頃に兄が口を開いた。
「問題ないよ。まったく問題ない。フルマラソンの三〇キロ地点で、脚の痛みもなく、異常な発汗もなく、ペースの乱れもない。それくらい順調にいってるよ」と僕は嘘をついた。もはや自分ですら嘘だと気付かないくらいに自然と口から出てくる言い慣れた言葉たち。東京で金をくれる女たちに散々同じ台詞を言ってきた。
「それはよかった。安心したよ」と言う兄の顔はあまり嬉しそうではなく、声も低かった。僕は嫌な予感がして思わず視線をそらす。
「安心してくれ。兄さんたち家族に迷惑をかけるようなことはしないさ。大丈夫だよ。僕たちはギャラガー兄弟とは違う」
「そうじゃない。そんなことを心配してるんじゃない。俺は兄として君に幸せになってほしいだけだよ。もう肉親は俺たちしか残ってないんだから」と言うと兄は一口だけウイスキーを舐めた。「いつまでそういう生き方を続けるつもりだ?」
「どうだろう。わからないな。風向き次第さ。風向きが変わればフリーのライターなんてやめて他の仕事を見つけるよ。いずれにしても、自由に風に吹かれて生きていくことに変わりはない。別に家を選んで生まれてきたわけじゃない。だから兄さんも肉親ってことだけで僕の存在に縛られることはないよ」
「別に縛られてるなんて思っちゃいないよ。むしろ俺の足元の地面をしっかりと固めてくれる存在なんだよ、家族っていうのは」
「それは兄さんがまっとうな人間で強いからさ」
「いや、俺は弱い人間だよ。ただ長男ってだけだ」
僕はなにか兄に声をかけたほうが良いような気がしたが、なにも適切な言葉が思い浮かばなかった。フリーライターという言葉を武器に仕事をしているはずなのに、いつだって言葉は僕から逃げていく。だから僕はウイスキーに口をつけてごまかした。再び、口を開いたのは兄のほうだった。
「こっちに帰ってきて、うちの会社を手伝わないか?」
兄の言葉にたいして、それほど驚きを感じることはなかった。僕自身、いつか兄にそう言われるだろうと、心のどこかで準備をしていたような気がする。兄はそういう人間なのだ。長男であり、父であり、心の優しい男だった。資本主義経済の中で確固たる基盤を作り上げることができていない僕は、彼にとっていつでも守るべき弱者であり続けて、彼のそんな優しさに触れるたびに僕は自分が弱者であることに気付かされる。
「ありがたいけど、さっきも言った通り、自由がいいんだ。それに伴う責任や苦労だって自分ひとりで引き受ける。兄さんは兄さんと義姉さんや子供のことだけ考えてくれていればいい」
「お前ならそう言うと思ってたよ。でも結論を急ぐ話じゃない。ゆっくりと考えてくれ。お前の大好きな風に吹かれながらさ」と兄は小さく笑った。
子供たちが風呂を出たのだろう。脱衣所が騒がしくなった。しばらくして甥っ子が裸のまま部屋の中に駆け込んできて、兄が嬉しそうに甥っ子の寝間着を抱えて追いかけた。追いかけっこが始まり、ちゃんとパジャマを着た義姉と姪っ子が部屋の中にやってきた。姪っ子も追いかけっこに参加する。僕はそれを眺めながらウイスキーを飲んだ。
夜九時を過ぎて子供たちが歯磨きを始めたタイミングで、「おやすみ」の挨拶をしてから僕は母が最期まで過ごした母屋に移動することにした。
「こっちに泊まればいいのに。あっちは寒いよ」と義姉が玄関まで出てきて言ってくれた。
「いろいろと向こうに思い出もあるし、最後に見ておきたいから。明日以降は兄さんたちの好きなように、いつ取り壊したっていいよ」
「あの人から聞いた?」
「帰ってこいってこと? 聞いたけど断った。兄さん、気を悪くしないといいけど」
「大丈夫。そんなことを気にする人じゃないでしょう。あなたが幸せならそれでいいのよ。でも、私も帰ってくればいいのに、って思ってる。東京ってそんなに魅力的なの?」
「別に東京がいいってわけじゃない。そこに特別な意味はないんだ。ニューヨークだってロンドンだって、なんならブエノスアイレスだってかまわない」
「でも、ここじゃダメなのね?」
義姉の言葉に僕は曖昧な返事をした。首は縦でも横でもなく斜めに動いて、それを見た義姉は笑って「おやすみ」と言った。僕も「おやすみ」と言ってからドアを開けて外に出た。
月明りに照らされた真っ白な雪には、さきほど兄と僕が残した足跡が二本だけ並んで母屋から兄の家に伸びていた。逆の道順を辿るように、僕は母屋に向かって歩く。零下の冷たい空気が、兄の家の空気と酒で温められた体に心地好かった。
母屋の中は兄の家とは対照的に、静まり返っていた。静寂が質量を持って体にのしかかってくるような鈍い痛みを感じた。僕には家の中のすべてがゆっくりと静かに死に向かっていることが感じ取れた。時の流れにより、朽ち果て、いつか化石になる運命だった。
まだこの家に住んでいた頃に僕の部屋として使っていた二階の南端の部屋に入り、電気と暖房をつけた。長い間使われていなかった暖房からは、埃の焦げるような臭いがした。
しばらくの間、生命感のない家の雰囲気に自分をなじませようと、ベッドに腰かけて部屋の中を眺めながらじっと動かないでいた。古いベッドはもうスプリングがバカになっていたし、マットレスはへたっていて、必要以上に身体が沈み込む。すっかり空っぽになった棚や学習机を眺める。かつてはそこに収められていたはずの小説やアルバム、CD、手紙のことを思い浮かべた。自分の意識のあり方をアジャストして、空間に僕という存在をなじませる。自分の輪郭が少しずつぼやけて曖昧になり、家の空気に溶け込んでいく。思い出の世界を巡り、僕は時の流れの歪みに心を滑り込ませていった。
僕はベッドから立ち上がって母の形見となった天体望遠鏡を取り出して組み立て、窓際にセッティングした。そして部屋の明かりを消して、覗き込む。西側の窓から見える冬の夜空には、オリオン座のペテルギウスやおうし座のアルデバランが見えた。
僕が小学生の頃に買ったその天体望遠鏡は今でもよく手入れされていてレンズも汚れていなかったから、クリアに星を眺めることができた。小学校四年生か五年生のときに、宮沢賢治の銀河鉄道の夜を読んで星座に興味を持った僕は、母にねだって星座早見表と天体望遠鏡を買ってもらった。
母はもともと天体に詳しいわけではなかった。望遠鏡の使い方も天体の見方もわからない僕に教えるために、近所の詳しい人に聞いたり図書館に行って調べたりしてくれた。父に相手をされなかった僕にとって、家の中では母がすべてだった。ずっと母にくっついて、母と一緒に天体望遠鏡を覗き込んで過ごした。
小学校の卒業文集に将来の夢として「新しい星を見つけて自分の名前を残す」と書いた僕のことを母は喜んでくれ、「二つ見つけてお母さんの名前も残してね」と笑っていた。中学生になって通過儀礼としての反抗期がやってきた頃でも、天体望遠鏡を覗くときだけは素直に母と話すことができた。
東京の大学に進学するために家を出るまでの間、僕と母は天体望遠鏡を媒介としてコミュニケーションをとっていたような気がする。東京の夜空で星を見る気にもなれず、望遠鏡は実家に置いて上京した。遠くに行った僕のことを母がどう思っていたのか、どのような想いで望遠鏡の手入れを続けていたのかはわからない。
それでも、今でも手入れの行き届いた望遠鏡を覗くと、まだ母とコミュニケーションを取れるような錯覚がした。死に向かっている家の中で、僕は望遠鏡を覗き続けた。星空も死で溢れていた。今、僕の目に届いている星の光も、すでに過去に死に絶えて失われた時代の光なのだ。
僕は新しい天体を見つけようとした。そして、その星に母親の名前をつけられたらいいと思った。しかし新しい星の発見なんて、そんな簡単にできるはずがない。
諦めて望遠鏡から顔を離してベッドに身体を倒した。古いスプリングがさび付いていて耳障りな悲鳴を上げ、埃が舞い上がるとともにかび臭さが漂った。ポケットの中にある固い物が太ももに当たって少しだけ痛む。ポケットに手をつっこんで取り出すと、昼に見つけた正体不明の謎の鍵だった。
僕はその鍵をしばらく眺めてから起き上がって、部屋を出た。もう一度だけ、この鍵に合うはずの鍵穴を探そうと思った。鍵である以上は、ピッタリと合う鍵穴がどこかに存在しているはずだ。それが鍵としての存在証明なのだから。仮に、ピッタリと合う鍵穴がないとすれば、この鍵はなんのために生み出され、存在しているのかわからなくなってしまう。
凍ったように冷たい床板を踏むたびに足の裏がかじかんで痛かった。それでも僕は家の中を歩き回った。目に入るドア、棚、金庫、壁に開いた穴までも、すべての鍵穴となった可能性を持つ穴という穴に鍵を突っ込んでみた。しかし、なにかが新たに開くことはなかった。すでに鍵が開いているか、ただ単に鍵穴ではない穴に鍵を突っ込んでいるだけだった。
家の中を二周してから諦めて、僕は自分の部屋に戻った。握っていた鍵を机の上に置く。もう日付が変わろうとしていた。暖房が効きすぎて部屋の中は暑く、冷え切った手足の指先が溶けるようにほぐれていった。それでも身体の内側の芯だけは、いつまでも凍ったように冷たく、僕は寒気がしていた。
部屋の明かりを消してベッドに入ると目を閉じた。身体が寒気のせいでがたがた震えている音がする。耳鳴りもした。それ以外の音は、死に向かう家の闇の中に吸い込まれてしまっていた。僕の意識も同じように闇の中に吸い込まれていって眠りに落ちた。
不意に目が覚めた。まだ窓の外に朝日の姿はなく、部屋の中は薄い墨汁を満たしたみたいに仄暗い。スマートフォンで時間を確認すると、夜中の二時四七分だった。
大量の汗をかいていて、寝間着もベッドもぐっしょりと濡れていた。もう寒気は止まっていて頭の中もクリアになっていた。僕は濡れて重くなった服をすべて脱ぎ捨てて床に広げて置いた。
その時、ドアを越して階下からなにか音が聞こえてきた。それはテレビの砂嵐のようなノイズ音に似ていたが、たまに大きくなったり小さくなったりしている。不明瞭で輪郭をつかみきれないノイズ音に耳を集中させた。
どうやらそれは大人数が騒いでいる様子だった。男も女もいるらしい。笑い声や叫び声、手を叩く音、床を踏み鳴らす振動音までした。そのとき、不思議と恐怖心を感じなかった。むしろ、小学生くらいの子どもが不意に通ったことのない知らない道を見つけたときのように、僕は好奇心を感じていた。
裸のまま部屋を出た。さきほどまで凍えるほど寒かった家の中が、今では暖かさを感じるほどになっていて、裸の僕の皮膚を優しく包み込むようだった。廊下を進んで階下に降りる階段の入り口に立ったとき、いよいよざわめきは輪郭を伴い、人々の騒ぎ声になった。どうやら居間で宴会が行われているらしい。それはある種の哀しさを感じさせるほど、はしゃぎ、騒ぐ声だった。
階段をゆっくりと一段ずつ確かめるように降りていった。古い家の階段は踏みしめるたびに短い悲鳴のような音をたてたが、居間で騒いでいる人たちは気が付いていないようだった。変わらず宴が続いている。
居間のふすまの前に立った。一センチほど開いたふすまの隙間から明かりが漏れてきて、暗闇に立つ僕の中心線に沿った部分の肌を明るくした。僕が足元に視線を落とすと、ペニスも光の中にあった。
隙間から覗き込むようにして、居間の中の様子を探った。中では十五人ほどの人々が肩を寄せ合うようにして車座で座っていて、手を叩いて笑ったり、腹をよじって涙を流したりしていた。異様なほどの熱狂が渦巻く興奮状態にあって、人々から発せられる熱気と、甘ったるい匂いが漂っている。その甘い匂いは僕の鼻の中にまとわりつき、やがて脳の一本一本の皺に入り込んで思考を麻痺させていった。
車座の中心部では女が一人、下着姿で踊っている。バラを思わせる深紅のブラジャーが二つの豊かな乳房を包み、同じ色の揃いのTバッグのパンティが尻の膨らみを強調していて、存分に女の身体性が持つ美しさが発揮されていた。女の踊りは激しいものではなく、粘度の高い蜜が垂れ落ちるようにゆっくりと滑らかで、艶めかしかった。
僕は女の姿に目を奪われた。鼓動が早くなり、吐き出す息が震えた。あれほど騒がしかった人々の歓声や手を叩く音、指笛が一瞬にして遠のき、もう僕の耳には届かなかった。代わりに、踊っている女の唇の間から漏れ出す吐息ばかりが聞こえてくる。僕の目も耳も、捉える情報のすべてが女で埋め尽くされた。
気が付いたときには、僕はふすまを開けて居間の中に足を踏み入れていた。入ってきた僕の姿に気が付いた女が驚いたように目を見開いて動きを止めた。それを合図に車座の人々も一斉に僕に視線を向けて息を飲む。突然に訪れた静寂が重苦しい。僕は入ってはいけなかったのかもしれない。不都合な闖入者。女性用の更衣室に間違えて入ってしまったような気持ちになる。
しかし静寂を突き破ったのは悲鳴ではなく、やはり大きな笑い声だった。その笑い声を発したのは、正面に座る老人だった。白髪と同様に白くなった長い顎鬚を垂らした老人は、爆竹が爆ぜるように大きな音で笑った。皺だらけで骨と皮だけの細い指で僕を示しながら笑った。
「こいつ、パンパンに膨らましてやがる。ずいぶんと立派になってるぞ。天晴れだ」
その老人の言葉を聞いて、周りの者たちも一斉に笑い出した。あまりの笑いの大きさで壁や床が揺れた。踊っていた女も顔を赤くして笑っている。僕が恥ずかしさを感じて俯くと、勃起したペニスが見えた。これまでに感じたことがないほど、硬く大きく膨張していて、疼くような痛みを感じた。
「おうい、そんなところに突っ立ってないで、こっちに来て座れ」と老人が笑顔で手招きをしてから自分の左隣の床をばんばん叩いた。
僕は言われるがままに部屋の真ん中を突っ切って歩いた。部屋の中央で女が首を傾げながら微笑み、上目遣いで僕を見ている。それはオードリー・ヘップバーン的清廉さではなく、マリリン・モンロー的妖艶さを纏っていた。すれ違いざまに女は僕の股間を撫で、顔を上げた僕と目が合うとウィンクをした。その光景を見て、また周りの者たちが大きく笑った。僕は顔が火照ったように熱を帯び、汗がにじみ出した。
老人の隣に腰を下ろして、部屋の中を見まわした。座っている者たちは、若い男も女も、老人も老婆もいた。身なりがみすぼらしく貧しそうな者もいれば、上質な上着を羽織って豪奢なアクセサリーをつけた裕福そうな者もいた。中には、まだ十代前半くらいの子どもも見える。そして、僕と老人が座る後ろには見たこともない大きな黒い金庫があった。その金庫は見るからに堅牢だった。分厚い鉄の板でしっかりと囲われ、いかにも重そうで、僕は床が抜けないか心配に思った。そして、金庫の両隣には屈強な男がふたり、腕と胸の筋肉を見せつけるかのように腕を組み、ガードマンみたいに立っていた。
隣の老人から小さな盃が顔の前に差し出された。僕がそれを受け取るとそのまま酒を注がれ、一口舐めてみると日本酒だった。果実のような甘く爽やかな香りが鼻に届き、柔らかな甘みが口の中に広がった。上質な酒だった。そのまま一息で飲みほした僕を老人は満足そうな笑みで眺めながら頷いて、また酒を注いでくれた。
「おお、おお。いいぞ。どんどん飲め。どんどん喰え。若いんだから股間を膨らましてるのもいいけどよ、まずは腹を膨らませなきゃなんねえぞ」
気が付くと僕の前には料理の乗った盆が準備されていて、湯気と香ばしい匂いを放っていた。鯛の煮つけや刺身の盛り合わせ、焼いた牛肉が皿からこぼれそうなほどに盛り付けられていて、ずいぶんと豪勢な食事だった。
「なにかのお祝いなんですか? こんな豪華な食事、なにか偉い人のパーティーとかでしかお目にかかれないから、僕には一生を通じて無縁だと思ってた」
「お祝いではないな。ただ、俺らが偉いっていうのは間違いない。だからありがたく喰えよ」
「ありがたいとは思うけど、別になにも返せないですよ。僕は見ての通り、ただの若造で金もなにも持っていない」
「別に金なんていらねえよ。お前、文字通りに裸だもんな」と老人はまた大きな声で笑った。「それにな、世の中なんでもギブ・アンド・テイクじゃつまらねえだろ。仕事じゃねえんだからよ。大事なことっていうのはいつだって社会とかシステムのルールの外側にあるんだよ」
「なにが大事なのか、僕はずっとわからないまま生きてる気がする。確固たる価値観もなければ、宝物と呼べるような存在を手にしたこともない」
「大事なことっていうのは、大人になると忘れちまうやつが多いのさ。忘れたふりをしているだけかもしれないけどな。子どもたちのほうがよっぽどよく知ってるぜ」
部屋の中央では、女がまた踊っている。僕はそれを眺めながら老人と喋った。食事と酒は進み、勃起はまだ治まらない。
しばらくした頃、踊りを終えた女がこちらに歩いてきて僕と老人の間に体をねじ込むようにして座った。女の甘い匂いがむせ返るほど香り立ち、僕と女の腕や太ももの肌と肌がくっついた。汗ばんでうっすらと桃色に赤みがかった女の肌は、滑らかで柔らかく僕の皮膚に吸い付くようだった。
女の顔は昔寝たことのある女の顔に似ていた。高校生の頃に、僕が初めて女の身体というものを教えられた相手だ。女の身体が持つ脆さや柔さ、淫らな湿り気と香り。初めて女を抱いたときの興奮や不安、後ろめたさがよみがえってきて息苦しくなる。彼女は今頃、どうしているのだろう、と思った。高校を卒業して以降、音信不通になって行方を知らない。名前はなんと言っただろうか。
「私の顔になにかついてる?」と見つめられていることに気が付いた女が余裕のある微笑みを浮かべながら訊いてきた。
「美しい目が二つに、形のきれいな鼻が一つ、そして魅力的な唇が二つだけついてる」
「私の顔が好き?」
「そうだね。目が三つ、鼻が四つ、唇が五つじゃなくてよかった」
僕がそう言うと女は楽しそうに笑った。笑みを浮かべながら僕に寄りかかり、体重を預けながら左手で僕の太ももを優しく撫でた。
「私に目が三つあったら嫌いになった?」
「いや、そんなことはない。君の目なら三つでも四つでも好きだと思う」
「優しいのね」
女はそう言って僕の太ももを撫で続けた。僕は女の言葉には応えずに酒を飲んだ。甘さが口の中いっぱいに広がり、音を鳴らして飲み込んだ。
いつしか部屋の中には疲労の色が影を落とし始めていた。さきほどまで大声で手を叩いて笑い転げていた者たちも、俯き加減で黙ったまま酒を飲んでいる。女の向こうに座る老人も今では誰とも喋らずに、時おり背後の黒い金庫のようなものを振り返っては静かに首を横に振っていた。昼と夜がゆっくりと入れ替わり、空間の中に漂う闇の粒子を増やしていくように、部屋の中には沈黙が少しずつ広がっていった。
「そういえば、この金庫みたいなやつってなにが入っているんですか?」と僕は金庫の横の屈強なふたりの男を気にしながら老人に訊ねた。男たちは僕を鋭い目つきで刺すように睨みつけたが動くことはなかった。
「俺らの宝さ。新しい仲間なんだけどな、迎えに来たんだけど嫌だって言って閉じこもっちまったのよ。それで困ったもんだから、とりあえず楽し気に宴会でもして、歓迎ムードを伝えようってわけ。それで楽しそうだなって出てきてくれりゃいいなってね」
僕は振り返って金庫を見た。分厚い鉄板が部屋の中の喧騒を跳ね返すように、冷ややかにしんと静かで寂しげで、中に誰かがいるとは思えなかった。その様子はまるで深い森の中にぽっかりと大きな口を開けた洞窟の暗闇で、一人膝を抱えて座る少女を僕に思わせた。
「どうして、こんな物に閉じこもるくらい嫌がってるんですか? みなさんはトムソンガゼルを群れで追い詰めるメスライオンみたいな集団なんですか?」
「まさか。とんでもねえ。正義のヒーローだよ、俺たちは。善と悪で言えば、善だな。もちろんライオンたちだって自分の生を全うするために全力で生きているんだから、それは善なんだけどよ。とにかくここを離れたくないんだってさ。よっぽど、この家が好きなんだな。でも、このままだと地縛霊みたいになっちまうよ」と老人は最後に力なく笑った。皺だらけの顔がより萎んで見えた。
「無理やり開けちゃえばいいじゃないですか。ものすごく怪力そうな人が二人もいるんだから」
「おいおい、それはスマートじゃねえな。紳士たるもの金庫と女の股は無理やり開けちゃいけねえよ。それにこの頑丈さだ。鍵がなくちゃ開かないね」
老人がそう言うと、僕の隣に座っていた女が僕に跨り、腕を僕の首の後ろにまわしてきた。眼前に甘い桜桃が二つ迫り、眩暈がしそうになる。ふらつく頭で僕は眠りにつく前まで握りしめていた鍵の存在を思い出していた。
「この金庫の鍵かわからないけど、鍵穴不明の鍵をひとつ持っていますよ。ぴたりと合う鍵穴のない鍵なんて、球を受けてくれるキャッチャーがいないピッチャーみたいでかわいそうなんだ」
僕がそう言った瞬間、部屋の中からすべての音が失われ、時が止まったように感じれらた。僕が突然のことに驚いて顔を横に向けたり、目の前に跨っている女の脇の下から覗き込んだりして部屋の様子を窺うと、その場にいる全員が見開いた眼で僕を見つめていた。困惑と恐怖が僕の前にぽっかりと穴を開けた。女だけが僕を落ち着かせるように乳房を僕の顔に押し当てて、頭を撫でてくれていた。
「どんな鍵だ?」と老人に低い声で訊かれた。先ほどまでの朗らかな声とは別人のように違う。腹の底に響くような声に尿意を覚えた。
「古い鍵です。長い棒の先っぽに申し訳程度にシンプルな凹凸があるようなシンプルな造りで。アンティークっぽくてアクセサリーにできそうなくらい古臭いやつですよ」
「持ってきてくれ。もう俺たちには頼れる術がそれしかない」
「わかりました」
僕がそう言うと、まずは女が立ち上がり、僕の手を引っ張って立ち上がらせた。僕たちは部屋の中央を突っ切ってふすままで歩いた。部屋中の視線が裸の肌に突き刺さって痛かった。居間を出て後ろ手でふすまを閉めると、緊張がほどけたように溜息が出た。疲れと酒の酔いで頭が鈍く痛んだ。僕たちは暗い廊下と階段を通って二階に上がり、僕の部屋に行った。暗闇は質量を持ったようにぬらぬらとした感触で、足元でなにかが蠢いているように感じた。
僕が先に部屋に入り、後から女が入ってきた。女は部屋に入るとドアを静かに閉め、背中から僕に抱き着いた。背中に柔らかな膨らみが押しつけられた感触が伝わる。そのまま両手の人差し指で僕の乳首を弄び、首筋にキスをしてきた。
「ねえ、しよ」
女に耳元で吐息混じりに囁かれ、頭が真っ白に麻痺して身体が軽く痺れた。僕は勢いよく振り向くと女の両肩をつかんでベッドに押し倒した。女から子猫のような愛らしい声が漏れる。ベッドに仰向けになった女に覆いかぶさり、下着を引きちぎるように剥がして、キスと愛撫を繰り返した。そのたびに女の吐息と鳴き声が耳に届いて、ますます僕は興奮していった。女も僕のペニスを握って、お互いを愛撫しあった。部屋の中は温度と湿度を増していき、僕の荒い息遣いと女の短い喘ぎ声だけが重なり合って響いた。
これまでに経験したどのセックスとも違っていた。肉体の感覚が一枚皮膚を剥いだようにクリアでリアルだった。それなのに快感によって頭の芯は痺れて麻痺し続けていた。最後に彼女の中で僕が果てるとき、彼女もまた痙攣し、激しく強烈に僕からすべてを搾り取ろうとした。その後もしばらく彼女と一つに繋がったままで、一緒にベッドに横になっていた。息がようやく落ち着いてきても、なお、僕は疲労を感じて身体を動かすことができなかった。
女は僕に優しくキスをしてから身体を起こした。腰の括れが美しい流線を描き、大きく膨らみながらも張りのある形のきれいな乳房が見える。女はベッドから降りて下着を身に着けると、机の上から鍵を手に取った。
「鍵って、これのことね。私が持っていくから、あなたはゆっくりと休んでて。大丈夫だから安心して眠りなさい」
女のその言葉の途中で、もう僕の瞼は閉じていた。まつ毛に紐を括りつけられて、その先にボーリング玉をぶら下げられたみたいに抗いようがなかった。そして女が言い終わるのとほとんど同時に僕は意識を失った。
窓から差し込む朝日が顔に当たって目を覚ました。まぶしさに目を細めながら身体を起こす。家の中は静かだった。物音ひとつしない。窓から外を見るとよく晴れていて、降り積もった雪に太陽光が反射して世界はきらめいていた。昨日の夜に僕と兄がつけた足跡だけが残されている。真っ白な絵のキャンバスみたいな雪には、それ以外の模様も色もなかった。
裸のむき出しの皮膚に日光が当たって暖かさを感じた。視線を落とすと、明かりを受けたペニスに女の愛液と僕の精液が混ざり合ったものが乾いて白くこびりついている。昨日の深夜に、あの老人たちや女が存在したことをその白い滓だけが証明していた。僕のペニスだけが、僕の、女の、彼らの存在証明だった。
僕は鞄から新しい下着と服を取り出して着た。それから床に落ちたままだった昨日の寝汗に汚れた服を畳んでしまった。部屋を出ると空気の冷たさが痛かった。洗面所に行って顔を洗ってからキッチンに行き、コーヒーを淹れて居間で飲んだ。当然だけれど、居間には僕だけしかいなくて、静かだった。それでも彼女の存在が感じられて、ペニスが軽く疼いた気がした。
十時過ぎのフライトに乗るために兄の車で旭川空港まで送ってもらった。道路は空いていて空港には早めに着いた。
「あの家はまだ残しておくからいつでも帰ってこいよ。こっちに戻ってくるなら、あの家に住んだっていいし、そのときはリフォームだってする。少し考えておいてくれ」
兄は見送りゲートでジーンズのポケットに手を突っ込んだまま言った。
「ありがとう。でも、まだ僕には東京でやらないといけないことがあるんだ。それが終わったら帰ってくるかもしれないけど、いつになるかわからない。少なくとも、あと数年は頑張ってみるつもりだし、もしかしたら二十年後や三十年後かもしれない。あるいは、帰ってこないかもしれない。先のことは誰にもわからないんだ」と僕は兄の顔を見て言った。兄は怒られてしょげてる子供みたいに俯いている。「だから、あの家は兄さんたちの好きなようにしていい。壊したっていいし、将来、子供たちと二世帯で住むときのために新しい家を建てたっていい。もう、あの家に母さんはいないんだ」
「わかった。こっちもゆっくり考えてみるよ」
兄と別れて、搭乗手続きを済ませると、僕はホールディングルームのベンチに座って鞄からノートを取り出した。ありふれたキャンパスノートだ。小説を初めて書こうと思った大学生の頃に買ったもので、結局は一ページも使われずに鞄に入れっぱなしだった。僕はそこに思いついた小説の始めの一文を書き込んでいく。書きたいことが山ほどあった。僕はその山を大きなショベルカーで削り取り、ダンプカーに乗せて運び、フィクションの形に変換して並べていく。やがて、山から削り取って並べた土に樹木や草が生え、生き物たちが集まってくる。
搭乗時間になって機内に乗り込むと、昨日の便で話したキャビンアテンダントの女性がいた。向こうも僕のことを覚えていたみたいで目が合うとにこりと営業用の笑顔で話しかけられた。
「お母様からの贈り物は受け取れましたか?」
「ええ。小説を書こうと思うんです」
「とても素敵なことですね」
「ありがとう」
僕は自分の席に座ると、またノートを取り出して小説の続きを書いた。しばらくしてから飛行機は動き出してキャビンアテンダントたちもシートに座った。あの女性の姿が見えて、眺めていると目が合った。僕はノートの端っこを千切って、そこに連絡先を書き込んでから、また小説を書き進めた。
小説は進み、飛行機は空を飛ぶ。僕を東京に運ぶために。僕が東京で生きていくために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
