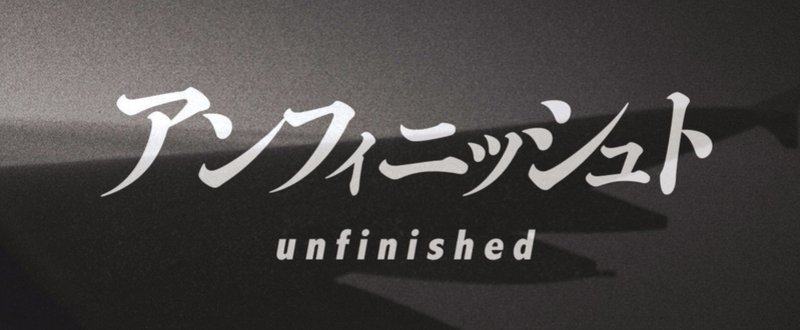
アンフィニッシュト 42-2
サンデー毎日(毎日新聞出版)にて2017年秋まで連載していたミステリー小説を毎週火・木にnoteにて復刻連載中。
1960年代後半の学生運動が活発だった日本を舞台に伊東潤が描くミステリー小説。
第四章 天国からの脱出
一
平成二十八年(2016)の正月が明けた。
国内では沖縄県知事が、宜野湾市にある米軍普天間飛行場の移転先とされていた名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認の取り消しを正式決定し、政府の方針と対立していた。
こうした中、格差社会が徐々に進み、貧困が深刻な社会問題となりつつあった。
貧困は各世代にも確実に浸透し始めていた。とくに簡宿火災で犠牲になった人たちのような六十代以上の層は、定年まで普通に働き、それなりに貯蓄があっても、本人や家族の不慮の怪我や予想外の病気によって、容易に貧困に陥ってしまう。
だが日本人にとって貧困は恥でもあり、貧困にあえぐ者やその予備軍は、声高に政府を非難したり、行政に助けを求めたりすることもなく、町の片隅でひっそりと暮らしているのが実態だった。
――これでよいのか。
寺島は、こうした話を聞くと義憤に駆られることがある。だがテレビは芸能人のどうでもいいニュースばかりを垂れ流し、週刊誌はスキャンダルを血眼で追っている。
その間も徐々に貧困は人々を蝕(むしば)み、次々と人々を簡宿のような場所に追い込んでいく。だが日本人は、同胞の苦境を直視しようとしない。
――何かが間違っている。
寺島は、無気力であきらめの蔓延(まんえん)した平成の世に疑問を感じていた。
しかも半年前の出来事にもかかわらず、世間では簡易宿泊所火災事件が話題になることもなくなり、建築基準法に違反している施設の是正も、遅々として進んでいない。
世間にとって、簡宿の火災はすでに過去のものになりつつあった。
寺島はもう一度、石山直人の住んでいた生麦のアパートに行ってみることにした。極めてか細い線だが、石山のライターから手繰る以外に、簡宿火災事件を解決する糸口はないように思えるからだ。
大家に連絡すると、案内することは快諾してくれたが、「石山さんの家財道具を処分しないことには、次の店子を入れられないよ」と、まくしたてられた。それにより、石山が戻ってきていないことが確認できた。
寺島は鶴見に向かった。
アパートは時代から取り残されたかのように、そこにあった。生麦という町自体が同じようなものなので、外景となじんではいるが、その殺伐とした雰囲気には近寄り難いものを感じる。
――かつては、このアパートからも笑い声が聞こえていたのだろうか。
すでにそうしたものが絶えてから、四半世紀は経っているように感じられる。
大家の文句を聞きながら部屋に入ると、以前に来た時よりも饐(す)えた臭いが鼻を突いた。積まれた衣類や畳の下などで、さらにカビが繁殖しているのだろう。
「やっぱり帰ってきてはいないようだね」
大家がため息をつく。
部屋の臭いと以前に入った時の記憶から、大家はそう思ったに違いない。
「そうですね」と生返事しつつ、寺島は注意深く部屋の中を歩き回った。
数カ月ほど前に来た時は、失踪したのかどうか半信半疑だったため、ざっと見回しただけだったが、今回は事件とつながりがありそうなものがないか、細かく見るつもりでいた。
以前よりも新聞は黄ばんでおり、家具や調度類に降り積もった埃(ほこり)も、確実に厚くなっている。
台所やトイレも見て回ったが、完全に乾ききっており、最近、使われた形跡はない。寺島はクロゼットや箪笥(たんす)の引き出しを丹念に調べたが、何かの手掛かりになるようなものは見当たらない。
内心、あのノートに結び付くような暗号の断片でも出てくることを期待していたのだが、そうしたものは一切ない。
――やはり、この線ではないのか。
かれこれ二時間ばかり見て回ったが、とくに収穫はなかった。そうしたことから寺島でさえ、石山が家賃を踏み倒すために、ガラクタを残してどこかに消えたのかもしれないと考えるようになっていた。
「こうしたもんは、家賃代わりに売り払っていいのかね」
大家の声に振り向くと、大家がLPのジャケットらしきものを見ていた。
「これぐらいしか価値のありそうなものはないからね。それとこのステレオだね」
大家に言われて気づいたのだが、狭い部屋の中に大きなオーディオセットが鎮座していた。むろん寺島も、その存在には気づいていたが、音楽の趣味が事件と結び付くとは考えられず、無意識裡に調査対象から外していたのだ。
――考えてみれば不自然だな。
「このオーディオセットは、随分と立派ですね」
「そうなんだ。石山さんは、音楽を聴くことだけが趣味と言っていたからね」
「そうだったんですか」
オーディオセットにはプレーヤーもあり、スピーカーの横には、十数枚のLPが立て掛けられている。
「何を聴いていたんですかね」と言いながら膝をつき、LPのジャケットを見たが、どれも馴染みのないものばかりだ。
「私は知らないよ。一度、外にいて聴こえてきたことがあるけど、なんかガチャガチャしたもんだったね」
「どうやらロックのようですね」
ジャケットの一枚には、楽器を持ったバンドの写真があったので、その類の音楽だとすぐに分かった。だが、流行りのJ-POPぐらいしか関心のない寺島には、全く知らないものばかりだった。
「しかも英米のバンドじゃないようですね。これはイタリアかな」
ジャケット写真は風光明媚なところで撮られているものもあり、ヨーロッパの雰囲気を漂わせている。
ジャケットの裏面に小さく書かれた文字は、英語とは異なる。
どうやら石山は、イタリアやドイツといったヨーロッパのバンドを好んで聴いていたようだ。
「こんなものの、何が面白いんだろうね」
大家が背後からのぞき込む。
「私にも分かりませんよ」
「そうだろうね。あんたの年で聴くようなもんじゃない。多分、六十年代か七十年代のものだろう。でも、こうしたものを好む人は、意外に多いらしくてね。石山さんによると、最近はリバイバルブームとかで、この手の連中が来日しているらしいよ。むろんこいつらも、皺くちゃのじじいになっているはずだけどさ」
大家が、白面の貴公子然としたメンバーの写るジャケットを手に取りながら笑う。
「へえ、石山さんはライブにも出かけていたんですか」
「そうそう。川崎駅前のクラブ何とかっていうホールに、こうした連中のなれの果てが、よく来ていると言っていたね」
――川崎駅前だと。
何かが閃(ひらめ)いた。
「それはクラブパーチェのことですかね」
「さあ、知らないよ」
――あそこでは洋の東西を問わず、マイナーなバンドのライブをよくやっている。火災のあった簡宿からは、徒歩で十分もかからない距離だ。
その時、レコードを包んでいたショップの袋が目に入った。黒一色の包装紙の中央に、朱字で「Disk Lord」と書かれたロゴが印刷されている。
――これは、どこかで見たことがあるな。
寺島が記憶をまさぐる。
――待てよ。簡宿の焼け跡写真だ。
突然、点と点が勝手に動き出し、つながってくるような感覚がした。
――あの日、クラブパーチェでライブはあったのか。
慌ててスマホを取り出すと、クラブパーチェで行われたライブの過去履歴を検索した。
――あった。
平成二十七年(2015)五月十六日、つまり簡宿火災の前日には、聞きなれない名のロックバンドがライブを行っている。
そのバンドの名を検索すると、イタリアのバンドだと分かった。さらに「Disk Lord」という店を調べると、川崎市内に店舗はなかった。
――ライブ会場で販売を受け持っていたのか。
早速、Disk Lordの本部に電話をすると、確かに同日、クラブパーチェで、LPやCDを販売していたという。
「あんた、どうしたんだい」
大家が心配そうに寺島の顔をのぞき込む。
「いや、何でもありません」
「そうかい。それならいいんだけどね。血相変えてスマホ見たり、どこかに電話したりしているから、どうしたのかと思ってさ」
「今日のところは、このぐらいで結構です」
「ああ、そうかい。それはいいんだけど、この部屋はもう片付けていいかい。石山さんは――」
大家の長口舌は続いていたが、寺島は室内やLPジャケットの写真を数枚撮ると、頭を下げてアパートを後にした。
著者:伊東潤(Twitter・公式サイト)
1960年、神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学社会科学部卒業。日本アイビーエム株式会社を経た後、外資系企業のマネジメントを歴任。2003年にコンサルタントに転じて2006年に株式会社クエーサー・マネジメントを設立。2007年、『武田家滅亡』(角川書店)でメジャー・デビュー。2010年に専業作家となって今に至る。
よろしければ、Twitterでも「#アンフィニッシュト」で、ぜひ感想をつぶやいてください。いただいたメッセージは、すべて読ませていただきます。サポートも歓迎です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
