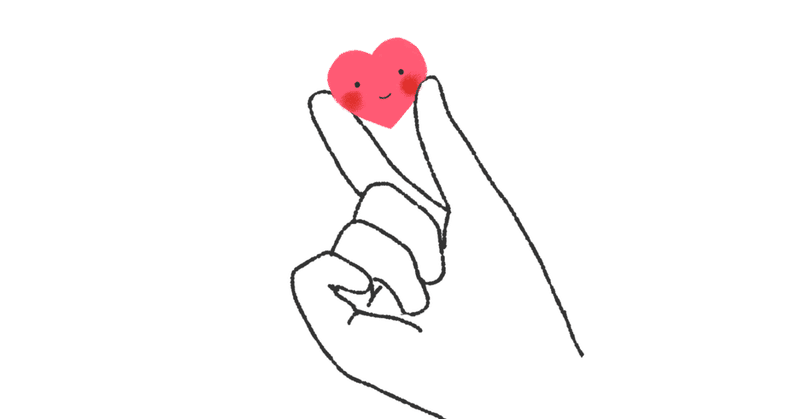
WISC、ちょっとだけ知っておこう〔結果をどーする?〕【語る教育×心理学③】
教育×心理シリーズ第3弾をお届けします。
過去記事はこちらです✨ぜひご覧ください。
今日は、発達知能検査の1つとして知られるWISCについて、結果からどんなことが分かるのか、簡単に解説したいと思います。
これまで過去3年間にかけてWISCなどの知能検査について研修を受け、多くの児童・生徒のWISC検査を実施し、分析してきました。
結果の資料からどんなことが分かるのか、現場での指導にどう活かすべきなのかというのは、色んな先生に周知し知っていただく必要があると思い、今回記事にしたいと思いました。
1.WISC(ウェクスラー式児童用知能検査)とは
WISCは、David Wechsler(1896-1981)というアメリカの心理学者によって開発されました。児童用以外にも、幼児用(WPPSI)と大人用(WAIS)の知能検査についても開発し、現在も医療・教育、様々な場で使われています。
WISCで分かることは、簡単にいうと
・全体の知能(FIQの数値で分かる)と『4つの知能のバラつき』の有無
です。その子の知的発達の様相を、個人内差も含めて知ることができるということですね。4つの知能とはこちらのことです。

昨年2月に、新版のWISC-Vが本国で導入され、PRIの指標がVSI(視空間指標)とFRI(流動性推理指標)というものに置き換わりました。
今後WISC-Vも日本でも導入が進み、教育界にも入ってくると思うので、また勉強したいと思います。
WISCの対象年齢は5歳0ヶ月〜16歳11か月です。
検査にかかる時間は60分〜90分程度と言われていますが、小学校高学年や中学生を対象に検査すると、2時間を要する子もいたりします。(というか、かかることが多い印象です。)特に熟考タイプのお子さんですね。
2.結果資料の数値の分析と指導への活用
1.結果を構成する数値について
WISCの検査結果は、次のような数値から構成されています。

一番左の項目は、先ほど説明した通り。全検査IQはFIQなどのように、英略語で書かれていることも多いです。
残りの4項目の数値や言葉について説明します。
まず、合成得点と記述分類。合成得点は、IQと置き換えて読む項目です。FIQが全体の知能指数、言語理解以下の4つの合成得点は、それぞれの項目のIQとなります。

IQということで、平均値は100。
正規分布で、85–115の間に約68%の人が収まり、70–130の間に約95%の人が収まる計算です。
記述分類は、そのIQに対応して書かれているもので、
・非常に低い 〜69
・低い(境界域)70〜79
・平均の下 80〜89
・平均 90〜109
・平均の上 110〜119
・高い 120〜129
・非常に高い 130〜
いずれか7つです。
大切なのは、IQの数値だけで子どもの能力を判断することはできない。4つの知能と合わせて総合的にみていくものだ、ということです。
FIQが “非常に低い”、〜69の児童・生徒には、知的障害の疑いがあると話をさせて頂くことがありますが、これはあくまで目安であり、おおよその値です。
当たり前ですが、FIQが同じ数値なら“みんな同じ”というわけではありません。4指標にばらつきがあるかないか、どのくらいあるのかによって、解釈は異なります。
個人内差(子どもの中の能力の差、ばらつき、得意苦手な力の差)に注目し、特徴を捉えて指導に活かしていく、子どもの生きやすさのために活用することが大事です。
続いて、「パーセンタイル順位」。これは、例えば100人の人がいた時に、その数値について『下から数えて』何位となるかを数えたものです。
下から数えるのがポイントです。つまり、パーセンタイル順位が100位と言うことは、上から数えて1番を取るくらいの値であるということとなります。
最後に、「信頼区間」という数値です。おそらく、ほとんどが【90%】【95%】のどちらかで書いてあると思います。
検査を行って出た数値が、その人の能力を絶対表しているか、と言ったら違います。体調、検査をする日の気候や気温などによってコンディションが異なるかもしれないし、検査員によっても違いが出るかもしれません。
信頼区間90%と書いてあり、そこに84ー95と書かれていたら、10回検査を受けると、その90%の9回はその信頼区間内である84から95のIQが算出されるはずですよ、ということになります。
2.解釈を支援に生かす

WISCの結果は、とにかく個人内差をどれだけその子の指導のために生かせるか、が大切です。今回は1つ、先ほど表で示したプロフィールについてを例に分析をしてみます。
グラフが一緒に示されることが多いですが、今回取り上げるのは、このように『逆N字』で言語理解とワーキングメモリーが高いお子さんのケースです。
得意な分野が、言語理解と耳からの情報処理。苦手な分野が目での情報処理とアウトプットや処理スピード(板書におけるアウトプットの要領についても処理速度で測る)、です。
目から多くの情報が入ってくると、頭が混乱してしまいます。視覚情報をよりシンプルに分かり易くしましょう。そして、耳で聞くのが得意なので、指示は口頭で。個別に近くで(あなたに伝えているよ、と分かるように)話してあげることで、理解がよく進みます。そして、情報の処理速度の苦手があります。板書に顕著に現れてくることが多いので、書かなくてはいけないアウトプットの量を少しでも減らしてあげる。ICT等を活用した記録を認めてあげることも有効に働いてきます。
このように読み解いていきます。4指標について、強みを生かす、弱点を補ってあげる工夫を考えていきます。考えられる弱さへの対応は、以下の通りです。
・VCI(言語理解)の弱さがある子
説明理解のための指示の出し方の工夫、随時確認しながら
知っている言葉を使いつつ、新たな知識・語彙を増やしてあげる
言葉に変わる、視覚的な手がかりを活用
静かな環境を保つ
・知覚推理(PRI)の弱さがある子
視覚情報を補うための明確な言語指示
書く作業に時間をたっぷり
視覚情報をより拡大
セルフトークでの自己解決
・ワーキングメモリー(WMI)の弱さのある子
課題や手順をすぐ忘れるので、記憶保持の方法を支援
指示の明確化、メモの活用やスモールステップの活用
集中できる環境整備
日課表の活用
・処理速度(PSI)の弱さがある子
活動時間の確保
課題の量ではなく、質を重視し評価してあげる
板書を補う方法・板書に変わる方法、ICT活用
集中できる教室環境
もし、クラスのお子さんの支援・我が子の支援に生かすことができる部分があれば、活用してみてください。
今回、WISCありきでこの記事を書いている形と一見するとなっていますが、このような検査を受けていない子への支援、手助けにあたるときも、これら4つの項目を見て、この子は何が苦手なのかな、生かせる得意な部分は何なのかなと考えて見るだけでも、児童生徒を見る目が変わるかもしれませんね。
本日も、お読みいただきありがとうございました♪
授業てらす 2期メンバー よう先生
3.参加受付中!Canvaビギナーズ講座 第3回!
来月3月5日に、Canvaの活用について学ぶセミナー第3回を行います!
初めての方でも大丈夫です。内容をみてもしご興味がある方はぜひ応募してくださいね!お待ちしています。
“キャンバる”ホリデー Canvaビギナーズ講座#03 Jump!編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
